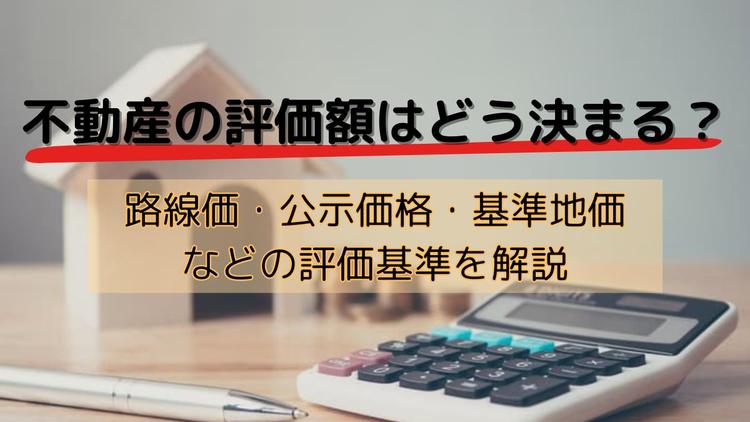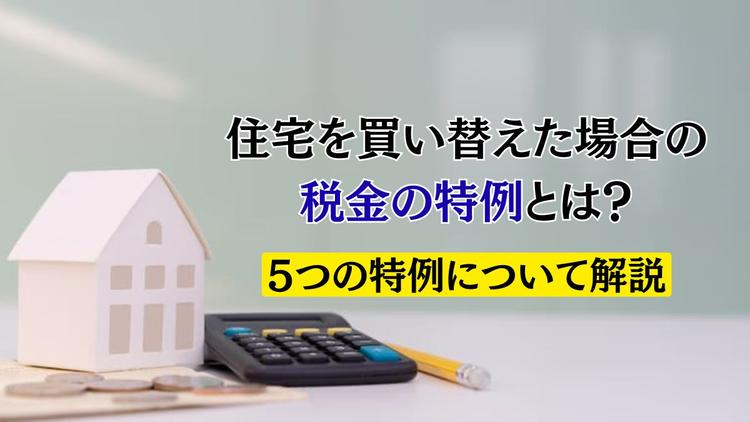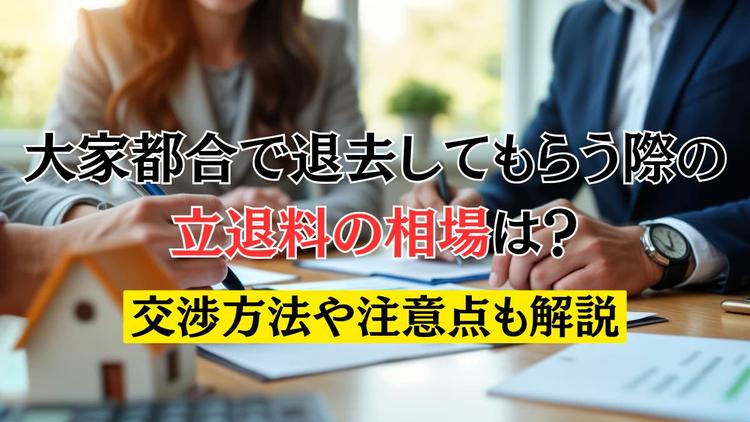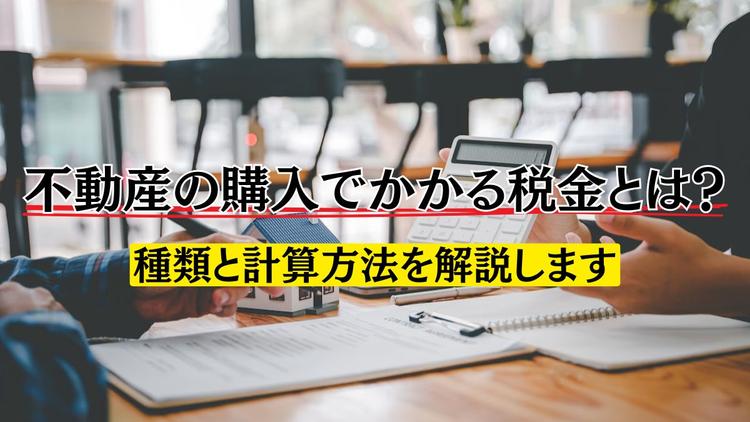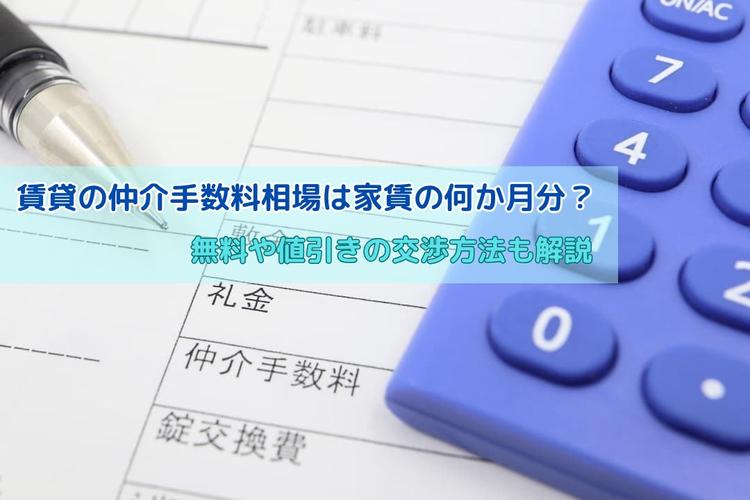不動産売却をする上で、極めて大切になるのが不動産評価だと聞きました。しかし、あまり内容が理解できていなんです…。
不動産の価格は、店頭に並べられた商品とは異なり、ひとつの物件に対して様々な評価額が付けられるんです。
築年数や家の状態が評価額に響くという事は理解できるのですが…そもそも何を基準に評価が付けられるのでしょう?
不動産会社は「路線価」「公示地価」「基準地価」といった複数のポイントを元に査定額を算出するんです。
初めて聞いた単語ばかり…。それぞれの内容や、どのように算出されるのかなどを売主として把握しておいた方がいいのでしょうか?
聞き慣れない言葉も出てきて不安かもしれませんが、大切な不動産を売却するのですかから、知っておいて損はありませんよ。基本的な不動産の評価額について解説をしていきましょう。
不動産評価の種類と役割
不動産は同じ物件であっても、使用目的によって、異なった価格が付けられます。
不動産評価にはどんな種類があって、それぞれどんな目的で用いられるのかみていきましょう。
公示価格(公示地価)
公示価格は、地価公示法に基づき国土交通省が選定した特定の土地の1月1日時点の地価です。
これを毎年3月の官報で公示します。
それでは、この公示価格はどういった目的で設定されているのでしょうか。
不動産の査定は、周辺の取引状況と比較検討して決めることがあります。
しかし不動産取引は地域的な要因や個人的な事情によって大きく左右されるために、周辺の取引と比較することが必ずしも適正だとはいえないのです。
この公示価格を不動産取引の指標として活用すれば、比較対象にしようとした取引が、特殊なケースなのか、一般的なものであるのかの、ひとつの判断の材料になり得ます。
また不動産会社に査定を依頼した際に、査定額が公示価格と大きく乖離していれば、その理由を問うことができます。
この他にも、公示価格には、都市計画道路等の公共用地の取得価額の算定基準としての役割があります。
基準地価(都道府県基準値標準価格)
基準地価は、国土利用計画法に基づいて公表される地価です。
各都道府県が特定の土地の7月1日時点の地価を毎年9月に公表します。
基準地価の調査ポイントは、公示価格とは別のポイントが設定されており、より広範で精緻にエリアを網羅しています。
また一部のポイントは、公示価格と同一のポイントを設定しており、連動させることで地価変動を適格にとらえることができ、統計データ等に活用することができます。
路線価(相続税路線価)
路線価は、相続税や贈与税の課税対象額の算定根拠として用いられるもので、相続税路線価とも呼ばれています。
国税庁が1月1日時点の道路ごとの価格を、毎年7月に公表します。
固定資産税評価額
固定資産税評価額は、固定資産税や都市計画税の算定根拠になる他、登録免許税や不動産取得税の算定基準になります。
固定資産税評価額は、全国の市区町村が決定します。
個別の評価額は不動産の所有者に直接知らされます。
時価(実勢価格)
実勢価格は実際に取引が行われなければ算出できませんが、「公示地価」を100%としたとき、おおむね110~120%の価格になります。
時価は売買されたときの成約価格ですから、厳密な意味では、現実に売買が行われないと正確な金額は分かりません。
しかし現実の売買では、時価を見極めたうえで売却金額を打ち出さなくてはいけません。
査定を依頼された不動産会社は、物件に適した査定方法で価格を算出しますが、複数の会社が査定すると、ほとんどのケースで、それぞれ異なった金額が提示されます。
つまり成約以前の段階では、時価にはある程度の幅があるということです。
路線価はどう決まるのか
相続税や贈与税の課税対象額を算出する際に用いる路線価ですが、土地の評価額はどのようにして決まるのでしょうか。
路線価図の見方とそこから評価額をどう算出するのかをみていきましょう。
路線価図の見方
路線価は国税庁のホームページ「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」で調べることができます1。
都道府県の選択から始めると、最終的に目的地付近の路線図にたどり着くことができます。
目的の不動産の前面道路を見ると「53E」や「480C」などの数記号が記されています。
・数字の後ろのアルファベット…借地権割合(Aの90%からGの30%まで、10%刻みに設定)
例えば、数字が「53」だと、1平方メートル当たりの価格は5万3千円ということになります。
路線価による土地の評価額の算出法
路線価が分かったら、どうやって土地の評価額を算出すればいいのでしょうか。
土地の評価額は次の数式によって算出することができます。
補正値とは、土地が不整形であったり、崖近くであったりする等の土地の条件を加味して補正する係数です。
かなり多岐にわたるため、国税庁のホームページの「補正率表」を参考にしてください2。
土地が整形な敷地であると仮定した場合、補正値は1.0になります。
路線価が「480C」で敷地面積が120平方メートルだとしたら、次のような計算になります。
48万円×120平方メートル×1.0=5,760万円
これにより、路線価による土地の評価額は5,760万円と算出可能です。
倍率方式による算出
路線価は、全国すべての道路を網羅しているわけではありません。
主に市街化区域で示されているため、路線価が表示されていない市街化調整区域等のエリアは倍率方式によって算定します。
固定資産税評価額はどう決まるのか?
固定資産税評価額は、固定資産税額の根拠となる評価額です。
毎年不動産の所有者に市区町村から送られてくる固定資産税課税明細書によってその額を知ることができます。
もし評価額に納得できない場合には不服審査の申出制度がありますから、算出根拠を知ることは、とても有意義だといえます。
土地と建物のそれぞれの算出法をみていきましょう。
固定資産税路線図の見方
固定資産税の路線価は、全国の市区町村の窓口で閲覧することができ、自治体によってはインターネットで情報の公開をしているところもあります。
あるいは、一般社団法人 資産評価システム研究センターのホームページ「全国地価マップ」で検索することができます。
なお、この「全国地価マップ」では、固定資産税ばかりでなく、これまで紹介をした路線価や公示価格等も検索できるようになっています3。
土地の固定資産税評価額の算出法
土地の固定資産税評価額は、次の数式により算出します。
補正値は、相続税路線価で用いた値と同じものになります。
間口が狭く奥行の長い、いわゆる「ウナギの寝床」と呼ばれるような敷地形状だと減額されますが、二方向に道路がある角地だと反対に加算されます。
建物の固定資産税評価額
建物の価額は総務省の「固定資産評価基準」に基づいて決定されます。
評価をするために、建物の完成から1カ月以内に自治体の担当者が家屋を訪ねてきて、内外装の仕上材料などをポイント制でチェックしていきます。
建物も3年に1度評価の見直しが行われます。
この際には現地調査は行いませんが、当初評価額に建築物価指数を乗じて、現在の再建築価格を算出したうえで、経過年数による減価係数を乗じることで、建物の評価額を算出します。
これを数式に表すと、次のようになります。
評価替えした評価額=再建築価格×経過年数による減価係数
時価の評価はどう決まるのか?
不動産の売却をする際は、売却価格を広告などで明らかします。
この価格は一般的には不動産会社の査定額が基本になりますが、これには必ず根拠があります。
宅建業法では、宅建業者は媒介価格について意見を述べる際には、その根拠を示さなくてはいけないことが明文化されているからです。
その根拠となる時価の評価方法には、いくつかの種類があり、物件の状況に応じて、それぞれ使い分けをしています。
どのような評価方法があるのかみていきましょう。
取引事例比較法
取引事例比較法とは、当該物件周辺の取引事例を収集して、それらの価格と比較しながら価格を決める方法です。
それぞれの取引には個別の事情があり、また不動産を取り巻く環境もそれぞれ異なっています。
このため取引事例比較法によって算出する場合は、それぞれの条件の違いをどのように補正していくのかという点が最も困難なポイントになります。
不動産会社は独自の方法で、周辺の取引情報を入手していきますが、一般の人でも国土交通省のホームページ「不動産情報ライブラリ(旧:土地総合情報システム)」によって不動産の取引価格を知ることができます4。
これは国土交通省が、実際に取引の行われた関係者にアンケートという形で質問をしたり、レインズのデータを参照したりして情報を収集し、公表しているものです。
特定の土地の取引価格や土地の形状などが表示されることから、不動産会社に査定を依頼した際にも、手持ちの資料として有効に活用できます。
原価法
原価法は、当該建物を再建築した場合の価格を基本に評価額を決める方法で、再建築価格から経年による減価修正を行います。
原価法は主に建物の評価に適した手法であるため、土地の評価については取引事例比較法や路線価格を用いて算出します。
それでは次のような物件は、原価法でどのように評価が導き出されるのかみていきましょう。
- 木造2階建て住宅
- 築15年
- 敷地面積 160平方メートル
- 建物延べ床面積 120平方メートル
- 敷地形状 整形
- 路線価 300E
まず土地の評価額は、路線価を元にして算出します。ここでは路線価は1平方メートル当たり30万円です。敷地形状は整形なので補正値は1.0です。
これにより路線価による土地の評価額が4,800万円だということが分かりました。
時価を算出するためには、路線価は実勢価格80%相当ということを拠り所にします。
これにより、土地の時価は6,000万円になります。
次に建物を算出していきましょう。建物の価格は、次の数式によって算出します。
建物の価格=再調達価格単価×延べ床面積×(残耐用年数÷耐用年数)
木造の1平方メートル当たりの再調達価格を15万円とします。木造の耐用年数は、国税庁の定めにより22年とされています。したがって、残耐用年数は、7年ということになります。
建物の時価は、約572万円です。これに土地の価格を合算します。
これにより、原価法によるこの物件の評価額は「6,572万円」という結果が導きだされます。
収益還元法
収益還元法は、不動産が将来生み出す収益に着目した方法です。
したがって、賃貸アパートやテナントビル、貸店舗などの物件を算定する場合に適した方法です。
一般家屋の場合は、借家として貸し出したと仮定して算出します。
ただし毎年一定割合で価値が下がっていくことが前提です。
世の中には様々な不確定要素があるために、今の価値は来年同じ価値だと確約できないとの考えに基づいています。
それでは次の条件の物件を収益還元法で算出してみましょう。
- 年間家賃収入 120万円 (月額10万円×12カ月)
- 保有期間 10年
- 割引率 5%
- 10年後の売却予定価格 2,000万円
割引率5%に設定した場合、次の表のように毎年5%ずつ収益価値が下がるものとして算定します。
| 年数 | 計算式 | 収益価値 |
| 1年目 | 120万円+(1+0.05) | 1,142,857円 |
| 2年目 | 120万円+(1+0.05)^2 | 1,088,435円 |
| 3年目 | 120万円+(1+0.05)^3 | 1,036,605円 |
| 4年目 | 120万円+(1+0.05)^4 | 987,243円 |
| 5年目 | 120万円+(1+0.05)^5 | 940,231円 |
| 6年目 | 120万円+(1+0.05)^6 | 895,458円 |
| 7年目 | 120万円+(1+0.05)^7 | 852,818円 |
| 8年目 | 120万円+(1+0.05)^8 | 812,207円 |
| 9年目 | 120万円+(1+0.05)^9 | 773,531円 |
| 10年目 | 120万円+(1+0.05)^10 | 736,696円 |
| 1~10年目の収益の合計 | 9,266,082円 | |
| 売却時 | 2,000万円+(1+0.05)^10 | 12,278,265円 |
| 収益+売却時の価値 | 21,544,347円 |
これにより収益還元法による評価額は「約2,100万円」という結果になります。
収益還元法は、賃貸マンションを棟ごと売却する場合の評価に適していますが、一般の一戸建て住宅の場合は、家賃や将来の売却額の設定が、市場に照らして適切であるかの判断が大きな課題になります。
まとめ
ここまで、不動産の評価額がどう決まるのかについて説明をしてきました。
不動産の評価は、使用目的によって価格が大きく異なってきますが、公示価格、基準地価、路線価、固定資産税評価額の公的価格は、根拠データが公開されているために、自分自身で検証することが可能です。
実勢価格については、売却を相談した不動産業者に判断を委ねることが多いのですが、諸事情によって、相場よりも相当安い金額で売りに出される可能性が無いわけではありません。
不動産の売却に際しては、公的評価を指標にして、査定金額が適正であるかをしっかりと自身でチェックすることが重要です。