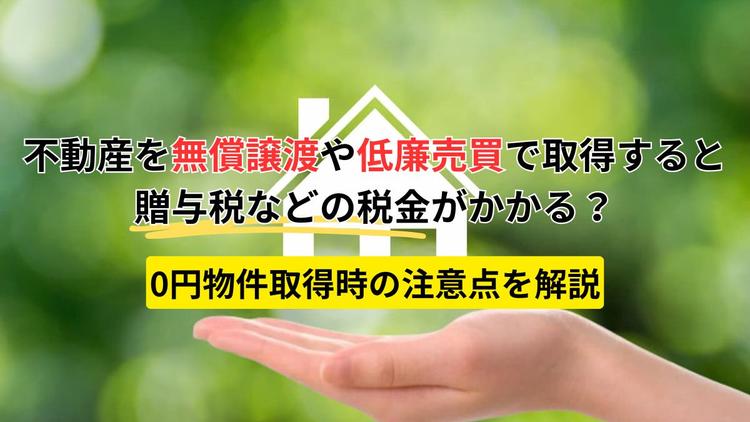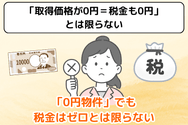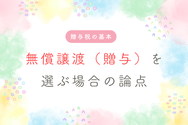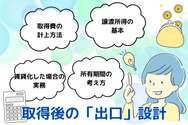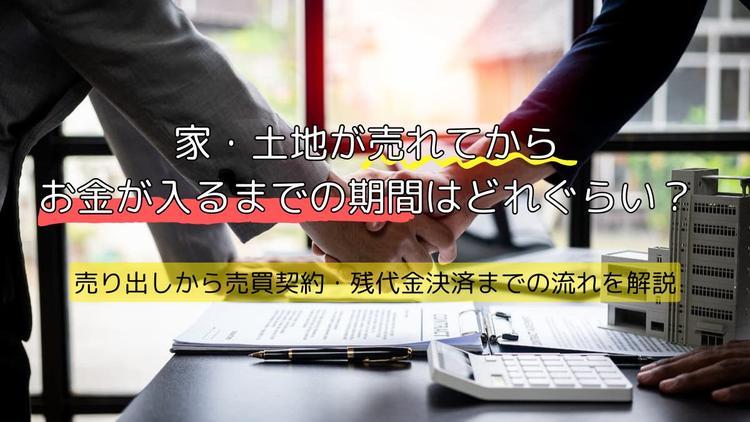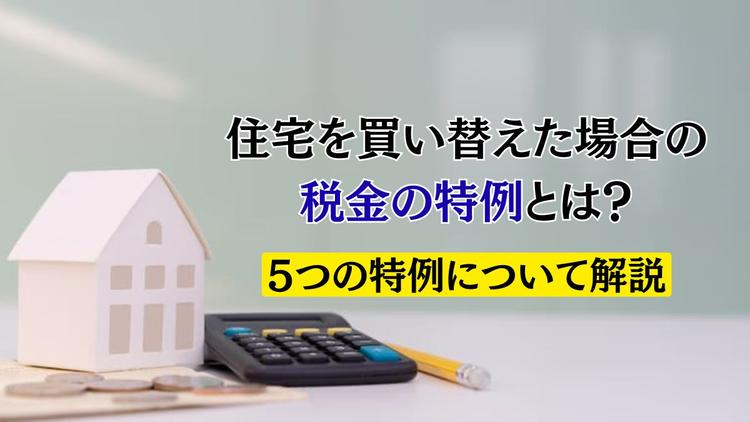空き家や老朽物件を「0円で譲ります」という話、魅力的に見えても税金はゼロとは限りません。無償譲渡や低廉売買では、時価と対価の差がみなし贈与とみなされて、贈与税の対象になることもあるのです。
この記事では、「時価」の考え方を押さえることで、関連する税金を明らかにするとともに、取得後の出口(売却・賃貸)まで見据えた税金計算の要点を解説します。
「0円物件」でも税金はゼロとは限らない
空き家や老朽不動産の増加に伴い、「引き取ってくれるなら0円で譲ります」「解体費や滞納管理費を負担してくれるなら無償でどうぞ」といった商談が身近になりました。
ところが、「取得価格が0円=税金も0円」とは限らないのです。むしろ、取得時点・登記時点・取得後のそれぞれで、性質の異なる負担が生じ得ます。
ここでは、どんな税金が、どんな根拠でかかり得るのかを解説します。
0円でも発生する主な税金
0円の物件を取得した場合、次のような税金が発生する可能性があります。
贈与税(国税)
無償譲渡や、著しく安い価格での売買(低廉売買)の場合、時価と対価の差額が「みなし贈与」と評価され、受け取る側に課され得ます。
基礎控除はありますが、物件規模によっては負担が大きくなります。
不動産取得税(都道府県税)
対価の有無を問わず、不動産を取得した事実に着目して課されるのが原則です(相続取得は非課税の取扱い)。住宅・宅地にかかる税率の軽減など、特例の適用可否は別途確認が必要です。
登録免許税(国税)
所有権移転登記に伴う税です。取得原因(売買・贈与・相続等)で税率体系が異なり、課税標準は通常「固定資産税評価額」となります。なお、0円の取引でも登記時の税負担は発生する可能性があります。
印紙税(国税)
売買契約書は原則課税文書です。贈与契約書は原則として課税対象外ですが、負担付贈与で実質売買に近い条項構成だと取扱いが変わる余地があるため、文面設計に注意が必要です。
(将来)譲渡所得課税(国税)
受け取った側が後日売却するときに発生する可能性がある税です。取得費や所有期間の起算が結果を大きく左右します。「0円取得→売却益が大きく見える」ため、課税が重くなるパターンに注意しなければいけません。
固定資産税・都市計画税(市町村税)
1月1日時点の所有者に税金が課されます(売主・買主間で日割精算するのは実務慣行)。固定資産税評価額を基に課税されるため、0円取引で取得した場合でも、翌年以降の税負担がほぼ確実に発生します。
なぜ「0円=非課税」ではないのか
税務上は「時価」を基準に判定します。贈与税はもちろん、低廉売買の差額贈与認定も、その物件の客観的な価値(時価)がいくらか、という一点に立脚します。
ここでいう時価は、単に売主の希望価格や固定資産税評価額そのものではなく、路線価や近隣の取引事例、法規制・物理的瑕疵を織り込んだ市場性から総合的に把握するものを指します。
無償譲渡(贈与)を選ぶ場合の論点
「0円で譲り受ける」=「贈与で受ける」を選ぶとき、受け手(受贈者)と渡し手(贈与者)の双方に税務・法務の論点が生まれます。
ここでは、贈与税の基本から、負担付贈与の扱い、取得費・所有期間の考え方、相続時精算課税の是非、契約書・登記実務まで整理します。
贈与税の基本と時価の押さえどころ
贈与は対価のない財産移転です。受贈者には原則として贈与税が生じます(暦年課税の基礎控除は110万円)。
不動産の贈与では、贈与財産の価額=時価の立証が肝心です。固定資産税評価額は登録免許税等の基準として使われますが、そのまま「時価」になるとは限りません。
路線価や近傍成約、劣化・法令制限・解体費等を織り込んだ合理的な説明資料をそろえ、「なぜその価額なのか」を第三者資料で補強しておくことが、後の否認リスクを下げます。
贈与者側の課税(みなし譲渡)に注意
贈与は無償なので、贈与者側には原則として譲渡所得課税は生じません。ただし、負担付贈与(受贈者が解体費・滞納管理費等の負担を引き受ける)や、対価性を帯びる条項が厚い場合は、負担部分が実質的な対価と評価され、贈与者側に譲渡所得課税が生じる可能性があるのです。
不動産などを相場よりも著しく安い価格で売る(低廉売買)場合、税法上では「本当は時価(適正な価格)で売ったのと同じ」と見なされて、譲渡所得税などの課税対象になることがあります。
このとき重要になるのが、法律に定められた「条文上の線引き」です。
つまり、「どの程度までの値引きなら通常の売買として認められ、どの程度安いと“みなし譲渡”と判断されるか」という法的な境界ラインのことです。
この線引きは、所得税法第59条や相続税法第7条などの条文で定められています。
例えば「著しく低い価額で譲渡した場合には、時価で譲渡したものとみなす」といった規定があり、税務上は“売買”ではなく“贈与やみなし譲渡”として扱われることがあります。
そのため、契約書に記載する売買金額がこの条文上の線引きを超えて不自然に低い場合、契約上は「売買」としていても、税務上は別の扱い(課税対象)になる可能性があるのです。
したがって、契約書の金額設定や文言を、条文での基準(線引き)と整合させておくことが非常に重要になります。
受贈者側の将来課税
贈与で取得した不動産を将来売却する際の譲渡所得計算では、取得費や所有期間の扱いによって税額が左右されます。一般に、贈与で受けた資産は、贈与者の取得費を引き継ぐ考え方や、支払った贈与税の一部を取得費に加算できる特例が論点になります(重課回避のための制度)。
一方、所有期間は受贈時から起算するのが原則で、相続のように被相続人の所有期間を通算できる取り扱いと異なる点に注意が必要です。
結果として、「0円(実質)で受けた」資産は取得費として計上できる費用が少ないため、売却益が膨らみがちです。取得直後に売るのか、中長期で保有して改修等を行うのか、戦略設計が不可欠です。
測量費、解体費、リフォーム費、登記費用など、取得・譲渡に直接要した費用は領収書を保管して、将来的に取得費として計上できるように準備しておきましょう。
▼関連記事:不動産売却時に経費(取得費・譲渡費用)になるものを完全解説
負担付贈与の注意点
空き家のマッチングサービスなどでは「解体費をあなたが負担してくれるなら0円であげます」といった条件が多く見られます。これは典型的な負担付贈与です。
- 受贈者(取得する人)側:贈与税の課税価額は、原則として時価から負担部分(解体・残置撤去・滞納管理費など確定額)を差し引いた純財産価額が基礎になります。負担額は見積書や契約条項で「確定性」を担保しましょう。概算・将来不確定の費用は控除根拠として弱いと考えてください。
- 贈与者(あげる人)側:負担部分は対価性があるため、その部分については譲渡所得課税が生じ得ます。条項設計次第で課税関係が変わるため、税理士にチェックしてもらうことを推奨します。
契約書には、負担の範囲、金額、支払方法、費用発生のタイミング、未達時の扱い(解除・清算条項)を明記します。
相続時精算課税を使う/使わない
直系尊属(親など)からの贈与の場合、2,500万円まで贈与税を非課税とでき、超過分も一律税率という「相続時精算課税制度」を選ぶ選択肢があります。
- メリット:贈与時点の支払額(贈与税)を抑えられ、大きな評価額でも受けやすい。
- デメリット:将来の相続時に贈与分を相続財産に合算して精算され、制度選択は原則取り消せません。
さらに、贈与時点での評価・取得費の考え方が将来の譲渡に響きます。 贈与者の相続対策全体(他資産・相続人構成・小規模宅地等の特例の可否)とセットで、キャッシュフロー・税負担の総額最小化を試算してください。
契約・登記・印紙・登録免許税の実務
実務では、「書く→貼る→申請する→納める」を抜けなく整えることが肝心です。順に紹介していきましょう。
- 贈与契約書:不動産の特定(所在・地番・家屋番号・地目・地積・種類・構造・床面積等)、贈与の意思表示、引渡し時期、負担付ならその内容、解除・清算条項、費用負担を記載します。
- 印紙税:負担付贈与の条項があるだけで直ちに課税文書になるわけではありません。課税対象になるのは、実質売買契約書や請負契約書、債務引受契約書など該当類型の文書が成立した場合です。
- 所有権移転登記(原因:贈与):登録免許税は固定資産税評価額に税率を乗じて計算します。売買・相続と税率体系が異なるため見積もりに反映を。具体率は当該年度の手引で確認してください。
- 必要書類:評価証明書、贈与契約書、登記原因証明情報、固定資産評価通知の写し、委任状、本人確認資料など。
- 不動産取得税:取得後に都道府県から納税通知が届くのが通例です。住宅軽減等の特例は、基本的に申告(届出)主義です。放置すると軽減が自動適用されません。要件を事前確認し�、必要なら申告を忘れずに行いましょう。
名義・能力・同意の確認事項
贈与の当事者に未成年者や意思能力に課題のある方(例:認知症)が含まれる場合は、親権者や成年後見人等の関与が必要になり得ます。将来の取消し可能性や利益相反の有無にも配慮し、手続と書面を整えておくことが肝要です。
共有不動産を贈与する際は、各共有者ごとに贈与契約と移転登記を行い、持分割合の整合を図ります。あわせて、将来的な共有物分割の見通しも立てておくと、後の紛争を避けられます。
さらに、配偶者や同居親族の居住・使用の実態がある場合は、賃借権や使用貸借が潜在している可能性を念頭に、贈与契約の条項で関係を明確化しておかないと、将来の売却や活用の障害となり得ます。
以上を踏まえ、当事者の能力、名義の持ち方、関係者の同意関係を事前に整理することが、実務上のトラブル回避につながります。
取得後の「出口」設計
「0円で受けとる」ことはスタート地点にすぎません。出口(売却・賃貸)での税負担とキャッシュフローが、最終的な損益を決めます。本章では、譲渡所得の基本、取得費の計上方法、所有期間の考え方、住居系の特例、賃貸化した場合の実務までを整理します。
譲渡所得の基本式と「取得費を作る」発想
不動産を売却したときの課税所得は、原則として次の式で計算します。
0円(または極小)で受けた物件は“取得費が小さい”ため、売却益が大きく見えがちです。ここで鍵になるのが、次の二点です。
- 取得費:贈与で受けた場合、贈与者の取得費を引き継ぐ考え方や、支払った贈与税の一部加算が論点になり得ます。相続と異なり、所有期間の通算はできない点に注意。
- 譲渡費用:仲介手数料、測量・筆界確定費、解体費、滅失登記費、各種書類取得費、広告費、貸主負担リフォームのうち“売却のため直接要した費用”は原則算入余地があります。
取得後に行う測量・境界確定、残置物撤去、危険空き家是正、インフラ引込、解体などは、将来の売却に不可欠なら証憑を残すことで経済的に「取得費/譲渡費用」を作れます。見積書・契約書・領収書・写真・発注経緯メモをワンセットで保管しましょう。
所有期間と税率の関係(長短判定)
譲渡所得は、所有期間により税率体系が異なります(一般に短期>長期)。
取得直後の売却は短期判定になりやすく税負担が重くなりがちです。長期化の判断と保有コストの比較を先に行い、賃貸活用や更地化のタイミングを含めてキャッシュフローで最適化します。
居住用の特例(利用可否の見取り図)
自宅として使った場合は、適用できる特例の可否が納税額に大きく影響します。代表例として、次のような制度があります。
- 居住用財産の3,000万円特別控除:一定要件を満たす自己居住用の譲渡益から最大3,000万円控除。転居後の期限・単身赴任・空き家期間など細かな要件があるため、早めに適用可能性を診断。
- 長期所有かつ居住用に関する優遇:所有・居住年数や買換え・交換特例など、選択適用の組合せで税額が変わるため、他資産・相続の設計と一体で比較検討。
賃貸へ転用した場合や、家財撤去後の空き家期間が長い場合は、居住用の特例適用が難しくなることがあります。「いつまでに売る/貸す」を最初にカレンダー化しておきましょう。
更地売り・建物付き売り・賃貸化の選択
同じ物件でも、どの出口を選ぶかで「先出しコスト」「売りやすさ」「税務の当たり方」がらりと変わります。
ここでは、①更地売り、②建物付き売り、③賃貸化の三択について、必要となる是正・解体・募集等の費用項目、譲渡費用や資本的支出への算入可否、キャッシュフローの山谷(いつ現金が出て、いつ入るのか)を横並びで整理します。
まずは“価格を上げるための投資”と“税務で取得費・譲渡費用にできる投資”を切り分け、最短で手取り最大化に近づく道筋を確認していきましょう。
更地売り
解体費・アスベスト調査除去費・仮囲い等の近隣対策費が発生する。
- メリット:老朽家屋でも、需要が広がりやすい。
- デメリット:再建築不可や新築需要の小さいエリアでは、買い手が限られる。
- 税務:解体費は売却のために直接要した費用として譲渡費用に算入しやすい。
建物付き売り
残置撤去・最低限の是正で売るか、リフォームして売るかの選択をする。
- メリット:解体を要しない分、先出しコストを抑えやすい。
- デメリット:建物の状態が悪い場合は需要が小さくなる。
- 税務:リフォーム費は性格により資本的支出(取得費側)か、単なる修繕(経費性が弱い)かの峻別が必要。
賃貸化(居住用)
家賃収入は非課税ではありません。
- メリット:長期保有により長期譲渡判定を待てる、空き家状態が続くことによる劣化を防げる。
- 税務:住宅の家賃は消費税非課税。減価償却費、固定資産税、管理委託費、損害保険、修繕費、仲介料等を必要経費に算入可能。原状回復費は修繕・資本的支出の区分に注意。
- 実務:管理会社の選定、入居審査、原状回復基準(国交省ガイドライン準拠)を契約で明確化。
マンスリー・民泊等
旅館業法・住宅宿泊事業法の規制、用途地域・管理規約の制限、消費税・地方税の論点が生じます。安易に転用せず、法令・規約を事前に確認しましょう。
まとめ
0円取得でも税はゼロになりません。
肝は①時価の立証(路線価・事例・瑕疵と是正費の証拠化)②スキーム選択(贈与/低廉売買/負担付贈与/使用貸借の比較と条項設計)③出口設計(売却・賃貸・更地化を前提に取得費/譲渡費用を計画的に作る)の三点です。
登録免許税・不動産取得税・将来の譲渡所得まで見通し、見積・契約・領収書・写真を時系列で保存すれば、「思わぬ重税」と「後日の否認」を大きく減らせます。