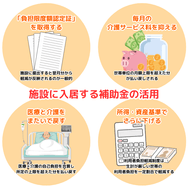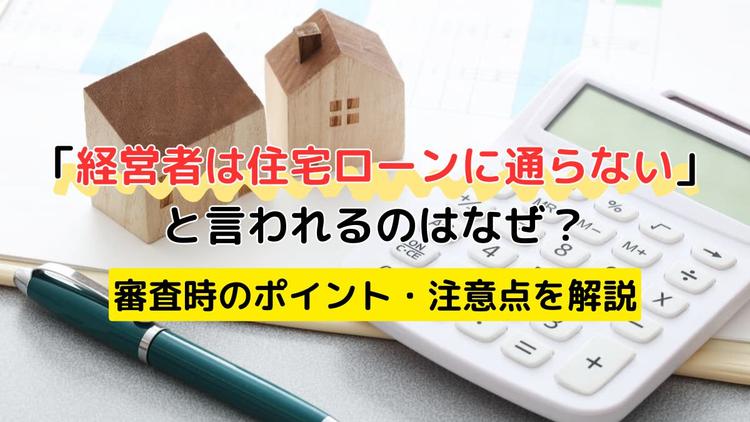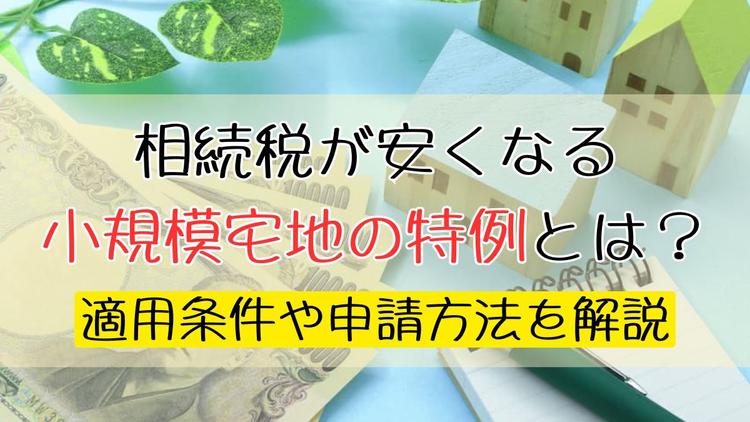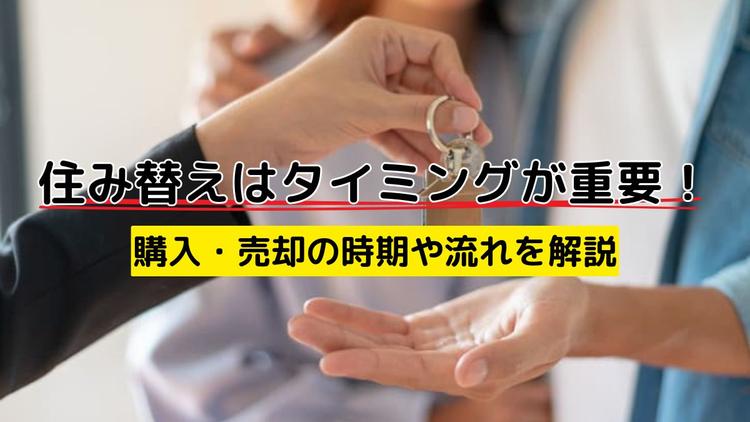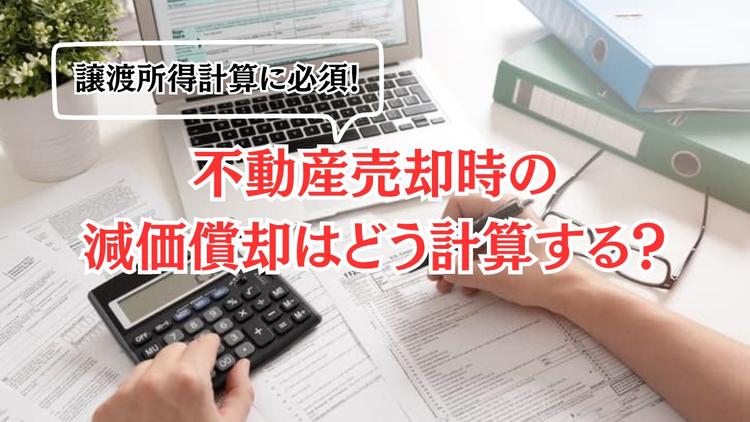親や親族が認知症になり「施設に入れたいが、お金がない」。そんな切迫した状況でも、手順を踏めば解決の道は見えてきます。
この記事では、施設の種類と費用の目安を整理し、資金確保の手段や補助金について解説します。
認知症で入居する施設の種別と費用感
認知症で入居する施設を選択する際に、検討すべき課題は主に次の二点です。
- どの施設が適しているのか
- 費用はいくらなのか
これらの情報が把握できると、施設選びを具体的に検討できるようになるでしょう。
ここでは、認知症の方が現実的に選ぶことの多い入所・居住系サービスを、役割(何を目的に暮らすか)と費用(初期・月額・変動)の二つの軸で整理します。
代表的な施設の特徴と役割
認知症で入居する施設には、次のような種類があります。
- 特別養護老人ホーム(特養)
- 介護老人保健施設(老健)
- 介護医療院
- 認知症高齢者グループホーム(GH)
- 有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
それぞれの特徴と役割を挙げていきましょう。
特別養護老人ホーム(特養)
特養は、原則は要介護3以上(ただし家族のやむを得ない事情等で要介護1・2でも特例入所が認められる場合があります。)を対象とした「終の住まい」です。
生活支援と見守りの体制が厚く、長期的に暮らす前提で設計されています。
介護老人保健施設(老健)
老健は在宅復帰・在宅生活の維持を目的とする「橋渡し」の場です。医師・看護・リハビリ・相談員が短〜中期で関わり、体調や生活機能の立て直しを図ります。
介護医療院
介護医療院は、慢性的な医療ケアと生活の場を同時に要する方の長期入所先で、褥瘡(じょくそう)、経管栄養、吸引などが日常的に必要なケースでも暮らしを支えやすい仕組みです。
認知症高齢者グループホーム(GH)
GHは、少人数・家庭的な環境で暮らしのリズムを整える場となります。家事参加や役割づくりを通じて、認知症特有の不安定な精神状態の緩和を狙います。
原則として同一市区町村の住民が対象ですが、外部から転入して入居できるかは自治体によって差があります。
有料老人ホーム
有料老人ホームは幅が広く、介護付は施設内で介護が完結、住宅型は外部の訪問系サービスを組み合わせます。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
サ高住は「住まい+見守り・生活支援」を基盤とし、介護・看護は外部サービスで積み上げるスタイルです。
費用の内訳と相場感をつかむ
費用は「初期費用(入居時)」「月額費用」「見落としやすい変動費」に分けて考えることで、誤差を抑えて具体的にシミュレーション可能です。
初期費用(入居時)
初期費用は、特養・老健・介護医療院・GHであれば入居一時金は原則不要で、敷金・保証金・入居準備品などを合算して、おおむね0〜20万円に収まることが多いでしょう。
有料老人ホームは支払い方式で差が開き、月払い型でも敷金等で0〜50万円、一時金型では物件により数十万〜数百万円に達することもあります。
サ高住は賃貸物件と類似する費用相場である場合が多く、敷金・礼金・保証金で20~30万円程度が一般的です。
月額費用
月額費用は、介護保険の自己負担(1〜3割)に家賃・管理費・食費・水光熱・生活費を合わせた総額で確認するようにしましょう。
目安として、各施設ごとの月額費用相場は以下の通りです。
- 特養8〜18万円
- 老健12〜20万円
- 介護医療院12〜22万円
- GH15〜25万円
- 有料(介護付/住宅型)18〜35万円
- サ高住10〜20万円+外部サービス利用分
これらの費用は地域差や個室/多床、各種加算、医療連携の濃さで上下します。
変動費
変動費として、
- 医療費・薬代
- 紙おむつ等の衛生用品
- 理美容
- 嗜好品
- 行事費、受診や外出の交通費
- 介護保険外サービス(自費)
などが積み上がり、毎月数千〜数万円の振れ幅が生じがちです。さらに、初月は日割りや備品購入で+1〜5万円程度上振れすることが多い点も、あらかじめ考慮しておきましょう。
認知症ケアとの相性を見極める
認知症の中核症状に加え、徘徊・夜間不眠・易怒・幻視/妄想・拒否などの不安定な精神状態の出方で、適した環境は変わります。施設の種別ごとの対応を把握しておきましょう。
- 特養……中等度〜重度まで幅広く受けとめられるが、夜間の人員配置や精神科連携、看取り方針の濃さは施設差が大きい。
- 老健……多職種で観察しながらのケア調整が得意で、症状が揺れる時期での利用に向くが、長期の住み切りは前提ではなく、在宅復帰・他施設への移行を前提とする中期滞在の位置づけ。
- 介護医療院……医療依存度と認知症特有の症状が同時に高いケースでも生活を組み直しやすい反面、身体拘束ゼロ方針やケアの質の実践度にばらつきがある。見学で運営姿勢を要確認。
- GH……少人数で役割づくりを通じて生活のリズムを整えやすく、認知症特有の症状の緩和が期待できるが、重症化時の増員や医療連携の限界も見極めが必要。
- 有料・サ高住……夜間の見守り体制、訪問看護の導入状況、センサー等の活用がケア品質の差につながる。
家族側は「困っている時間帯と場面」を具体化し、見学時に、その場面でどう支えるかを問い、実例ベースで確認すると判断材料になるでしょう。
見学・比較で外せない着眼点
パンフレットでは伝わりにくい「運営の癖」が満足度を左右します。
- 深夜(0〜6時)の人員配置と巡回頻度
- ナースコールの�平均応答
- 入浴・排泄・服薬といった基本ケアの標準手順
- 急変時の医療連携(往診・救急搬送後の復帰支援・精神科バックアップ)
- 身体拘束ゼロの実績
- 認知症の行動・心理症状の悪化や長期入院時の退去基準
上記は契約前に具体例で確認したい項目です。
可能なら異なる時間帯で複数回見学し、日中と夜間の運営の温度差も見ておくと安心です。
施設に入居する資金確保の手段
入居時は「初期費用の山」と「毎月の固定費」が家計を圧迫します。本章では、家計内の工夫と契約・資産面の手当てで道筋をつける方法を示します。
まず支出を下げる
同じ施設でも、契約内容で費用負担は変わります。個室→多床や、広い個室→標準個室への切替、オプション(洗濯・リネン・レクリエーションなど)の精査、食事コースの見直しで固定費を圧縮できるでしょう。
入居一時金がある場合は月払い型への変更や分割の可否、サ高住・GHでは敷金の分割預入や入居月の日割りの扱いを交渉します。
見積書と重要事項説明書に支払いサイトを明記し、初月の上振れは別枠で予算化しておくと崩れません。
当面のキャッシュを確保する
支払い時期が重なると資金繰りが苦しくなることもあります。
クレジットカード・口座振替の締め日/引落日をずらす、光熱・通信の支払方法を統一してキャッシュアウト日を集約、医療・介護用品は月末まとめ買いで管理しましょう。
家財では不要な貴金属・家電・趣味資産を計画的に売却し、相見積もりで手取りを最大化します。
生命保険・金融商品の活用
生命保険の契約者貸付や解約返戻金は即効性が高い反面、将来の死亡保険金が減ります。必要額だけ、返済計画とセットで利用を検討しましょう。
投信・株式は売却手数料や課税(譲渡益・損益通算)を見込み、入居予定日から逆算して現金化していくのが有効です。定期預金は中途解約ペナルティを確認し、短期の定期へ組み替えて流動性を上げます。
不動産を急がず安全に現金化
不動産は売却を急ぐと買い叩かれる可能性があります。すぐに売らず、まずは現金化のための選択肢を確認しましょう。
たとえば、民間リバースモーゲージ(自宅を担保に毎月の資金を借りる)、リースバック(一度売ってまとまった額を現金化し、家賃を払って住み続ける)、賃貸化(定期借家)、駐車場・トランクルーム化などの選択肢がありますが、どれが有利かは「手取りの多さ」ではなく、空室期間・原状回復費・固定資産税まで含めた「実質利回り」で決めます。
売却する場合、手取りのできるだけ多くするためには「仲介(不動産会社に買主を見つけてもらう)」での取引が適しています。
媒介契約を結ぶのは1社に絞る「専任または専属専任媒介契約」として、施設の利用費を用意しなければならない時期までに販売するため、業者による買取での出口までを見据えた計画を立てましょう。
価格設定は近隣成約相場から大きく外さないのが原則です。販売価格は、目安として2~3週反応が少なければ段階的に見直す、といった市場の反応で調整する工夫が有効です。
親族からの援助は「生��活費扱い」
親族援助は通常必要な範囲・即時の生活費充当なら実務上の扱いが穏当です。余剰の貯蓄化は贈与課税の対象になり得ます。また高額の一括贈与は相続で特別受益の火種になりがちです。
振込記録・使途メモを残し、簡単な家族間覚書で「金額・期間・使途」を共有してください。立替精算は月締めルールを決めておくことで感情的対立を避けられます。
法的枠組みで安全にお金を動かす
認知症が進み、本人の判断力に波が出はじめた段階では、先に「権限」と「資金の通り道」を作ることが安全運用の出発点です。代表的なのが任意後見と家族信託、そして判断がすでに難しい場合の成年後見です。
いずれも「誰が・どの財産を・どこまで動かせるか」を明文化し、第三者(金融機関・不動産会社・施設)に対して通用する根拠を用意する仕組みです。
任意後見
任意後見は、元気なうちに本人が信頼できる人(任意後見人)を選び、公証役場で契約しておく方法です。将来、判断能力が低下した際に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で効力が発生します。
日常の口座管理、施設費の支払い、各種契約の更新・解約など、生活と財産管理を幅広く委ねやすいのが利点です。発効まで時間がかかるため、早めの準備が向いています。
家族信託
家族信託は、特定の財産(自宅、預金の一部、賃貸不動産など)に限って、家族(受託者)が目的に沿って管理・処分できるようにする仕組みです。たとえば「自宅を売って入居費に充てる」「家賃収入を毎月の費用に回す」といった資産ごとの使い道を細かく設計できま��す。
対象や権限の範囲は信託契約で個別に定めるため、準備段階での設計の良し悪しが実務のしやすさを左右します。
▼関連記事:家族信託した不動産は売却可能?必要手続きや手順を解説します
成年後見
成年後見は、すでに判断が難しい状態で利用する制度です。家庭裁判所が後見人を選び、財産管理や身上監護の権限を与えます。法的安定性は最も強い一方で、本人の自由度は下がりやすく、大きな取引(自宅売却など)には裁判所の許可が必要になることがあります。
▼関連記事:認知症の親や親戚の家は勝手に売れない!成年後見制度を利用した売却手続きの流れ
施設に入居する補助金の活用
入居費用を「公的な軽減」で下げる方法も有効です。自治体の独自助成や、社会福祉法人の利用者負担軽減制度、さらに税制上の控除を重ねると、手取り負担を段階的に落とせます。ここでは、公的補助金について整理します。
「負担限度額認定証」を取得する
特養・老健・介護医療院(※GHは除外)等への入所では、介護保険の自己負担とは別枠でかかる食費・居住費(滞在費)に、所得・資産に応じた上限額が設けられています。対象はおおむね住民税非課税の方で、預貯金等の資産要件や同一世帯・配偶者の資産状況も見られます。ただし、名義移動や駆け込み贈与は不利に働くケースがあります。
手続きは市区町村(介護保険担当)に申請し、「負担限度額認定証」を取得。施設に提出すると、翌月分から軽減が反映されるのが一般的です(遡及は限定的)。毎年度の更新が必要で、年金額や預貯金残高、課税・非課税区分を証明する書類を求められます。
ポイントは、入居前から準備しておくことです。課税証明・年金振込額・通帳写し・賃貸借や固定資産の状況など、要求されやすい書類をセットで揃えておくと、適用開始が早まります。
毎月の介護サービス料を抑える
デイ・訪問・ショートステイ等を含む介護サービスの自己負担(1〜3割)は、世帯単位の月額上限を超えた分が払い戻しされます(施設入所中も対象、食費・居住費は対象外である点に注意)。
上限額は所得区分で変わり、同一世帯の被保険者分を合算できます。多くの自治体では初回申請後は自動払いになりますが、運用は自治体で異なるため確認してください。
実務上のコツは、領収書・利用明細を月単位で保管し、家計簿側に「戻り予定」欄を作ることです。
入金は翌月〜数か月後になるため、資金繰りの見通しを立てられるようにしておきましょう。負担割合(1・2・3割)や年間収入が変わったときは、上限も変動するので、介護保険負担割合証の更新時期に合わせて確認しましょう。
医療と介護をまたいで戻す
医療費が高くなった月は高額療養費で自己負担に上限がかかります。加えて、1年単位(8/1〜翌7/31など)で医療+介護の自己負担を合算し、所定の上限を超えた分を払い戻すのが高額介護合算療養費です。褥瘡治療や感染症による入院・通院が重なった年度は効果が大きく、家族全体の明細を一か所に集めるだけで戻り額が変わることがあります。
手続き先は、医療は加入医療保険(国保・後期高齢者・健保組合等)、介護は市区町村です。入院が見込まれる場合は、病院の医事課で限度額適用認定証の事前発行を確認し、窓口負担自体を抑制することが可能です(原則としてマイナ保険証の適用が求められる)1。
所得・資産基準でさらに下げる
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度は、生計が厳しい世帯の利用者負担(1割等)を一定割合で軽減する仕組みです。対象サービスや軽減率は自治体・事業者の運用差があるため、地域包括支援センターか事業者に直接確認をしてください。
まとめ
入居の成否は、①目的に合う施設を見極めること、②費用を「初期・月額・変動」に分解して可視化することから始まります。
個室/オプションの見直しや食事コースの調整で固定費を圧縮し、支払日の調整や備品購入の後ろ倒しで資金の波をならす。保険・金融は“必要額のみ”を原則に、任意後見・家族信託・成年後見などで権限と口座動線を整えてから安全に現金化します。
不動産は、まずリバースモーゲージ/リースバック/賃貸化/駐車場化等を実質利回りで比較し、それでも売却なら専任媒介+期間設定、近隣成約相場に沿った初期価格、2〜3週の反応を見た段階的な見直しで“売れ残り”を防ぐのが定石です。
最後に、公的な補助・軽減制度を重ねて手取り負担をさらに下げる。数字と手続きを積み上げれば、「払えない」は具体的な計画に変わります。
▼関連記事:介護施設に入った親の家を売却・賃貸するには?手続きの流れを解説します