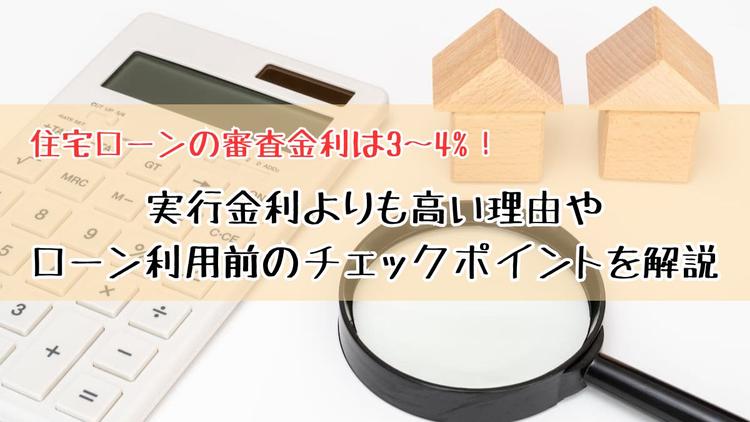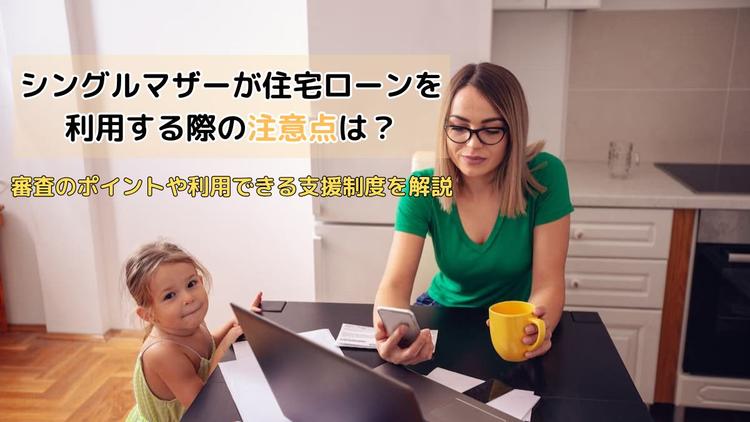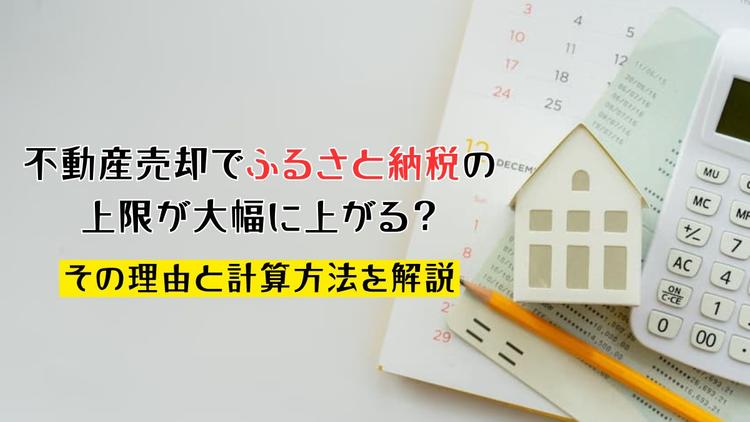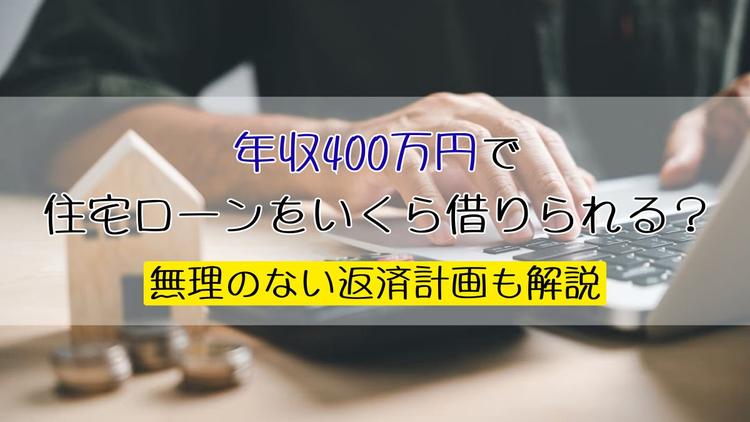住宅ローンの審査では、審査金利を用いられるのが一般的です。
審査金利は店頭金利や実行金利とは異なるので、違いや設定について理解しておくことが重要です。
この記事では、住宅ローンの審査金利の基本や相場、高い理由について詳しく解説します。
あわせて、住宅ローンを選ぶ際に押さえておきたいポイントも紹介するので参考にしてください。
住宅ローンの審査金利とは
住宅ローンの金利には、主に以下の3種類があります。
- 審査金利
- 店頭金利
- 実行金利(適用金利)
それぞれ金利や使われ方が異なるため、違いを理解しておくことが大切です。
ここでは、種類別の違いに触れながら審査金利の基本をみていきましょう。
住宅ローン審査時に用いられる金利
「審査金利」とは、住宅ローン審査時に用いられる金利です。
それに対し、各金融機関が提供する住宅ローンの金利(定価)が「店頭金利」です。
住宅ローンの広告やホームページに記載されている金利は店頭金利になります。
店頭金利からさらに割引や優遇を適用し、実際に住宅ローン融資実行時に適用されるのが、「実行金利(適用金利)」です。
審査金利は店頭金利、実行金利とは異なり、審査の際にのみ用いられる金利です。
そのため、店頭金利で借りられるかシミュレーションしていると、審査金利との差で審査に通らない場合があるので注意しましょう。
実行金利より高い金利が採用されるのが一般的
住宅ローンの審査では、個人の年収や勤務先、勤続年数など、さまざまな項目をもとに「融資しても大丈夫か」「いくらまで融資できるか」を判断されます。
もし審査金利が実行金利よりも低いと、実際に融資を受けた後に返済が厳しくなる恐れがあるでしょう。
一方で、審査金利を高めに設定しておけば、将来的に実行金利が今より上がっても返済を続けられる可能性があります。
このように、審査金利は実行金利よりも高く設定され、将来に渡り問題なく返済できるかを判断するために用いられているのです。
住宅ローン審査金利の相場は?
では、審査金利はどれくらいに設定されているのでしょうか。
ここでは、住宅ローン審査金利の相場についてみていきましょう。
住宅ローン審査金利の相場は3~4%程度
住宅ローン審査金利は、基本的にほとんどの金融機関で明確な数値を公表していません。
一般的には、店頭金利に2~3%ほど上乗せした金利3~4%ほどが相場と言われています。
先述したように、審査金利を店頭金利よりも低く設定すると意��味がないため、同程度以上であると考えられることからも、3~4%程度でシミュレーションしておくと安心でしょう。
ただし、審査金利の数値や、そもそも審査金利を利用しているかは金融機関によって異なります。
住宅ローンの審査方法は金融機関によっても異なるため、同じ条件でも審査に通る金融機関もあれば落ちる金融機関もあることは覚えておきましょう。
住宅金融支援機構のフラット35は実行金利と審査金利が同じ
ほとんどの金融機関で審査金利については明確にしていませんが、住宅金融支援機構のフラット35については、審査時の返済比率は実行金利で算出するとされています。
たとえば、2025年7月の最頻金利は1.84%です。
住宅ローンの「最頻金利」は、実際に利用者が借り入れた住宅ローンの中で、最も多く選ばれている金利水準を指します。
つまり、2025年7月のフラット35は1.84%で借り入れている人が一番多く、審査時もこの金利が参照される場合が多いということです。
民間の金融機関では審査金利が3~4%であるのに対して、フラット35では審査時の金利が低くなるため、審査において有利になる(=同じ金額の借り入れでも審査時点での返済比率が低くなり、借入額を上げられる)可能性があるでしょう。
住宅ローンの審査金利が実行金利より高い理由
住宅ローンの審査金利が実行金利よりも高い理由には、以下の3つが挙げられます。
- より厳しい条件で返済能力を審査する
- 住宅ローン金利の上昇に備える
- 金融機関の損失リスクを低減する
それぞれ見ていきましょう。
より厳しい条件で借入能力を審査する
住宅ローン審査では、年収などから個人の借入能力(返済能力)がチェックされます。
審査の際の基準となる審査金利が低いと審査も緩くなり、本人の借入能力以上の融資になる恐れもあるでしょう。
本人の借入能力以上の融資になると、将来返済できない、返済できても苦しいという好況になりかねません。
審査金利を高く設定し、より厳しい条件で借入能力をチェックすることで、将来の延滞や破綻リスクを避けやすくなります。
住宅ローン金利の上昇に備える
変動金利または固定期間選択型金利で借入する場合、将来金利が上昇するリスクがあります。
借入後に金利が上がると、返済の負担も大きくなり返済できない状況に陥る恐れもあるでしょう。
たとえば、3,000万円を35年ローンで借入れている場合、当初の金利0.5%が5年目で1.5%に上昇すると、毎月の返済額は以下のように変わっています。
- 金利0.5%:77,875円
- 金利1.5%:89,893円
毎月の返済額が1万円以上上昇しており、家計状態によっては生活費を大きく圧迫する恐れもあります。
その点、仮に審査金利が3.0%であれば、1.5%に上昇しても無理なく返済を続けられる可能性が上がります。
このように、審査金利を高く設定することで、将来の�金利上昇リスクに備えやすくなるのです。
ちなみに、審査金利が実行金利であるフラット35は、全期間固定金利タイプです。
借入後に金利が上昇することはないので、実行金利で審査していても大きな影響がないといえるでしょう。
金融機関の損失リスクを低減する
審査金利を高く設定することで、借入する側は将来の返済が延滞、破綻するリスクを下げやすくなります。
同時に、金融機関側も返済されないリスクの回避につながります。
仮に、住宅ローンの返済が滞ると金融機関は競売によりローン残債の回収が可能です。
とはいえ、金融機関にとっては延滞せずに毎月返済してもらった方が利益は大きくなり、反対に延滞や破綻されると損失になる恐れがあります。
そのため、借入する人が長期的に無理なく返済できるかどうかを、審査金利を高く設定して慎重に見極めることが重要になってくるのです。
審査金利から借入可能額を計算する流れ
住宅ローンの審査では、借入の可否だけでなく借入の上限額(借入可能額)も算出されます。
家の購入を検討している際には、あらかじめ借入可能額を把握しておくと無理のない範囲の家を検討でき、住宅ローン審査に通らず家が購入できないとなるリスクを避けやすくなるでしょう。
借入可能額の算出方法は金融機関によっても異なりますが、以下の計算式でもおおよその額を把握できます。
年間返済��額は、返済比率をもとに算出します。
たとえば、年収600万円で返済比率30%の場合、年間返済額は180万円です。
ただし、年間返済額からは他の借入の返済額を差し引く必要がある点には注意しましょう。
この場合、審査金利が3%、返済期間35年と仮定して借入可能額をシミュレーションします。
100万円を審査金利3%で35年借入した場合の毎月の返済額は、3,848円です。
そのため、借入可能額は以下のようになります。
ちなみに、審査金利を1.0%にすると、借入可能額は約5,315万円にアップします。
仮に、3,800万円と5,300万円を金利1.0%で35年ローンを組んだ場合の毎月返済額は、以下のとおりです。
- 3,800万円借入:107,268円
- 5,300万円借入:149,611円
このように、審査金利で借入可能額が大きく変わり、借入可能額ギリギリで借入れると返済額も大きく変わってくる点は覚えておきましょう。
▼関連記事:住宅ローンの平均返済額はいくら?世帯年収別に無理のない返済プランを解説
ローン利用前のチェックポイント
住宅ローンは将来まで大きく関わってくるので、無理なく返済し続けられるかを慎重に検討することが大切です。
ここでは、審査金利以外にも利用前にチェックしておきたいポイントとして以下の3つを紹介しま��す。
- 金利タイプを理解し自分に合った金利タイプを選んでいるか
- 借入可能額ではなく実際に返済できる額をシミュレーションしているか
- 諸費用を把握して総返済額を正確に見積もっているか
それぞれ見ていきましょう。
金利タイプを理解し自分に合った金利タイプを選んでいるか
住宅ローンの金利タイプには、以下の3つがあります。
- 全期間固定金利:返済期間中に金利が変動しない
- 変動金利:一定期間で金利が見直される
- 固定期間選択型金利:一定期間固定金利で以降固定金利か変動金利かを選ぶ
それぞれのタイプによってメリット・デメリットが異なるため、自分に合った金利タイプを選ぶことが重要です。
主なタイプ別のメリット・デメリットは以下のようになります。
| メリット | デメリット | |
| 全期間固定金利 | ・金利上昇リスクを避けられる ・返済計画を立てやすい | ・金利が下がっても返済額が変わらない ・他の金利タイプより金利が高い |
| 変動金利 | ・他の金利タイプより金利が安い ・金利が下がれば返済の負担を軽減できる | ・金利上昇リスクがある ・返済計画を明確にしにくい |
| 固定期間選択型金利 | ・金利が下がれば返済の負担を軽減できる | ・金利上昇リスクがある ・返済計画を明確にしにくい |
変動金利
変動金利は金利が安く、返済の負担を軽減できるというメリットがあります。
しかし、一般的に半年ごとに金利が見直されるため、見直しのタイミングで金利が上昇すると返済の負担が増えるリスクがあるので注意が必要です。
変動金利を選ぶ場合は、繰り上げ返済する、頭金を多く入れるなど金利上昇リスクへの備えもあわせて検討する必要があります。
全期間固定金利
一方、全期間固定金利は金利上昇リスクを避けられますが、他の金利タイプに比べて金利は高くなります。
将来金利が上昇局面になければ、総返済額の負担は大きくなるので注意しましょう。
とはいえ、金利上昇のリスクを気にせずに済むため、安定した返済を希望する人や、金利のチェックなど細かな対策が苦手な人には向いています。
借入可能額ではなく実際に返済できる額をシミュレーションしているか
借入可能額は、あくまで借入できる金額であり、無理なく返済できる額とは異なります。
借入可能額ギリギリで借入すると、将来収入が下がった、支出が増えたといった場合で、返済が難しくなる恐れがあるので注意しましょう。
借入額を考える際には、長期に渡り無理なく返済できる額であることが大切です。
適切な金利プランや借入額は、長期的なライフプランを踏まえた返済計画をもとに慎重に判断するようにしましょう。
自分のシミュレーションだけでは不安という方は、ファイナンシャルプランナー(FP)や不動産会社などのプロに相談することを�おすすめします。
諸費用を把握して総返済額を正確に見積もっているか
住宅ローンを借入する際には、以下のような諸費用が発生します。
- 金融機関の事務手数料
- 保証会社の保証料
- 保険料
たとえば、事務手数料は定率型で借入額×2.2%が一般的です。
仮に、3,000万円借入すると手数料は66万円になります。
手数料込みで借入できるケースも多いですが、その分返済の負担は大きくなります。
借入する際には、諸費用まで含めた借入額や返済額を把握するようにしましょう。
まとめ
住宅ローンの審査の際には、審査金利が用いられるケースがあります。
審査金利は3~4%と実行金利よりも高く設定されているのが一般的なため、実行金利でシミュレーションしていると審査に不利になる恐れがあるので注意しましょう。
住宅ローンに通るか、いくら借りられるかは住宅購入の大きな関門です。
住宅ローンに不安がある方は、不動産会社などのプロに相談しながら、適切なローン計画を立てられるようにするとよいでしょう。