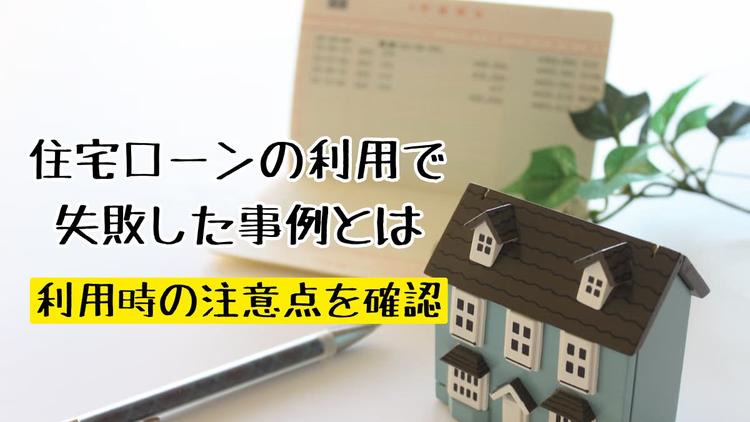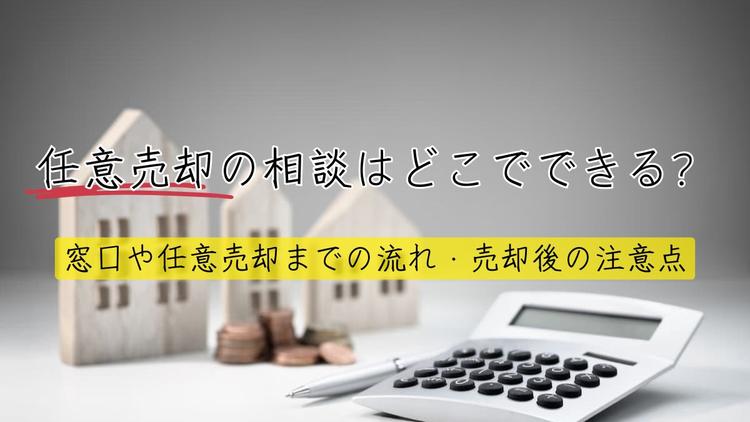住宅や建物を新築・リフォームする際、多くの人は「住み心地の良さ」や「設備の充実」に目が向きがちです。
しかし、それらの設備が固定資産税の評価額に影響し、結果として毎年の税負担を増加させる可能性があることをご存じでしょうか。
本記事では、固定資産税が高くなる主な設備や注意点、事前に確認すべきポイントについて解説します。
固定資産税の基本的な仕組み
住宅や土地を所有していると、毎年課されるのが「固定資産税」です。
これは、不動産を保有している限り発生する継続的な負担であり、家計や不動産の維持計画に大きく関わってきます。
まずは、固定資産税がどのように計算されるのか、その仕組みを正しく理解しておきましょう。
固定資産税とは
固定資産税は、土地・建物・償却資産(事業用資産)を所有している人に課される市町村税(東京23区では都税)です。
課税の基準日は毎年1月1日で、その時点で登記上の所有者となっている人に対し、その年の税額が課されます。通知書は通常4~6月頃に送付され、年1回または数回に分けて納付します。
税額の計算方法
固定資産税の税額は、次の計算式で求められます。
ここでいう課税標準額とは、原則として「固定資産評価額」のことです。
この評価額は、市町村が定めた評価基準に基づき、土地・建物ごとに個別に算出されます。
なお、自治体によっては税率を1.5%や1.6%に引き上げている場合もあるため、実際の負担額には地域差があります。
また、都市計画区域内の不動産については、「都市計画税」が別途かかることがあり、この税率は0.3%以内と法律で上限が定められており、標準税率は0.3%です。
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に請求される。なお、一般的に「固定資産税」と呼ばれるのは、固定資産税と都市計画税を合算したものであるケースが多い。
建物の評価額の決まり方
建物の評価額は、「再建築価格方式」によって算出されます。
これは、同じ建物を再び建てるとした場合にかかる費用(再建築価格)をもとに、経年劣化などを反映した「減価補正率」をかけて求める方法です。
具体的には、建物の構造(木造・鉄骨造など)、延べ床面積、仕上げ材、設備内容(キッチン・浴室・空調など)といった要素が細かく点数化され、その合計が評価額に反映されます。
つまり、設備や仕様が充実しているほど再建築価格は高くなり、それに伴って固定資産税も高くなるという仕組みです。
評価額は定期的に見直される
固定資産税の評価額は、土地・建物ともに3年に1度の「評価替え」によって見直されます(基準年度:2021年、2024年、2027年、2030年…)。
ただし、この評価替えは個別に現地調査を行うのではなく、あくまで市町村が定めた基準に基づく一律の見直しです。そのため、実際の劣化状況や市場の動きとはズレが生じることもあります。
この評価タイミングを把握しておけば、新築やリフォーム後に固定資産税がどのように変化するかを、あらかじめ予測することができます。
固定資産税が高くなる主な設備
新築やリフォームにあたって住宅設備を充実させることは、快適な住まいづくりにおいて重要な要素です。
しかし、こうした設備の中には「建物の評価額を上げる要因」となるものもあり、結果として固定資産税の増加につながる場合があります。
ここでは、固定資産税が高くなる主な設備について具体的に見ていきましょう。
高級仕様のキッチン
システムキッチンは、設置状況によっては建物と一体とみなされ、固定資産税の課税対象となることがあります。
特に、アイランド型キッチンや、天然石(大理石など)を用いたカウンター、ビルトイン型の食洗機・オーブン・IHコンロなどを備えた高級仕様のキッチンは、評価額が高くなるでしょう。
また、収納の作り付けや造作家具なども、場合によっては課税対象に含まれることがあります。
床暖房や全館空調
取り外し可能な家電(エアコン等)は、固定資産税の課税対象にはなりません。
一方で、床暖房や全館空調のように建物に埋め込まれている設備は、「建物の構造の一部」とみなされ、課税対象となります。
特に、全館空調は設置費用が高額なため、再建築価格に大きく反映され、評価額が押し上がる要因になるのです。
浴室のグレードアップ
一般的なユニットバスに比べて、在来工法による浴室や、浴室テレビ・ミストサウナ・ジェットバスなどの特殊機能付き浴槽を導入している場合は、設備費用が評価に影響します。
- ユニットバス:あらかじめ工場でつくられたパーツを現場で組み立てるタイプ
- 在来工法:タイルや防水加工を使って一つひとつ組み立てるオーダーメイドタイプ
さらに、タイル張りの高級内装や、温泉風呂のような機能を備えた浴室も、評価額の加算要素です。
ホームエレベーター
戸建て住宅でも、2階以上の移動のためにホームエレベーターを設置するケースが増えていますが、これも課税対象設備になります。
エレベーターは構造物と一体化しており、評価額への影響が大きい代表例の一つです。
地下室や屋上バルコニー
地下室やルーフバルコニーは、居住面積には含まれない場合でも建物の構造とみなされるため、評価対象になります。
特に、地下室は建設コストが高く、構造も複雑なため、再建築価格が高く評価されやすい傾向にあります。
ビルトインガレージ
車庫を建物内部に組み込んだ「ビルトインガレージ」は、延床面積に含まれるため、その分建物評価額が増加します。独立したカーポートとは異なり、構造の一部として扱われるため注意が必要です。
シャッター付きで内装が整っているものほど、高評価となります。
趣味室・シアタールームなど
設備面だけでなく、特殊な用途のために設けられた部屋や設備(防音室、大型プロジェクター用の造作スペース、音響設備など)も、建築費用に応じて評価額が上がる要因となります。
特に、間仕切りや壁材が専用設計の場合、加算対象になる可能性が高いです。
▼関連記事:一戸建ての固定資産税の平均は10〜15万円!計算手順や軽減措置も解説
新築・リフォームの際に注意したい評価ポイント
住宅の新築やリフォームを行う際、多くの人は建築費やデザイン、快適性に目を向けがちですが、長期的な費用として見落とされやすいのが「固定資産税」です。
設計や設備の選択次第で、税額が思わぬ形で増える可能性があるため、事前に評価のポイントを把握しておきましょう。
建物と一体とみなされるかどうかが課税の分かれ目
固定資産税で評価対象となるのは、「建物に固定された設備」です。
たとえば、床暖房や全館空調のように建物の構造に組み込まれているものは課税対象ですが、置き型のエアコンや家電製品は対象外です。キッチンや浴室の設備も、造り付けかどうか、グレードがどれほどかによって評価額に影響します。
設計段階で「設備が取り外し可能かどうか」を意識しておくと、不要な税負担を避けるための手助けになるでしょう。
ビルトインの構造物は延床面積に含まれる
ビルトインガレージや収納スペース、地下室など、建物の内部に組み込まれている空間は「延床面積」に含まれるため、建物全体の評価額が上がります。
たとえば、独立したカーポートであれば原則として課税対象外ですが、建物と一体化している場合は課税対象となります。
延床面積が増えれば再建築価格が上がり、固定資産税にも反映されるため、スペース設計には注意が必要です。
設計図面と現況との整合性が評価に影響
新築や大規模リフォームを行った場合、翌年に自治体の「固定資産評価員」が現地調査を行います。
この調査では、提出された建築確認申請図面と現況が一致しているかど�うかが評価の基礎となります。
もし未申告の増築や設備の追加があると、後年の評価替え時に課税漏れを指摘され、さかのぼって課税されることもあるため注意が必要です。
また、自治体によっては、完成後に所定の申告書類の提出が義務づけられていることもあるため、事前に所管の市区町村に確認しておきましょう。
高額設備の導入には長期的視点が必要
設備のグレードアップによって快適性が向上すれば、生活の質も高まります。
ただし、初期費用だけでなく、それに伴って増加する固定資産税も踏まえて、総合的に判断することが重要です。
特に、ホームエレベーターや音響室、サウナルームといった不要不急の高額設備は、評価額に大きな影響を与える可能性があります。
本当に必要な設備かどうか、ランニングコストも含めて慎重に検討することが望まれます。
税額を抑えるための工夫とアドバイス
固定資産税は、建物を所有している限り毎年課税されるため、長期的に見ると大きなコストになります。
新築やリフォームの際には、快適性やデザイン性だけでなく、税負担を意識した工夫も取り入れることが重要です。
ここでは、固定資産税の負担を抑えるために実践できる具体的な対策やアドバイスを紹介します。
固定資産評価の対象となる設備を理解する
前提として、「建物の構造と一体とみなされる設備」は課税対象であることを認識しておきましょう。
たとえば、床暖房や全館空調、ビルトインタイプのキッチン設備や浴室設備などは、評価額を押し上げる要因となります。これに対して、後付けが可能な家具や家電は課税対象外です。
住宅設備を選ぶ際は、「建物と一体か」「取り外しが可能か」を意識することで、無用な評価額の上昇を回避できます。
延床面積の増加を慎重に検討する
建物の評価額は、延床面積によっても大きく左右されます。
地下室やビルトインガレージ、屋上バルコニーなど、延床面積に含まれる構造を追加すると、その分評価額が上がり、結果として固定資産税の負担も増加します。
収納スペースや駐車スペースを設けたい場合は、建物とは独立した形で設ける(外部の物置やカーポート)ことで、課税対象外となるケースもあります。
ただし、物置でも基礎がある構造の場合には課税される可能性があるため、事前に自治体へ確認することが大切です。
減額制度・特例措置の活用
固定資産税には、一定の条件を満たすことで減額される制度があります。
代表的�なものとしては、以下のような特例措置があります。
- 新築住宅の軽減措置……一般的な住宅であれば、120平方メートルまでの部分について新築後3年間(長期優良住宅は5年間)、税額が1/2に軽減されます。
- 耐震改修による減額……旧耐震基準の住宅を耐震補強した場合、一定期間の減額措置を受けることができます。
- バリアフリー・省エネ改修の減額……一定の条件を満たす改修工事(手すりの設置、断熱工事など)についても減額の対象になります。
これらの制度を利用するためには、事前の申請や証明書の提出が必要となるため、計画段階でしっかり確認し、工事後は速やかに申請手続きを行うことが重要です。
評価額に疑問がある場合は審査請求も可能
建物の評価額について納得がいかない場合は、「固定資産評価審査委員会」に対して審査請求を行うことができます。
たとえば、過大な設備評価や、劣化が十分に反映されていない場合などは、再評価によって税額が軽減される可能性があります。
ただし、審査請求には提出期限(通常、納税通知書が届いてから3か月以内)があるため、速やかに対応することが重要です。
住宅性能に応じた減税とのバランスも考慮する
高機能な住宅設備や仕様は、固定資産税の評価額を押し上げる要因となりますが、一方で「長期優良住宅」や「省エネ性能の高い住宅」などの認定を受けることで、税額が軽減される特例措置を受けられる場合があります。
たとえば、長期優良住�宅は評価額が高くなりがちですが、新築から5年間は、120平方メートルまでの部分について固定資産税が1/2に軽減されるなど、一定期間の税負担が軽くなる仕組みです。
また、省エネ改修やバリアフリー改修も、一定の条件を満たせば、1年間の税額軽減措置を受けられます。
つまり、住宅性能を高めることで評価額は上がるものの、それに見合った減税制度を活用できれば、トータルでの負担を抑えられる可能性があります。
設備選びの際には、「初期費用」「評価額への影響」「減税制度の有無」の3つをバランスよく考慮することが重要です。
これらの減税制度を利用するには、認定の取得や申請手続き、工事内容が制度の条件に合致していることなどが必要になります。
そのため、計画段階から建築士や住宅メーカー、税理士などの専門家と連携し、制度の適用を見据えた設計・申請を進めることが、無駄のない設備投資につながるでしょう。