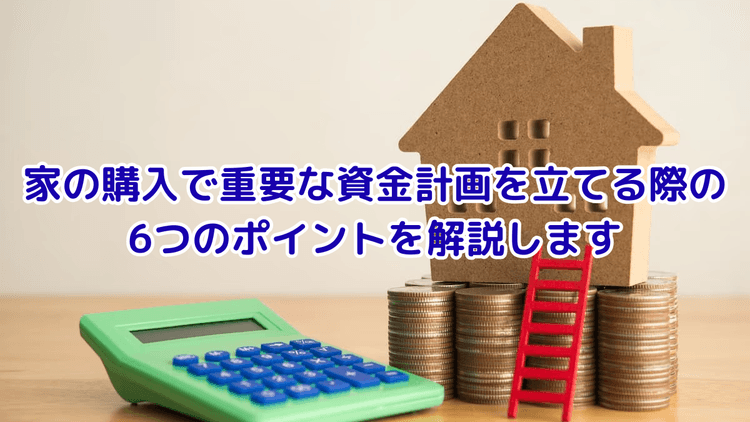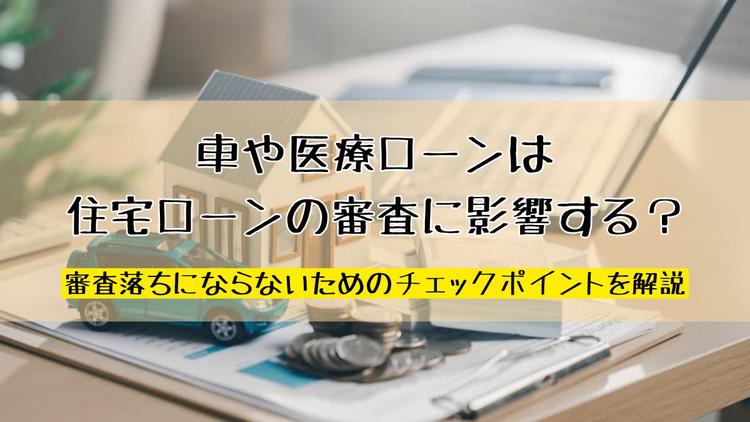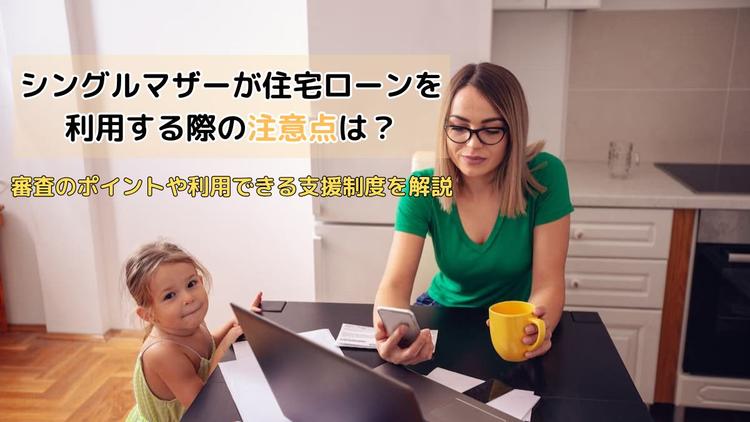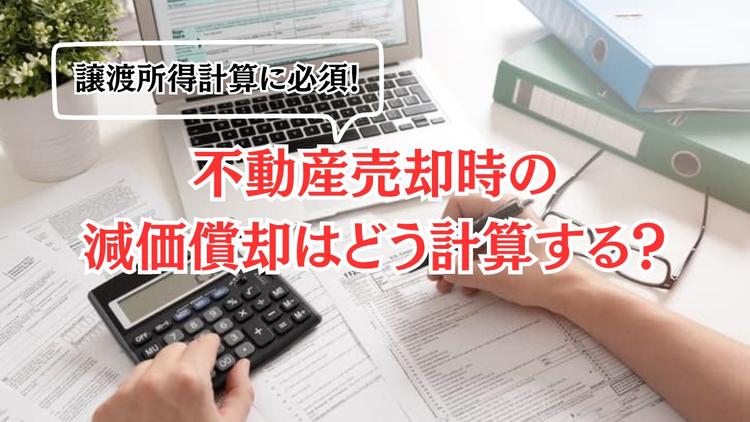家は一生の中でも大きな買い物と言われるほど、購入時には大きなお金が動きます。
家の購入はその後の人生にも大きな影響が出るので、慎重に資金計画を進めることが大切です。
とはいえ、はじめて家を購入するとなると資金計画をどう立てればいいか分からないという方もいるでしょう。
そこで、今回は家購入の際の資金計画を立てるポイントを、流れに触れながら分かりやすく解説します。
家の購入で資金計画を立てる流れ
家の購入では数千万円のお金が必要になるので、資金計画が欠かせません。
資金計画が曖昧なまま家の購入を進めてしまうと、予算オーバーで家選びを一からやり直す必要がある、予算オーバーのままローンを組んで返済が苦しくなるなどの恐れがあります。
家購入の資金計画とは、家の予算を決めるだけではありません。
どのように資金を調達し、どうやって返済していくのかまで長期的な計画を立てることが資金計画です。
具体的には、以下のポイントを押さえながら資金計画を立てていきます。
1. 現在の家計を算出する
2. 土地取得に必要な資金を算出する
3. 建物建築に必要な資金を算出する
4. 諸経費を算出する
5. 住宅ローンの借入額を算出する
6. 家に住んだ後にかかる費用も把握しておく
資金計画がしっかりしていれば、購入費が予算内に収められるだけでなく、購入後も無理のない返済を続けられるでしょう。
以下では、それぞれポイントを詳しく解説するので参考にしてください。
資金計画を立てる流れとポイント1:現在の家計を算出する
家の購入費は住宅ローンだけでなく、頭金として自己資金も必要です。
また、購入後には毎月住宅ローンを返済することになるので、家計状況の把握が必要になります。
毎月追加で負担できる住居費の額を算出する
今の収支を��洗い出し、毎月いくらまでなら住宅ローンの返済に充てられるのかを算出しましょう。
この際、直近の収支だけでなく将来の収支も考慮して住宅ローンの返済額を検討する必要があります。
今の家計なら返済が問題なくても、将来家族が増えて支出が増えたり収入が減少したりすると、返済が厳しくなる恐れがあるので注意しましょう。
また、余裕がある分をすべて住宅ローンに充ててしまうと、自己資金が蓄えられずにいざというときの支出に対応できなくなるので、貯蓄も考慮することが大切です。
家の購入に充てられる自己資金の額を算出する
家の購入費は住宅ローン+自己資金(頭金)で賄うことになります。
そのため、自己資金の額によって住宅ローンの借入額も変わってきます。
自己資金を多く入れれば住宅ローンの借入額が少なくなり、審査に通りやすくなったり、毎月の返済額の軽減が可能です。
一方、自己資金を抑えれば購入時の自己資金が大きく減るのを防げ、その後の支出などにも対応しやすくなります。
なお、預貯金のすべてを自己資金に充てるのはおすすめできません。
家購入後にも税金などの支出があるだけでなく、突発的な支出や収入減少にも備えておく必要があります。
一般的には、生活予備費として毎月の生活費の6か月分があれば安心と言われています。
住宅購入に充てる自己資金はいくらが適しているかは、個々の資産状況などによって異なります。
不安に思う場合は、FPなどのプロに相談するとよいでしょう。
▼関連記事:住宅の購入で親からの金銭支援を受けたら特例が利用できる
資金計画を立てる流れとポイント2:土地取得に必要な資金を算出する
注文住宅を建てる場合、前提として土地が必要です。
そのため、建物の建築費以外に土地の購入費も予算計画に含めておかなければなりません。
土地を持っている場合は土地取得費を抑えることができる
相続した土地がある場合や、親から土地をもらう予定がある場合などで、土地を持っているなら土地の取得費はその分抑えられます。
土地代がかからない分、建物に費用を充てられるだけでなく資金計画もシンプルになりやすいでしょう。
土地を購入する際は、土地代だけでなく不動産会社への仲介手数料や登記費用などの諸費用も掛かるため、トータルの費用を踏まえて、土地にいくらまで予算を割けるかを考えておく必要があります。
また、土地購入費用は住宅ローンの融資実行前に必要になるので、どのように費用を賄うのかも検討することが大切です。
自己資金だけで賄うのが難しい場合は、分割融資やつなぎ融資を検討するとよいでしょう。
- 分割融資:1回の住宅ローン契約で、住宅完成までに複数回に分けて融資を受ける。
- つなぎ融資:住宅ローンとは別に住宅完成までの資金を借り入れ、完成後に住宅ローンに一括で借り換える。
なお、注文住宅ではなく建売住宅であれば、土地+建物で販売されているので、土地代も総額に含まれており、別途土地費用を考える必要はありません。
土地から探す場合は土地と建物どちらにお金をかけるか優先順位を��決めておく
土地も購入する場合は、土地の予算も含めて資金計画を立てる必要があります。
総予算のうちいくらまで土地に充てられるのか、また、土地と建物どちらの優先度が高いかはあらかじめ明確にしておきましょう。
基本的に、要件の良い土地は価格も高くなりがちです。
同じ総予算でも、立地を優先するなら建物にかける費用を見直す必要があるでしょう。
反対に、建物にお金を割きたいなら立地はある程度妥協が必要になってきます。
土地にかける予算や優先度が決まっていないと、土地を購入してから土地で予算オーバーして建物にお金を掛けられなくなったとなりかねないので、注意が必要です。
土地次第で建てられる建物の大きさや必要な諸費用の額が変わる
建てられる建物の大きさや高さなどは、土地に設けられた規制によって制限されます。
たとえば代表的な規制としては、用途地域ごとに設けられている建ぺい率や容積率・高さ制限などがあります。
そのため、土地を購入しなければ、どのような家が建てられるかを具体的に決めることができない点には注意が必要です。
また、土地によっては、電気・ガス・水道などのライフライン整備費や地盤改良費などが必要になるケースもあり、土地と建物購入費以外の費用も大きく変動します。
土地の購入から始めるケースでは、土地次第で予算計画が大きく変わってくる可能性がある点は覚えておきましょう。
希望の立地が絞れているなら、相場だけでなく建築に対する制限や必要な諸費用までシミュレーションしておくと、資金計画が崩れにく�くなります。
▼関連記事:低層住居専用地域とは?家、土地を購入・売却する際の注意点を解説
資金計画を立てる流れとポイント3:建物建築に必要な資金を算出する
建物建築にかかる費用を算出していきます。
国土交通省の「建築着工統計調査 住宅着工統計」 によると、持ち家・木造一戸建ての1㎡あたりの工事予定額は25万円です1。
また、総務省統計局によると一戸建ての延べ床面積は平均128.64㎡ のため、仮に延べ床面積120㎡の家を建築する場合の、建築費の目安は3,000万円となります2。
ただし、注文住宅の建築費は建築する家や地域・ハウスメーカーによって大きく異なるので、希望するハウスメーカーの商品なども考慮して費用を算出するとよいでしょう。
建物の大きさや性能で費用が変わる
建物の建築費は、基本的に建物の規模が大きくなったり、性能がよくなるほど高くなります。
近年は、高断�熱・高気密といった高性能住宅も増えていますが、これらは性能のいい資材や設備の仕様、特殊な工法などにより、一般的な住宅に比べて建築費が高くなりがちです。
ただ、性能のいい家は光熱費などのランニングコストを削減しやすいので、トータルの費用を考慮して予算と性能のバランスを検討しましょう。
平屋や3階建ては建築費用が高くなりやすい
同じ延べ床面積で建築する場合、もっとも費用が割安になるのはシンプルな2階建てです。
反対に、平屋や3階建ては費用が高くなりやすいので、希望する場合は建築費を多めに組んでおく必要があります。
同じ延べ床面積でも、平屋はすべてを1階部分でまかなうため、基礎や屋根の面積が広くなり、その分建築費が高くなりがちです。結果として、2階建てよりも総費用が高くなる傾向があります。
3階建ては高さが必要になるため、構造計算が複雑になる・地盤改良が必要・足場をより設置しないといけないなどで建築費が嵩みます。
建築費を抑えたい場合は、外からみて凹凸の少ない四角形の2階建てにするのが1つの方法です
また、内部の間取りも特殊になると費用が高くなりやすいので注意しましょう。
二世帯住宅を建てて親子でローンを返済する方法もある
二世帯住宅では、親子の収入を合算できる「親子リレーローン」が利用できます。
親子リレーローンとは、当初から一定期間を親世帯が返済し、その後子世帯が返済を引き継ぐローンです。
親子リレーローンであれば、親世帯と子世帯の収入の合計で借入額が決まってくるので、どちらかの収入では��借入額が下がる場合でも合算することで高額な借入が期待できます。
ただし、親子リレーローンは親子が同居するのが条件となるので、注意しましょう。
収入を合算する方法としては、夫婦の収入を合算する収入合算やペアローンがあるので、収入が低くてローンが組みにくい場合は検討するとよいでしょう。
資金計画を立てる流れとポイント4:諸経費を算出する
家を購入する際には、土地購入代金と建物の建築費だけが必要になるのではなく、それぞれ諸経費が発生します。
諸経費まで見込んで資金計画を立てないと、諸経費が入ることで予算オーバーしてしまうリスクがある点には注意しなければなりません。
諸経費の内訳
土地と建物を購入する際の諸経費としては、以下のようなものが挙げられます。
| 土地購入関連 | 建物購入関連 |
| 仲介手数料 印紙税 登記費用 不動産取得税 など | 地盤改良費 ライフラインの引き込み費用 登記費用 印紙税 設計や申請などの手数料 |
なお、ライフラインの引き込み費用などは諸経費ではなく付帯工事費に含まれる場合もあるので注意が必要です。
また、住宅ローンを組む際にも金融機関の手数料や保証料・登記費用などが発生します。
諸費用は、一般的に土地代金+建築費の10%ほどが目安と言われています。
仮に、土地+建物で4,000万円のとき400万円ほど諸費用がかかってくるため、諸費用もシミュレーシ��ョンしたうえで資金計画を立てるようにしましょう。
住宅会社によって諸経費は変動する
建物建築の際の諸費用は、依頼する住宅会社によって大きく異なります。
注文住宅を建てる際の費用の内訳は、大きく次の3つです。
- 本体建築工事費
- 付帯工事費
- 諸経費
どの項目が建築費で何が諸費用にあたるのか、諸費用以外で追加料金が発生しないかは慎重に確認することが大切です。
住宅会社によっては、広告に表示する建物価格を安く見せるために、建築価格が少なく反対に諸費用が高くなるケースもあるので注意しましょう。
建物を購入する際には、建物価格だけでなく諸費用や追加費用まで含めたトータルで考えることが重要です。
庭が広いと外構費用は高くなりやすい
外構費とは、駐車場や庭・フェンスなど、敷地内で建物以外にかかる工事の費用で、付帯工事費に含まれます。
外構費用は庭が大きい・庭のデザインをこだわるといった場合で高くなりやすいので注意しましょう。
また、外構を住宅会社でなくエクステリア(外観部分)の専門業者に別途依頼する場合は、別に費用を計画しておく必要があります。
地盤調査は土地決済後でないとできないケースが多い
土地から購入する場合、建物を建てる前には地盤調査が必要です。
地盤調査は基本的に土地の購入後に行うため、調査の結果地盤改良が必要になると別途改良費がかかってきます。
地盤改良は数十万円かかるので、あらかじめ必要になることを想定して予算を立てておくとよいでしょう。
土地の売�主によっては保有している地盤調査報告書を見せてくれるケースもあるので、相談するのもおすすめです。
なお、土地購入前は土地の所有者は売主になるので、勝手に地盤調査は行ないので注意しましょう。
仮に、購入前に承諾を得た場合でも、費用の負担や調査後の対応などでトラブルになりやすいので注意が必要です。
資金計画を立てる流れとポイント5:住宅ローンの借入額を算出する
家の購入ではほとんどが住宅ローンを利用します。
そのため、住宅ローンでいくら借入するのかを明確にしておくことが大切です。
家を建てるのに必要なトータルの費用から自己資金額を差し引いた額を算出する
注文住宅を土地の購入から行う場合、家を購入するのに必要な費用は以下の合計です。
- 土地購入費用と土地購入時の諸費用
- 注文住宅の購入費用(建築費+付帯工事費+諸費用)
- 住宅ローンを組むための諸費用
- その他の費用(家具家電購入や引越し費用など)
これらの費用を「住宅ローン+自己資金(頭金)」で賄うことになります。
そのため、家の購入に必要な費用を算出し、頭金に充てる自己資金を明確にしたら、残りが住宅ローンで必要な額です。
なお、諸費用などを住宅ローンに組み込めるかは金融機関によって異なるので、注意しましょう。
また、住宅ローンは家が完成してから融資が実行されるので、それ以前に発生する土地購入代金や着工金・中間金をどのように賄うかを明確にしておくことが大切です。
自己資金だけで賄えない場合は、つなぎ融資や分割融資を視野に入れるとよいでしょう。
借入可能額を超える場合は土地や建物を見直す必要がある
住宅ローンは希望する額を借りられるわけではなく、金融機関から判断された借入可能額内での借入となります。
借入可能額を超えての借入はできないので、先の計算で必要な住宅ローン額が借入可能額を上回る場合は、予算の見直しが必要でしょう。
なお、借入可能額は金融機関によっても異なります。
金融機関のサイトには借入可能額のシミュレーションができるツールが設けられているケースもあるので、活用して自分の借入可能額を把握しておくようにしましょう。
どうしても借入可能額が足りない場合は、親子リレーローンやペアローンを検討するのも1つの方法です。
返済していける額から借入額を決めることが大切
住宅ローンで借りる額を決める際、借りられる額ではなく返せる額で判断することが大切です。
借入可能額はあくまで借入できる上限額であり、無理なく返済し続けられる額とは異なります。
借入可能額ギリギリでローンを組むと、支出が増えた・収入が減った際などで大きな負担となる恐れがあるので注意が必要です。
将来的なライフプランを含めて長期的な返済シミュレーションをしたうえで、無理なく返済し続けられる額で借り入れるようにしましょう。
資金計画を立てる流れとポイント6:家に住んだ後にかかる費用も把握しておく
家を購入すると、所有期間中は固定資産税や修繕費といったランニングコストもかかってきます。
資金計画を立てるう�えでは、購入費だけでなく長期的な家にかかる費用も考慮することが大切です。
不動産取得税は引っ越してしばらく経ってから費用を請求される
不動産取得税とは、不動産を購入した際にかかる税金です。
家を購入する場合、土地購入時と家購入のそれぞれで不動産取得税が課税されます。
不動産取得税の税額は以下のとおりです。
不動産取得税:不動産評価額×4%(年度や不動産種類によって軽減が適用)
たとえば、土地+建物の評価額が4,000万円なら不動産取得税は160万円となります。
ただ、不動産取得税は購入時に支払うのではなく、購入後半年ほどしてから自治体から納税通知書が送られ納税するものです。
自治体によっては1年後というケースもあるので、家の購入ですべての資金を使い果たすと納税に対応できないとなりかねません。
購入後時間をおいて納税が必要になる点を考慮して、資金計画を立てておくようにしましょう。
毎年固定資産税を支払う必要がある
土地と建物はそれぞれ固定資産税の対象となり、毎年固定資産税が課税されます。
固定資産税はその年の1月1日時点の所有者に課税されるので、土地を購入した年は売主と所有期間に応じて按分するのが一般的です。
一方、新築の建物については建築した翌年から課税されます。
固定資産税の税額は以下のとおりです。
税率はほとんどの自治体で1.4%ですが、異なる自治体もあるので調べるようにしましょう。
また、不動産の所在地によっては都市計画税も対象です。
固定資産税・都市計画税は不動産によっても異なりますが、年間10~30万円ほどかかるので、あらかじめ納税の資金計画も立てておくようにしましょう。
修繕費も想定しておくのがおすすめ
マンションであれば、毎月修繕積立金や管理費を支払うことで、マンションの維持管理が行われます。
しかし、持ち家のメンテナンスや修繕は自分で行う必要があり、その費用も計画的に蓄えておかなければなりません。
たとえば、外壁や屋根は定期的な塗り替え・葺き替えが必要になり、1回のメンテナンスで数十万円や百万円以上かかります。
他にも、老朽化の修繕や故障した設備の交換・台風による突発的な修繕費なども発生するものです。
修繕費用を貯えておかないと修繕できずに家の劣化が進んでしまいかねないので、事前に修繕計画と資金計画も立てておくようにしましょう。
まとめ
家の購入では、大きなお金が動くので入念な資金計画が欠かせません。
家の購入では建築費以外にも、土地代や諸経費などさまざまな費用がかかります。
さらに、購入後にも税金や修繕費などが必要です。
これらの費用がいくら必要でどのように調達し、返済し続けるのかを明確にしておくことで、満足いく家の購入ができ購入後も安心して返済し続けられるようになります。
資金計画を立てる際には本記事のポイントを参考に、トータルの費用を考慮して計画するようにしてください。