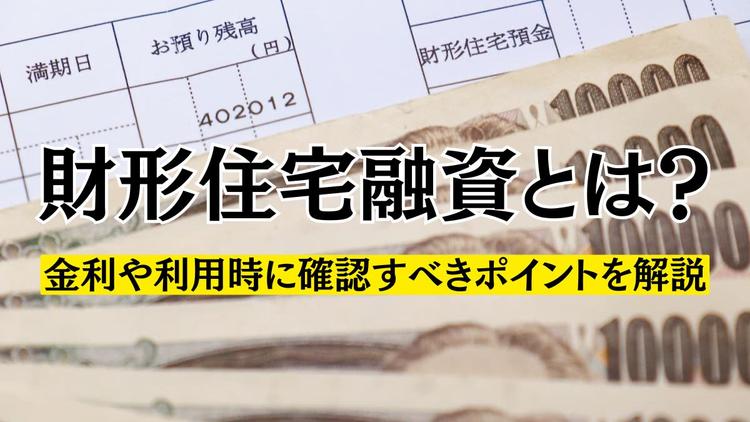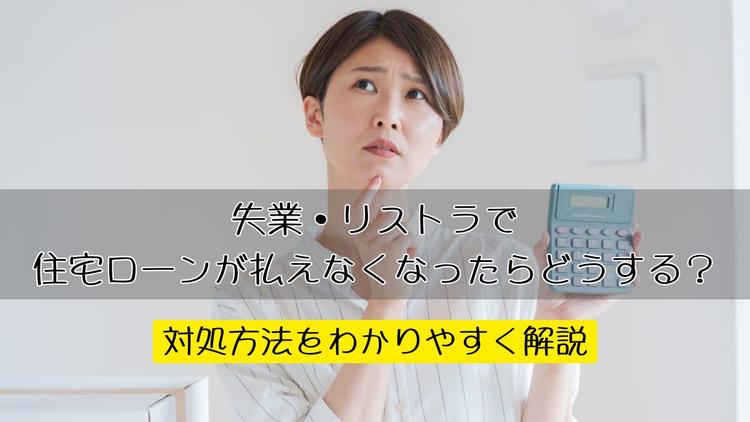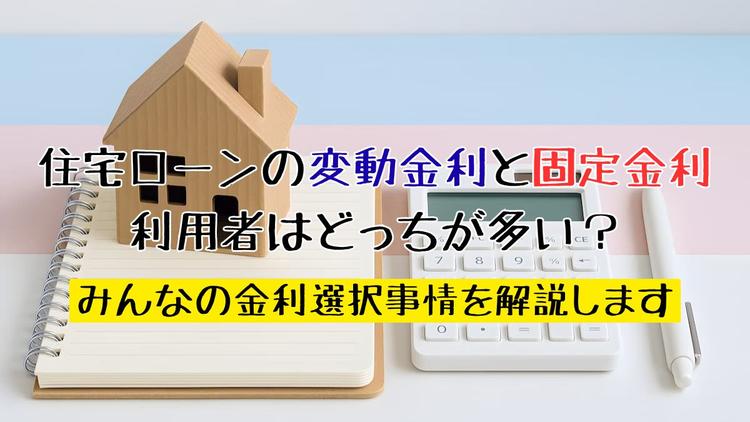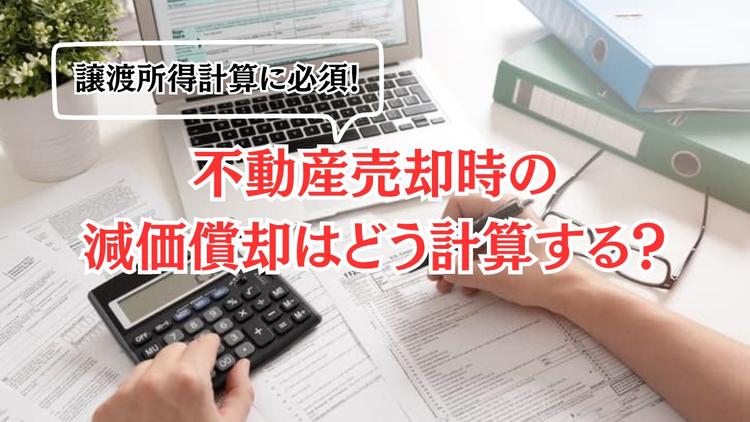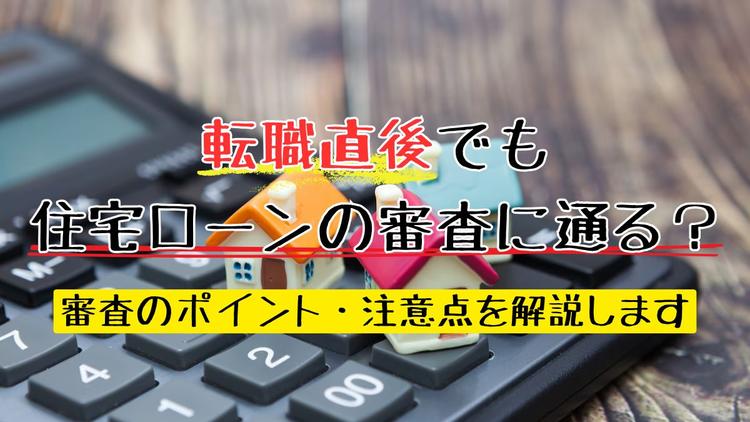マイホームを購入するなら、少しでも有利な条件で住宅ローンを組みたいと考えるのが当然ですよね。そこで重宝するのが、企業に勤めている人なら利用できる「財形住宅融資」です。
しかし、財形住宅融資について「聞いたことはあるけれど、どういう仕組みなのか分からない」「財形貯蓄をしているけど、実際に使えるのか不安」と感じている人もいるのではないでしょうか。
そこで、当記事では財形住宅融資の基本的な仕組みや金利の特徴、利用するための条件、メリット・デメリットまで、初心者にもわかりやすく解説します。
財形住宅融資の仕組みと特徴
財形住宅融資は、財形貯蓄をしている勤労者を対象とした公的な住宅ローン制度です。
企業で働く人が、自分の給与から積み立てた財形貯蓄を担保にすることで、民間の住宅ローンよりも有利な条件で借り入れることができます。
以下では、財形住宅融資の基本的な仕組みと特徴について、順を追って解説していきます。
そもそも「財形貯蓄」ってどんな制度?
財形貯蓄とは、企業に勤める人が給与から自動的に積み立てる制度です。主に「一般財形」「財形年金」「財形住宅」の3種類あります。
一般財形は使い道に制限が無いのに対して、年金型と住宅型は老後資金や住宅を購入するなど明確な目的が設定されています。
一定の条件を満たすことで、財形年金と住宅貯蓄は合わせて550万円まで利子が非課税になるなど、税制優遇が受けられるのが大きなメリットといえるでしょう。
しかし、決められた目的以外の理由でお金を引き出すと、過去にさかのぼって課税される点に注意が必要です。
例えば、マイホームを購入するために財形住宅貯蓄で積み立てているとします。その資金を車の購入や教育費などに使った場合、非課税扱いだった利子に対して約20%の税率で課税されます。
財形貯蓄を担保にした固定金利ローン
財形住宅融資は、勤務先を通じて行う財形貯蓄制度を利用して一定額以上の貯蓄を行っていることを条件に受けられる公的住宅ローンです。
財形貯蓄の残高を担保にする仕組みであるため、原則として残高が50万円以上あることが利用の前提となります。
金利の点でも、民間住宅ローンとは性質が異なります。民間ローンでは、変動金利型・固定期間選択型・全期間固定型などから金利タイプを選べるのが一般的ですが、財形住宅融資では固定金利(公的固定金利)のみが適用されます。
そのため、選択肢の自由度は低いものの、一定の条件を満たせば低金利で借りられる特例措置も用意されており、金利が返済期間中に変動しないため返済額が予測しやすいというメリットがあります。
金利は5年固定制で申込から5年間適用される
財形住宅融資の金利は、5年固定金利制が採用されています。具体的には、5年ごとに金利の見直しが行われて、5年間は金利が固定されるという制度です。
例えば、借入の申し込みをした時点で金利が2.5%なら、最初の5年間にわたってその金利が適用されます。
また、財形住宅融資の金利には、上限や下限といった制限がない点も留意すべきポイント。なぜなら、金利の見直しがされたタイミングで金利が大きく上昇した場合、返済額が増加する恐れがあるからです。
3つの条件を満たす範囲で借り入れが可能
財形住宅融資では「いくらまで借りられるか」が明確に定められている点も、民間ローンとは若干異なります。
民間ローンの場合、申込者が借入れしたい金額を申告し、金融機関が厳しく審査したのちに融資額が決定します。
一方、財形住宅融資は以下のように3つの借入上限と条件が定められています。これらの条件を満たす範囲で借入が可能です。
①財形貯蓄残高の10倍まで
財形貯蓄をきちんと積み立ててきた人に多くの融資枠を与えるためのルールです。貯蓄残高が70万円あれば、その10倍にあたる700万円までが上限となります。
②取得価格の90%以内
購入・新築・増改築にかかる費用のうち、90%までが融資の対象になります。総額3,000万円の住宅を取得する場合、融資上限は2,700万円です。
③最大4,000万円まで
借入額の上限は一律4,000万円までと決まっています。希望する物件の価格が4,000万円以上だったとしても、上限を超えて融資を受けることはでき�ません。
実際に借りられる金額は、これら3つの条件の中で最も低い金額となります。
例えば、財形残高が70万円、物件価格が3,000万円というケースでは以下のようになります。
②物件の取得価格の90% = 2,700万円
③財形住宅融資の借入上限 = 4,000万円この中で最も低い700万円が実際に借りられる上限額となります。
返済期間は最長35年・完済は70歳まで
財形住宅融資では、返済期間と完済時年齢が定められているのも特徴のひとつです。返済期間は一般的な住宅ローンと同様に、最長35年と定められています。
一方、完済時の年齢は70歳未満と義務付けられており、民間のローンに比べると厳しめに設定されている点が異なります。
例えば、35歳で融資を受けた場合は35年返済が可能です。しかし、40歳で借りた場合は最長でも30年まで、50歳なら20年までしか借りることができません。
財形住宅融資は若い世代に多くのメリットがある半面、高齢になってから借入を検討している人にとっては高いハードルになる可能性もあります。
財形住宅融資を利用するための主な利用条件
財形住宅融資は、公的な制度ではありますが、誰でも自由に利用できるわけではありません。次のような一定の条件を満たしている必要があります。
- 勤務先が財形制度を導入している必要がある
- 1年以上の継続と過去2年以内の定期的な積立実績がある
- 申込時に財形残高が50万円以上あること
以下では、財形住宅融資を申し込むうえで知っておく�べき主な利用条件について、分かりやすく解説していきます。
勤務先が財形制度を導入している必要がある
財形住宅融資を利用するには、勤務先が財形貯蓄制度を導入していることが前提となります。
財形貯蓄は、会社から受け取る給与の中から毎月一定額を天引きして、自動的に積み立てていく制度です。
企業が財形貯蓄制度を導入していなければ、そもそも財形住宅融資を利用することができません。
財形住宅融資を利用してマイホームの購入を検討している人は、勤務先が財形制度を導入しているかを、人事・総務部門や福利厚生担当に確認しましょう。
1年以上の継続と過去2年以内の定期的な積立実績がある
財形住宅融資を申し込むには、財形貯蓄を1年以上継続して行っていることに加えて、申込日の2年前から現在にかけて、定期的に積立を続けていることが求められます。
積み立て期間は1年としていますが、通算で1年間貯蓄したという意味ではありません。継続して12か月以上、毎月積み立てを行っていることを指しています。
例えば、以下のようなケースでは条件を満たしていないとみなされます。
- 最近積み立てを始めたばかり
- 過去に積み立てを中断した期間がある
- 一時的に積み立てをしているだけ
- 2年以内に積立実績がない
財形住宅融資を検討している場合は、事前に積立履歴を確認することをお勧めします。不明な点があれば、早めに勤務先や金融機関へ相談しておきましょう。
申込時に財形残高が50万円以上あること
財形住宅融資を申し込むには、申込時点で50万円以上の財形貯蓄残高��があることが求められます。対象となるのは「財形住宅貯蓄」または「財形年金貯蓄」の残高です。
申込日時点で残高が50万円を下回っている場合は申し込みができません。また、一般財形は対象外となるため注意しましょう。
財形住宅融資のメリット
財形住宅融資には、民間の住宅ローンとは異なる公的制度ならではの次のようなメリットがあります。
- 低金利の公的融資を利用できる
- 保証料がかからず費用を抑えられる
- 団信に加入するか選べる自由度
以下では、財形住宅融資を活用することで得られる主なメリットを解説します。
低金利の公的融資を利用できる
「財形住宅融資」では、公的固定金利(5年間据え置き)が採用されており、借入時に決定された金利が原則5年間は変更されません。これにより、返済額が一定期間変わらないため、返済計画を立てやすいというメリットがあります。
また、民間の住宅ローンと比較しても金利が低めに設定されている点も大きな特徴です。
たとえば、2025年5月現在の民間住宅ローンの全期間固定金利は年1.8%~2.7%前後で推移しています。
これに対して、財形住宅融資の金利は、一定の条件を満たすことで特例措置が適用され、年1.7%程度で借り入れることが可能です。
一方、民間の変動金利型ローンは年0.3%〜0.7%前後と一見すると低金利に見えますが、将来的な金利上昇リスクがあるため、長期的な安定を重視する方には向かない場合もあります。
したがって、財形住宅融資は、金利上昇リスクを避けたい方や、返済額を一定に保ちたい方に適した選択肢といえ��るでしょう。
▼関連記事:変動金利は一気に上がる?
保証料がかからず費用を抑えられる
財形住宅融資の大きな特長のひとつとして、保証料がかからないことが挙げられます。
保証料とは、住宅ローンの契約者に万が一のことがあって返済ができなくなった場合に備えて、金融機関が保証会社に支払う費用をいいます。
通常の住宅ローンを利用する場合、契約者は数十万円以上の保証料を一括で支払うか、金利に上乗せする形で負担するのが一般的です。
一方、財形住宅融資では、保証会社を利用せずに金融機関が直接融資を行うため、保証料を支払う必要がありません。
高額の保証料が不要になるため、初期費用を抑えたい人にとって大きなメリットとなります。
財形住宅融資のデメリット
財形住宅融資には、公的制度ならではのメリットがある一方で、利用にあたって次のようなデメリットも存在しています。
- 勤務先で制度を導入していないと利用できない
- 利用条件が厳しく対象者が限られる
- 融資額や対象物件に制限がある
ここでは、財形住宅融資を検討する際に知っておきたい主なデメリットや注意点について、実際に利用する場面を想定しながら分かりやすく解説します。
勤務先で制度を導入していないと利用できない
そもそもの大前提として、勤務先が財形貯蓄制度を導入している、財形住宅融資の取扱が可能な企業でなければいけません。
一般的な住宅ローンであれば、金融機関の窓口で手続きを行うだけで審査を受けることができます��。
それに対して財形住宅融資は、勤務先が制度に対応していなければ融資を利用することができません。
勤務先次第で融資の利用ができない点は、民間ローンにはない財形住宅融資ならではのデメリットといえます。
財形住宅融資の利用を検討する際は、まず勤務先の総務・人事部門などに制度を導入しているかを確認しましょう。
利用条件が厳しく対象者が限られる
財形住宅融資を利用するには、いくつもの条件を満たしている必要があります。
民間の住宅ローンであれば、申し込んだあとは金融機関や保証会社が申込者の信用情報や勤務状況、年齢や収入などをもとにして審査が行われます。
事前審査や本審査を無事に通過したら、融資が実行されるのが一般的な流れです。
一方、財形住宅融資を利用するには、次のような条件を満たしていなければいけません。
- 財形貯蓄を1年以上継続して行っていること
- 借入申込日までの2年以内に定期的に積立をしていること
- 財形貯蓄残高が50万円以上あること
- 申込時に70歳未満で完済時は80歳未満であること
- 申込時に勤務先に在籍していること
これらの条件を満たしていることが前提となっており、融資実行までに退職・転職してしまうと利用できなくなるケースもあります。
財形住宅融資は一般的な住宅ローンと異なり誰でも利用できるわけではありません。対象者が限られた制度である点はデメリットといえます。
融資額や対象物件に制限がある
財形住宅融資では、借入可能額や対象になる物件に制限が設けられています。
民間の金融機関であれば1億円まで、フラット35は8,000万円までを借入限度額としているケースがほとんど。
一方、財形住宅融資は、次の3つの条件の中で最も低い金額が上限となります。
- 財形貯蓄残高の10倍まで
- 物件の取得価格の90%以内
- 最大4,000万円まで
例えば、財形貯蓄の残高が100万円であれば、どんなに物件価格が高くても上限は1,000万円になります。逆に、貯蓄残高が多くても物件価格の90%や4,000万円という制限を超えることはできません。
また、借入ができる物件についても条件が定められています。新築・中古・リフォームいずれも借入は可能ですが、床面積や耐震性などの基準を満たす必要があります。
中古住宅であれば「40㎡以上、280㎡以下」「耐震基準を満たすこと」といった条件が課せられています。これらの条件を満たしていない物件は、制度の対象外となる場合もあります。
収入と物件の状態に応じた範囲であれば希望の金額を借りられる民間の住宅ローンに比べて、財形住宅融資は制限が多いのがデメリットです。
財形住宅融資を利用する前に確認すべきポイント
財形住宅融資は、一定の条件を満たせば低い金利で借入ができるメリットの多い住宅ローンです。
ただし、利用するにはいくつかの条件があるため、誰でもすぐに申し込めるわけではありません。
「マイホームを購入するために財形住宅融資を検討していたけど、条件を満たしていなかったために申し込めなかった」ということもあり得ます。
そこで以下では、財形住宅融資を利用する前に確認しておきたいポイントを解説します。
勤務先が財形住宅融資の対象か
財形住宅融資は、一定の条件を満たさなければ利用できない住宅ローンです。
申し込みに必要な前提条件のひとつが「勤務先が財形貯蓄制度を導入している企業であること」です。
いくら財形住宅融資を利用したいと考えていても、勤務先が制度を導入していなければ利用することはできません。
財形住宅融資を利用してマイホームの購入を検討しているのであれば、まず最初に勤務先の総務部や人事部に問い合わせて、制度を取り扱っているかを確認しましょう。
財形貯蓄の残高が50万円以上あるか
財形住宅融資を利用するには、財形貯蓄の残高が50万円以上あることが絶対条件となります。
財形貯蓄には、一般財形・年金財形・住宅財形の3種類があります。これらを合算した残高が50万円以上であれば、財形住宅融資を利用することが可能です。
例えば、一般財形30万円+住宅財形10万円+年金財形10万円であれば、合計50万円以上になるので条件を満たしたことになります。
積立期間が利用条件を満たしているか
財形住宅融資を利用するには、積立額だけでなく積立期間の条件も満たしていなければいけません。
具体的には、申込日から遡って2年以内に、少なくとも1年以上継続して財形貯蓄を行っている実績が必要です。
たとえ財形貯蓄をしていても、短期間に一括で50万円以上を積み立てたり、積立が途中で中断している場合は条件を満たしていないと判断される可能性があります。
財形住宅融資の申し込みをする前に、積立期間が利用条件を満たしているから、あらかじめ確認しておきましょう。
希望する借入額が条件に収まっているか
財形住宅融資には、次のように3つの借入上限が定められています。
- 財形貯蓄残高の10倍以内
- 取得価格(建物+土地)の90%以内
- 最大4,000万円まで
このうち最も少ない金額が実際の借入限度額になります。
例えば、3,500万円の物件を購入したいと考えたとしましょう。財形貯蓄の残高が300万円しかなければ、借入上限はその10倍の3,000万円となります。
この場合、残りの500万円は自己資金でまかなうか、他の住宅ローンと併用する必要があります。
例えば、以下のような併用パターンが考えられます。
パターン1:財形住宅融資+フラット35
- 財形住宅融資:3,000万円(5年固定金利)
- フラット35:500万円(全期間固定金利)
パターン2:財形住宅融資+民間金融機関の変動金利ローン
- 財形住宅融資:3,000万円(5年固定金利)
- 民間ローン:500万円(変動金利)
併用することで、必要な資金を確保できるだけでなく、金利のバランスを取りながらリスクを抑えることも可能です。
ただし、返済条件や金利タイプが異なるため、無理のない返済計画を立てることが大切です。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございます。今回は、財形住宅融資について解説しました。
財形住宅融資は、企業に勤める人が低金利で公的な住宅ローンを利用できるお得な制度です。
5年固定金利制なので返済の計画が立てやすく、保証料も不要なため初期費用を抑えたい人にピッタリ。
一方で、財形住宅融資を利用するには、次の条件を満たしている必要があります。
- 勤務先が制度を導入していること
- 財形貯蓄が50万円以上あること
- 継続的な積立実績があること
また、借入可能額にあらかじめ上限が設けられているため、希望する額を借入れることが難しい可能性もあります。
財形住宅融資の利用を検討しているのであれば、これらのメリット・デメリットを把握することが重要です。
まずは自分の勤務先で制度が利用できるか、そして貯蓄条件を満たしているかを確認するところから始めてみましょう。