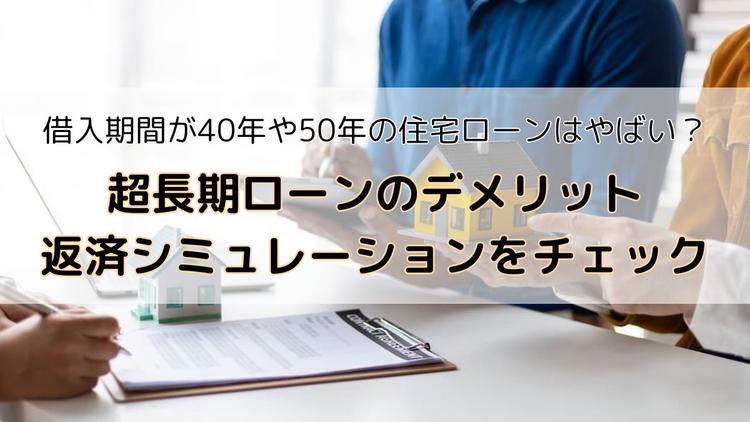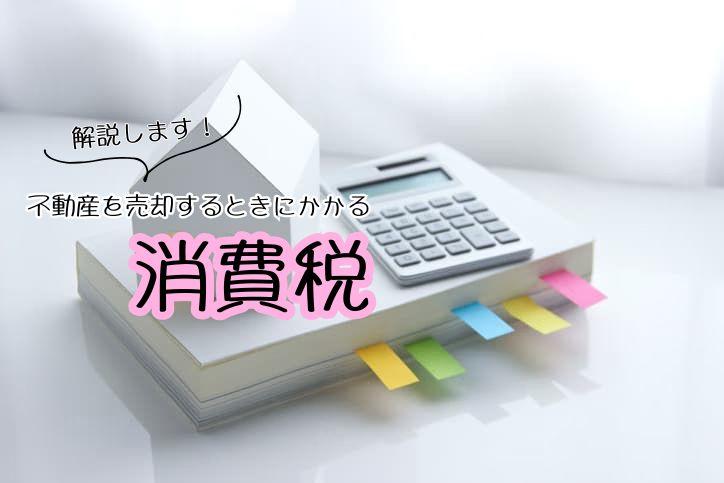超長期住宅ローンは毎月の返済額を低く抑えやすいという魅力があり、気になっている方もいるでしょう。
しかし、超長期で組むと返済総額が大きくなりやすいなどのデメリットもあるので、メリット・デメリットを理解しておくことが重要です。
この記事では、借入期間40年・50年の超長期住宅ローンのメリット・デメリットから具体的な返済シミュレーションまで分かりやすく解説します。
借入期間40年や50年の住宅ローンの取り扱い銀行とは?
住宅ローンを検討していると「フラット35」を耳にする機会は多いでしょう。
「フラット35」の商品名が表すように、2025年現在ではフラット35に限らず、住宅ローンの借入期間は35年で組むことが多いです。
一方、近年では35年を超えて40年・50年といった超長期で借り入れ可能な住宅ローンを提供する金融機関が増えています。
一部の地方銀行で取り扱いがあるケースがある
借入期間40年・50年の住宅ローンを取り扱っているのは、主に一部の地方銀行です。
たとえば、関東地方であれば以下のような銀行で提供されています。
ただし、地方銀行でも取り扱っていないケースもまだ多いので、検討する場合は事前に確認するようにしましょう。
住信SBIネット銀行の住宅ローン
地方銀行がメインの40年・50年住宅ローンですが、2023年に大手ネット銀行である住信ネット銀行が提供をスタートしたことで、ネット銀行や全国規模の銀行でも取り扱うケースが増えています。
住信SBIネット銀行の50年住宅ローンの概要は以下のとおりです5。
| 項目 | 詳細 |
| 借入年利 | 借入時満18歳以降満65歳以下で完済時満80歳未満 |
| 借入期間 | 1年以上50年以内 |
| 借入金額 | 500万円以上3億円以下 |
| 金利 | 借入期間35年超~50年の場合、住宅ローン適用金利に年0.15%上乗せ |
| 金利タイプ | 変動金利 固定金利(2年・3年・5年・7年・10年・15年・20年・30年・35年) |
| 団信加入の有無 | 加入が必要 |
申し込みは18歳以上65歳以下であれば可能ですが、完済年齢が80歳未満である点に注意が必要です。
仮に、50年でローンを組む場合は20代で組む必要があります。
住宅金融支援機構のフラット50
全期間固定金利で代表的な「フラット35」を提供する住宅金融支援機構でも「フラット50」という50年借入できる住宅ローンの提供が始まっています。
フラット50の概要は以下のとおりです6。
| 項目 | 詳細 |
| 返済期間 | 36年~50年 |
| 金利の範囲 | 年1.970%~年2.440% ※融資率9割以下の場合 (2025年8月時点) |
| 申込時年齢 | 満44歳 ※借入期間は80歳-申込年齢または50年のいずれか短い方が上限 |
| 借入額 | 100万円以上8,000万円以下 |
| 金利タイプ | 全期間固定 |
フラット50でも「80歳-申込時年齢」または「50年」のいずれか短い方が借入期間の上限となるので、50年の借入を行うには20代で申込む必要があります。
また、フラット50はフラット35同様に住宅金融支援機構と民間の金融機関が提携して提供されるため、申込窓口は金融機関です。
そのため、検討している金融機関で取り扱っているかどうか事前に確認するようにしましょう。
借入期間40年や50年で住宅ローンを組むメリット
借入期間40年・50年の住宅ローンのメリットは、以下の3つです。
- 毎月の返済額を安く抑えることができる
- 借入可能額を大きくしやすい
- 長期間団信を受けられる
それぞれ見ていきましょう。
毎月の返済額を安く抑えることができる
同じ条件で借入する場合、返済期間が長い方が毎月の返済額が下がります。
たとえば、3,000万円を金利1.0%(全期間固定金利)で借入した場合の毎月の返済額は以下のとおりです。
| 借入期間 | 毎月の返済額 |
| 35年 | 84,685円 |
| 40年 | 75,856円 |
| 50年 | 63,557円 |
35年と50年では毎月の返済額が2万円以上変わってきます。
収入がまだ大きくなりにくい若者世代や支出が大きくなりやすい子育て世帯にとっては、毎月の返済額を軽減できるのは大きな魅力といえるでしょう。
借入可能額を大きくしやすい
借入可能額は、返済比率に大きく左右されます。
返済比率(返済負担率)とは年収に占める年間の返済額の割合です。
たとえば、年収600万円で年間の返済額が150万円なら、返済比率は150万円÷600万円×100=25%となります。
一般的に住宅ローンの返済比率は30~35%以下が目安です。
年収300万円で毎月の返済額が8.5万円(35年ローン)なら返済比率は34%とギリギリになります。
一方、毎月の返済額が6.4万円(50年ローン)なら返済比率が25%まで下がるので、希望額を満額借入できる可能性が高くなるのです。
借入可能額が上がり希望額を借入れできれば、家の選択肢も広がります。
年収が低い場合、希望額では借入できずに家の選択肢が狭まるケースは珍しくありません。
長期借入にすることで、年収が低くてもより理想の家を手に入れやすくなるのは大きなメリットといえるでしょう。
「借り��入れ可能な上限額は年収の何倍か」の視点では、
- 35年→年収の7倍
- 50年→年収の10倍
が目安になるでしょう。
長期間団信を受けられる
基本的にほとんどの金融機関で住宅ローン加入時に団信(団体信用生命保険)への加入を必須としています。
団信に加入することで、万が一契約者が死亡や高度障害などで支払えない状況に陥っても、保険金で住宅ローンが完済されるため、住む場所に困ることはありません。
40年・50年もすれば病気になるリスクは高くなるでしょう。
一般的な生命保険であれば、年齢が高くなるにつれ保険料が値上がりするケースが多いものです。
一方、団信であれば保険料は金利に上乗せなしのものが一般的なので、長期的に見ればお得な生命保険といえます。
また、団信に加入することでその分民間の生命保険の見直しができ、長期的な保険料節約にもつながるでしょう。
借入期間40年や50年で住宅ローンを組むデメリット
借入期間が長いことはメリットになる反面、デメリットも生じます。
超長期の借入のデメリットは生活にも大きな影響が出る恐れがあるので、デメリットまで理解し慎重に検討することが大切です。
借入期間40年・50年の住宅ローンのデメリットとして、以下の3つが挙げられます。
- 返済総額が大きくなる
- 完済が遅くなる
- ライフプランの変化に対応しづらくなる
それぞれ見ていきましょう。
返済総額が大きくなる
借入期間が長くなるほど金利の負担が大きくなるため、同じ条件で借入した場合の返済総額は大きくなります。
たとえば、3,000万円を金利1.0%(全期間固定)で借入した場合の返済総額は以下のとおりです。
| 借入期間 | 毎月の返済額 |
| 35年 | 35,567,804円 |
| 40年 | 37,266,577円 |
| 50年 | 39,134,399円 |
上記のように35年と50年では返済総額が350万円近く変わってきます。
また、変動金利で組む場合は、金利上昇のリスクがさらに大きくなる点にも注意が必要です。
長期の借入は金利がたった数%上昇するだけで返済額に大きく影響してきます。
35年でも言えることですが、金利が将来どうなるかは分かりません。
35年よりも長期になる40年・50年を変動金利で検討する場合は、金利上昇リスクへもしっかり備えておくことが大切です。
完済が遅くなる
30歳で35年ローンを組んだのであれば、完済時年齢は75歳です。
仮に、75歳で定年するとなればぎりぎり現役世代中に完済が可能です。
老後の資金計画に影響が出る可能性
一方、30歳で40年ローンを組めば完済時が80歳となり、定年後にも住宅ローンの返済が続きます。
収入が減少する老後に住宅ローンが残っていると、生活の大きな負担となる恐れがあるので注意が必要です。
40年・50年の借入は、20代で借入して�も完済が遅くなります。
老後に返済が残ると老後破綻の恐れもあるため、繰り上げ返済なども視野に入れ現役中になるべく元金を減らせるように計画しましょう。
超長期ローンは住み替え・売却で不利になりやすい
また、完済が遅くなることで売却がしにくくなる点にも注意が必要です。
40年・50年の住宅ローンは毎月の返済額が少なく、金利負担は大きいため、元本の減りが悪くなります。
たとえば、30年ローンで10年返済していれば単純計算で3分の1にローン残債は減少します。
しかし、50年ローンでは10年返済してもまだ5分の1にしかなりません。
売却を検討する段階でローン残債が大きくなりやすく、売却しようにも売却できないとなりかねない点には注意しましょう。
ライフプランの変化に対応しづらくなる
超長期のローンを抱えることで、ライフプランの変化に柔軟に対応できないリスクもあります。
20代で住宅ローンを組んだ場合、まだライフプランの変更が大きい時期でもあります。
転職や結婚・出産、子どもの成長などでさまざまな変化が起きやすいため、ライフプランも当初と大きく変わっている可能性があるでしょう。
家を購入し超長期のローンを抱えていると、ライフプランの変化に対応できずその時取れる選択肢が狭まる恐れがあるのです。
借入期間40年や50年の住宅ローンの返済シミュレーション
こ��こでは、具体的に40年・50年の借入期間での返済シミュレーションをしていきます。
条件は以下のとおりです。
- 借入時年齢:28歳
- 借入額:4,000万円
- 適用金利:1.5%(全期間固定)
借入期間40年住宅ローンの返済シミュレーション
まずは、借入期間40年の場合の返済額をシミュレーションしましょう。
毎月の返済額・返済総額は以下のようになります。
- 毎月の返済額:110,868円
- 返済総額:53,216,962円
ちなみに、同条件で35年ローンを組んだ場合の返済額は以下のとおりです。
- 毎月の返済額:122,473円
- 返済総額:51,438,816円
35年ローンよりも毎月の返済額を1万円以上軽減できています。
しかし、返済総額は200万円ほど高くなっている点には注意しましょう。
借入期間50年住宅ローンの返済シミュレーション
次に、同条件で50年ローンを組んだ場合の返済額をみていきましょう。
返済額は以下のとおりです。
- 毎月の返済額:94,802円
- 返済総額:56,881,223円
毎月の返済額は大きく軽減できていますが、返済総額の負担は増えます。
また、28歳で50年ローンを組んだ場合、完済時の年齢は78歳と定年後のローンが残っている可能性が高くなります。
繰り上げ返済する・退職金で一括返済するなど、老後に返済が残らないような工夫も検討しておくことが大切です。
▼関連記事

借入期間40年や50年の住宅ローンに関するよくある質問
最後に、借入期間40年や50年の住宅ローンに関するよくある質問をみていきましょう。
借入期間40年の住宅ローンがやばいといわれる理由は?
借入期間40年の住宅ローンは毎月の返済の負担を軽減できる反面、返済総額が大きくなります。
また、借入期間が長いほど金利上昇リスクや収入減少時などのリスクも起きやすいでしょう。
住宅ローンの減りが悪いことで、いざというときに家を売却しにくくなる点に、やばいといわれる要因があると考えられます。
借入期間50年の住宅ローンがやばいといわれる理由は?
借入期間40年同様のリスクがあり、さらに借入期間50年は40年以上にそのリスクも高くなります。
50年の住宅ローンがやばいといわれる理由としては以下のようなものが考えられます。
- 返済総額が大きくなりやすい
- 金利上昇など借入期間中のリスクがある
- 老後に返済が残る可能性がある
- ライフプランの見通しが立てにくい
- 元本の減りが悪い
メリット・デメリットを比較し、入念に返済シミュレーションを立てたうえで検討するようにしましょう。
ろうきんで借入期間50年の住宅ローンを組むことはできる?
ろうきんでは住宅金融支援機構との提携商品であるフラット50を組むことが可能です。
また、ろうきんによっては40年の住宅ローンを提供しているケースがあります。
ろうきんであってもエリアによって提供する住宅ローンは異なります。
ろうきんはそのエリアに住んでいるもしくは働いている人が対象となるのが一般的なため、まずは対応エリアのろうきんで確認してみるとよいでしょう。
まとめ
借入期間が40年・50年の住宅ローンであれば、毎月の返済額の負担を軽減し、収入が低くても理想の家を手に入れられるチャンスがあります。
ただし、長期間で借入するため金利の負担が大きく、返�済総額が大きくなりやすい点には注意しましょう。
また、完済年齢も高くなりやすく老後資金に影響が出やすい点も覚えておきましょう。
40年・50年ローンを検討する場合は、長期的な返済シミュレーションや35年ローンとの比較・リスク対策をしたうえで検討することが大切です。