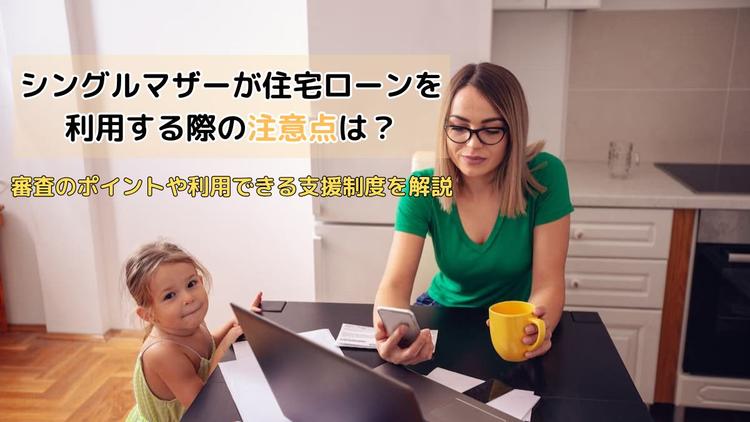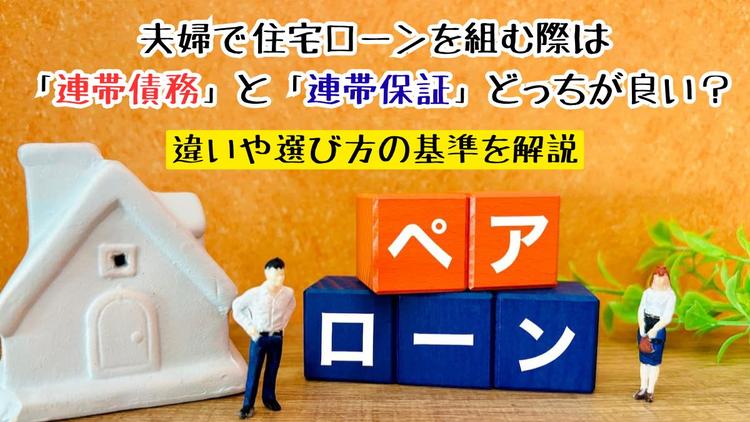土地を売却すると、確定申告が必要になるケースがあります。
とはいえ、どのケースで確定申告が必要か、どのように手続きすればいいのか分からないという方も多いでしょう。
確定申告が必要にも関わらず申告を怠ってしまうと、ペナルティが課せられる恐れもあるので、期日を守って確定申告を行うことが大切です。
この記事では、土地売却で確定申告が必要なケースや、税金の計算方法、節税方法などを分かりやすく解説します。
土地の売却で確定申告が必要なケースと不要なケース
まずは、土地の売却で確定申告が必要なケース・不要なケースをみていきましょう。
また、確定申告が不要でも申告したほうがお得になるケースもあるので、あわせて紹介します。
確定申告が必要なケース
確定申告が必要なケースは、以下の2つです。
- 土地の売却で利益が出る
- 特別控除などの特例を適用する
譲渡所得(売却益)が出た場合
土地の売却の利益は「譲渡所得」と呼ばれ、所得税・住民税の課税対象になります。
譲渡所得税が発生する場合は、確定申告をして納税をする必要があります。
なお、譲渡所得税は給与所得など他の所得とは分けて課税される分離課税です。
そのため、会社員などで年末調整をしている場合でも、不動産の売却益が年末調整に影響することはありません。
しかし、別途確定申告が必要になります。
特例の適用のために確定申告が必要
また、譲渡所得にかかる税金については、3,000万円特別控除など税負担を軽減する特例がいくつか設けられています。
そのような特例を適用する場合も、確定申告での申請が必要です。
特例を適用すれば税金が発生しない場合でも、確定申告は必要なので「特例で税金が発生しないから申告不要」と誤認しないように気を付けましょう。
譲渡所得にかかる所得税・住民税の計�算や特例については、後ほど詳しく解説するので参考にしてください。
確定申告が不要なケース
確定申告が不要なのは「売却益が発生しないケース」です。
具体的には、土地の値下がりや売却時の諸経費が高額になり、購入時の価格+売却時の諸経費が売却金を上回るようなケースが挙げられます。
売却益が発生しなければ、譲渡所得にかかる税金も発生しないため、確定申告は必要ありません。
ただし、前述のとおり特例を適用して税金が発生しないケースでは確定申告が必要です。
あくまで特例を適用せずとも税金が発生しないケースであることは押さえておきましょう。
不要でも申告したほうがよいケース
売却で利益が出ない(損失が出ている)場合、確定申告は不要です。
しかし、譲渡所得では損失発生時にも適用できる特例がいくつか設けられており、確定申告をして適用することで税金が軽減される場合があります。
例えば、売却時の損失を給与所得と損益通算できる特例であれば、給与所得にかかる所得税・住民税の節税が見込めます。
損失時に適用できる特例がある場合は、確定申告するのがおすすめです。
土地売却時の所得税・住民税の計算方法
土地売却では、利益が出ると税金が発生します。
あらかじめ税金の計算方法を押さえておかないと、思ったよりも手元にお金が残らない、納税の資金がないなどの状況に陥ってしまうので注意しましょう。
ここでは、売却の利益にかかる所得税・住民税の計算方法を解説します。
大まかなステップは次の2つです。
- 課税譲渡所得を求める
- 税率を掛け合わせる
それぞれ見ていきましょう。
課税譲渡所得を求める
売却の利益は「譲渡所得」と呼ばれ、所得額に対して所得税・住民税がかかります。
まずは、税金の計算のベースとなる利益=譲渡所得を計算します。
課税譲渡所得の計算方法は以下の通りです。
取得費とは、購入時にかかった費用です。
土地の場合は、
- 土地代
- 仲介手数料
- 印紙税
- 登録免許税
- 測量費
- 造成費
などが該当します。
一方、譲渡費用は、仲介手数料や解体費用などの売却時にかかった費用のことを言います。
売却額からこれらの取得費や譲渡費用を差し引いた額が譲渡所得となります。
また、譲渡所得には3,000万円特別控除などで、さらに差し引ける控除もあるので、それらも差し引いた額が課税対象額となります。
税率を掛け合わせる
課税対象額が分かれば、その額に譲渡所得にかかる所得税・住民税の税率を乗じて税額が算出できます。
税率は、土地の所有期間に応じて以下の2種類に分かれます。
| 所有期間 | 所得税・復興特別所得税 | 住民税 | 合計税率 | |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
上記のように、所有期間5年を境に「短期譲渡所得」「長期譲渡所得」に区分され、税率が大きく異なるので注意しましょう。
また、2037年までは、東日本大震災の復興資源として復興特別所得税も課税されます。
なお、これらの譲渡所得にかかる税金を総称して譲渡所得税と呼ぶこともあるので覚えておきましょう。
土地売却時の確定申告で利用できる特別控除
土地売却の利益にかかる税金は、特例などを上手に活用することで節税が見込めます。
ここでは、土地売却で適用を検討できる代表的な特例を紹介します。
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
この特例では、相続した土地を売却した際、譲渡所得の計算で取得費に相続税の一定額を加算することが可能です1。
支払った相続税の一部を譲渡所得から差し引けるので、その分節税できます。
特例を適用するためには、以下のような要件を満たす必要があります。
- 相続や遺贈により取得した不動産
- 相続税が課税されている
- 相続開始の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年以内の売却
相続税を支払っていることが条件でもあるので、相続で取得した土地であっても相続税が発生していないケースでは適用できません。
また、売却までの期限も設けられているので注意しましょう。
3000万円特別控除などマイホーム売却時に利益が出たときに適用を受けられる特例
売却した土地がマイホームの敷地であった場合、利益が出た際に以下のような特例の適用を検討できます。
- 3,000万円特別控除
- 10年超所有軽減税率の特例
- 買換え特例
マイホームの売却で適用できる代表的な特例が「3,000万円特別控除の特例」です2。
この特例では、譲渡所得から最大3,000万円を控除できるので、譲渡所得3,000万円以下であれば税金が課税されません。
解体後に売却しても一定の期間内であれば適用できる
マイホームを解体した後の更地であっても、住まなくなってから3年以内かつ解体して1年以内の売却であれば適用可能です。
なお、相続した空き家の場合はマイホームとみなされないので、この特例は適用できません。
ただし、相続した空き家は一定の要件を満たせば「相続空き家の3,000万円特別控除」を適用できる可能性があります。
また、所有期間が10年を超えるマイホームの場合は、「10年超所有軽減税率の特例」が適用可能で、譲渡所得6,000万円以下の部分の税率を14.21%に引き下げられます。3。
3,000万円特別控除と10年超所有軽減税率の特例は併用できるので、大きな節税が見込めるでしょう。
買い替えの特例と3,000万円控除はどちらか1つしか使えない
住み替えによる土地の売却であれば、買換え特例4を適用することで、売却利益を新居の売却時まで繰延することが可能です。
しかし、買換え特例は3,000万円特別控除との併用はできないため、どちらがお得になるかは慎重にシミュレーションする必要があります。
これらのマイホームの売却時に適用できる特例は、マイホームを解体した更地であっても要件を満たすことで適用可能です。
ただし、解体から3年以上経過したり、もとから更地であったりした場合は適用できないので注意しましょう。
マイホーム売却時に損失が出たときに適用を受けられる特例
売却で損失が出た場合でも、以下のような特例の適用を検討できます。
- マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
- 特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
マイホームを買い換えた場合の特例5は、買換え時の売却損失、特定のマイホームの譲渡損失の特例6は、住宅ローンを下回る売却になった際に適用可能です。
どちらも損失額を給与所得などと損益通算できるので、所得税・住民税の節税につながります。
なお、実際に譲渡損失を計算する際は、建物部分の減価償却を考慮した上で、取得費等を計上することができます。
また、売却した年だけでは控除しきれない分は、翌年以降3年に渡り控除できるので、長期間での節税も見込めます。
土地売却時の税金シミュレーション
ここでは、土地売却の税金を具体的にシミュレーションしてきます。
条件は、以下の通りです。
- 売却額:3,000万円
- 所有期間:8年
- 購入時の価格:2,000万円
- 購入時の諸費用:150万円
- 売却時の諸費用:200万円
課税譲渡所得は以下のようになります。
所有期間8年は長期譲渡所得に区分され、税率は20.315%です。
よって、税額は次のようになります。
譲渡所得にかかる所得税・住民税:650万円×20.315%=約132万円
なお、この土地で3,000万円特別控除を適用できれば課税譲渡所得が0円となるため、税金が発生しません。
このように、特例が適用できるかによっても税額は大きく異なってくるので、慎重にシミレーションして判断するようにしましょう。
土地売却の確定申告の必要書類
土地売却の確定申告での必要書類は以下の通りです。
- 確定申告書
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
- 売却時の売買契約書
- 登記事項証明書
- 購入時の売買契約書や領収書
- 売却時の費用の分かる領収書 など
確��定申告の際には、確定申告書に加えて譲渡所得の内訳書が必要です。
また、各種費用を証明するための売買契約書や領収書なども必要になります。
費用を証明する書類が無ければ費用計上できないので、領収書などは大切に保管しておくようにしましょう。
さらに、譲渡所得に関する特例を適用する場合は、適用のための書類も必要になります。
土地売却時の確定申告手続きの流れ
土地売却時の確定申告の大まかな手続きの流れは以下の通りです。
- 必要書類を用意する
- 確定申告書に記入する
- 期限内に確定申告する
それぞれ見ていきましょう。
必要書類を用意する
前述したような必要書類を用意します。
必要書類の中には取得に時間がかかるものもあるので、早めに用意するようにしましょう。
確定申告書に記入する
必要書類を揃えたら、確定申告書と譲渡所得の内訳書を作成します。
国税庁のホームページに記載例が公開されているので、確認しながら漏れやミスの無いように記入しましょう。
e-taxを利用すれば、質問に答えると自動的に申告書が作成されるので、簡単に作成できます。
記入に不安がある場合は、税理士や自治体の相談コーナーなどでアドバイスをもらいながら作成することをおすすめします。
期限内に確定申告する
確定申告の時期は、土地を売却した年の翌年2月16日から3月15日の間です。
この期間に管轄の税務署に必要書類を提出して申告しましょう。
申告方法としては以下の3つがあります。
- 税務署に持参して申告する
- 郵送で申告する
- e-taxで申告する
税務署の窓口であれば簡易的なチェックも受けられるので、申告に不安のある方におすすめです。
ただし、確定申告時期の税務署は混みあう可能性があるので、時間に余裕をもって申告する必要があります。
郵送またはe-taxの利用が便利
窓口に行く時間が取れない場合は、必要書類を郵送する方法もあります。
また、e-taxでの申告であれば時間や場所にとらわれずいつでも自分の好きな時間に申告できます。
事前にダウンロードや設定などが必要ですが、一度設定すれば翌年以降はスムーズに利用できるので、自営業の方などはこれを機に設定してみるのもよいでしょう。
申告を忘れないようにする
確定申告が必要なケースで申告を怠ると、無申告加算税などのペナルティが科せられる恐れがあります。
確定申告に慣れていない方は時間もかかりやすいので、早めに用意して期限内に手続きできるようにしましょう。
土地売却時の確定申告に関するよくある質問
最後に、土地売却の確定申告に関するよくある質問をみていきましょう。
自分で確定申告できる?
確定申告は自分でも可能です。
必要書類を揃え確定申告書を作成し、税務署に申告しましょう。
ただし、土地売却の利益の計算が複雑になる場合や、適用できる特例に不安があるケースでは税理士などのプロに相談することをおすすめします。
とくに、取引金額が大きい場合は税金も高額になってくるので、プロのアドバイスを受けながら慎重に申告するほうがよい�でしょう。
確定申告時期になれば税務署や自治体で相談コーナーが設けられるケースも多いので、そちらを活用するのもおすすめです。
無申告だとどうなる?
無申告の場合、状況によっては無申告課税や延滞税などのペナルティが科せられる恐れがあります。
土地売却が行われたことは、基本的に税務署も把握しています。
確定申告されていないことで税務署の調査が入る可能性が高くなり、調査の結果によって無申告課税などのペナルティが科せられるケースがあるのです。
さらに、無申告が故意や悪質だと判断されると、より重いペナルティが科せられる恐れもあるので、期日にしっかり確定申告するようにしましょう。
住民税も確定申告する必要がある?
所得税の確定申告をしている場合、住民税の申告は不要です。
所得税の確定申告後に住民税は自動的に手続きされます。
その場合、5月~6月頃に納付書が送られてくるか、職場で源泉徴収されている方は職場の方で手続きがなされることになります。
まとめ
土地売却で利益が出た場合、確定申告をして納税が必要です。
土地売却の利益では節税につながる特例も用意されているので、あわせて確定申告して適用しましょう。
また、売却で損失が出た場合は確定申告不要ですが、損失時の特例を適用する場合は確定申告が必要です。
土地売却の確定申告が不安であったり、売却額が高額の場合は、不動産会社や税理士などのプロに相談しながら手続きを進めることをおすすめします。