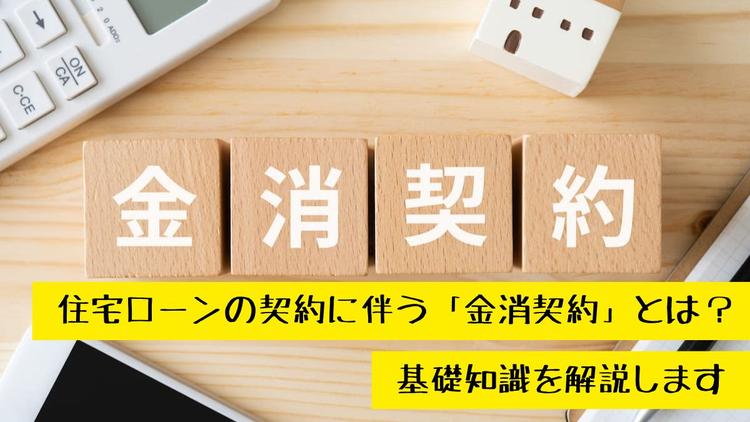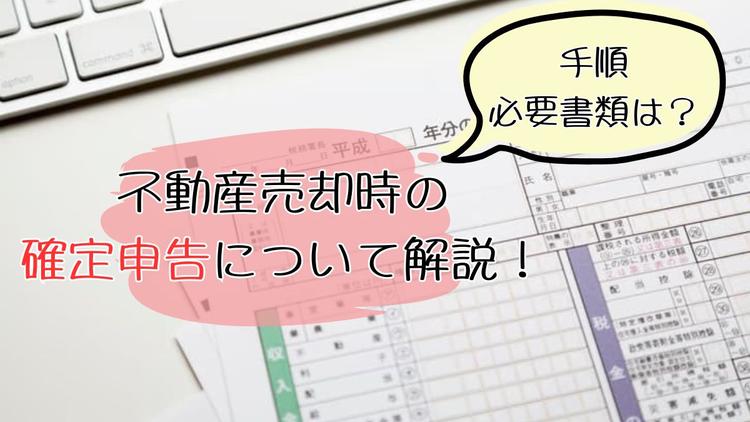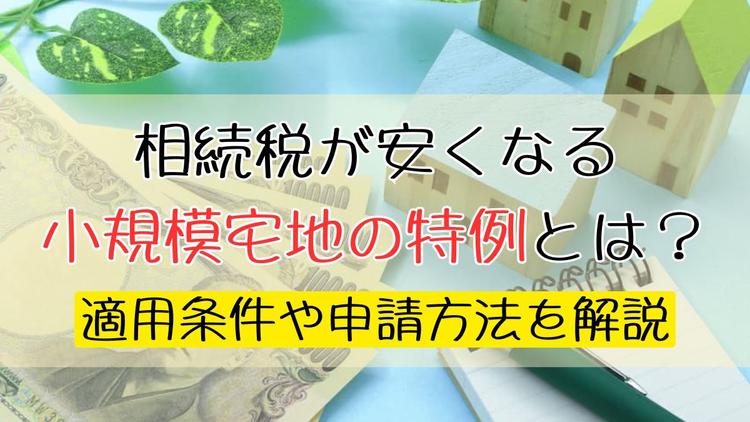「家は人生の中でももっとも大きな買い物」と呼ばれるように、高額なお金が必要です。
年収に適した予算で購入しないと、購入できない、または購入しても生活が苦しくなる恐れがあります。
とはいえ、自分の年収でどれくらいの家が買えるのかよく分からないという方も多いでしょう。
そこでこの記事では、家の購入に必要な年収や借入可能額の計算方法、物件別・年収別のシミュレーションなどを分かりやすく解説します。
購入できる家の価格は年収の6~7倍が目安
フラット35を提供する住宅金融支援機構の「2023年度フラット35利用者調査」による、融資区分別の年収倍率は以下の通りです1。
| 融資区分 | 年収倍率 |
| 中古戸建 | 5.3倍 |
| 中古マンション | 5.6倍 |
| 建売住宅 | 6.6倍 |
| 注文住宅 | 7.0倍 |
| マンション | 7.2倍 |
| 土地付注文住宅 | 7.6倍 |
年収倍率とは、家購入の所要資金を世帯年収で割った数値をいいます。
この結果では、年収のおおよそ6~7倍の家を購入していることが分かります。
例えば、年収600万円なら3,600万円~4,200万円の家が目安となるでしょう。
基本的には、家の購入費用は住宅ローンで賄うことになります。
そのため、いくらの家を購入できるかを考える際には、自分の年収でいくらの住宅ローンを組めるかを理解して�おくことが重要です。
借入可能額の計算方法
一般的に住宅ローンの借入可能額は、以下の方法で計算できます。
年間返済可能額は、返済比率をもとに考えることになります。
返済比率(返済負担率)
返済比率とは、年収に占める年間返済額の割合です。
例えば、年収600万円で年間の住宅ローン返済額が150万円なら、返済比率は25%となります。
金融機関では、住宅ローンの返済比率を30~35%を目安としているので、返済比率をもとに返済額を計算してみるとよいでしょう。
審査金利
また、審査金利とは金融機関が審査の際に用いる金利です。
審査金利がいくらに設定されているかは基本的に公表されていませんが、3~4%が目安といわれています。
例えば、以下の条件で借入可能額を計算してみましょう。
- 年収500万円
- 返済比率30%
- 審査金利3%
- 借入期間30年
返済比率が30%なので、年間返済可能額は150万円です。
また、100万円を金利3%で30年間借入する場合の毎月の返済額は4,216円となります(審査金利での100万円あたりの返済月額)。
よって、借入可能額は以下のとおりです。
この場合、約3,000万円が借入可能額の目安となります。
年収別の借入可能額早見表(返済比率30%、審査金利3%、借入期間30年)
| 年収 | 借入可能額(※) |
| 400万円 | 2,372万円 |
| 500万円 | 2,965万円 |
| 600万円 | 3,558万円 |
| 700万円 | 4,151万円 |
| 800万円 | 4,744万円 |
| 900万円 | 5,337万円 |
| 1,000万円 | 5,930万円 |
※借入可能額は、上記シミュレーションの条件に基づく計算であり、審査に通ることを保証するものではありません。
必要なお金は物件価格+各種経費
家の購入の際には、家だけのお金が必要なわけではありません。
仲介手数料や各種税金など、さまざまな費用が発生するため、トータルの費用を考えておく必要があります。
例えば、中古で家を購入する場合、以下のような費用が必要です。
| 費用の項目 | 概要と目安額 |
| 印紙税 | 売買契約書にかかる税金 【目安額】1~10万円(売買金額に応じる) |
| 登録免許税 | 所有権移転登記・抵当権設定登記の際にかかる税金 【目安額】【所有権移転登記】不動産の評価額×2% 【抵当権設定登記】借入額×0.4% |
| 司法書士費用 | 登記を司法書士に依頼した際の費用 【目安額】3~10万円 |
| 仲介手数料 | 不動産会社への仲介手数料 【目安額】売買金額×3%+6万円+消費税 |
| 不動産取得税 | 不動産を取得した際にかかる税金 【目安額】不動産の評価額×(原則)4% |
| 住宅ローン契約にかかる費用 | 事務手数料や保証料など住宅ローンを組むための費用 【目安額】事務手数料:借入額×2~3% |
| その他費用 | 引越し費用や家具購入費など |
諸費用の目安は物件価格の5~10%
諸費用の目安は、家の購入価格の5~10%程といわれています。
例えば、3,000万円の家を購入するなら150万円~300万円の諸費用が別途必要となるのです。
諸費用がどれくらいになるかは、どのような家を購入するかによっても大きく変わってきます。
中古であれば仲介手数料が必要ですが、注文住宅の新築なら仲介手数料は不要です。
新築で土地から購入するとなったら、さらに土地購入費もかかってきます。
諸費用は住宅ローンに組み込めることがある
必要な諸費用はケースバイケースとなるため、自分の場合はどれくらいになるかを、事前にしっかりシミュレーションしておくことが大切です。
また、諸費用の項目によっては住宅ローンに組み込めるものもあります。
ただし、組み込めるかどうかは金融機関によっても異なるので、事前に確認するようにしましょう。
民間の金融機関は借入可能額が低くなるケースがある
借入可能額を計算する際に用いる金利は、実行金利と審査金利(基準金利・店頭金利と呼ばれることもある)に分かれます。
実行金利とは、実際に住宅ローンを貸し出す際の金利です。
一方、審査金利は審査の際に用いる金利を指します。
審査金利は実行金利よりも2~3%程高く設定されているので、実行金利で計算するよりも借入可能額が低くなります。
どの金利を用いるかは公表されていませんが、基本的にほとんどの民間の金融機関は融資後の金利上昇も考慮し、高めに設定した審査金利で借入可能額を算出します。
しかし、フラット35に関しては実行金利で審査されます。
2024年10月時点で、フラット35(借入期間21年以上35年以下/融資率9割以下)の最も多い金利は1.820%なので、民間金融機関の審査金利よりも低いです。
借入可能額を上げたいという場合は、フラット35を検討するのも一つの手と言えるでしょう。
家を買う際の世帯年収の考え方
住宅ローンは、申込者個人の年収で判断されます。
しかし、年収が低くて希望額の借入ができないといったケースでは、世帯年収で申込むことが可能です。
世帯年収であれば、個人の年収よりもアップするため、希望額で借入できる可能性があるでしょう。
夫婦で収入を合算できる
世帯年収で申込むケースでは、夫婦の収入を合算するのが一般的です。
夫婦で年収を合算して住宅ローンを検討する場合、次のような選択肢があります。
- 収入合算
- ペアローン
収入合算とは、夫婦の収入を合算した額で住宅ローンを審査する方法です。
合算する収入者は連帯保証人になります。
一方、ペアローンとは夫婦それぞれが契約者となってローンを組む方法です。
例えば、4,000万円の家を購入するために、夫は2,500万円の住宅ローンを組み、妻は1,500万円の住宅ローンを組むという形になります。
この場合は、それぞれが契約者であり、さらにもう片方の連帯保証人にもなるのが一般的です。
収入合算・ペアローン共に、妻側も勤続年数や年収などの一定の条件をクリアする必要があります。
条件は金融機関によって異なりますが、パートや契約社員・派遣でも申し込める金融機関も多いので、検討してみるとよいでしょう。
親子リレーローンという方法もある
収入を合算する相手は配偶者だけでなく、親子というケースもあります。
親子で住宅ローンを組む代表的な方法が親子リレーローンです。
親子リレーローンとは、親世帯と子世帯の年収を合算して住宅ローンを組み、最初に親世帯が返済し、その後子世帯が返済を引き継ぐ住宅ローンのことをいいます。
ただし、購入する家が二世帯住宅等などで、同居が条件となるのが一般的です。
収入合算できる親族の範囲
収入合算ができる親族の範囲は、金融機関によっても異なりますが一般的には配偶者と親子です。
配偶者については、婚約者も認められるケースがあります。
一方、兄弟姉妹は対象とならないケースが多いでしょう。
また、対象者である場合でも、同居が前提となるのが一般的です。
収入合算できる範囲や条件は金融機関によって異なるので、事前に確認するようにしましょう。
住宅ローンの借入可能額と理想の返済額の違い
住宅ローンの借入可能額は、あくまで借入できる額であり、余裕をもって返済できる額とは異なります。
借入可能額の満額借りると返済が厳しくなるケースもある
例えば、以下の条件で見てみましょう。
- 年収:600万円
- 返済比率:35%
- 借入期間:35年
- 審査金利:3%
上記の場合の借入可能額は以下の通りです。
この場合で4,500万円を金利2%・35年で借入すると、毎月の返済額は約15万円となります。
ちなみに、年収600万円の手取りは450万円~510万円が目安となるので、手取り年450万円のとき月の手取りは37.5万円です。
つまり、月の手取り37.5万円のうち15万円が住宅ローンの返済となります。
この返済額が多いかは家庭状況などによっても異なりますが、年収で考えていると手取りとの差で生活の負担になる恐れがある点は覚えておきましょう。
返済負担額25%以内が一つの目安
住宅ローンの審査では返済比率は30~35%以下が目安となりますが、理想の返済比率は20~25%以下と言われています。
例えば、年収600万円の場合の返済額は以下の通りです。
| 返済比率 | 20% | 25% | 30% | 35% |
| 年間返済額 | 120万円 | 150万円 | 180万円 | 210万円 |
| 月の返済額 | 10万円 | 12.5万円 | 15万円 | 17.5万円 |
返済比率が20%と35%では、月額で7.5万円もの差になってきます。
また、年収600万円は手取りとは異なる点にも注意が必要です。
借入額を考える際の注意点
家庭状況によっていくらの返済額が適しているかは異なります。
子どもが多い家庭は子どもの成長に伴い支出も多くなり、住宅ローンの返済が負担になりやすいです。
親と近居や同居しており、生活費を抑えやすいケースでは、返済額が多少大きくても負担にならない場合もあるでしょう。
収入の減少や、金利が変動するリスク
仮に、今は問�題なくても将来、転職で収入が減少するリスクや、変動金利で金利が上昇するリスクも考えておく必要があります。
住宅ローンの返済は長期に渡り、生活に大きく関わってくるものです。
現在の家庭状況、将来のライフプランなどによっても適切な額は異なってくるので、自分の状況に合わせて長期的な返済計画を立てて借入額を検討するようにしましょう。
【世帯年収別】物件の購入額と住宅ローン借入額の相場
ここでは、以下の条件でシミュレーションしていきます。
- 年収の7倍の家を購入する
- 諸費用は家の購入額の10%
- 返済負担比率25%で借入する(金利2%(全期間固定)・借入期間35年)
- 年収の手取りは80%
なお、借入可能額は審査金利3%/返済負担率35%/借入期間35年で計算しています。
まずは、年収別の諸費用まで含めた家の購入額は以下のとおりです。
| 年収 | 200万円 | 300万円 | 400万円 | 500万円 | 600万円 |
| 家の価格 | 1,400万円 | 2,100万円 | 2,800万円 | 3,500万円 | 4,200万円 |
| 諸費用 | 140万円 | 210万円 | 280万円 | 350万円 | 420万円 |
| 合計 | 1,540万円 | 2,310万円 | 3,080万円 | 3,850万円 | 4,620万円 |
一方、借入可能額と返済比率25%での借入額は以下のようになります。
| 年収 | 200万円 | 300万円 | 400万円 | 500万円 | 600万円 |
| 家の購入総額 | 1,540万円 | 2,310万円 | 3,080万円 | 3,850万円 | 4,620万円 |
| 借入可能額 | 約1,500万円 | 約2,200万円 | 約3,000万円 | 約3,800万円 | 約4,500万円 |
| 25%での借入額 | 約1,000万円 | 約1,600万円 | 約2,200万円 | 約2,700万円 | 約3,300万円 |
借入可能額で借入できれば年収7倍の家であっても購入は可能です。
しかし、返済の余裕を考慮し返済比率25%で借入する場合、頭金を増やすか、家の選択肢を変更するかが必要になることが分かります。
それぞれの年収別に以下で詳しくみていきましょう。
年収200万円のケース
年収200万円のケースで、借入可能額満額・25%の返済比率で借入れた場合を、返済月額まで含めてみると以下の通りです。
| 借入可能額満額で借入 | 返済比率25%で借入 | |
| 家の購入費用総額 | 1,540万円 | 1,540万円 |
| 借入額 | 1,500�万円 | 1,000万円 |
| 差額(頭金) | 40万円 | 540万円 |
| 毎月の返済額 | 49,689円 | 33,126円 |
| 手取り月収 | 約13万円 | 約13万円 |
年収200万円の場合、借入可能額は1,500万円とはいえ年収の低さで審査が厳しくなる恐れがあります。
一般的に住宅ローンで必要な年収は300万円が目安といわれています。
金融機関によって収入の目安は異なりますが、収入合算も視野に入れるとよいでしょう。
年収300万円のケース
年収300万円では以下のようになります。
| 借入可能額満額で借入 | 返済比率25%で借入 | |
| 家の購入費用総額 | 2,310万円 | 2,310万円 |
| 借入額 | 2,200万円 | 1,600万円 |
| 差額(頭金) | 110万円 | 710万円 |
| 毎月の返済額 | 72,877円 | 53,002円 |
| 手取り月収 | 約20万円 | 約20万円 |
年収300万円であれば、住宅ローンの審査の通る可能性は十分あるでしょう。
しかし、借入可能額は大きくなりにくいため家の選択肢が狭まります。
希望の家を購入するためには、頭金を増やす、年収が上がるのを待つなどの工夫も検討する必要があるでしょう。
年収400万円のケー�ス
年収400万円では以下のようになります。
| 借入可能額満額で借入 | 返済比率25%で借入 | |
| 家の購入費用総額 | 3,080万円 | 3,080万円 |
| 借入額 | 3,000万円 | 2,200万円 |
| 差額(頭金) | 80万円 | 880万円 |
| 毎月の返済額 | 99,373円 | 72,877円 |
| 手取り月収 | 約27万円 | 約27万円 |
フラット35の利用者調査では、年収400万円未満で住宅ローンを利用する層は全体の19.8%とそう多くはありませんが、借入できていることが分かります。
ただ、返済比率25%で借入れる場合、借入額がそれほど大きくないため、頭金を十分に用意しておく必要があります。
年収500万円のケース
年収500万円では以下のようになります。
| 借入可能額満額で借入 | 返済比率25%で借入 | |
| 家の購入費用総額 | 3,850万円 | 3,850万円 |
| 借入額 | 3,800万円 | 2,700万円 |
| 差額(頭金) | 50万円 | 1,150万円 |
| 毎月の返済額 | 125,879円 | 89,440円 |
| 手取り月収 | 約34万円 | 約34万円 |
年収500万円であれば、住宅ローン審査に通る可能性は高くなり、借入額から見る家の選択肢も広くなるでしょう。
年収600万円のケース
年収600万円では以下のようになります。
| 借入可能額満額で借入 | 返済比率25%で借入 | |
| 家の購入費用総額 | 4,620万円 | 4,620万円 |
| 借入額 | 4,500万円 | 3,300万円 |
| 差額(頭金) | 120万円 | 1,320万円 |
| 毎月の返済額 | 149,068円 | 109,316円 |
| 手取り月収 | 約40万円 | 約40万円 |
フラット35の利用者調査 によると、2023年度の平均世帯年収は661万円です。
年収400万円〜600万円で利用する層は、全体の37.5%と最も多い世帯年収層でもあります。
また、同調査による家の所要資金は、土地付注文住宅で4,903万円、中古戸建で2,536万円となっています。
年収600万円での借入であれば、家の選択肢の幅はかなり広がると言えるでしょう。
【物件価格別】家を買える人の年収
ここでは、物件の価格別に買える人の年収をみていきましょう。
条件を以下のようにしてシミュレーションしていきます。
- フラット35を想定(金利1.8%・借入期間35年)
- 諸費用:物件価格の10%
3,000万円の家を買える人の年収
3,000万円の家を購入する際には、諸費用を含めて3,300万円が必要です。
よって、各年収別の借入可能額・返済比率25%の借入額と比較した場合の差額は以下のようになります。
| 年収 | 200万円 | 300万円 | 400万円 | 500万円 | 600万円 |
| 借入可能額 | 1,500万円 | 2,200万円 | 3,000万円 | 3,800万円 | 4,500万円 |
| 差額 | 1,800万円 | 1,100万円 | 300万円 | – | – |
| 返済比率25%での借入額 | 1,000万円 | 1,600万円 | 2,200万円 | 2,700万円 | 3,300万円 |
| 差額 | 2,300万円 | 1,700万円 | 1,100万円 | 500万円 | – |
借入可能額で見れば、年収400万円以上であれば比較的検討しやすいでしょう。
一方、返済比率を25%に抑えるなら年収500万円以上は必要になります。
それ以下の年収の場合は、頭金を十分に用意するか収入合算などを検討する必要があるでしょう。
5,000万円の家を買える人の年収
諸経費込みで5,500万円必要とした場合、各年収別の差額は以下の通りです。
| 年収 | 400万円 | 500万円 | 600万円 | 700万円 | 800万円 |
| 借入可能額 | 3,000万円 | 3,800万円 | 4,500万円 | 5,300万円 | 6,000万円 |
| 差額 | 2,500万円 | 1,700万円 | 1,000万円 | 200万円 | – |
| 返済比率25%での借入額 | 2,200万円 | 2,700万円 | 3,300万円 | 3,800万円 | 4,300万円 |
| 差額 | 3,300万円 | 2,800万円 | 2,200万円 | 1,700万円 | 1,200万円 |
借入可能額で見れば、頭金をいくら用意できるかにもよりますが、年収600万円以上で現実的といえるでしょう。
一方、返済比率を25%に抑えて借入するなら、年収800万円でもそれなりの額の頭金が必要なことが分かります。
7,000万円の家を買える人の年収
諸経費込みで7,700万円必要とした場合、各年収別の差額は以下の通りです。
| 年収 | 700万円 | 800万円 | 900万円 | 1,000万円 | 1,100万円 |
| 借入可能額 | 5,300万円 | 6,000万円 | 6,800万円 | 7,600万円 | 8,300万円 |
| 差額 | 2,400万円 | 1,700万円 | 700万円 | 100万円 | – |
| 返済比率25%での借入額 | 3,800万円 | 4,300万円 | 4,800万円 | 5,400万円 | 6,000万円 |
| 差額 | 3,900万円 | 3,400万円 | 2,900万円 | 2,300万円 | 1,700万円 |
借入可能額で見れば、年収900万円以上はあった方がよいと言えるでしょう。
また、返済比率でみるなら年収1,100万円でもハードルが高くなります。
借入可能額や返済比率25%の数値は、あくまで目安です。
実際に金融機関が算出する借入可能額や自分に適した返済比率は、ケースによって異なります。
そのため、自分の条件に合わせてシミュレーションや、金融機関のサイトをチェックするなどして調べることが重要です。
そのうえで、家購入の計画を立て、希望の家を無理なく購入できるようになるでしょう。
まとめ
住宅ローンの借入可能額は年収によって左右されます。
年収が低い場合、借入可能額を大きくできないため希望の家を購入できないケースもあるでしょう。
その場合は、世帯で収入を合算する、頭金を増やすなどの工夫が必要です。
ただし、借入可能額満額で住宅ローンを組むと、返済の負担が大きくなりすぎる恐れもあります。
借りられる額ではなく、無理なく返済できる額をしっかりシミュレーションしたうえで、住宅ローンを検討することが大切です。