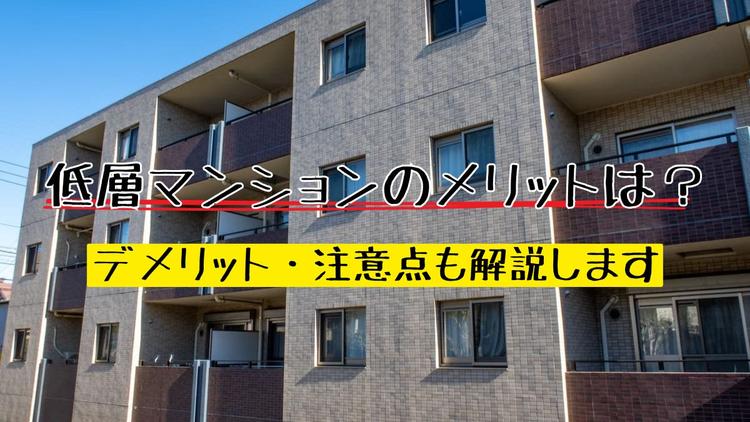日本は地震大国です。阪神・淡路大震災(1995年)以降、多くの分譲マンションで耐震性の確認・補強が課題となってきました。
特に、旧耐震基準(1981年5月31日以前の建築確認)で建てられたマンションは、新耐震基準(同年6月1日以降)より耐震性能が劣る可能性があるため、購入前・居住中を問わず自ら性能を確認する必要があります。
この記事では、管理組合に所属する区分所有者や、これから購入を検討する方でも実践できる耐震性の調べ方について解説します。
建築年と「新旧耐震基準」を確認する
マンションの耐震性を調べるうえで、まず手がかりとなるのが建築年(正確には建築確認日)です。
日本では、1981年6月1日を境に建築基準法の耐震基準が大きく見直されており、これを「新耐震基準」と呼びます。これ以前に建てられた建物は「旧耐震基準」とされ、耐震性が劣る可能性があるため注意が必要です。
旧耐震基準と新耐震基準では、耐震性能に比較的大きな差があり、大規模な地震が発生した際の被害状況にも顕著な差が見られる。
ここで重要なのは、「建築年=完成年」ではなく、建築確認申請が下りた日が基準になるという点です。
たとえば、1981年10月に完成した建物でも、建築確認が5月中に済んでいれば旧耐震基準で設計されている可能性があります。
建物の「建築確認日」を確認するには、以下の方法があります。
- 管理組合に問い合わせる:分譲マンションであれば、管理組合が建築確認済証や設計図書を保管していることがあります。
- 法務局で登記簿を確認する:建物の登記簿に「建築年」が記載されているが、これはあくまで竣工年であり、目安程度にとどまります。
- 役所で「建築台帳記載事項証明書」を取得する:最も確実な方法です。建築主や設計者が行った建築確認申請の内容が記録されており、日付や用途、構造が明記されています。
1981年以降に建てられた新耐震基準の建物であっても、設計・施工の不備や老朽化、地盤条件によっては必ずしも十分とはいえません。一方で、旧耐震基準の建物でも、後年に耐震補強を受けて安全性が高められているケースもあります。
つまり、「建築年=安全」の単純な図式は成り立ちません。まずは建築確認日を調べ、そのうえで診断歴や補強履歴に目を向けることが、正確な耐震性チェックの第一歩となります。
管理組合に耐震診断と補強履歴を尋ねる
建物の耐震性を把握するうえで、管理組合への確認は欠かせません。特に分譲マンションの場合、建物の維持管理や修繕計画は管理組合が主体となって行っており、耐震診断や補強工事に関する情報も保管しているのが一般的です。
まず確認したいのが、耐震診断の実施状況です。耐震診断には段階があり、おおむね以下の3つに分類されます。
- 一次診断:設計図や建築資料をもとに、壁量や柱の配置などを机上で評価するもの。コストは低めだが、精度は限定的。
- 二次診断:実際にコンクリートの「コア抜き」や鉄筋調査を行い、構造強度を詳しく評価。より現実的な耐震性能がわかる。
- 三次診断:コンピュータによる地震応答解析を用いて、震度6強〜7程度の揺れを想定し建物の挙動をシミュレーションする高度な手法。
診断結果は「Is値(構造耐震指標)」として数値化されており、一般にIs≧0.6であれば大地震でも倒壊しにくいとされます。0.3~0.6の場合は補強が推奨され、0.3未満では耐震性が著しく不足していると判断されます。
診断が実施された場合、管理組合には「耐震診断報告書」や「改修工事記録書」「アスベスト除去報告書(補強工事と並行することが多い)」などが保管されているはずです。これらの資料は、理事会や総会の議事録、修繕積立金の使途明細と合わせて確認すると、過去にどのような判断がなされ、どの程度の改修が実施されたのかを具体的に把握することができます。
加えて、管理会社に業務委託している場合は、建物点検記録や耐震補強の提案書などがあることもあります。必要に応じて、管理会社経由で資料の閲覧を申し出るとよいでしょう。
なお、旧耐震のマンションで耐震診断を実施していない場合でも、「未実施であること」自体がリスク情報になります。購入を検討している方は、「なぜ診断をしていないのか」「診断を予定しているのか」といった点も含めて確認し、将来的な補強計画の有無や積立金の状況と合わせて総合的に判断する必要があります。
図面・構造計算書・検査済証を入手する
マンションの耐震性をより専門的・客観的に把握したい場合、設計図面や構造計算書、検査済証などの技術資料を入手して確認することが非常に有効です。これらの資料には、建物の構造的な安全性を裏付ける重要な情報が含まれています。
まず注目したいのが、竣工時の設計図面(竣工図)です。平面図、立面図、構造図などから、壁の配置や柱・梁の太さ、耐震壁の位置などが読み取れます。
これにより、建物全体の構造的バランスが視覚的に把握でき、耐震診断を依頼する際の基礎資料にもなります。
さらに専門性が高いのが、構造計算書です。これは、建物がどのような地震力に耐えられるように設計されているかを数値的に示したもので、梁・柱・壁の断面性能や鉄筋の量、床スラブ(床を構成する鉄筋コンクリートの板)の厚さなどが詳細に記載されています。
新耐震基準に基づいた計算であるか、また、後年の耐震補強を反映して再計算されているかどうかも重要なチェックポイントです。
また、検査済証の有無も見逃せません。これは建物が設計通りに施工され、完了検査に合格したことを示す証明書であり、法令に適合した建築物であることを第三者が認めた証拠となります。
検査済証が交付されていない場合、増改築や補修工事に制約が出る可能性があり、金融機関の融資や売買契約においても不利に働くケースがあります。
これらの資料は以下の方法で入手・閲覧が可能です。
- 管理組合または管理会社に確認する:大規模修繕や売買時に備えて資料が保管されていることがあります。
- 建築設計事務所・施工会社に問い合わせる:原設計者や元請業者が保管している場合もあります。
- 役所で『建築台帳記載事項証明書』を取得する:最も確実な方法です。市区町村の建築主事課で申請でき、手数料は数百円程度です。
なお、古い建物では資料が散逸しているケースも少なくありません。その場合は、耐震診断の際に新たに現地調査を行い、実測値から図面を再構成することも可能です。
いずれにせよ、根拠となる資料があるかないかは、マンションの耐震性を評価する上で大きな分かれ目となります。
耐震基準適合証�明書の有無を確認する
旧耐震基準の建物であっても、適切な補強工事が施され、十分な耐震性能が確保されている場合は、「耐震基準適合証明書」を取得することができます。
この証明書は、建物が現行の新耐震基準に適合していることを第三者が認定する公的な書類であり、売買や税制上の優遇措置を受けるうえで非常に重要な役割を果たします。
証明書の発行には、専門の建築士や指定評価機関による耐震診断の結果(Is値0.6以上など)と、補強工事の実施記録が必要です。診断と補強を経て、新耐震基準を満たしていると判定された場合、申請を行うことで証明書が交付されます。
なお、建物全体が対象となるため、分譲マンションの場合は管理組合単位での取得が前提です。
こうした背景から、この証明書の有無は、特に以下のような場面で大きな意味を持ちます。
- 住宅ローン減税の適用が可能になる
中古住宅を購入する際、旧耐震の物件でも耐震基準適合証明書があれば、築年数要件にかかわらず住宅ローン控除を受けられます。 - 登録免許税・不動産取得税の軽減が受けられる
不動産登記時の登録免許税や、購入後に課される不動産取得税が軽減されるため、数十万円単位の節税につながることがあります。 - 資産価値の証明として有効である
将来的な売却時にも、耐震性能の裏付けとして買い手に安心感を与え、売却価格の維持・上昇に寄与します。
証明書の取得には、耐震診断費や補強工事費を含めて50万~200万円程度のコストがかかることが一般的で��すが、自治体によってはこれらの費用に対する補助制度が用意されています。
購入を検討しているマンションに証明書がない場合は、「証明取得の予定があるか」「過去に申請した経緯はあるか」などを、管理組合に確認しておくとよいでしょう。
なお、耐震基準適合証明書は取得時点での状態を示すもので、恒久的な保証ではありません。証明書があるからといって経年劣化が止まるわけではなく、定期的な点検・補修の履歴とあわせて確認することが重要です。
証明の有無を入り口として、建物の維持管理体制そのものを見極める姿勢が求められます。
▼関連記事:耐震基準適合証明書とは?売買時に取得すべき理由と手続きの流れを解説します
まとめ
マンションの耐震性は、建築年だけでなく、建築確認日、診断・補強履歴、図面や構造計算書の有無、そして耐震基準適合証明書など、多面的に確認する必要があります。
とりわけ旧耐震基準の建物においては、管理組合の対応や記録の整備状況が、安全性と資産価値に直結します。
購入検討中の方はもちろん、既に所有している方も、これらの情報を丁寧に確認・共有しながら、安心して住み続けられる体制を整えていくことが重要です。