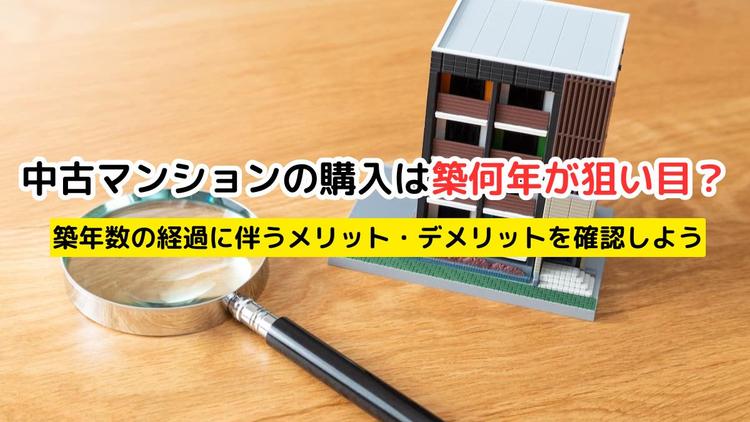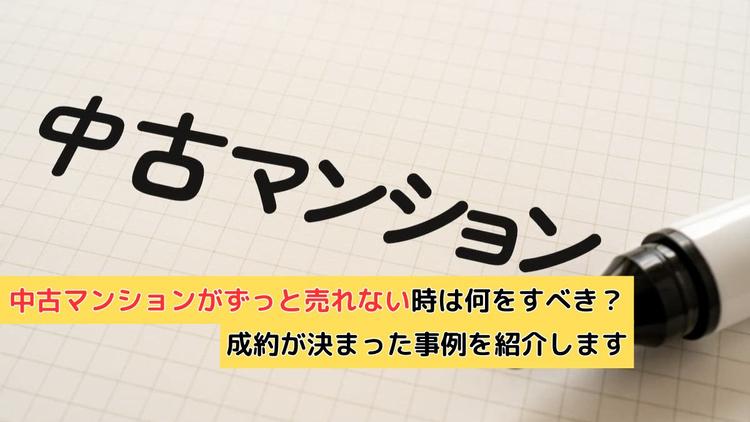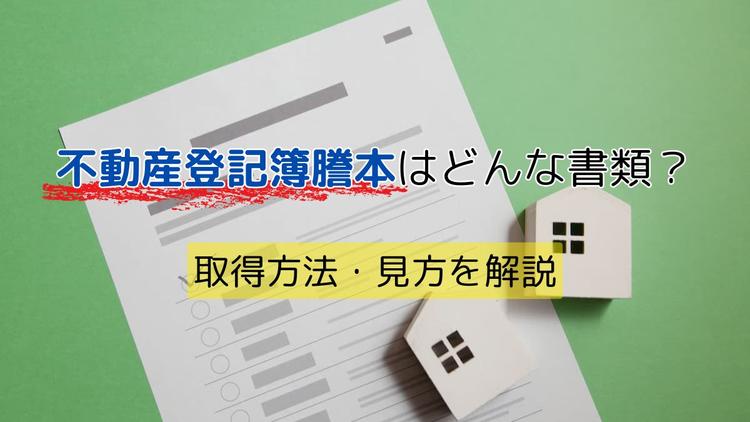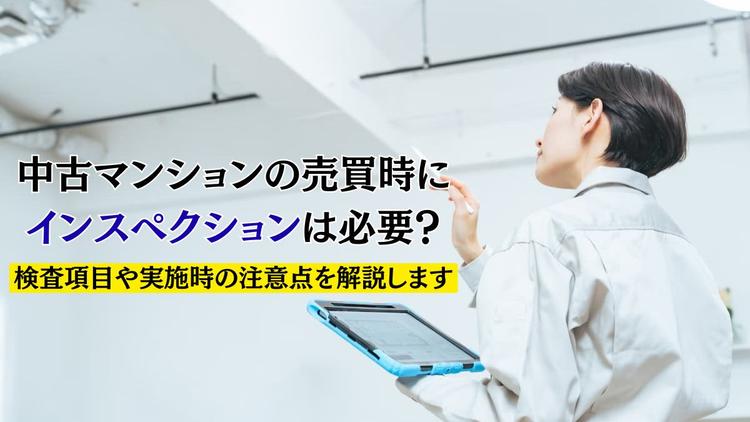中古マンションは、築年数にも価格が大きく左右されます。
とはいえ、築浅から築古まで幅広くあり、築年数によってもメリット・デメリットがあるので、どれくらいの築年数を目安にすればいいか分からないという方もいるでしょう。
中古マンションを購入する際には、築年数に応じた特徴を押さえておくことが大切です。
この記事では、中古マンションの築年数ごとの価格推移やメリット・デメリットを詳しく解説します。
【築年数別】中古マンションの価格推移
中古マンションは、基本的に築年数が経過するほど価格が下がります。
東日本不動産流通機構によると、首都圏における築年数別の中古マンション成約価格は以下のとおりです1。
| 築年数 | 価格 |
| 築0~5年 | 7,808万円 |
| 築6~10年 | 7,158万円 |
| 築11~15年 | 6,619万円 |
| 築16~20年 | 5,972万円 |
| 築21~25年 | 5,320万円 |
| 築26~30年 | 3,835万円 |
| 築31~35年 | 2,455万円 |
| 築36~40年 | 2,742万円 |
| 築41年~ | 2,351万円 |
築年数0~5年に対し築20年までで約24%価格が下がり、築30年を超えると半分以下になっているのが分かります。
ちなみに、同調査で築年数別の成約構成比は以下のとおりです2。
| 築年数 | 価格 |
| 築0~5年 | 9.3% |
| 築6~10年 | 12.9% |
| 築11~15年 | 10.3% |
| 築16~20年 | 13.8% |
| 築21~25年 | 11.9% |
| 築26~30年 | 9.3% |
| 築31~35年 | 6.4% |
| 築36~40年 | 6.1% |
| 築41年~ | 20.0% |
築6年~築25年の価格帯が約半数を占めており人気が高いことが分かります。
この築年数帯は室内の状態が比較的きれいなことが多く、さらに築浅よりも価格が下がることから人気が高くなっています。
ただ、築41年~でも高い需要があり、これは価格を抑えて購入しリフォームやリノベーションする需要があると考えられるでしょう。
このように、マンションの特徴や価格は築年数によっても異なるので、メリット・デメリットや価格感を押さえておくことが大切です。
以下では、築年数ごとに詳しい価格の特徴や購入するメリット・�デメリットを見ていきましょう。
築10年以下のマンションを購入するメリット・デメリット
築10年以下のマンションは状態が良いケースが多く、価格は新築に比べ割安になることから、人気が高い築年数帯です。
価格面における特徴
築10年以下のマンションは、新築に比べ価格が大きく下がる傾向があります。
新築には、新築プレミアムという価格の上乗せが働くため、価格が高騰しがちです。
新築住宅には販売する業者の利益も上乗せされているため、建物自体の価値と差が生じる要因のひとつになっている。
一方、新築プレミアムは新築でなくなったとたん価格が大きく下がるので、築浅物件であっても新築に比べると価格は下がります。
例えば新築で3,000万円の物件を購入し、直後に売却しようとした場合、市場での評価は2,700万円といったように10%近く下がることがあります。
とはいえ、築10年以内は需要が高いことから、一定の価格は維持されるケースが多いです。
▼関連記事:「新築マンションは買うな」と言われる理由は?
購入するメリット
築10年以下のマンションを購入するメリットは以下です。
- 内装や設備の状態が良い
- リフォームの必要がない物件が多い
- 修繕積立金が安い
築10年以下であれば室内や外観の状態が良く、新築とそれほど変わらないケースも多くあります。
築年数による劣化もそれほど進んでいないので、購入後にリフォームする必要がない物件が大半です。
修繕積立金は、築年数に応じて高くなるように設定しているケースが多く、築10年以下であれば築古に比べ低い傾向があります。
マンションでは、経年劣化に伴う補修を行うための資金をプールする「修繕積立金」を所有者から毎月徴収している。築年数の経過とともに修繕積立金の増額を計画しているマンションが多い。
購入するデメリット
築10年以下のマンションを購入するデメリットは以下です。
- 価格が高い
- 築5年以下は物件が少ない
- 設備などに問題が出ているケースもある
築10年以下のマンションは新築に比べれば割安ですが、中古マンションとしては価格が高い傾向にあります。
とくに、築浅と言われる築5年以下は価格が高いだけでなく供給自体も少ないため、築5年以下に限定して物件を探すと選択肢が狭くなります。
また、築10年以下は比較的状態はいいですが、なかには劣化が進んでいるケースもあります。
設備は10年ほどで交換時期を迎えるものも多いので、築10年以下だから大丈夫と考えずに状態はしっかりと確認しましょう。
▼関連記事:築浅でも避けた方がいい物件の特徴
築11年~20年以下のマンションを購入するメリット・デメリット
築11年~20年以下のマンションは、価格と状態のバランスが良く人気の高い物件です。
価格面における特徴
築10年以下の物件は、新築に比べ価格が大きく減少するのに対し、築11年~20年以下は価格の減少の幅が比較的落ち着いてきます。
とはいえ、築浅に比べ2割以上価格が下がるので、購入しやすい価格帯の物件も多くあります。
購入するメリット
築11年~20年以下のマンションを購入するメリットは以下です。
- 内装や設備が大きく劣化していない
- 部屋が広い物件が多い
- 住宅ローン控除を活用しやすい
築20年以下であれば、まだ内装や設備が大きく劣化しておらず、リフォーム費用を抑えつつ住むことが可能です。
また、比較的他の築年数帯に比べて面積が大きいという特徴もあります。
東日本不動産流通機構の築年数別の面積は以下のとおりです3。
| 築年数 | 価格 |
| 築0~5年 | 61.93㎡ |
| 築6~10年 | 65.60㎡ |
| 築11~15年 | 66.62㎡ |
| 築16~20年 | 70.20㎡ |
| 築21~25年 | 71.20㎡ |
| 築26~30年 | 66.45㎡ |
| 築31~35年 | 60.56㎡ |
| 築36~40年 | 57.54㎡ |
| 築41年~ | 56.65㎡ |
築20年前後の物件が、他の築年数帯に比べて面積が広いことが分かります。
築浅のマンションは、資材や人��件費高騰の影響を受けており、建築コスト削減のために専有面積を小さくしているケースが多いのです。
ファミリー世帯などの世帯人数が多いなら、面積の広い築20年前後がお勧めといえるでしょう。
また、住宅ローン控除は中古物件の場合、適用できる借入残高が住宅性能に応じて以下のように分かれます。
- 認定長期優良住宅、認定低炭素住宅など:3,000万円
- 一般住宅:2,000万円
住宅性能表示の交付制度は2000年からスタートしており、それ以降に建築される物件では住宅性能が高水準なケースが少なくありません。
そのため、築20年以下であれば省エネ基準を満たし、住宅ローン控除の上限額が高くなっている可能性があるのです。
住宅性能が優れていれば、税制面だけでなく住み心地にも良い影響が期待できます。
購入するデメリット
築11年~20年以下のマンションを購入するデメリットは以下のとおりです。
- 修繕積立金が高額になる可能性がある
- 購入後にリフォームが必要になりやすい
マンションでは定期的に大規模修繕工事が行われます。
大規模修繕工事は10年~15年を目安に計画されているケースが多く、築11年~20年以下は1回目の大規模修繕工事の時期に該当する可能性があります。
大規模修繕工事が行われる場合、修繕積立金の徴収状況によっては一時金としてまとまった額を徴収される恐れがあります。
また、1回目の大規模工事が終了すると、2回目に向けて修繕積立金が値上げされるケースもあるので注意しましょう。
築20年以下は比較的リフォーム箇所が少なく、そのままでも住める可能性があります。
しかし、築年数による劣化は確実に進行しているため、入居後早い段階でリフォームが必要になるケースも多いのです。
とくに、配管の交換が必要となると修繕費が高額になりがちなので、購入前にリフォーム履歴をチェックし購入後の修繕費まで資金計画を立てておくようにしましょう。
築21年~35年以下のマンションを購入するメリット・デメリット
築21年~35年以下のマンションは、価格を抑えやすいことからリフォームを前提に購入する人におすすめの物件です。
価格面における特徴
築21年以降も価格の下落は続き、とくに築30年を超えると築0~5年と比べ半分ほどまで価格が下がります。
築26年を超えると、比較的購入しやすい3,000万円まで下がってくるので、リフォーム・リノベ�ーション費用を考慮しても新築よりもコストを抑えやすいでしょう。
購入するメリット
築21年~35年以下のマンションを購入するメリットは以下のとおりです。
- 価格を抑えて購入できる
- 新耐震性基準で建てられている
- 管理状態をチェックできる
先述のとおり、築30年を超えると築浅に比べ価格が半分ほどに下がります。
仮に、フルリノベーションで1,000万円かけたとしても、築浅や築20年以下の物件よりもトータルコストを抑えられる可能性があるでしょう。
マンションの価格を抑えやすくリフォーム・リノベーションに費用をかけやすいため、自分の好みの家の実現もしやすくなります。
また、耐震基準は1981年6月1日以降の新耐震基準と、1981年5月31日以前の旧耐震基準に分かれますが、築35年であっても新耐震基準が適用されています。
新耐震基準であれば耐震性に安心しやすいだけでなく、住宅ローン審査や税制控除の上でも有利になりやすいでしょう。
旧耐震基準と新耐震基準では、耐震性能に比較的大きな差があり、大規模な地震が発生した際の被害状況にも顕著な差が見られる。
築30年前後は2回目の大規模修繕工事の前後の時期です。
1回目の大規模修繕工事は問題なく行えても、2回目は資金難などで実施されないケースもあります。
反対に、2回目の大規模修繕工事やそれまでのメンテナンスが適切にされているマンションであれば、管理状況が良いといえます。
管理状況の長期の履歴からしっかり判断できるのも、築年数が経過したマンションのメリットです。
購入するデメリット
築21年~35年以下のマンションを購入するデメリットは以下のとおりです。
- 住宅ローンの借入期間が短くなりやすい
- 修繕積立金が高くなりやすい
- リフォーム費用が高額になりやすい
住宅ローンは基本的に、法定耐用年数を超える期間で借入できません。
マンションで一般的なRC造りの場合、法定耐用年数は47年です。
仮に、築35年で購入する場合、47年-35年=12年までしか住宅ローンが組めないため、希望額を借入できなかったり、返済の負担が大きくなるといった恐れがあるでしょう。
修繕積立金は築年数に応じて高くなるケースが一般的です。
修繕積立金が高いと初期費用を抑えられても毎月の負担が大きくなりやすいので、事前に資金計画をたてておくようにしましょう。
2回目の大規模修繕工事が直前という場合も、事前の一時金徴収や値上げの恐れがあるため、購入前に工事計画などを確認することが大切です。
マンション価格を抑えた分リフォーム費用に充てやすいといっても、リフォーム費用が高額になる可能性もあります。
築30年前後は、ほとんどの設備交換だけでなく配管の交換も必要というケーも多いので、リフォーム費用込みで予算計画を立てるようにしましょう。
築36年~のマンションを購入するメリット・デメリット
最後に、築36年~のマンションについてみていきましょう。
価格面における特徴
築36年を超えると築0~5年に比べ価格は7割ほどまで下がります。
しかし、以降は価格の減少幅は緩やかになるため、価格はほぼ底に近いといえるでしょう。
そのため、安く購入でき売却しても損失を出しにくいお得な物件と言えます。
購入するメリット
築36年~のマンションを購入するメリットは以下のとおりです。
- 安値で購入できる
- 立地が良い物件が多い
築36年~のマンションは築浅に比べ3分の1ほどの価格で購入できるので、リフォーム・リノベーション費用を考慮してもコストを抑えやすい物件です。
また、早く建てられたマンションほど立地が良いケースが多いため、築浅に比べ立地がよいマンションも多くあります。
築浅よりも物件数も多くなるため、エリアを優先して物件を探したいなら築古のマンションを視野に入れた方が選択肢の幅は広くなるでしょう。
購入するデメリット
築36年~のマンションを購入するデメリットは以下のとおりです。
- 耐震性に不安がある
- 住宅ローンの審査に不利になる
先述のとおり、新耐震基準は1981年6月1日以降となるため、築36年以降のマンションは旧耐震基準で建てられている可能性が高くなります。
旧耐震基準であってもすぐに倒壊するわけではありませんが、新耐震基準に比べ倒壊リスクは高くなるので注意が必要です。
さらに、旧耐震基準では住宅ローンの対象外になるケースも多いため、住宅ローンを利用できる物件かは事前に確認するようにしましょう。
狙い目の築年数は?
価格と状態のバランスでいえば、築11年~20年以下の物件が狙い目です。
築20年以下であれば劣化がそれほど進んでおらず状態が良いケースが多いうえ、価格も築浅よりも大きく下がります。
また、住宅ローンや各種税制控除を活用しやすいといったメリットもあるため、トータルでお得になる可能性があるでしょう。
2000年以降に建築されていれば、現行の耐震基準である2000年基準を満たしている点も、安心して住みやすい大きな要因となります。
ただし、価格は中古マンションとしては高い部類に入り、購入後にリフォームが必要なケースもあるので、状態はしっかりチェックし資金計画を念入りに立てることが重要です。
築11年~20年以下に限らず、それぞれの築年数帯に魅力やデメリットがあります。
価格が高くても状態の良さや設備の充実した物件が良ければ築浅が適しており、価格を抑えてリフォームしたいなら築古がおすすめです。
また、築年数が古くても状態が良い物件もあれば、築年数が浅いのに状態が悪い物件もあるように、築年数だけでは一概に良い・悪いは言えません。
どの築年数が適しているかは購入の目的などによっても異なるので、築年数だけに固執せず信頼できる不動産会社に相談しながら自分にぴったりの物件を探すようにしましょう。
中古マンションの築年数に関するよくある質問
最後に、中古マンションの築年数に関するよくある質問をみていきましょう。
中古マンションを買うなら築何年がいい?
価格と状態のバランスで言えば築11~20年以下がおすすめです。
しかし、築浅なら状態が良く設備が充実しているというメリットがあります。
反対に、築年数が古ければ立地の良さや価格を抑えて自分で好きにリフォームできるという魅力があるでしょう。
予算や購入の目的に応じて自分に合ったマンションを選ぶことが重要です。
築20年の中古マンション購入で後悔する事例とは?
築20年のマンションを購入して後悔する事例としては、以下のようなケースがあります。
- リフォーム費用が高額になった
- 修繕積立金が高額でランニングコストが高い
- スムーズに売却できなかった
比較的リフォーム費用は抑えやすいですが、状態によっては配管や設備を丸ごと交換しないといけないなどで、費用が高額になるケースもあります。
事前にリフォーム履歴や見積もりを取ったうえで、予算計画を立てるようにしましょう。
また、修繕積立金も高額になりやすいので、長期的なランニングコストを考慮することも大切です。
築20年で購入し、10年所有してから売却するとなると築30年になっています。
築年数が経過しているマンションは売却時に不利になる恐れもあるので、購入の段階から売却も踏まえ資産価値の落ちにくい物件を選ぶことが大切です。
▼関連記事:安い中古マンションを買って失敗するケースとは?
築35年の中古マンションはいつまで住める?
マンションの法定耐用年数は47年のため、法定耐用年数でみればあと12年で資産価値はゼロです。
しかし、法定耐用年数はあくまで税務や会計上で使用するものであり、実際に住める期間とは異なります。
国土交通省によると、RC造りの寿命は鉄筋コンクリート部分で120年、外装仕上げにより150年まで延命できるという調査もあり、耐用年数を超えてもメンテナンス次第で長期間住み続けられるでしょう4。
まとめ
中古マンションは築年数が経過するほど価格が下がります。
築年数によって特徴やメリット・デメリットは異なるので、それぞれ押さえたうえで自分に合った物件を選ぶことが大切です。
また、購入時には売却のことも視野に入れ資産価値の高い物件を選んでおくことをおすすめします。
売却の目的や予算・将来の資産価値などを踏まえて、信頼できる不動産会社に相談しながら満足いく物件を選ぶようにしましょう。