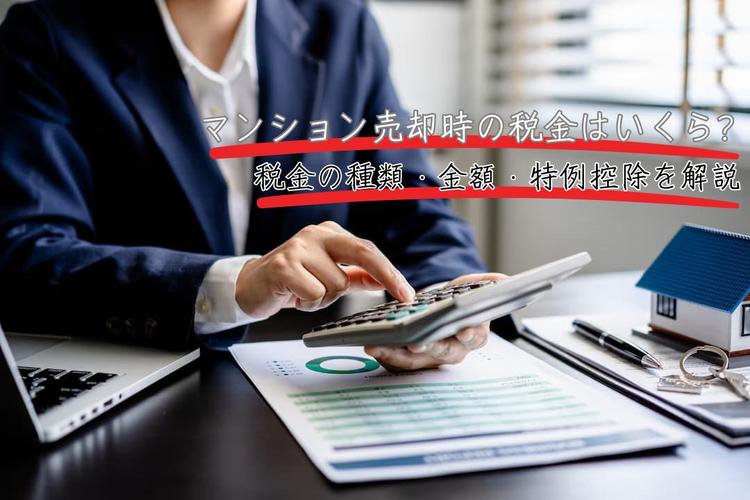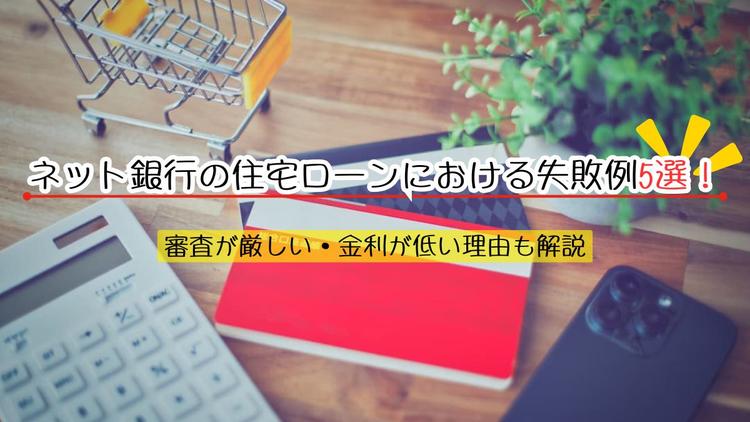マンションの売却で必ず関わってくるのが税金です。納めるべき税金がよく分からずに、マンション売却を不安に感じる方もいるのではないでしょうか。この記事では、マンションを売却したときの税金の種類や金額について解説をします。
マンション売却でかかる税金の種類
マンションを売却したとき、関係する税金として次の3種類があります。
- 印紙税
- 登録免許税
- 譲渡所得税(所得税・住民税)
また、2037年まで、所得税には復興特別税が加算されます。
それぞれの税金の概要を紹介していきましょう。
印紙税
印紙税は、マンションを売却する際に買主と交わす売買契約書に貼る収入印紙にかかる税金です。
記載された金額に応じて税額がきまり、契約書に収入印紙を貼ることで納税します。
印紙税の税額と納税時期
印紙税の税額は次のとおりです。
- 500万円を超え1千万円以下 ……1万円
- 1千万円を超え5千万円以下……2万円
- 5千万円を超え1億円以下……6万円
- 1億円を超え5億円以下……10万円
ただし、土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書で、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成されるものは、次のように軽減されます。
- 500万円を超え1千万円以下 ……5千円
- 1,000万円を超え5,000万円以下……1万円
- 5,000万円を超え1億円以下のもの……3万円
- 1億円を超え5億円以下のもの…… 6万円
印紙税は、購入した収入印紙を契約書に貼り付けて納税完了となりますので、納税の時期は契約時となります。
マンションの売買契約書は、買主と売主がそれぞれ1通ずつ原本を保管します。収入印紙も双方の契約書に貼り�付けるので、印紙税は買主と売主で折半するのが一般的です。
登録免許税
登録免許税は、マンションの所有権を売主から買主へ移転する際の登記手続きに伴って支払う税金です。ただし、売買に伴う所有権移転登記は、買主が行うのが一般的ですので売主には登録免許税は発生しません。
売主に関係するのは、抵当権の抹消登記に関わる部分です。抵当権の抹消登記とは、マンション購入の際に組んだ住宅ローンの担保として設定されていた抵当権を取り除く手続きのことです。
登録免許税の税率と納税時期
マンションの購入時に住宅ローンを利用している場合、返済の保証として抵当権が設定されています。売却の際には、この抵当権を外さなければなりません。
そのため抵当権抹消の登録免許税が必要になります。抵当権抹消登記の登録免許税は、不動産1件につき1,000円です。マンションでは、土地と建物がありますので、それぞれ抵当権抹消登記が必要になり、合計で2,000円です。
譲渡所得税(所得税・住民税)
譲渡所得税は、マンションを売却して譲渡所得が発生した際にかかる税金です。譲渡所得とは、売却で生じた所得を指します。確定申告で所得税を納めると、後日、地方自治体から住民税の納付書が届きます。
万が一、売却額が購入したときの価格よりも安くなったなどの理由により譲渡所得が発生しなかった場合には、譲渡所得税は発生しません。
譲渡所得税は高額になることがあるので、次の項で詳しく解説します。
復興特別税
復興特別税とは、東日本大震災の復興のために使われる税金で、2037年まで��、所得税にこの復興特別税が加算されます。
復興特別税にかかる税率は所得税額の2.1%で、マンションを売却した翌年に譲渡所得税の確定申告をする際に同時に提出する形になります。
譲渡所得税の税率と納税時期
譲渡所得税は、マンションの売却で譲渡所得があれば発生する税金です。
譲渡所得税の税率と納税時期を解説していきましょう。
譲渡所得とは
譲渡所得とは、マンションを売却したときに得られる収入からその物件の取得費用と不動産会社への仲介手数料、土地の測量費、登記費用などの諸費用を引いた金額です。
譲渡所得税では、まず譲渡所得を次の式により算出します。
計算する際に注意したいのが、取得費に含まれる「建物の購入価格」です。建物の購入価格はそのまま合算せずに「減価償却費」を差し引かなければなりません。
減価償却費とは、経年劣化によって下がった建物の価値です。減価償却費の計算方法には「定額法」と「定率法1」がありますが、建物では定額法が用いられます。
定額法は次のように計算します。
もし資料の紛失などでマンションの取得費が分からない場合は、譲渡収入額の5%を取得費とする簡便な方法を用いることができます。
関連記事:減価償却費の計算方法
譲渡所得税の税率
譲渡所得税の税率は、マンションの所有期間によって異なります。所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」であり、5年を超える場合は「長期譲渡所得」です。それぞれの税率は次のとおりです。
- 短期譲渡所得の税額=短期譲渡所得×(所得税30%+住民税9%)
- 長期譲渡所得の税額=長期譲渡所得×(所得税15%+住民税5%)
これに2037年(令和19年)まで復興特別税(基準所得税額×2.1%)が加算されるので、最終的な税率は次のようになります。
- 短期譲渡所得の税額(5年以下)……39.63%
- 長期譲渡所得の税額(5年超)……20.315%
マンションの所有期間は、実際に所有していた期間ではなく、マンションを取得した日から売却した年の1月1日の時点で決まります。たとえば、2019年3月に取得したマンションを2024年10月に売却すると、実際の所有期間は5年7カ月ですが、税法上は4年10カ月が所有期間になります。
これにより、短期譲渡所得として扱われ、税率は39.63%が適用されます。
譲渡所得税の計算(短期譲渡所得)
マンションを3,000万円で売却した場合の税金をシミュレーションしてみましょう。売却したマンションの要件を次のとおりとします。
- 売却価格…… 3,000万円
- 売却時にかかった経費…… 100万円
- 所有期間…… 4年11カ月
- 取得費…… 2,000万円
まずは譲渡所得を算出します。譲渡所得は、マンションを購入した価格と経費を売却価格から差し引いた価格です。
これにより、900万円が譲渡所得となります。
マンションの所有期間は4年11カ月ですから、短期譲渡所得となり、適用する税率は39.63%です。
所有期間4年のマンションを売却したときの譲渡所得税は約356万円となります。
譲渡所得税の計算(長期譲渡所得)
それでは同じ条件のマンションを5年2カ月所有して3,000万円で売却した場合の譲渡所得税はどうなるでしょうか。
譲渡所得は短期譲渡所得と同じ900万円とします。
マンションの所有期間は5年2カ月ですから、譲渡所得税の適用する税率は20.315%です。
長期譲渡所得の税額は約182万円です。売却時期が3カ月違うだけで、短期譲渡所得の税額と比べて、約174万円安くなることが分かります。
所得税の納税時期
譲渡所得税の納税時期は、マンションを売却した翌年の確定申告の期間になります。つまり、2月16日から3月15日(土日祝日に該当する場合は翌平日)までです。
また、申告の際に振替納税の手続きをすることもできます。その場合、4月頃に銀行口座から自動で引き落とされます。
住民税の納税時期
住民税は所得税の確定申告をすることで手続きが不要になります。
�申告した年の5月以降に地方自治体から納付書が届くので、一括払いか年4回の分割払いを選択し、いずれかの方法で納税します。
譲渡取得税の節税方法
マンションの売却で譲渡益(利益)が出ると、譲渡所得税が発生します。譲渡益が大きければ、思わぬ高額になることがありますから、節税方法を有効に活用することが非常に重要です。
節税には次のような方法があります。
- 譲渡益の計算を精査する
- 3,000万円特別控除の利用
- 居住10年超で売却する
- ふるさと納税の利用
- 取得費加算の特例の利用
譲渡所得税に活用できる節税方法について、項目ごとに解説していきましょう。
譲渡益の計算を見直す
譲渡所得税の申告では、正確な計算をすることが重要です。それぞれの項目に見落としがないよう精査することが節税に繋がります。
取得費の根拠資料を探す
マンションを購入したときの費用は、譲渡収入金額から所得費を控除することができるので、所得費の正確な金額を提示することが譲渡所得税の節税につながります。
マンションの購入費用の根拠としては、売買契約書や領収書が非常に有力です。
もしこれらの資料を紛失して明確な取得費がわからない場合「譲渡価額の5%」から算出した概算取得費を用いることになり、譲渡所得が大きくなる点に注意しましょう。
売買契約書が見当たらない場合は、住宅ローンの金銭消費貸借契約書や登記の抵当権設定額から取得費を推測する方法もありますが、税務署によっては認めてもらえないことがあるので、事前の確認が必要になります。
なお前�述の通り、購入した費用のうち建物の価格については、築年数に応じて減価償却をする必要があるので注意してください。
取得費に経費を加算する
マンションの取得にかかった経費を取得費に加算することで、譲渡所得を減じることができます。たとえば、次のような項目は取得費に加算することができます。
- 不動産会社への仲介手数料
- 売買契約書に貼付けした印紙代
- 所有権移転登記したときの登録免許税
- 司法書士への報酬
- 不動産取得税
- 購入時の整地、埋立て、地盛りの費用、下水道、擁壁の設置費用
- リフォーム費用
これらの諸経費は、取得時の購入額に加えて土地と建物に配分しますが、建物に配分された分は建物購入額として減価償却を行います。
またリフォーム費用は、リフォームをした時期に、全額を建物購入額として加えます。その後、建物購入額として減価償却を行います。
譲渡費用を精査する
譲渡費用についても精査することで、節税となります。
譲渡費用としては、つぎのような支出が計上できます。
- 売買契約書の印紙代
- 売却活動時の広告料
- 売却のために測量した測量費
- 売却のために鑑定をした場合の鑑定料
- 登記費用
ただし、次のような支出は譲渡費用として認められません。
- 抵当権抹消費用
- 遺産分割のために要した支出
- 移転先家屋の購入費、修繕費、移転費用等
- 譲渡資産の維持管理費等
- 引越代
3,000万円特別控除の利用
一定の要件を満たすマイホームの売却であれば、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(3,000万円特別控除)」を使って譲渡所得税を節税することができます。
3,000万円特別控除を利用した場合、譲渡所得は次のように計算します。
一定の要件を満たすマイホームは「居住用財産」と呼ばれます。3,000万円特別控除が適用できる居住用財産とは、次の要件を満たした不動産です。
- 自分が住んでいる家屋を売る。転居した場合は、住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売ること。
- 売った年の前年および前々年にこの特例の適用を受けていない。
- 売った年、その前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていない。
- 売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていない。
- 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
- 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
居住10年超で売却する
譲渡所得税は、所有5年以下であれば短期譲渡所得、5年超であれば長期譲渡所得の税率が適用されます。長期譲渡所得の方が税率が低いので、売却の時期が所有5年前後であれば、長期譲渡所得が適用される期間を待ってから売却すると節税できます。
また、所有期間が10年を超えると「所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(軽減税率の特例)」を適用することで、さらに税率が低くなります。
適用される長期譲渡所得の軽減税��率は次のとおりです。
課税長期譲渡所得金額
- 6,000万円以下……課税長期譲渡所得金額×10%
- 6,000万円超……(課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×15%+600万円
譲渡所得金額は、3,000万円特別控除の適用後の譲渡所得です。
この軽減税率の特例の適用を受けるには、次の5つの要件すべてに当てはまることが必要です。
- 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地を売ること。転居した場合には、住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売ること。
- 売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。
- 売った年の前年および前々年にこの特例の適用を受けていないこと。
- 売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例の適用を受けていないこと。
- 親子や夫婦など「特別の関係がある人」に対して売ったものでないこと。
ただし、軽減税率の特例は住宅ローン控除と併用することができません。
マイホームの買換え特例の利用
居住用財産の売却で譲渡所得が3,000万円を超える場合には、居住用財産の買換え特例を利用する方法もあります。
居住用財産の買換え特例は、売ったマンションよりも新しく購入した家のほうが高ければ、課税を繰り延べできるという特例です。
譲渡所得が3,000万円を超える場合には、3,000万円特別控除を利用しても譲渡所得は一部残ったままになるので、居住用財産の買換え特例を使うことで売却時の税負担が軽減できます。
ただし、この特例は控除ではなく、今回の売却時点で��は課税しないということに過ぎません。将来、買換えた物件を売却する時期が来れば、今回の売却に遡って課税されることになります。
譲渡所得が3,000万円を超えていて、今回の売却では税負担を避けたいという場合であれば、居住用財産の買換え特例を検討するのもひとつの選択肢です。
ふるさと納税の利用
ふるさと納税は、地方自治体からの返礼品が社会的注目を受集めている制度ですが、法律上は寄付行為であり、寄付をすることで寄付金控除を受ける仕組みです。
ふるさと納税の控除上限額内であれば、寄付合計額から自己負担である2,000円を控除した額が、住民税から控除(所得税から還付)されることになります。
所得が増えることで、ふるさと納税控除上限額も増えるので、不動産売却によって所得が増えた年は、例年以上の返礼品が期待できます。
さらに、ふるさと納税は住宅ローン控除と併用することが可能です。新居物件を購入した際に住宅ローン控除を利用するのであれば、ふるさと納税は効果的な節税対策となり得ます。
関連記事:不動産を売却して、所得が増えた際のふるさと納税の利用方法
取得費加算の特例の利用
取得費加算の特例は、親から相続したマンションを売却する際に、そのマンションの取得費として相続税の一定額を加算できる制度です。
譲渡所得税は、売却した金額から物件の購入費や手数料などの経費を差し引いた利益に対して発生します。これに取得費加算の特例が適用されれば、マンションの相続税を経費として差し引くことができるのです。
相続したマンションを売却する場合は、譲渡所得税のほかに相続税もかかることがあるので、売主の負担は大きくなります。しかし、この特例によって、相続税が発生しても譲渡所得税を抑えることが可能です。
譲渡損失が発生したときの税金対策
マンションを売却しても利益があるとは限りません。相場が下落した、想定した価格で売れなかったなどの理由で、譲渡損失が発生したときの税金対策としては、次の方法があります。
- 居住用財産の買換えにかかる譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例の利用(マイホームの譲渡損失の買換え特例)
- 居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例の利用(マイホームの譲渡損失の特例)
それぞれ解説していきましょう。
マイホームの譲渡損失の買換え特例
居住用財産の買換えで譲渡損失が発生した場合、マイホームの譲渡損失の買換え特例を利用することで税金の還付を受けることができます。
たとえば年収600万円の会社員が、売却により1,000万円損失したとします。この年600万円の収入に対して1,000万円損失したことで、損益通算によってこの年の所得をマイナス400万円とすることができます。
会社は年収600万と見込んで源泉徴収をしていますので、確定申告することで天引きされていた源泉徴収税額の還付を受けることができます。
この年で控除しきれなかった損失は繰越控除によって翌年以降3年間繰り越すことができます。
マイホームの譲渡損失の特例
住宅ローン残債よりも売却額が下回ることをオーバーローンといいます。
買換えを伴わない、単独の�売却でオーバーローンとなる場合には、マイホームの譲渡損失の特例を利用することで節税をすることができます。
マイホームの譲渡損失の特例も、マイホームの譲渡損失の買換え特例と基本的には同じですが、譲渡損失の買換え特例では譲渡損失部分が全額繰越控除限度額となるのに対し、マイホームの譲渡損失の特例ではオーバーローンの部分のみが繰越控除限度額となります。
還付が受けられる効果は前項のマイホームの譲渡損失の買換え特例の方が大きいので、買換えであれば、そちらの特例を利用してください。
このマイホームの譲渡損失の特例は、オーバーローンになるマンションを売却し、買い替えしない(賃貸物件等に住む)「単純売却」の場合に有効な特例です。
マンション売却に伴う確定申告の注意点
マンションを売却して納税するときには確定申告が必要ですが、いくつかの注意点があります。
確定申告を忘れない
確定申告は、1月1日から12月31日までに得た所得について行う手続きです。申告する期間は翌年の2月16日から3月15日までです。つまり、マンションの売却で収益があれば、売却した年の翌年に確定申告を行う必要があるのです。
確定申告を怠ると、加算税や延滞税などのペナルティが発生します。確定申告の時期を過ぎてから申告を忘れていることに気づいた場合には、「期限後申告」を行うことができますので、急いで手続きを進めてください。
控除や特例の利用を忘れない
マンションの売却に伴う譲渡所得に対しては、3,000万円特別控除などさまざまな特別控除や特例が設けられています。これらを利��用できるのは確定申告のときです。確定申告に際しては、どのような控除を利用するのかを見定めたうえで、必要な手続きを行ってください。
マンションの売却で利益がなければ確定申告は不要
マンションの売却で損失が発生した場合は、そのマンションの売却に関しての所得税や住民税の納付はないため、そのために確定申告を行う必要はありません。
一方、長期譲渡所得に該当する居住用財産を譲渡した際に損失が生じた場合、その金額について一定の要件を満たせば、譲渡をした年に給与所得など他の所得との損益通算をすることができます。
確定申告を行うことでトータルとして節税になることがあるので、検討する価値があります。
まとめ
マンションの売却に伴って支払うべき税金は、主に印紙税、登録免許税、譲渡所得税の3種類です。
特に譲渡所得税は、売却による利益が大きいほど納める税額も高額になるため、しっかりと対策を講じることが重要です。
この記事でご紹介した特例や控除を活用することで、税金負担を軽減できる可能性があります。
譲渡所得税の計算や特例の適用は、複雑で見落としがちですが、適切に対応すれば大きな節税効果を得られることもあります。
もしマンション売却を検討しているのであれば、まずは税金に関する知識をしっかりと把握し、専門家に相談することをおすすめします。
適用できる特例控除などを確認し、売却の成功と最大限の利益を手に入れましょう。