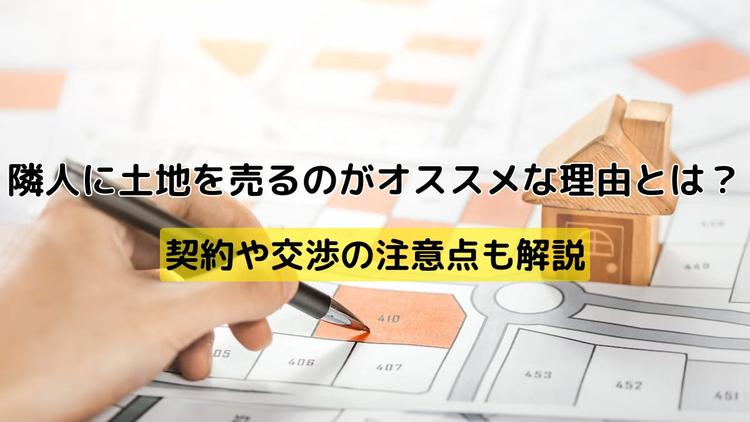空き家になった実家を売却しようとしたら、「市街化調整区域」にあることを知りました。これはネックになるのでしょうか?
「市街化調整区域」は市街化を抑制するエリアで、例えば駅やスーパーなど、生活をする上で便利な施設が少なかったりすることがあります。
購入者にとってもデメリットになりそうですね。なぜそのようにエリアを制限する必要があるのでしょうか?
その理由のひとつとして、建築制限が厳しいことが挙げられます。「市街化調整区域」というだけで、建築不可だと考えている人は少なくないんですよ。
えっ…本当に市街化調整区域では、建て替えができないのでしょうか!?
気になりますよね。それでは、この記事では「市街化調整区域」で建築をする方法と物件を売却する際の注意点を解説していきましょう。
市街化調整区域とは
都道府県は、市町村の市街地を含む一定のエリアを都市計画区域に指定します。
都市計画区域は、さらに市街化区域と市街化調整区域(不動産会社では「調整区域」と呼ばれることが多い)とに区分されます。
計画的に市街化を図るべき区域です。行政は積極的にインフラを整備して建物が建てられる環境を整備します。
市街化を抑制すべき区域とされています。このため市街化調整区域では、建築行為が厳しく制限されています。
たとえば住宅であれば、既存宅地以外の場所で新築できるのは農業従事者とその家族に限定されています。
会社勤めの人が、見晴らしのいい土地を見つけて、定年後に家を建てたいと思っても、そこが市街化調整区域であれば、たとえ自己所有地であったとしても建築は許可されません。
このため「市街化調整区域は憲法で保障する財産権を侵すものではないか」と国会で質疑が出されたことがありましたが、政府は「都市機能の低下と公共投資の非効率化を防ぐものであり、公共の福祉に適合している」と答弁しています1。
なぜ市街化調整区域に建築物があるのか
市街化調整区域内を移動していると、いくつかの建物があることに気づかされます。
建築行為が厳しく制限されているのに、なぜ建築物が存在しているのでしょうか。
そこにはいろいろな理由があります。
市街化調整区域に建築物が存在している根拠を解説していきましょう。
農家住宅
農業従事者が居住する住宅は、市街化調整区域であっても建築することが可能です。
農業従事者とは、単に農作物を栽培しているだけではなく、10アール以上の市街化調整区域内の農地で年間60日以上農業に従事している農家の世帯責任者をさします。
農業従事者であることを証明するために、農業委員会で農業従事者証明を交付しています。
農業従事者ばかりでなく林業従事者や漁業従事者が居住する住宅も同様の扱いになります。
農業用建築物
農業従事者が使用する農業用倉庫や作業小屋等の農業を営むのに欠かせない建築物を建築することは可能です。
公益上必要な施設
駅舎などの鉄道施設、図書館、公民館、学校などの公益上必要な施設は建築が認められています。
またデイサービス等の社会福祉施設も許可の条件に適合すれば建築ができます。
線引き以前から存在していた建物の建て替え
都市計画法は1968年に施行された法律です。
法の施行を受けて都道府県では、1970年代から都市計画区域を制定し、市街化区域と市街化調整区域の区分をしました。
この区分は一般的に「線引き」と呼ばれています。
線引きが行われる以前から市街化調整区域に存在して�いた建物は、同規模同用途であれば建て替えが認められています。
たとえば古くから旅館を営んでいたのであれば、同規模の旅館として建て直すことは可能です。
この場合の同規模とは既存建物の延べ床面積の1.5倍以内の範囲です。
旧住造法で造成された宅地の建物
かつては、一定規模の宅地造成を規制するために住宅地造成事業法という法律がありました。
現在では廃止された法律ですが、これに基づき造成された宅地であれば、建築することは可能です。
日用品店舗
市街化調整区域居住者のための日常生活物品、加工、修理の業務を営む店舗で、床面積が50平方メートル以内のもので、市街化調整区域居住者が営む店舗であれば建築は可能です。
地区計画区域内の建築物
既存の集落などで地区計画を制定することで、市街化区域のように建築することが可能です。
空き家対策に有効な手法として、各自治体で取り組みが進められています。
世帯分離住宅
農業従事者の子ども世帯で、基本的に建築が認められているのは、農業後継者のみです。
この原則どおりに運用すると、たとえば長男が農業後継者であれば、二男や三男は集落内に家を建てられないことになります。
しかし市街化調整区域の農業従事者は広大な敷地を有していることが多く、やがて二男や三男にも相続されることになります。
こうした土地を有効に活用できないのは不合理であることから、やむを得ない事情があり、一定の条件を満たしていれば、開発審査会の同意を得たうえで世帯分離住宅の建築が許可されます。
なお「��やむを得ない事情」として認められる基準は、都道府県によって異なりますが、次のようなケースが考えられます。
- 婚姻により独立して世帯を構成する場合
- 退職、転勤等により現住宅を立ち退かなければならない場合
- 現に居住している住宅が狭小過密である場合
- 疾病等の理由により転地のやむを得ない事情がある場合
- Uターンにより故郷に定住する場合
農家住宅は売却できるのか
市街化調整区域であっても不動産の売買自体は自由に行うことができます。
しかし、住宅ローンを利用して購入しようとしても、都市計画法に適合している物件でないと、融資を受けることはできません。
したがって農家住宅を一般の会社員が購入しようとしても、住宅ローンの融資が受けられないのです。
それでは、農家住宅は売却できないのでしょうか。
農家住宅として売却するケースと一般住宅として売却するケースをみていきましょう。
農家住宅としてはまず売れない
市街化調整区域の農家住宅を農業従事者に売却する場合、都市計画法上の手続きは一切不要です。
しかし結論からいえば、農家住宅を購入する農業従事者は、まずいないでしょう。
売却しようとする物件のエリアに住む農業従事者は、ほぼ全員が何らかの形で住宅に住んでいるからです。
また農業後継者もやがて相続する土地に新居を構えるのが一般的であるため、わざわざ他人の住宅を購入する可能性は極めて低いといえます。
一般住宅として売るために用途変更申請をする
農家住宅は、一般住宅として売り出す方法が現実的です。
現在、国は空き家対策として、既存住宅の用途変更を状況に応じて行う運用方針を打ち出しています。
運用方針には拘束力がないため、実際にどのように運用するかは、都道府県の判断に委ねられていますが、現在多くの都道府県で、農家住宅から一般用住宅への用途変更を認める流れに�なっています。
ただし転売目的の農家用住宅の建築を防ぐために「10年以上農家住宅として使用した実績がある」といった判断基準が定められています。
この用途変更が認められれば、誰でも住宅として利用でき、建て替えも可能になりますから、売却する際の支障はありません。
自治体によっては、国の弾力化方針を受けて民泊や農家レストランへの用途変更を認めていることもありますから、購入希望者の間口も広くなっています2。
用途変更の許可申請は農業従事者が行う
用途変更を行うには許可申請が必要ですが、この場合の申請者は、不動産の所有者である農業従事者に限られます。
万が一用途変更許可を受けないまま、一般住宅として売却をすると、次の買主は用途変更が行えないばかりか、増築や建て替えに関するすべての許可申請が認められない、事実上の再建築不可物件になる可能性があります。
不動産を有効に生かすためにも、農業従事者である所有者の用途変更許可申請は不可欠です。
ただし、農村部の空き家対策は大きな課題になっていることから、農村に移住した人が取得した住宅の用途変更を認める方針が打ち出されています。
具体的な事案については市区町村の窓口で相談するのが良いでしょう3。
▼関連記事:農地転用して売却するための手続き
建築敷地を増やすことはできない
市街化調整区域においても建ぺい率や容積率の制限があります。
既存住宅よりも大きな家を建てるために隣地を買い足しても、敷地を増やした部分は建築敷地とは認められません。
線引き以前から建てられていた住宅は売却できる
市街化調整区域の線引き以前に既に建っていた建築物は、同規模同用途であれば、建て替えを行うことができます。
このため線引き以前から建築物があったことを証明できれば、売却も比較的スムーズに行うことが可能です。
線引き以前からあったことを証明する
市街化調整区域で住宅の建て替えや増築を行う場合、建築確認申請書に開発許可不要証明書を添付する必要があります。
この証明書を得るためには、線引き以前に建てられていた建築物であることを客観的なデータで証明しなければいけません。
証明の方法としては次のようなものがあります。
土地の全部事項証明書(土地の登記)
登記地目が線引き以前から現在まで継続して宅地である場合は、宅地性が認められます。
ただし、表題部に線引き以前からの地目が宅地として表示されていることが必要です。
固定資産評価証明書
線引きのあった年度の固定資産評価証明書において、課税地目が宅地であれば、宅地であると認めらます。
築物の全部事項証明書(建築物の登記)
土地の全部事項証明書で地目が宅地以外である場合は、線引き以前に表題部が作成されている建築物の登記が存在していれば、その所在欄に記載のある地名地番については、宅地であると認められます。
都市計画図白図・航空写真
線引き以前に作成された、自治体が航空写真を基に作成している2,500分の1程度の都市計画図に建物の表示があれば、線引き以前から宅地であった証明になります。
また地方自治体は、都市計画図を作成する際に航空写真を撮影しているので、その画像の写しを情報公開請求で入手することで証明できることがあります。
建築確認済証
建築計画概要書、建築確認通知書、確認済証、建築確認申請書等によって線引き以前に建築したことが分かる書類があれば証明になります。
現実の事務処理においては、都市計画図や航空写真では、誰が見ても建築物だと分かるほど鮮明ではありません。
一方で建築確認申請書は、建物の計画を示した書類に過ぎないため、それだけでは建物が存在していたという証明にはなりません。
しかし両方の証明書類があり、かつ当該建物が現存していれば、それぞれのデータの欠点が補完できるため有力な証明となりえます。
▼関連記事:市街化調整区域の土地は購入できる?建築制限やローンの利用可否など注意点を解説
更地として売却する
建物が現存しない土地は、更地として売却する方法があります。
ただし土地の使用用途が限られますから、購入希望者が現れる可能性はかなり低いものになります。
市街化調整区域での更地の活用法は、資材置き場や駐車場として使用しているケースが多く見られます。
原則建築物は建てられませんが、資材置き場であれば、5平方メートル程度の管理棟と便所であれば許可の対象です。
また露天駐車場であれば、5平方メートル以内の料金収容施設や便所は許可の対象になります。
市街化調整区域の物件売却で注意すること
市街化調整区域の物件であっても、一般用住宅に用途変更されたものや線引き前の既存宅地であれば売却できる可能性があることは分かりました。
しかし購入希望者が建物の建て替えを希望しているのであれば、その要望に応えられることを確認しておく必要があります。
市街化調整区域の物件売却で注意する事項を解説していきましょう。
農地転用ができているか
物件の地目が農地のままでは家を建てることができません。
現実に宅地として使用していても地目の変更を怠り、農地や山林として登記されていることがあります。
建築できる敷地の範囲を明確にする
市街化調整区域で建築目的の敷地を増やすことはできません。しかし農村部の土地は敷地境界が不明瞭なケースが多くあります。
建築できる用途、規模を説明する
市街化調整区域の物件は、建て替えできるものは同規模同用途とされています。
接道義務基準を満たしていることを確認する
市街化調整区域にある道は、農業や林業に使用する通路や単なる散策路といったものが多く存在しています。
このため敷地が広い通路に接しているからといって、必ずしも建築基準法上の道路とは限りません。
まとめ
市街化調整区域では、建築が厳しく制限をされていることから、建て替えに際しては、さまざまな法律の縛りがあります。
とくに農家住宅に関しては、農業に従事していない人が居住することでトラブルに発展するケースもあります。
所有する物件が農家住宅の場合は、用途変更手続きを行ったうえで売却を進めましょう。
また線引き以前に建築されていたと思い込んでいた物件も、詳しく調査をすると違法に建築された物件だったというケースが少なからずあります。
こうした物件を建て替え可能な不動産として売却すると、契約不適合責任に問われることになりますから、必ず線引き以前から存在していたことを証明するデータを確認しておきましょう。