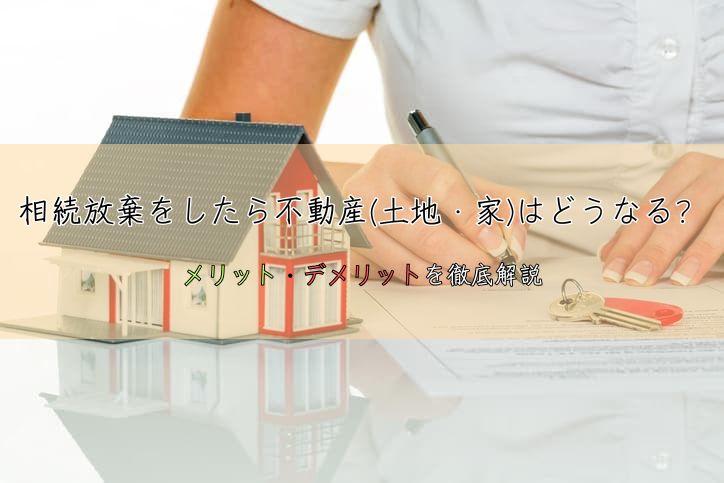「土地と建物の名義が違うけど、立ち退きを要求されたらどうしよう…」
このような不安を抱えている方もいるでしょう。
借りた土地に家を建てたといった理由で、土地と建物の名義が異なるケースは珍しくありません。
この場合で、立ち退き請求されたら応じないといけないかは契約形態によって異なり、トラブルにも発展しやすいので注意が必要です。
この記事では、土地と建物の名義が異なる理由や立ち退きトラブル、対処法まで分かりやすく解説します。
土地と建物の名義が異なってしまうよくあるケース
どのようなケースで、土地と建物の名義が異なってしまうのでしょうか。
まずは、土地と建物の名義が異なってしまうよくある5つのケースを紹介します。
親の土地のうえに子が家を建てるケース
親の土地に子ども名義の家を建てる場合、以下の方法が考えられます。
- 土地を売却・贈与して名義も子どもに変更する
- 土地を子どもに貸す
売買や贈与によって土地を子どもに譲れば、土地と建物の名義はともに子どもとなり、名義の不一致は生じません。
ただし、売買の場合は売却資金、贈与の場合は贈与税が発生するため、まとまった資金が必要となります。
そこで、資金をかけずに子どもが家を建てる方法として、親が子に土地を貸すという方法があります。
子どもへの貸し方としては、通常の賃貸契約として地代が発生するパターンと、無償の使用貸借契約を結ぶ方法があります。いずれの場合も、土地の名義は親のままです。
一方、子供が借りた土地に家を建てると、建物の名義は子ども、土地の名義は親という状態になります。
親の土地のうえに親子が共同で家を建てるケース
親の土地のうえに二世帯住宅を建てるケースでも、土地の建物の名義人が分かれることがあります。
二世帯住宅の名義人は、資金の負担割合に応じて設定されます。
たとえば、親が全額出すまたは親名義でローンを組む場合は、建物の名義人は親が単独で持ちます。
一方、親と子どもが費用を按分した場合では、負担割合に応じた共有持分が設定されるのです。
そのため、子どもが全額資金を負担した、もしくは親と子どもで按分したケースでは、土地と建物の名義が異なります。
土地を相続したが相続人が相続登記せずに家を建てたケース
不動産を相続すると、被相続人(亡くなった人)から相続人に名義人を変更する「相続登記」と呼ばれる手続きが必要です。
令和6年4月1日より相続登記は義務化されていますが、それ以前は義務ではなかったので、相続登記を怠るケースは珍しくありません。
相続登記を行わずに相続人が自分名義の家を建てると、土地の名義人は被相続人のまま、建物の名義は相続人というように分かれてしまうのです。
なお、相続登記の義務化により、施行日以前の相続も義務の対象となっています。
施行日以前の相続については、施行日から3年以内の相続登記が必要となり、怠ると罰則の恐れがあるので早めに手続きするようにしましょう。
被相続人だけでなく、数代前から相続登記を怠っているケースでは、手続きが複雑になるので司法書士への相談をおすすめします。
被相続人が第三者に借地して建物が建っていて底地を相続したケース
親が第三者に土地を貸していて、その土地(底地)を相続するケースです。
親から土地を借りた第三者は家を建てる権利を有し(借地権)、その家の所有者は土地を借りた人になります。
一方、土地の名義人は相続により親から子どもに移るので、土地の名義人は子ども、建物の名義人は第三者となるのです。
なお、底地を相続しても、借主がいる以上相続人は自由に活用できません。
さらに、複数の相続人で底地を共有状態にすると、地代の配分などで揉めやすいので注意しましょう。
被相続人が借地のうえに立てていた家を相続したケース
被相続人が借地に家を建てている場合では、家を相続してみると土地の名義人が異なっていたことに気づくケースもあります。
借地の借主には借地権があり、借地権は相続の対象となります。しかし、建物に相続が発生しても、土地の名義人である地主には影響はありません。
そのため、建物の名義人は被相続人から相続人に変更されますが、土地の名義人は地主のままとなり、建物と土地の名義人が異なるのです。
借地権は相続できるので、相続人は相続した家に住むことが可能です。
しかし、地主との関係性によっては、相続をきっかけに立ち退きを求められたり、地代の値上げを要求される恐れがあるので、注意しましょう。
立ち退きトラブルについては後ほど詳しく解説するので参考にしてください。
▼関連記事:借地権を相続したらどうするべき?
底地と借地権に関する基礎知識
家を建てる場合、土地を所有して家を建てる方法と、土地を借りて家を建てる方法のいずれかがあります。
土地を自分で所有している場合は、土地と建物の名義は同一です。
一方、土地を借りる場合は土地の名義人は土地の所有者、建物の名義人は土地を借りた人となり、権利が複雑になります。
ここでは、土地を借りて家を建てる場合に発生する「底地」と「借地権」についてみていきましょう。
底地とは
底地とは、借地権が設定されている土地です。
つまり、貸し出している土地のことをいい、土地の所有者から見た言い方になります。
ちなみに、借主側から見た場合は借地です。
底地と借地は誰から見た土地かという違いがありますが、物理的には同じ土地を指します。
借地権とは
借地権とは、建物の所有を目的として、地代を払って土地を借りる権利です。
借りた土地に家を建てると家の名義人は借りた人になりますが、土地の名義人は所有者のままです。
また、建てた家は、土地の所有者の許可なく売却や増改築ができないといった制限があります。
借地の契約には契約期間が設けられており、期間終了後に契約を更新しないのであれば、更地にして返還が必要です。
基本的には契約終了後の更新が認められますが、契約方法によっては契約更新できない場合もあるので注意しましょう。
土地と建物の名義が異なるときに気を付けておきたい立ち退きトラブル
ここでは、土地と建物の名義人が異なるときに気を付けておきたい立ち退きトラブルとして、以下の2つを解説します。
- 借地上に建てた家を相続したが立ち退きを要求された
- 借地上に建てた家の解体を要求された
それぞれ見ていきましょう。
借地上に建てた家を相続したが立ち退きを要求された
借地権は相続の対象であり、相続するにあたって地主の承諾や承諾料の支払いは必要ありません。
しかし、地主によっては相続のタイミングで立ち退きを要求してくるケースがあるのです。
この場合、相続を理由とした立ち退き要求に応じる必要はありません。
借地権で立ち退きを要求するには正当な理由が必要ですが、相続は正当な理由に該当しないのです。
ただし、賃料を滞納しているなどの契約違反があると、正当な事由として立ち退きに応じなければいけないので注意しましょう。
また、契約�方法が定期借地契約の場合、契約期間終了後の更新ができないので立ち退く必要があります。
まずは、契約内容を確認したうえで、対応に悩む場合は弁護士に相談するとよいでしょう。
借地上に立てた家の解体を要求された
契約期間中であれば地主による家の解体要求はできず、仮に要求されても応じる必要はありません。
しかし、契約期間が終了し更新しないのであれば、解体して返還する必要があり、この際の解体費用は借主が負担するのが一般的です。
契約期間終了後の解体に借主が応じない場合、貸主は訴訟手続きで解体を請求することができます。
ただし、交渉次第では建物を買い取ってくれたり、解体費用を貸主が負担してくれる場合もあるので、相談してみるのもよいでしょう。
▼関連記事:借地に建てた家の解体費用が払えない場合はどうする?
土地と建物の名義が異なることを理由にトラブルに発展した場合の対処法
土地と建物の名義が異なるとトラブルが起きやすく、一度トラブルに発展すると解決が難しくなりがちです。
ここでは、トラブルに発展した場合の対処法を解説します。
貸主と借主で話し合いをする
トラブルになった場合は、まずは貸主と借主がしっかり話し合いすることが大切です。
この際、事前に契約内容をしっかりと確認しておくことで、認識違いによるトラブルの解決は図りやすくなります。
ただし、当事者同士で直接話し合いすると冷静に判断できずに、トラブルが深刻化する恐れもあります。
当事者同士の話し合いが不安な場合は、弁護士に間に入ってもらうことも検討するとよいでしょう。
話し合いで解決しない場合は法に則って対処する
話し合いでの解決が難しい場合は、法に従って対処します。
たとえば、前述のように相続のタイミングで立ち退きや解体を要求されたとしても、ルール上応じる必要はありません。
借地権は相続でき、相続時に地主の承諾は不要です。
また、普通借地契約であれば契約期間終了後でも更新でき、地主が更新を拒否するには賃料滞納などの正当な理由が必要です。
一方、定期借地契約であれば契約期間終了後の更新は認められておらず、解体して返還しなければなりません。
借地での対応は契約内容や法に則ることで解決が図れる場合があるので、借地について知識を持っておくことも大切です。
最終的には裁判の判決を仰ぐ
どうしても解決が難しい場合、訴訟などの裁判手続きで解決を図ることになります。
しかし、訴訟まで発展すると解決に時間や手間、費用がよりかかります。
さらに、解決したとしても地主との関係性が悪くなっていることも予測できるでしょう。
訴訟になる前に解決できるように、早めに専門家に相談することをおすすめします。
借地権が設定されている家のトラブルの解決方法としては、売却も1つの選択肢です。
借地権が設定されている家であっても、地主の承諾を得られれば売却できます。
とはいえ、借地権で建てられている家は住宅ローンの審査で不利になりやすいため、買い手がつきにくい点には注意が必要です。
仲介での売却が難しい場合は、借地権付きの不動産の取り扱いが豊富な不動産会社の買取�を視野に入れるとよいでしょう。
土地と建物の名義が違う場合のよくある質問
最後に、土地と建物の名義が違う場合のよくある質問を見ていきましょう。
土地と建物の名義が違う場合の固定資産税はどうなる?
固定資産税は、毎年1月1日時点の不動産所有者に課せられる税金であり、建物・土地は別に課税されます。
そのため、土地と建物の名義が異なる場合は、土地は土地の名義人、建物は建物の名義人が納税義務を負います。
毎年4~6月頃に送付される納税通知書もそれぞれの所有者に届くので、それぞれで対応するようにしましょう。
土地と建物の名義が違う場合の建物の解体費用は誰が負担する?
基本的に、解体費用は建物の所有者が負担します。
ただし、地主都合の契約解除や解体であれば、地主が負担するケースもあります。
また、借主は契約終了にともない「建物買取請求権」で、地主に建物の買取を要求できるケースもあります。
どちらが負担するかは契約内容やケースによって異なるので、判断に悩む場合は専門家に相談するとよいでしょう。
兄弟間で土地と建物の名義が違う場合に相続が発生した場合はどうすればいい
たとえば、「兄の土地」と「弟の建物」というケースで、兄に相続が発生すると、兄の土地は兄側の相続人が相続することになります。
兄に配偶者と子どもがいれば、土地は配偶者と子どもが相続することになり、弟には相続権はありません。
さらに、相続人が多いほど、相続後の土地と建物の権利関係が複雑になりがちです。
この場合、弟に土地と建物の名義を統一する方法として、遺言書や遺産分割協議で弟に相続させる、相続後に弟が土地を購入するなどが検討できるでしょう。
土地と建物の名義人が異なると、相続を繰り返すうちに権利関係がさらに複雑になります。
トラブルを避けるには、早い段階で名義人を統一しておくとよいでしょう。
また、土地と建物を地主と借主が協力して同時に売却するのも1つの選択肢です。
借地権付きの土地と建物は別々に売却することもできますが、別々に売ると制限の多さから買い手がつきにくくなります。
一方、一緒に売却できれば、買い手にとっては通常の「土地+建物」と同じ扱いになるため、好条件で売却できる可能性もあるでしょう。
ただし、同時に売却する場合でも地主に売却交渉するなどのハードルは高くなります。
借地権付き建物の売却に強い不動産会社に相談しながら、適切な売却方法のアドバイスや交渉のサポートなどを受けるとよいでしょう。
まとめ
土地と建物の名義は、親の土地に家を建てた、相続した土地が借地だったなどで異なるケースがよくあります。
名義人が異なると、相続時に立ち退きや解体を要求される可能性がありますが、普通借地契約で契約違反がないなら応じる必要はありません。
一方、定期借地契約では契約期間終了にともない土地の返還が必要なので注意しましょう。
土地と建物の名義人が異なるとトラブルに発展しやすいので、トラブルを避けるには売却が有効な方法です。
借地権付きの土地・建物の取り扱いに慣れた不動産会社に相談しながら、スムーズに売却できるようにしましょう。