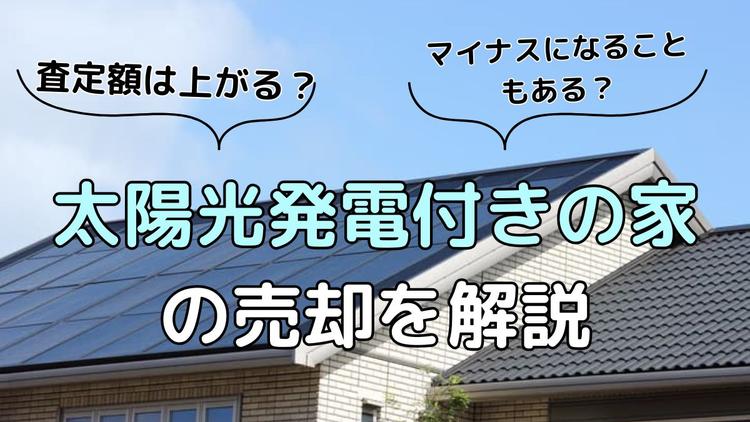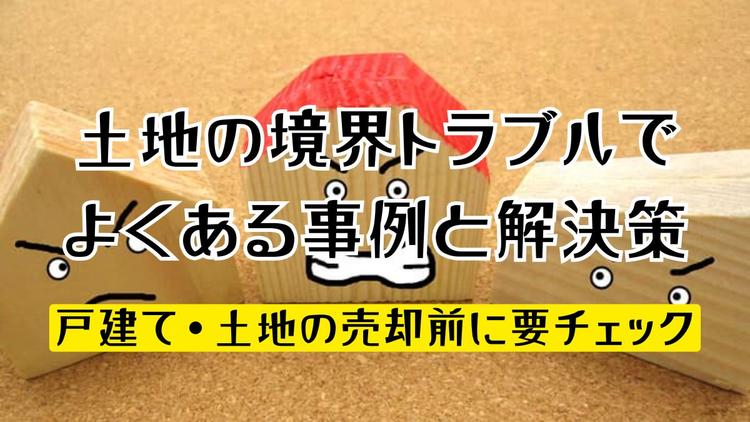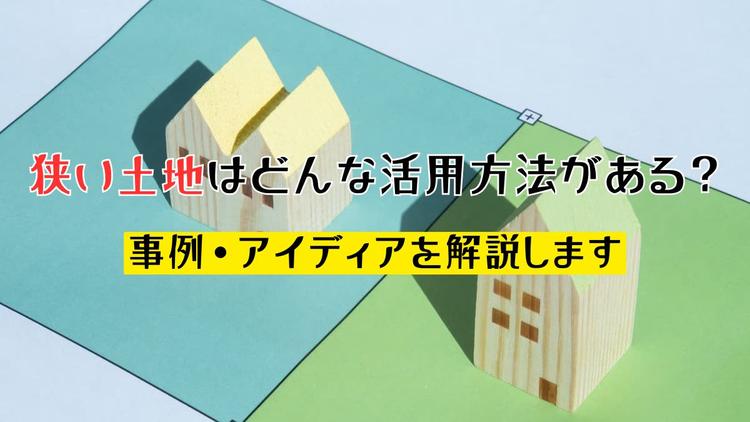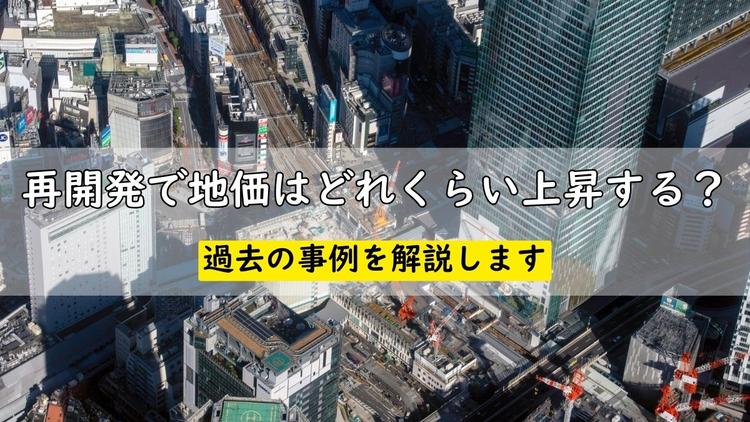擁壁(ようへき)は、土砂崩れなどの災害から私たちを守る、とても重要な役割を果たしています。
しかし、時間の経過とともに劣化が進行するため、安全性に不安を抱く方も少なくありません。
この記事では、擁壁の安全性を調査すべきケースを明らかにしたうえで、具体的な調査方法や費用について解説します。
擁壁とは?
擁壁とは、傾斜地や段差のある土地において、土砂崩れを防ぎ、安全な生活空間を確保するために設置される構造物です。
擁壁を設置する目的
擁壁は、主に斜面地で大雨や地震などの自然災害から人命や財産を守る目的で設置されます。
また、宅地造成の際には、傾斜地を平らな土地に変え、住宅や建物を建てるための基礎を作る目的でも使われます。
さらに、道路や鉄道の路盤を安定させ、安全な通行を確保するためにも設置されることがあります。
擁壁の種類
擁壁にはさまざまな種類があり、設置場所の状況や目的に応じて適切なものが選ばれます。
主な種類は次のとおりです。
- コンクリート擁壁……最も一般的な擁壁で、耐久性に優れています。
- 間知ブロック積擁壁……斜面に積み上げられたコンクリート製のブロックによって土砂崩れを防ぐ擁壁です。
- 石積み擁壁……自然石を積み上げた擁壁で、景観に配慮した設計が可能です。
- 鋼製擁壁……鋼材を使用した擁壁で、強度が高く、狭い場所にも設置できます。
コンクリート擁壁は主に重力式コンクリート擁壁と鉄筋コンクリートL型擁壁があります。
重力式コンクリート擁壁
重力式コンクリート擁壁は、擁壁自体の重さ(自重)によって、背後の土圧に抵抗し安定を保つ構造です。そのため、断面が大きく、コンクリートを大量に使用します。
鉄筋コンクリートL型擁壁
鉄筋コンクリートL型擁壁は、鉄筋コンクリートの強度と、L型擁壁の底版上の土の重さによって、土圧に抵抗します。そのため、重力式擁壁に比べて断面を小さくすることができます。
重力式コンクリート擁壁は、比較的安定した地盤で大規模な擁壁が必要な場合に適しています。一方、鉄筋コンクリートL型擁壁は、軟弱な地盤やスペースに制限がある場合に有効です。
外観によって擁壁の安全性を調査すべきケース
擁壁は、私たちの生活を土砂崩れなどの災害から守る重要な構造物ですが、時間の経過や環境の変化によって劣化し、安全性が損なわれることがあります。
擁壁の外観がどのような状況のときに安全性を調査すべきなのか、みていきましょう。
擁壁に目に見える異常がある
擁壁を目視したときに、次のような症状があれば、安全性を調査すべきです。
- ひび割れ……表面の小さなひび割れから、構造を脅かす大きな亀裂まで、様々な種類のひび割れがあります。
- 傾き・膨らみ……擁壁が明らかに傾いていたり、部分的に膨らんでいたりする場合、内部の土圧に耐えられなくなっている可能性があります。
- 排水不良……水抜き穴の詰まりや排水溝の破損は、擁壁内部に水が溜まり、劣化を早める原因となります。
- 鉄筋の露出・錆……鉄筋コンクリート擁壁の場合、鉄筋の露出や錆は、構造的な強度低下につながります�。
- コンクリートの劣化……コンクリートのひび割れ、剥がれ、欠損などは、擁壁の寿命を縮めます。
増し積みされた部分がある
既存の擁壁の上に、新たに別の擁壁が増し積みされている場合、当初の設計時に想定されていない力が加わることがあり、崩壊等の可能性が高くなります。
こうした擁壁は、許可や確認申請などの法的手続きがされていないことが多く、基準に適合しているかどうか確認できません。
二段擁壁である
二段擁壁とは、斜面の安定性を確保するために、一段の擁壁では高さが足りない場合に、近接して二段に分けて設置される擁壁のことです。
二段擁壁は一段の擁壁よりも構造が複雑なため、設計や施工が不適切だと崩壊のリスクが高まります。
特に、古い二段擁壁や適切な排水処理がされていない二段擁壁は、注意が必要です。
塀用のコンクリートブロック擁壁である
塀用のコンクリートブロック擁壁とは、塀などに使われている一般的な厚さ10㎝のコンクリートブロックを積み重ねて構築される擁壁のことです。比較的安価で施工が容易なため、住宅地の造成などで広く利用されています。
しかし、多くの場合、簡易な土留めとして設置されていることがあり、水抜き穴がないなど不適切なものも存在します。
また、厚さ10㎝のコンクリートブロックで造られた擁壁のほとんどは、構造計算による検証が行われていません。
周辺の状況から擁壁の安全性を調査すべきケース
擁壁自体の劣化ではなく、周辺の状況の変化により、擁壁の安全性を調査すべきケースがあります。
擁壁の築造時期や履歴が不明
古い擁壁で、「都市計画法」や「宅地造成及び特定盛土等規制法」が改正される前の古い擁壁は、現在の基準を満たしていない可能性があります。
また、そもそも擁壁の築造時期や設計図がない場合、安全性を確認することが困難です。
さらに、過去に補修履歴がある場合は、 補修が適切に行われているか、補修箇所に新たな問題が生じていないかを確認する必要があります。
「都市計画法」(1968年制定)と「宅地造成及び特定盛土等規制法(旧・宅地造成等規制法)」(1970年制定)は、宅地造成に伴う災害を防ぐために擁壁の構造基準を定めています。
2000年・2023年の改正では、豪雨や地震による擁壁崩壊リスクを減らすための規制が強化され、擁壁の高さや勾配、排水対策などの基準が厳格化されました1。
そのため、改正前に築造された擁壁の中には、現在の耐震・排水基準を満たしていないものが多く、ひび割れや排水不良による崩壊リスクが高いケースがあります。
周辺環境に変化があった
地震や大雨の後、擁壁には大きな負荷がかかり、目に見えない損傷が生じることがあります。また、擁壁の近くで行われる掘削工事や重機の使用は、擁壁の安定性を損なう可能性があります。
さらに、近隣で地盤沈下が発生した場合、擁壁に不均等な力がかかり、変形やひび割れを引き起こすことがあるので注意が必要です。
不動産の売買を検討している
購入したい土地に擁壁がある場合、安全性を確認することは非常に重要です。
また、売主の立場だと、擁壁の安全性を証明することで買主の安心感を高め、スムーズな取引につながります。
▼関連記事:擁壁がある家・土地を売買する際の注意点
擁壁に近接して建築する場合
擁壁に近接して建物を建築する場合、擁壁の上面に建てる場合も下面に建てる場合も、建築確認申請の審査の中で、擁壁の安全性の検証が求められます。
その擁壁が、検査済証を取得している場合は、許可番号と検査済証の交付日を記載することで審査を通過しますが、それらが不明な場合は、個別に安全性を確認する必要があります。
擁壁の安全性の調査方法
擁壁の安全性を調査する方法は、擁壁の種類や状態、周辺環境などによって異なります。
ここでは、主な調査方法を紹介します。
資料調査と現地確認
まず、擁壁の設計図、構造計算書、施工記録などを入手し、擁壁の構造や�築造時期を確認します。この時、過去の災害履歴や周辺の地盤情報を収集し、擁壁に影響を与える可能性のある要因を把握します。
次に、擁壁の全体像や周辺環境を目視で確認し、異常の有無を把握します。擁壁の種類(重力式、鉄筋コンクリートL型など)や規模、排水状況なども記録しましょう。
一次調査(目視調査と簡易調査)
資料調査と現地確認が終わったら、目視調査と簡易調査を行います。
まず、擁壁表面のひび割れ、傾き、膨らみ、剥離、鉄筋の露出などを目視で詳細に確認し、排水施設の詰まりや破損、周辺の地盤沈下なども確認します。
次に、ハンマーなどで擁壁を叩いて強度を推定します。この時、音の違いによって内部の空洞やひび割れも検知できます。
さらに、レーザー距離計などを用いて擁壁の傾きや変形を測定し、クラックスケールなどを用いてひび割れ幅の計測を行いましょう。
二次調査(精密調査)
目視調査と簡易調査が終わったら、精密検査を行います。
まず、ボーリング調査で土を採取し、強度や透水性を調べたら地盤の強度や地層構成から、擁壁の安定性を評価します。
この地盤調査の結果や擁壁の構造に基づいて、擁壁の安定性や耐力を計算し、地震や大雨などの荷重に対する安全性が評価できるのです。
次に、レーダー探査により、擁壁内部の鉄筋の配置や空洞を調べます。超音波探傷検査により、コンクリートの内部のひび割れや劣化を調べることができます。
調査結果の評価と報告書作成
調査結果を総合的に評価し、擁壁の安全性や劣化状況を判定したうえで、調査結果、評価、対策案などをまとめた報告書を作成します。
擁壁の安全確認を行う際は、擁壁の種類や状態、周辺環境などに応じて、適切な調査方法を選ぶことが求められます。
そのため、専門的な知識や技術を持つ専門家に依頼し、正確な調査と評価を行うことが重要です。調査結果に基づいて、適切な補修や改修を行うことで、擁壁の安全性を確保できます。
擁壁調査を行う場合は、国土交通省が出している「宅地擁壁老朽化判定マニュアル(案)」等を参考にするとよいでしょう。
擁壁の調査にかかる費用
擁壁の安全性を調査する費用は、調査内容や擁壁の規模、立地条件などによって大きく異なります。
ここでは、費用の目安を解説します。
目視調査
専門家が、ひび割れ、傾き、排水不良などの擁壁の表面的な状態をチェックします。
費用は、数万円程度です。
簡易調査
目視調査に加えて、打音検査や簡易的な測量などを行います。これにより、詳細な擁壁の状態を把握できます。
費用は、数万円~10万円程度です。
精密調査
地盤調査、構造計算、非破壊検査など、専門的な調査を行います。擁壁の安全性について、詳細なデータに基づいた評価を得られます。
費用は、数十万円~100万円以上です。
費用を左右する要因
擁壁の高さや延長が長くなるほど、調査費用は高くなります。
また、重力式擁壁よりも鉄筋コンクリート擁壁の方が調査項目が多くな�ります2。
さらに、擁壁が急斜面や狭い場所にある場合、調査が困難になるため、費用が高くなることがあります。
調査を依頼する際は、調査会社によって料金体系や得意とする調査内容が異なるため、複数の業者から見積もりを取り、内訳を比較検討することが重要です。
加えて、調査内容を精査し、本当に必要な調査のみを行うことで、費用を抑えることが可能です。
擁壁の適法性の調査方法
安全性の確認を行う上で、擁壁が適法に設置されているかどうかを確認することは非常に重要です。違法に設置された擁壁は、安全性が確保されていない可能性が高く、将来的に大きな問題を引き起こす可能性があります。
そのため、現地調査と合わせて、法的な面の調査も行うと安心です。
一定の高さ以上の擁壁は、次のいずれかの手続きを行う必要があります。
- 建築確認申請(建築基準法)
- 盛土規制法の許可申請
- 開発許可申請(都市計画法)
これらの申請履歴を追うことで、その擁壁が適法であることを確認することができます。
建築確認申請(工作物)
建築基準法では、擁壁は「工作物」に該当し、高さが2メートルを超える場合は建築確認申請が必要です。
建築確認申請が無事通って建築確認済証が交付されると、工事を開始できます。設計図とおりに正確に施工して工事が完了したら、��完了検査を申請し、検査に合格すると検査済証が交付されるという流れです。
これらの履歴は、地方自治体の建築指導課などの建築確認申請を取り扱う部署で、建築計画概要書を閲覧することで確認できます。
なお、宅地造成及び特定盛土等規制法(旧:宅地造成等規制法)に基づき許可を受けた擁壁については、建築確認申請は不要となります(建築基準法第88条第4項)。
宅地造成及び特定盛土等規制法の許可申請
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)は、宅地造成工事によるがけ崩れや土砂崩れなどの災害を防止するために設けられた法律です。
宅地造成等工事規制区域内において、一定規模以上の宅地造成工事を行う場合には許可が必要です。
擁壁についても、以下の条件に該当する場合は許可が必要になります。
- 盛土によって、高さが1メートルを超える崖が生じる場合。
- 切土によって、高さが2メートルを超える崖が生じる場合。
- 切土と盛土を同時に行い、合計の高さが2メートルを超える崖が生じる場合。
なお、盛土規制法に基づく許可申請の履歴は、地方自治体の宅地造成担当課に問い合わせることで確認できます。
開発許可申請
開発許可申請は、1000平方メートル(三大都市圏は500平方メートル)以上の一団の土地を宅地化する際に必要な手続きです。
開発許可を受けた土地には、その内容を記載した「開発登録簿」が作成され、指定された場所で閲覧することができます。
開発登録簿には、許可年月日、許可番号、許可を受けた者、開発区域の面積、予定建�築物の用途などが記載されています。
閲覧場所は、都道府県や市区町村によって異なりますが、一般的には開発許可を取り扱っている部署で閲覧可能です。
まとめ
擁壁は、土砂崩れから私たちの生活を守る上で非常に重要な役割を果たしていますが、時間の経過とともに劣化が進み、安全性が低下することがあります。そのため、安全な生活を送るためには、定期的な点検と適切な対策が不可欠です。
擁壁の安全性を調査すべきケースとしては、ひび割れ、傾き、排水不良など目に見える異常がある場合や、地震や大雨の後、または周辺で工事や地盤沈下があった場合などが挙げられます。
また、擁壁の築造時期や履歴が不明な場合、増し積みされた部分や、二段擁壁、コンクリートブロック擁壁など構造的にリスクがある場合、不動産の売買を検討している場合、擁壁に近接して建築する場合なども調査が必要です。
擁壁の安全性調査は、資料調査と現地確認から始まり、一次調査(目視調査、簡易調査)、二次調査(精密調査、地盤調査、構造計算など)へと進みます。
調査にかかる費用は、目視調査であれば数万円程度、簡易的な調査であれば数万円から10万円程度、精密な調査であれば数十万円から100万円以上と幅があります。
擁壁の安全確認は、専門的な知識と技術が必要です。信頼できる専門家に相談し、適切な調査と対策を実施することが重要です。