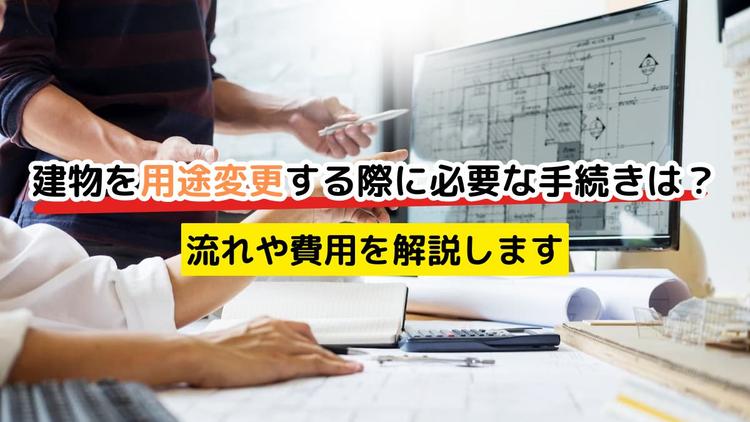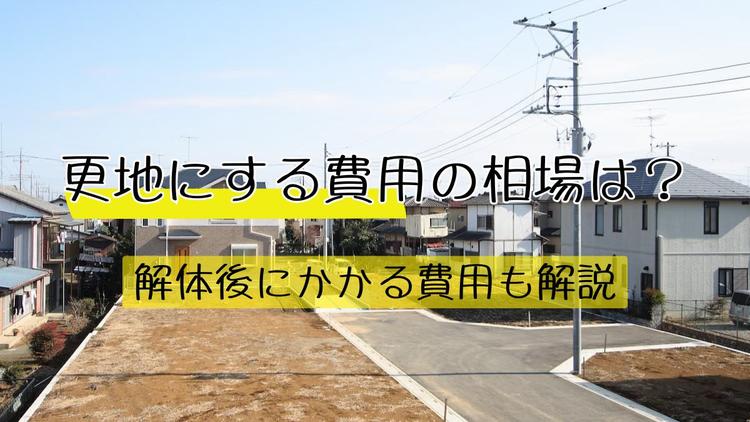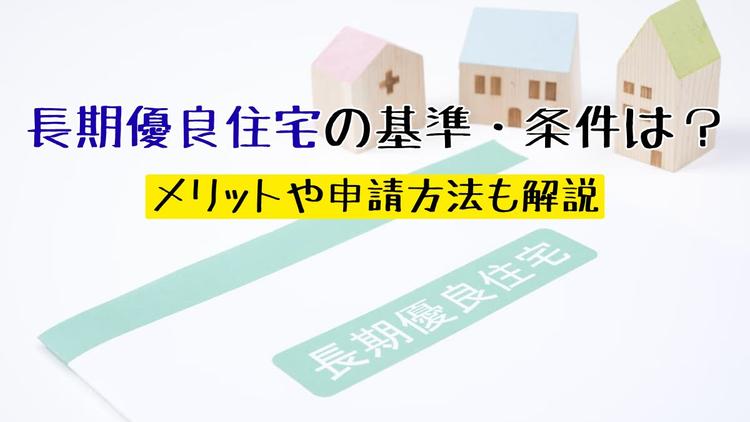家を建てる際には「幅4m以上の道路に2m以上接道していなければならない」という接道義務を満たす必要があります。
このため、家を売却するときには、売却前に自分の土地が接道義務を満たしているか確認しなければなりません。
本記事では、接道義務について解説すると共に、接道義務を満たさない場合の対処法等、家の売却時に注意しなければならないポイントをご紹介します。
接道義務とは
土地の上に建物を建てるには建築基準法の規制をクリアする必要がありますが、建築基準法には「接道義務」と呼ばれる規制があります。
接道義務とは「都市計画区域内」の土地において、建物を建てるにはその敷地が「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」というものです。
このため、道路に全く接していない敷地や、道路に接していてもその道路の幅員や接道幅が規定以下の場合には原則として建築確認の許可を得ることができません。
接道義務の目的
そもそもなぜ接道義務が設けられているかというと、一つには火事が起きたときに消防車や救急車などの緊急車両が現場までスムーズに駆けつけられるようにするため、ということが挙げられます。
自動車の行き来がスムーズにできれば、周辺の往来が増えて活発になりやすいといったこともあるでしょう。
車が自由に往来できることにはさまざまなメリットがあり、そのために敷地からスムーズに人が出入りできるよう、接道義務が定められているのです。
建築基準法の道路とは
接道義務を満たすための道路は「建築基準法で認められた道路」でなければいけません。
建築基準法で認められた道路には以下のようなものがあります。
- 道路法による道路(建築基準法第42条1項1号)
- 2号道路(建築基準法第42条1項2号)
- 既存道路(建築基準法第42条1項3号)
- 都市計画法などにより2年以内に造られる予定の道路(建築基準法第42条1項4号)
- 位置指定道路(建築基準法第42条1項5号)
- みなし道路(建築基準法第42条2項)
以下、それぞれについて見ていきましょう。
道路法の道路
国道や都道府県道、市町村道のことで、幅員が4m以上のものです。
一般的な道路のことを指していると考えればよいでしょう。
2号道路
宅地造成など一定規模以上の開発行為を行う場合、土地の中に道路を通すと、その道路が2号道路となります。
都市計画法による開発許可を受けてできる道路のため、開発道路と呼ばれることもあります。
原則として6m異常の幅員を持ちますが、通行上支障がない場合は4m以上の幅員で認められることもあります。
なお、市道に接する開発道路の場合、開発が終わった後に市に管理が引き継がれて市道となるのが一般的です。
既存道路
建築基準法が施行された昭和25年時点ですでに存在した道路で、幅員4m以上のものを既存道路と呼びます。
既存道路の多くは私道のため、建物を建てるのであれば上下水道や都市ガスの管を通すことができるかどうかが問題になることが多いです。
購入を考えてい�る敷地に接している道路が既存道路だった場合、その所有者は誰か、上下水道管やガス管はどうなっているのかなど確認することが大切です。
計画道路
道路法や都市計画法、土地区画整理法などにより、2年以内に新設または変更される予定の道路のことを指します。
実際に道路が存在しなくても、そこに道路があるものとみなされます。
位置指定道路
位置指定道路とは、「一定の技術的基準に適合するもので特定行政庁からその位置の指定を受けたもの」です。
大きな面積を持つ土地を分筆して複数の宅地に造成するようなケースでは、全ての土地が道路に接していなければ建物を建てることができません。
通常、造成地内に設置された道路は敷地延長といって、実際には個人の所有する土地を道路のように扱うことで接道義務を満たします。
しかし、奥に複数戸の建物を建てるようなケースではその全てに幅2m以上の接道幅を持たせる必要があります。
実際にそのようにして接道義務を満たしている土地もありますが、この私道部分について位置指定道路として扱ってもらうことができれば、その部分が幅4m以上あればよいことになります。
2項道路
2項道路とは幅員4m未満で一定の条件を満たす道路のことを指します。
例えば、敷地に接する道路の幅員が3mであっても、敷地の内1mを道路にすることで合計の幅員を4mとすれば2項道路とみなされ、建物の建築が可能となります。
このことをセットバックと呼びます。
接道義務について家の売却時に確認しておくべき3つのポイント
家を売却するときは、接道義務を満たしているかどうかを改めて確認しておくことが大切です。
ここでは、接道義務を確認するための3つのポイントをご紹介します。
都市計画区域内かどうか
まず、都市計画区域内かどうかを確認しましょう。
都市計画区域内でない場合、接道義務を満たさずとも建物を建築することが可能です。
都市計画区域は役所に設置された都市計画課や、市区町村によってはWebサービスで確認できることもあります。
例えば、東京都の場合は以下のURLから確認できるようになっています。
都市計画情報等インターネット提供サービス接道している道路の種類
次に、先ほどご紹介した内容を参考に、接道している道路の種類を確認しましょう。
道路法による道路の場合は特に問題がありませんが、既存道路の場合はどのような権利関係となっているか等を考えなければなりません。
また、私道で敷地延長されている場合には、どのように接道義務を満たしているのかより綿密に調査する必要があるでしょう。
なお、道路の種類についても先述の都市計画に関するWebサービスで確認できます。
道路の幅員と接道幅
最後に、道路の幅員と接道幅を確認しましょう。
特に私道で敷地延長の場合には、誰が私道部分の所有権を持っているのか、しっかり接道幅2mを確保できているのかを確認�する必要があります。
2項道路(みなし道路)に接道している場合、幅員2mの規定を満たすためにセットバックが必要なことがある。
道路を挟んで河川等がある場合、幅員の規定を満たすために、通常よりも長めのセットバックが求められることがある。
また、2項道路の場合には敷地をセットバックする必要があるため、建てられる建物に制限が課される場合があります。
接道義務に関する注意点
ここでは、接道義務に関する注意点をお伝えします。
旗竿地の接道義務
敷地の形が旗竿地になっている場合、竿の部分の幅に注意が必要です。
接道義務は、「幅員4m以上の道路に2m以上接道している」必要があります。
これは、単に接道幅が2m以上あればよいということではなく、敷地の入り口から敷地内まで全て幅員2m以上なければなりません。
このため、旗竿地の竿にあたる部分の一部でも幅員が2m以下になっている部分があると、接道義務を満たさなくなってしまいます。
造成された旗竿地はしっかり計算されているのが普通ですが、周辺の土地が分筆されたことにより生まれた土地のようなケースでは、一部分だけ幅2mを満たさないといったこともあるため十分注意が必要です。
共有持分道路に注意
私道で敷地延長の場合、道路部分について共有持分を持つのが一般的です。
この共有持分は、土地の造成地にはしっかり計算されていても、その後権利関係の変動が進むことで接道義務を満たさなくなることがある点に注意が必要です。
接道義務を満たさない土地はどうなる?
接道義務を満たさない道路はどうなるのでしょうか?
原則として建物を建てられない
まず、原則として接道義務を満たさない敷地は建物を建てることができません。
もちろん、住宅だけでない賃貸アパートやマンション、店舗、事務所等も建てられません。
建物を建てられない敷地になってしまうと、資材置き場や家庭菜園といった使い方をすることしかできなくなってしまいます。
接道義務を満たさない土地は売却価格が大幅ダウン
上記の通り、接道義務を満たさない土地は活用方法が非常に限られてしまうため、同エリア内にある土地と比べて売却価格は大幅にダウンしてしまいます。
物件にもよりますが相場の1割~3割程度まで下がってしまうこともあります。
ただし書きの規定に基づく許可を受けられることがある
接道義務を満たさない敷地であっても、以下のような条件を満たすことができれば但し書き道路として建築許可を得られることがあります。
- 敷地の周囲に公園、緑地、広場などの広い空地があるまたは、広い空地に2m以上接している
- 敷地が農道や類する公共の道(幅員4m以上のもの)に2m以上接している
- 避難および安全のために十分な幅員を有する道路に通ずるものに有効に接している
建築許可を得られるかどうかはケースバイケースなので、上記に当てはまりそうであれば役所の窓口で相談してみるとよいでしょう。
接道義務を満たさない土地の取扱い
接道義務を満たさない土地の場合、建築物を建てることができず、それ故に売却価格も大幅にダウンしてしまいます。
ただし書き道路の規定も利用できない場合、どのように対処するとよいのでしょうか?
セットバックする
まずは、敷地の前面道路の幅員が4mに満たず、接道義務を満たさないケースでは敷地の一部を道路とみなすことで建築許可を得るセットバックという方法が取れないか検討してみましょう。
これは不動産会社や住宅会社に相談すればすぐに調査してもらえます。
隣地を利用する
接道義務を満たさない土地の内、敷地延長部分が2mの接道幅を取れないようなケースではセットバックで解決することもできません。
こうしたケースでは、隣地を購入したり、逆に隣地の所有者に土地を売却したりすることを検討するとよいでしょう。
隣地を購入して接道義務を満たすことができるようになれば、合わせて売却してもよいですし、合筆した後、改めてそれぞれが接道義務を満たすように分筆して売却するといったこともできます。
隣地の所有者から、土地の一部だけ買い取るといった対策も考えられるでしょう。
その逆に、接道義務を満たさない土地の利用価値は非常に低いですが、隣地の所有者にとっては、購入することで活用の幅が広がる見込みが生まれます。
通常であれば二束三文で売却しなければならないところ、隣地の所有者に売却するのであれば相場程度の価格で売却できる可能性もあります。
▼関連記事

専門業者に売却する
接道義務を満たさない土地については、専門の業者が買い取るようなケースもあります。
こうした業者では、安く土地を購入した後、時間をかけてでも隣地を買い取ることで、マンション用地として売ると言った方法で利益を上げるのです。
上記のような方法を含め、接道義務について不安が�ある場合はまずは不動産会社に相談してみるのがよいでしょう。
不動産会社に相談するのであれば、「イエウリ」がおすすめです。
「イエウリ」であれば複数の不動産会社からの査定を一度に受ける事ができるのに加え、物件の購入希望を出した会社の中から売主が連絡をとる相手を選べます。これによって、不動産会社を見つける手間と不特定多数の不動産業者による一方的な営業電話に応じる手間が大幅に解消され、スムーズに売却活動を始める事ができます。
また、幅広い不動産会社からの登録があるため、思わぬ価値を見出してくれる不動産会社が現れる可能性もあるでしょう。
ただし、「イエウリ」は現在、土地だけの買取では利用できないため注意が必要です。
「イエウリ」で物件の無料査定に申し込む
まとめ
接道義務についてお伝えしました。
不動産の売却を考えるにあたり、接道義務は最初に確認しておくべきポイントです。
市町村道路や都道府県道など公道に面している道路であればそう難しくはありませんが、既存道路や2項道路の場合には判断が難しい場合もあります。
接道義務について不安がある敷地の売却を進める場合、最初から不動産会社に相談しておくと安心です。
その際には、「イエウリ」を利用して相談することで、最終的な高値を高くできる可能性を高めることができるでしょう。