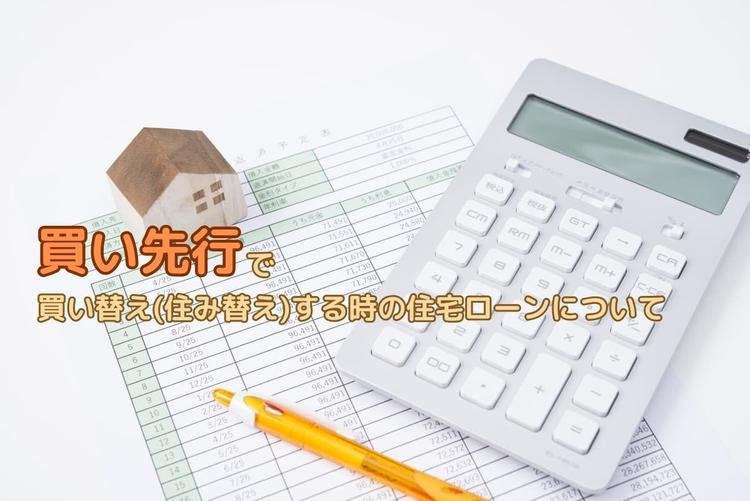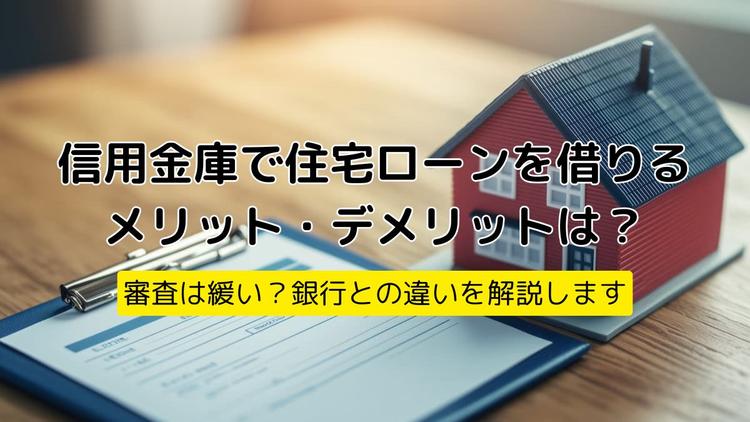家を建てる、あるいは購入する際に、「住宅性能評価書」というものがあることを知った方も多いのではないでしょうか。これは、住宅の性能を客観的に評価・表示する制度であり、品質や安全性に対する信頼性を高めるうえで重要な役割を担っています。
この記事では、住宅性能評価書とは何か、その種類や取得方法、評価項目から分かる情報について解説します。
住宅性能評価書とは?
住宅性能評価書とは、住宅の「性能」を国が定めた基準に基づいて客観的に評価・表示した書類のことです。
専門の第三者機関(指定住宅性能評価機関)が、住宅の設計内容や実際の施工状況をチェックし、その結果を等級や数値で示します。評価は、構造の強さや断熱性能、劣化のしにくさといった、住まいの安心・快適に関わる項目にわたります。
この制度は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」にもとづいて2000年に創設されました。これにより、一般の消費者が住宅の性能を比較しやすくなり、設計・施工の透明性や信頼性の向上にもつながっています。
簡単にいえば、「住宅性能評価書」とは、目に見えない住宅の性能を可視化し、安心して家を選ぶための指標となる公的な証明書です。住宅購入や新築を考える際には、その有無や評価内容を確認することが、後悔しない住まい選びへの第一歩となります。
評価書には大きく分けて2種類あり、ひとつは設計段階で評価を行う「設計住宅性能評価書」、もうひとつは実際に建てられた住宅を現場で検査し、その結果を記載する「建設住宅性能評価書」です。特に後者は、住宅ローンの優遇や地震保険料の割引、万一の紛争時の対応などにも活用できるため、取得するメリットは大きいといえるでしょう。
性能評価の種類:「設計」と「建設」
住宅性能評価書�には、「設計住宅性能評価書」と「建設住宅性能評価書」の2種類があります。それぞれ評価のタイミングや内容が異なり、役割も明確に分かれています。
ここでは、両者の違いや取得の流れ、活用方法について解説します。
設計住宅性能評価書とは
設計住宅性能評価書は、住宅の設計段階で交付される評価書です。設計図書や構造計算書、仕上げ仕様書などに基づき、専門の評価機関が各性能項目を審査します。
この段階では、まだ実物の建物は存在せず、設計上の性能に対する評価となります。
主な特徴は次のとおりです。
- 住宅が建築される前に取得できる
- 評価内容は、図面や仕様書にもとづいた「設計上の性能」
- 施工ミスや仕様変更の抑止力となる
- 分譲住宅などでは広告資料に活用されることもある
設計評価は、これから家を建てる人や購入しようとしている人にとって、建物の完成前にその性能を把握する手段として有効です。特に、売主側が性能評価を取得している場合は、購入前の信頼性を高める材料になります。
建設住宅性能評価書とは
建設住宅性能評価書は、実際に建築された住宅について、現場での検査を通じて評価を行い、設計どおりに施工されているかを確認したうえで交付される書類です。つまり、設計通りの性能が“実物として”実現されているかどうかを、第三者が客観的にチェックするものです。
主な特徴は次のとおりです。
- 建築中および完成時の現場検査に基づいて交付される
- 指定された検査工程(基礎、構造躯体、断熱材、竣工時など)を複数回確認
- 設計評価とセットで取得することが一般的(単独でも可)
- 各種優遇制度(フラット35S、地震保険の割引など)の利用条件となる場合がある
建設評価は、購入者にとって施工精度の「お墨付き」ともいえる存在で、信頼性の高い住宅を選ぶための重要な判断材料となります。
中古住宅として将来売却する際にも、性能が保証されている証拠として有利に働くことがあります。
2つの評価を併せて取得する意義
設計住宅性能評価書と建設住宅性能評価書は、単独で取得することも可能ですが、両方を取得することで制度の本来の目的を最大限に活かすことができます。
この2段階の評価によって、住宅の計画から完成まで一貫して性能が管理され、見た目だけでは判断できない構造や設備の質を把握することが可能になります。
どちらを取得すべきか?
住宅を「建てる人」「買う人」「売る人」それぞれの立場によって、取得すべき評価書の種類や組み合わせが異なります。
- 注文住宅を建てる人:設計・建設の両方の取得が望ましい。設計の意図通りに施工されているか確認できる。
- 分譲住宅を購入する人:設計評価しかない場合は、建設評価があるかどうかも確認。両方あればより安心。
- 住宅販売を行う事業者:信頼性をアピールするためには、2種類とも取得しておくと購入者への説得力が増す。
評価項目と等級の見方
住宅性能評価書には、住宅の品質や安全性、快適性などを測るための10分野の評価項目が設けられています。各項目は、国の定める技術的基準に基づいて、等級(数字や記号)で評価されます。
ここでは、代表的な評価項目とその見方を中心に、どのように等級を読み解けばよいかを解説します。
構造の安定(耐震等級)
地震大国である日本において、最も注目される項目です。建物の構造が地震や台風などの外力にどの程度耐えうるかを評価します。
- 耐震等級1:建築基準法で定められた最低限の耐震性能(震度6強〜7程度の地震に耐える)
- 耐震等級2:等級1の1.25倍の強さ。学校や病院など、防災拠点建築に相当
- 耐震等級3:等級1の1.5倍。最高ランクの耐震性能。消防署や警察署などが基準
一般住宅でも、等級2以上を目指すケースが増えています。等級3は地震保険料の割引率にも有利に働きます。
劣化の軽減(劣化対策等級)
建物の構造部材(柱、梁など)がどれだけ長持ちするかを示す指標です。耐久性の高さが将来の修繕・建て替えリスクを軽減します。
- 等級1:通常の維持管理で25年程度の耐久性
- 等級2:おおむね50年程度の耐久性
- 等級3:おおむね75年〜90年程度の耐久性
長期優良住宅などの認定を受ける場合には、等級3が求められることもあります。
維持管理・更新の容易性(配管の点検・更新)
給排水管やガス管、電線などの点検や更新のしやすさを評価します。
- 等級1:最低限の維持管理が可能
- 等級2:ある程度点検・交換が容易
- 等級3:点検口の設置や更新作業が非常にしやすい構造
マンションなどで長期間使用することを前提にするなら、等級2以上が望ましいでしょう。
温熱環境・省エネルギー性(断熱性能等級/一次エネルギー��消費量等級)
断熱性能や冷暖房の効率の良さを評価する項目です。光熱費の節約や、夏冬の快適性に大きく関わります。
- 断熱等性能等級(1〜7)
等級が高いほど断熱性が高く、省エネ効果が大きい。等級6〜7はZEH水準に相当。 - 一次エネルギー消費量等級(1〜6)
建物全体のエネルギー消費量(冷暖房・照明・給湯など)を評価。等級6は省エネ基準を超える高性能住宅。
温暖化対策やランニングコストを重視する場合、等級の高い住宅を選ぶことが推奨されます。
空気環境(ホルムアルデヒド対策・換気性能)
シックハウス症候群の原因となる化学物質の使用量や換気設備の設置状況を評価します。
- ホルムアルデヒドの発散量:JIS表示でF☆☆☆(3つ星)〜F☆☆☆☆(4つ星)で示され、F☆☆☆☆が最も安全
- 機械換気の有無:24時間換気システムが整っているかが評価対象
新築住宅では、法令により24時間換気設備の設置が義務化されています。
音環境(遮音性能)
床や壁を伝わる音をどれだけ遮断できるかを評価します。特に集合住宅では、生活音トラブルを避けるうえで重要です。
- 床衝撃音遮断性能:上階からの足音などへの対策
- 空気音遮断性能:隣室との間の会話・テレビ音などの遮音性能
遮音性能は数値(dB)で示され、値が高いほど防音性に優れています。
高齢者等への配慮(バリアフリー性能)
バリアフリー設計のしやすさや、高齢者や身体の不自由な人への配慮がされているかを評価します。
- 移動のしやすさ(廊下の幅や段差の有無など)
- 手すりの設置性、出入口の有効幅など
将来的に高齢者と同居を予定している家庭などでは、事前に確認しておきたい項目です。
火災時の安全性(避難・延焼対策)
万一火災が発生した際に、住人が安全に避難できるか、または火が広がりにくい構造かを評価します。
- 内装材の燃えにくさ(難燃性)
- 避難経路の確保
- 隣接住宅への延焼のしにくさ
火災保険の契約時にも、評価が影響する場合があります。
防犯対策(侵入防止性能)
玄関ドアや窓など、外部からの侵入に対する防御性能を評価します。マンションや都市部の住宅ではとくに注目される項目です。
- 防犯ガラスや二重ロックなどの有無
- 開口部(窓・ドア)の構造と強度
「CPマーク」付き建材(警察庁推奨の防犯性能部材)が使われている場合、高い評価を受ける傾向にあります。
住宅性能評価書の取得方法
住宅性能評価書を取得するには、国土交通大臣の登録を受けた「指定住宅性能評価機関」に申請し、審査・検査を受ける必要があります。評価書は設計段階と建設段階の2種類があり、それぞれ取得までの手続きが異なります。
ここでは、評価書を取得するための基本的な流れや必要書類、注意点をわかりやすく解説します。
評価機関の選定
まず行うのが、住宅性能評価を実施している機関の選定です。評価業務は「指定住宅性能評価機関」として国から登録された法人が担っており、各都道府県に複数の機関が存在します。
評価機関を選ぶ際のチェックポイント:
- 対応エリア(地域によって対応できる範囲が異なる)
- 評価にかかる費用と納期
- 過去の実績や専門性
大手では日本ERI、住宅保証機構、JIOなどが広く知られていますが、地元密着型の評価機関も存在します。
設計住宅性能評価の申請
住宅の設計がある程度まとまった段階で、設計評価の申請を行います。評価機関に対し、建築士が作成した設計図書一式を提出します。
提出書類は次のとおりです。
- 配置図、平面図、立面図、断面図などの設計図
- 各種構造計算書
- 仕上げ表、仕様書
- 申請書、委任状(必要に応じて)
評価機関はこれらの資料を審査し、各評価項目に応じた性能等級を決定します。設計内容に不備や基準未達の箇所があれば、差し戻しや修正の指導が行われます。
設計評価が完了すると、「設計住宅性能評価書」が交付されます。設計段階の性能が明文化されることで、施工段階での性能確保の指針にもなります。
建設住宅性能評価の申請
設計評価書を取得したら、次に「建設住宅性能評価」の申請を行います。建設評価では、実際に建築される住宅が設計通りに施工されているかどうかを、現場検査を通じて評価します。
検査の主なタイミングは次のとおりです。
- 基��礎配筋工事完了時
- 構造躯体工事完了時
- 断熱材施工完了時
- 完成時(外観・仕上げ・設備確認)
各検査は事前に予約が必要で、工程に遅れが出た場合には再調整が必要となります。施工業者と評価機関との密な連携が求められる工程です。
現場検査で問題がなければ、住宅完成後に「建設住宅性能評価書」が発行されます。これが取得されていれば、住宅ローン減税や地震保険の割引といった優遇措置を受けやすくなります。
▼関連記事:住宅ローン控除の利用条件になる高性能住宅とは?基準を解説します
評価書取得にかかる費用
住宅性能評価の申請には、評価機関ごとに定められた費用がかかります。住宅の構造や規模、評価項目の範囲によって異なりますが、おおよその相場は次のとおりです。
- 設計住宅性能評価……約5〜10万円
- 建設住宅性能評価……約10〜15万円
一部の項目だけを評価対象とする「部分評価」を選択すれば、費用を抑えることも可能です。ただし、フラット35や地震保険の割引を利用したい場合は、必要な評価項目を満たしているかどうかを事前に確認しましょう。
申請は誰が行うのか?
評価書の申請手続きは、原則として建築主(施主)が行いますが、実務上は設計事務所や施工業者が代行することが一般的です。代行にあたっては、委任状が必要になります。
分譲住宅などでは、売主側(ディベロッパーやハウスメーカー)が評価書を取得したうえで販売するケースも多く、購入者はその内容を確認するだけで済みます。
申請のタイミングと注意点
申請のタイミングは次のとおりです。
- 設計評価は建築確認申請前後の早い段階に行うのが望ましい
- 建設評価は基礎工事前には申請を済ませておく必要あり
注意すべき点はつぎのとおりです。
- 事前調整が重要:検査スケジュールと施工工程の整合をとっておかないと、現場の進行に支障を来すことがあります。
- 再検査のリスク:検査で基準未達となれば、是正・再検査が必要になります。設計通りの施工が徹底されているかが問われます。
- 部分評価の場合の条件確認:優遇制度を受けるには、必要な評価項目がそろっているかどうかを慎重にチェックしましょう。
まとめ
住宅性能評価書は、住まいの品質や安全性を客観的に示す公的な証明書です。設計段階と建設段階の2種があり、それぞれ住宅の計画と施工の信頼性を高めます。
評価項目は耐震性・断熱性・劣化対策など多岐にわたり、等級表示により比較検討がしやすくなります。また、住宅ローン優遇や地震保険料の割引といった制度にも活用可能です。家を建てる・買う・売るすべての場面で、その有無と内容を確認することが、安心・納得の住まい選びにつながります。