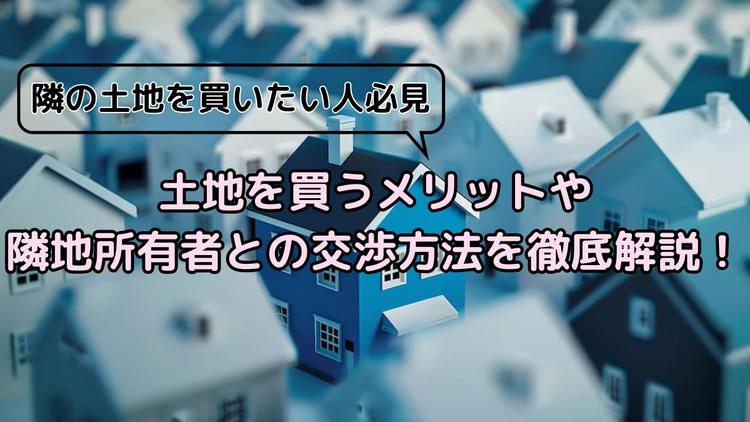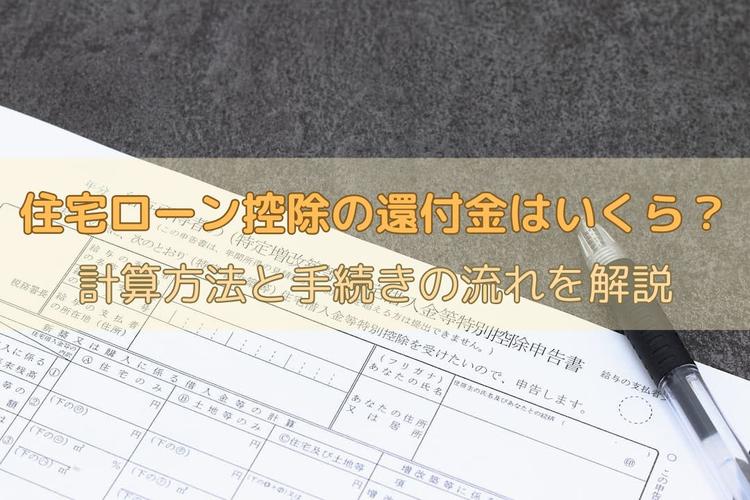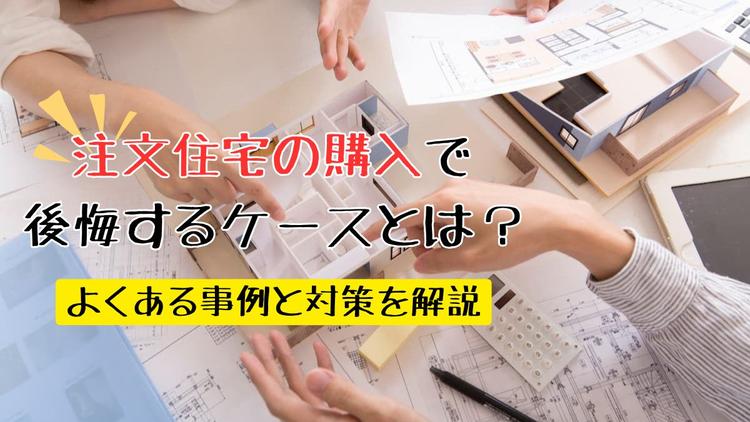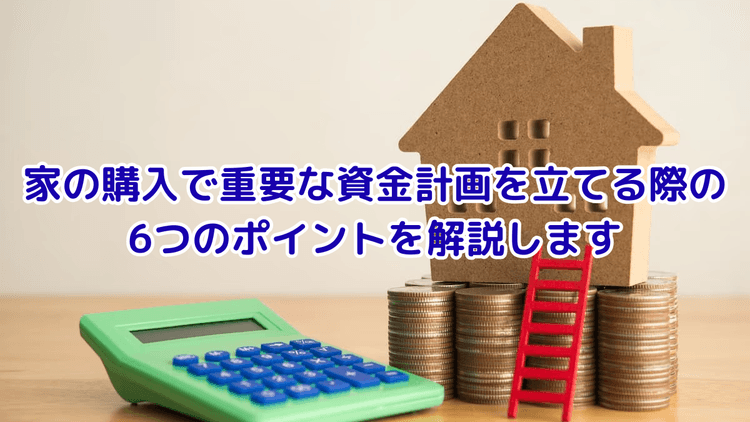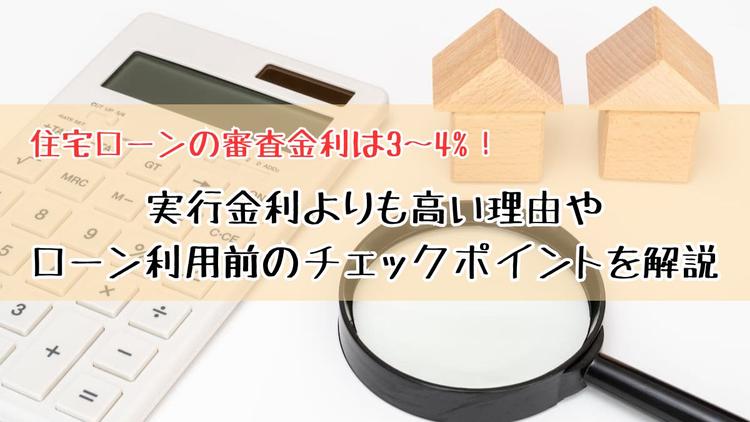「隣の土地は借金してでも買え」という言葉があるように、隣地購入は資産価値の向上や利便性の向上に大きく貢献する可能性があります。
しかし、実際に購入を検討する際には、隣地の状態や相場、交渉の難易度などをしっかり把握し、自分にとって本当に価値のある選択なのかを見極めることが重要です。
また、隣の土地を買うことで、交渉や管理、税金などの負担も伴います。
この記事では、隣の土地を買うメリット・デメリットや注意点、スムーズに取引を進めるためのポイントを詳しく解説します。
隣地購入を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
隣の土地を買うメリット
隣の土地を買うメリットは主に以下の3点です。
- 土地条件が良くなる
- 幅広く土地を使えるようになる
- 相続税対策になる
それぞれを詳しく解説します。
土地条件が良くなる
隣の土地を購入することで、現在の土地条件が良くなるのが大きなメリットです。
例えば、所有する土地が不整形地の場合、隣地を併せることで整形地となり建築や活用の幅が広がります。
また、隣地が幅広い道路に面している場合は容積率が増加し、建物の延床面積を拡大できるケースもあります。
幅広く土地を使えるようになる
隣の土地を購入することで所有する敷地が広がるため、土地を幅広く使えるようになります。
例えば、現在の土地が狭くて建物の増築や庭の拡張が難しい場合でも、隣地を買えばこれらが可能になります。
また、土地の形状が整うことで建築の自由度が増すため、理想的な住まいや施設の建設が実現しやすくなるのも大きなメリットです。
相続税対策になる
隣の土地を購入することで相続税対策に有効です。
現金をそのまま保有していると相続時に高い税負担が発生します。しかし、現金を不動産に変えると評価額が現金より低くなるため、相続税の負担を軽減できます。
例えば、1,500万円の現金を相続する場合、その全額が課税対象です。
一方、同額の土地を購入し、その評価��額が1,200万円であれば課税対象は1,200万円となり、相続税の負担が減少します。
相続税の計算には「路線価」が用いられますが、これは市場での実際の取引価格(実勢価格)よりも低く設定されています。
相続税路線価は、実勢価格よりも低い額で算出されるケースが多い。
この差を利用し、実勢価格よりも低い評価額で相続税を計算できるため、税負担を軽減できます。
隣の土地を買うデメリット
隣の土地を買うデメリットは以下の3点です。
- 隣地所有者と交渉しなければならない
- 管理の手間が増える
- 税金負担が増える
メリットと併せて確認しておきましょう。
隣地所有者と交渉しなければならない
隣地所有者と交渉しなければならないのが大きなデメリットです。
交渉時には以下の点において難航する可能性があります。
- 売却意思の不明確さ
- 価格設定の難しさ
- 感情的な要素
そもそも、隣地所有者に土地を売る意思があるかどうかを確認しなければなりません。
また、所有者によっては価格を高く設定してくるケースもあるため、周辺相場よりも高い価格で購入しなければならない可能性も考えられるでしょう。
ほかにも、隣人との関係性も売買に関係してくるため、普段からの付き合いなどが影響してきます。
なお、隣地の所有者が住んでおらず、登記情報から所有者を確認しても連絡できる手段が無いといった場合は「所有者不明土地・建物管理制度」を利用して購入できる可能性があります。
▼関連記事:所有者不明土地を購入する流れ
管理の手間が増える
管理の手間が増える点にも注意が必要です。
例えば、土地購入後は草刈りや清掃などを定期的におこなう必要�があり、これらを怠ると景観の悪化や近隣トラブルの原因となる可能性があります。
専門業者へ管理委託できますが、委託料として費用が発生します。
隣の土地を買う際は、管理の手間が増えることに注意しましょう。
税金負担が増える
隣の土地を購入すると、固定資産税や都市計画税などの税金負担が増加します。
固定資産税と都市計画税は、土地の評価額に基づいて計算され、所有する土地が増えるとその分税額も増加するのが特徴です。
さらに、隣地を購入してもすぐに活用できない場合、未利用地として高い税率が適用されることもあります。
隣の土地を買った方がよいケース
隣の土地を買った方がよいケースは以下の2点です。
- 現在の土地が狭い場合
- 旗竿地の場合
それぞれを詳しく解説します。
現在の土地が狭い場合
現在所有している土地が非常に狭く、不便を感じている場合は隣の土地を購入するメリットは大きいです。
隣地を買えば利用できる敷地が広がるため、建物の増築や駐車スペースの確保、庭の拡張など、多様な活用が可能です。また、土地の形状が改善されることで資産価値の向上も期待できます。
今の土地だけでは不十分だと感じている場合は、隣の土地の購入を検討してみましょう。
旗竿地の場合
所有している土地が旗竿地の場合も隣の土地を買った方がよいです。
旗竿地とは、道路に面した狭い通路(竿部分)を通じて、奥に広がる敷地(旗部分)を持つ土地形状を指します。
旗竿地は、敷地全体が狭い且つ特殊な形をしているのが特徴です。
そのため、隣地を買うことで敷地全体の形状が整い、建物の配置や設計の自由度が高まります。
また、日当たりや風通しの改善にも期待でき、駐車スペースの確保や庭の設計もしやすくなります。
現在所有している土地が旗竿地の場合は、隣の土地を買って利便性を良くしてみましょう。
隣の土地を買わない方がよいケース
隣の土地を買わない方がよいケースは以下の2点です。
- 購入しても土地条件が良好にならない場合
- 価格が相場より極端に高い場合
それぞれを詳しく解説します。
購入しても土地条件が良好にならない場合
隣の土地を購入しても土地条件が良好にならない場合は買わない方がよいです。
例えば、所有している土地がすでに整形地であり、隣地と併合しても形状や利用価値がほとんど変わらない場合などです。
この場合、隣の土地を買っても利便性が大きく変わらず、資産価値の向上も期待できません。
また、購入する隣地が狭小地や旗竿地などの特殊な土地の場合は購入するメリットが少なく、むしろ扱いにくい土地をになるため、購入には向いていません。
価格が相場より極端に高い場合
隣の土地の価格が相場よりも極端に高い場合も買わない方がよいです。
価格は隣地所有者と合意の上で取引しなければならないため、相手が高額売却を狙って極端に高い価格を要求するケースがあります。
購入後に土地を有効活用できなかったり資産価値として上昇しなかったりすれば大きく損することになるため、購入するかどうか慎重に判断すべきです。
隣の土地を買うべきかどうか判断できない場合は、不動産会社へ相談するのがよいでしょう。
隣の土地を買うための7つの手順
隣の土地を買う際は、以下7つの手順で進めましょう。
- 隣の土地の状態を確認する
- 隣の土地の相場を調べる
- 相場に合わせて購入後の建築プランを計画する
- 不動産会社へ相談する
- �隣地所有者と交渉する
- 売買契約を結ぶ
- 引き渡し
それぞれの手順を詳しく解説します。
STEP①:隣の土地の状態を確認する
まずは隣の土地の状態を確認しましょう。
- 所有者の確認
- 抵当権の有無
- 境界線の確認
- 土地の用途地域と建築制限
- 土地の形状と面積
所有者と抵当権は、法務局にある「登記簿謄本」を取得して確認できます。境界は、地積測量図で確認できます。
また、土地の用途地域と建築制限も重要です。これらは、その土地に建てられる建物の種類や規模の制限を意味しているもので、土地によって制限内容が異なります。
ほかにも、土地の形状や面積を確認して、どのような建物が建てられるのか想定しておきましょう。
STEP②:隣の土地の相場を調べる
次に隣の土地の相場を調べましょう。
相場を調べることで、売り出し価格が適正かどうかを判断できます。
相場を調べる方法には以下があります。
- 「不動産情報ライブラリ」で調べる
- 不動産ポータルサイトで調べる
- 不動産会社へ相談する
「不動産情報ライブラリ」とは、国土交通省が提供している不動産情報サイトです。不動産価格や相場動向などを掲載しており、相場を見極める際に参考になります。
また、「SUUMO」や「ホームズ」などの不動産ポータルサイトでは、実際に売り出されている土地の価格や規模を調べられるので参考にできます。
さらに詳しい相場を知りたいのであれば、不動産会社へ相談しましょう。隣地の面積や形状などを考慮した��うえで、想定される価格を教えてくれます。
STEP③:相場に合わせて購入後の建築プランを計画する
相場を調べたら、相場に合った建築プランを計画しましょう。
プランを立てる際には、土地の形状や面積、法的規制を考慮し、専門家と相談しながら計画を進めることが重要です。
「どんな家を建てられるのか」「建てる際の制限はなにか」などを把握しておきましょう。
具体的な建築プランを事前に計画することで、土地を有効活用できるようになります。
STEP④:不動産会社へ相談する
建築プランを計画したら不動産会社へ相談しましょう。
隣の土地を購入する目的や意図などを伝え、売買を仲介してもらえないか相談します。
そもそも、不動産の個人間取引はトラブルが起こりやすいです。さらに不動産の知識が少ない人同士であれば、契約後に取り返しのつかない問題に発展するケースも少なくありません。
不動産会社へ相談して、より安心・安全な土地取引を目指しましょう。
STEP⑤:隣地所有者と交渉する
次に隣地所有者と交渉しましょう。
交渉の際は、直接話に行くか手紙でのアプローチ方法があります。
隣地所有者との関係により適切な方法は異なりますが、普段から世間話をするような親しい間柄であれば直接伝え、あまり交友関係がないのであれば手紙でのアプローチが無難です。
手紙には、自身の氏名や連絡先を明記し、隣地購入に関心がある旨を丁寧に伝えましょう。
交渉は長期戦になることも多いため、焦らずじっくりと進める姿勢が大切です。
STEP⑥:売買契約を結ぶ
交渉の結果、隣地所有者が納得したら売買契約を結びましょう。
売主と買主の間で価格や支払い方法、引き渡し時期などの条件を明確にして合意します。この際、口約束ではなく正式な売買契約書を作成し、双方が署名・押印することで後々のトラブルを防げます。
契約書には土地の詳細情報や支払い条件、引き渡し方法などを具体的に記載します。
これらの手続きには専門的な知識が必要なため、不動産会社に仲介してもらうのがよいでしょう。
なお、売買契約時には取引価格の5~10%程度の金額を手付金として支払い、残代金を引き渡し時に支払うのが一般的です。
STEP⑦:引き渡し
売買契約を完了させたら、いよいよ引き渡しです。
引き渡し当日は、売主と買主(不動産会社へ仲介依頼していれば担当者も)が集まり、売買代金の支払いや抵当権抹消登記、所有権移転登記などをおこないます。
登記手続きは自分でも手続きできますが、専門的な知識が必要なので司法書士へ依頼するのが一般的です。
また、購入する隣地に抵当権が設定されている場合は、抵当権者の金融機関等に確認を取った上で司法書士に登記を依頼しなければ、取引が認めてもらえない場合がほとんどです。
これらの登記手続きが完了してから実際に引き渡しとなります。
引き渡しを受けた際、土地の規模により都道府県知事への届出が必要となる場合があるため、事前に確認しておきましょう。
参考:東京都都市整備局|国土利用計画法に基づく土地取引の届出
隣の土地をスムーズに買うための重要ポイント3選
隣の土地をスムーズに買うためは以下3つのポイントを押さえましょう。
- 隣地所有者との付き合いを良くしておく
- 相手の細かい条件は受け入れる
- 不動産会社に仲介してもらう
それぞれを詳しく解説します。
隣地所有者との付き合いを良くしておく
スムーズに土地を買うためにも、日頃から隣地所有者との付き合いを良くしておきましょう。
日頃から挨拶や会話を心がけ、信頼関係を深めておくと購入の提案を受け入れてもらいやすくなるからです。
また、相手の立場や事情を理解し、無理な要求を避けることで交渉が円滑に進みます。
隣地購入は一般的な不動産取引と異なり、売り出されていない土地について交渉するため、普段からの関係性が取引の成功につながります。
スムーズに買うためにも、普段から良好な関係を築いておきましょう。
相手の希望する条件は受け入れる
相手の希望する条件はできるだけ受け入れましょう。
売主が提示する細かな要望に柔軟に対応することで交渉がスムーズに進み、契約成立の可能性が高まります。
特に、隣地購入は長期戦になることが多いため、相手の条件を尊重して信頼関係を築くことが重要です。
価格や引き渡し時期、契約時の決まり事などに関して売主の要望があれば、できるだけ受け入れましょう。
不動産会社に仲介してもらう
不動産会社に仲介してもらうのも重要なポイントです。
不動産会社へ仲介してもらえば、交渉や売買契約などを代わりにおこなってくれるため、トラブルなくスムーズに取引できます。
不動産取引は専門的な知識が必要であり、価格も高額になるケースが多いです。不動産知識の少ない人が取引を行うと、思わぬトラブルへ発展する恐れがあります。
スムーズ且つ確実に取引を成功させるためにも、不動産会社に仲介してもらうのがよいでしょう。
▼関連記事:土地の売買契約書は自分で作成できる?確認事項とリスク・注意点を解説
隣の土地を買う際の注意点
隣の土地を買う際は以下4つの注意点に気を付けましょう。
- 土地の制限を確認しておく
- 急かすような交渉はしない
- 個人で取引を進めない
- 弁護士等の代理人を立てた交渉は慎重に行う
それぞれを詳しく解説します。
土地の制限を確認しておく
土地にどのような制限があるかを確認しておきましょう。
土地には都市計画法や建築基準法などの法律に基づく以下のような制限があります。
- 用途地域
- 建ぺい率
- 容積率
- 高さ制限
これらの制限により、建てられる建物の種類や大きさ、高さが決まります。
例えば、住宅地では商業施設の建築が制限されている場合が多いです。また、建ぺい率や容積率によって建物の面積や高さが制限され、希望する建物が建てられない可能性もあります。
さらに、日影規制や斜線制限などにより、建物の形状や配置が制約されることもあります。
このように、土地にはさまざまな制限が設定されているケースが多いため、不動産会社へ相談するなどして事前に確認しておきましょう。
急かすような交渉はしない
急かすような交渉は避けましょう。
交渉を急かすと相手に不信感を抱かれる恐れがあり、取引に応じてくれない場合があります。
仮に取引に応じてくれたとしても相手に不信感を抱かれながら進めることになるため、満足のいく取引ができない恐れもあります。
確実に土地購入を成功させるためにも、相手の状況や考えを理解し、時間をかけて丁寧に話し合う姿勢を見せましょう。
個人で取引を進めない
個人で取引を進めないようにしましょう。
不動産取引は複雑で、契約内容や手続きに不備が生じると、後々トラブルに発展する可能性があります。
特に、隣地の購入は感情的な要素も絡みやすいため、第三者である不動産会社に仲介を依頼することでスムーズな取引を実現できます。
不動産会社に仲介を依頼し、担当者に進めてもらうことにより安全に取引できるでしょう。
弁護士等の代理人を立てた交渉は慎重におこなう
弁護士等の専門家へ依頼する際の交渉は慎重におこないましょう。
専門家へ依頼した場合、隣地所有者が身構えてしまうリスクがあります。
身構えられてしまうと、取引に応じてくれなくなったり取引が停滞したりする可能性があります。
専門家へ依頼するのはトラブルを避けるために重要ですが、相手方が取引に慎重になりすぎてしまうリスクがあることを理解しておきましょう。
「隣の土地を買いたい」に関するよくある質問
隣地購入に関するよくある質問をご紹介します。
土地を買った後の固定資産税はいくら?
固定資産税は、土地の場所や面積、利用状況によって異なります。
まず、土地にかかる固定資産税は、固定資産税評価額をもとに計算されます。
次に課税標準額を求めます。
宅地(建物を建てる目的の土地)の場合、土地の面積によって異なり、200㎡以下の土地であれば評価額の6分の1、200㎡を超える部分は3分の1が課税標準額です。
その後、課税標準額に1.4%をかけた金額が固定資産税として課税されます。
例えば、評価額3,000万円の土地で小規模住宅用地150㎡の場合は以下の計算となります。
固定資産税 = 500万円 × 1.4% = 7万円
このように、評価額や土地の面積によって固定資産税額が異なるため、事前に確認しておきましょう。
なお、固定資産税評価額は、市区町村から毎年送付される「固定資産税納税通知書」に記載されています。
隣地所有者との適切な交渉方法は?
良好な関係を築けていれば直接交渉し、そうでなければ手紙で購入の旨を伝えるのがよいでしょう。
隣地を購入するためには隣地所有者と交渉しなければなりません。日頃から良好な関係を築けていれば気軽に交渉できますが、挨拶程度の関係であればいきなり交渉するのは億劫に感じるでしょう。
その場合、まずは手紙を送って購入の意思を伝えるのが無難です。ワンクッション置くことで交渉に応じてくれる可能性が高まる場合もあります。
直接交渉するのが難しい場合は手紙を送ってみましょう。
「隣の土地は借金してでも買え」とはどういう意味ですか?
「隣の土地は借金してでも買え」とは、隣接する土地を購入することで得られる多くのメリットを意味しています。
具体的には、土地の面積が広がることで建物の設計や�活用の幅が広がり、資産価値の向上に期待できます。また、隣地を所有できれば将来的なトラブルや不安も未然に防げるため、購入するメリットが大きいです。
そのため、「借金してでも早い段階で買った方がいい」という意見があります。
ただし、隣地を買ったからといって必ずしも資産価値が向上するとは限らず、ローンを利用する場合は借金が膨らみます。土地の面積や形状、土地上の制限、隣地を購入した後の活用方法などをしっかりと考慮したうえで購入するかどうか判断しましょう。
まとめ
隣の土地を買うメリットやデメリット、注意点などを解説しました。
隣の土地を買うメリットは「土地条件がよくなる」「資産価値が上がる」などがあります。一方で「隣地所有者と交渉しなければならない」「管理の手間がかかる」などのデメリットもあります。
これらの特徴を理解していないと、購入後に後悔したり損したりする可能性があるので注意しましょう。
また、土地の取引は、専門的な知識が必要であり高額な取引になりやすいです。不動産知識の少ない人同士での取引は、契約後に思わぬトラブルへ発展する恐れがあるため、不動産会社へ依頼するのがおすすめです。
お近くの不動産会社、もしくは不動産一括査定などを活用して自分に合った不動産会社へ相談してみましょう。