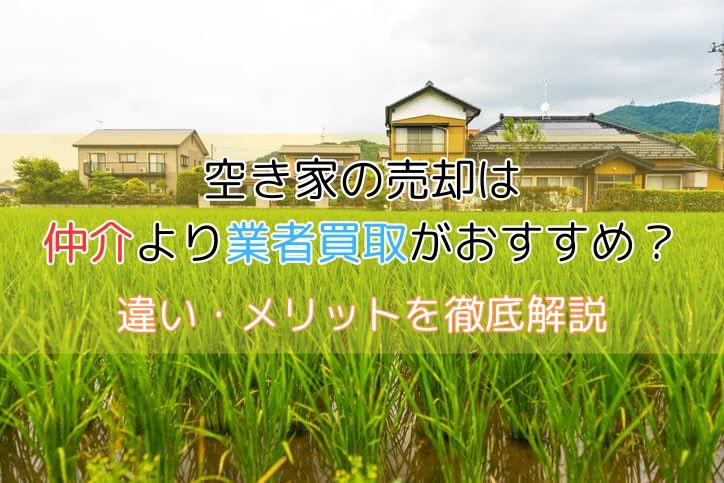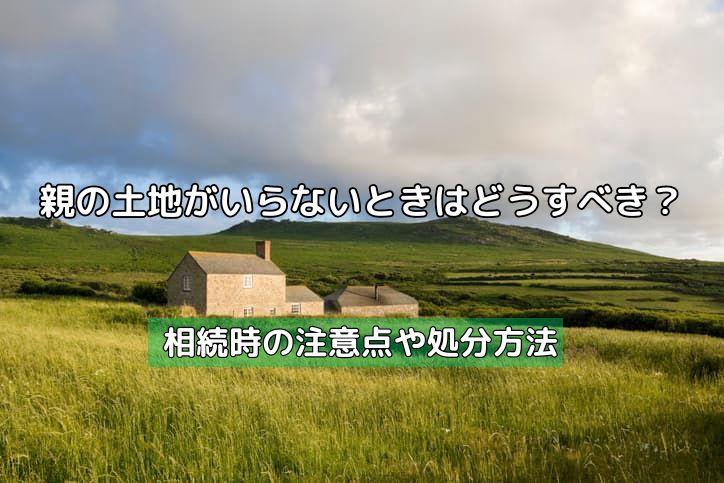前回の記事では、売却価格よりも、その売却のために要する手間暇や費用が上回ってしまうために値段がつかず、所有者から「処分費用」を受け取って物件を引き取る「有償引取業者」の存在について紹介しました。
しかし有償業者にしても、使い道がなく、維持費もかかる負動産を無限に引き取り続けるわけにはいきません。ある程度の所有コストを見越して引取料金を設定しているとはいえ、不動産は粗大ごみのように捨てることができません。
そのため、引取り業者自身が売主となって、引き取った物件の販売を行っているケースはよく見られます。
引き取り後の不動産はどうなる?
お金を払わなくては処分ができない物件が果たして売れるのか、という疑問は誰もが抱くところですが、実はこれが意外と引き取り手が見つかるものです。
もちろん高値が付くような物件ではないので、その価格は1万円とか10万円といった底値の価格、あるいは無償譲渡ですが、ともあれ誰かしらはその「負動産」を引き取って活用したいと考えているのです。ではそれらの引き取り手は、果たして値段がつかない負動産をどのように活用しているのでしょうか。
これは空き家、空き地、リゾートマンション等、物件の種類によって事例も様々なので、ケースごとに紹介していきたいと思います。
空き家
「空き家問題」のイメージに反し、負動産の中で最も引き合いが強いのは空き家です。0円物件を扱うサイトによく登場するような、負動産となる空き家の典型は、相続したものの利用する予定もなく持て余された、主に農村の古民家や、地方の小都市の古い民家です。
老朽化が進んでいて修繕に多額の費用を要したり、少子化が進んだ近年の核家族で生活するにはあまりに広すぎるようなものもあります。
空き家の売却・活用に伴う手間とコスト
その地域に中古物件の需要がある程度あったとしても、一般の中古住宅として売りに出すためには、一定の清掃や修繕が必要です。まずは内見可能な状態まで敷地内の整備や掃除を行い、残置物を処分しなけ��れば、なかなか買い手を見つけることはできません。
そうした手間を省いて、すべて前所有者の生活の痕跡が残ったままの状態で売りに出している物件もありますが、当然物件価格は、周辺相場からその整備や残置物の処分費用を差し引いた価格でなければなりません。その煩わしさを嫌って、無償譲渡、有償引取で処分を行う所有者も少なからず存在します。
こうした空き家が、例えば0円物件で登場した場合、物件によっては購入希望者が多数現れ抽選になることもあります。その申し込みが、きちんと熟慮した結果での行動であるかは別の話として、こうした申込者は大きく二つに分けて、自己使用目的と投資目的の2通りがあります。これは、一般の中古住宅と同様です。
買取再販業者
一般的な中古住宅の場合、近年では通常の仲介のほかに、業者自身が未リフォームの中古家屋を廉価で取得し、リフォームを施したうえで利益を上乗せして販売することがよくあります。買取再販業者のひとつ「カチタス」がこの手法で業績を伸ばし、近年は多くの買取再販業者が盛んに空き家の買取りを行っています。
ただし負動産と呼ばれるような空き家は、そのリフォームに多額の費用を要し、まともに業者を入れていたら周辺の中古住宅の相場より高くなってしまうものなので、一般的な買取再販業者が手を出すことはありません。
こうした物件を、一般の利用者がDIYで修繕して居住用に使用することがあります。
DIYリフォーム
DIYでのリフォームを夢想する方は多く、YouTube等でも人気のコンテンツのひとつです。買取再販業者によるリフォーム済物件は、必須となる修繕費用を低金利の住宅ローンに含められるというメリットがありますが、すべて1から思い通りの空間を作りたいDIY派の欲求を満たすものではありません。
実際にはDIYは誰でも簡単にできるようなものでもなく、根負けして修繕を断念してしまう方も少なからずいるのが実情なのですが(そのような修繕途上の物件が再び市場に出ることもあります)、多くの引き取り手がDIYリフォームに挑戦します。
これは自己利用の引き取り手だけでなく、負動産の空き家を賃貸物件に転用する投資家も同様です。同じく地元の賃貸市場の賃料相場では、業者を入れてのリフォームでは利回りが極端に低くなってしまいます。
収益物件として旨味のない負動産を、DIYで修繕することによって初期投資を抑え、安価な賃料でも収益性を確保しようというビジネスモデルです。
「ボロ戸建投資」の実態
俗に「ボロ戸建投資」などと呼ばれる手法は、個人的な印象では、投資目的の方のほうが収益に関わっている分、DIYにも熱心な傾向があると思います。
ただし専門の施工業者による修繕ではないのでその仕上がりの水準は千差万別で、また利回りを高めるために、総じてどの投資家もごく最低限のリフォームで済ませる傾向があります。1棟で3~4万円程度の賃料しか望めない立地の古家ではやむを得ません。
あるいは一切のリフォームを施さず、倉庫として貸し出したり、借主によるDIYでの修繕を許可し、退去時にも原状回復義務を課さない「DIY賃貸物件」として貸し出す投資家もいます。
こうした低賃料の賃貸物件は、仲介・管理する業者も限られるので、保証会社だけは外部の業者を利用し、ジモティーやその他個人向けの賃貸物件掲載サイトに自分で広告を出し、契約や問い合わせの応対などもすべて自分で行う、自主管理による賃貸経営を行う投資家もいます。
空き家活用の成功ポイント
率直に言ってそれらの賃貸物件の中には、いくら賃料が安くても、この建物をそのまま住戸として利用するのは厳しいのではないか、と思うような物件もあります。
しかし世の中にはどうしても予算が限られている方もいれば、外国人労働者のように、根本的に物件の選択肢が限られている人もいます。そうした隙間需要を埋める形で、こうした空き家が投資物件として転用されているようです。
自己利用、投資目的のいずれにも共通するのは、作業も含め、可能な限り自力で行うことで初めて費用面でのメリットが生まれるという点です。
一般論として、修繕を途中で断念した形跡が残る物件(特に素人工事によるもの)は中古物件市場で忌避される傾向にあるので、自己使用であれ投資用であれ、挑戦するのであれば自分の力量��や予算、スケジュールを充分に考慮したうえで取り掛かるのが良いでしょう。
空き地
空き家よりも格段に利活用な困難なものが空き地です。一般的な不動産市場においては、建て替えを前提とした古家が残されている土地より、更地のほうが価格が高くなるものなのですが、価格が付かないような負動産が発生するエリアにおいては真逆の現象が起こります。
更地が都会ほど稀少ではなく、土地の値段がいくら安くても、新築工事の費用は都会も田舎もそれほど違いはないため、需要が限られているためです。
国庫帰属制度のデータから見る実態
法務省が公開している「相続土地国庫帰属制度の統計」によれば、2025年4月30日時点における、国庫帰属申請のあった土地の地目の種別について、1位は「田・畑」(農地)で38%ですが、2位は「宅地」の35%で、1位の農地と拮抗しています1。
宅地は固定資産税が掛かることが多いため所有者の負担感も強く、一方で需要もないために、特に交通不便なエリアに開発され、今なお空き地が数多く残るような住宅分譲地においては、更地の売買市場は事実上崩壊しています。分譲地、別荘地の空き地は0円物件の常連でもあります。
近隣住民による利活用
こうした宅地について、もっともよく見られるのは、隣地や近隣の住民が購入し、菜園用地や駐車場として利用するケースです。今ほど公共交通網が衰退していなかった1970年代、80年代頃に開発された分譲地は、敷地内に1台分の駐車スペースしか確保されていないことが多く、自家用車による移動が前提となった現在では不充分のため、敷地外で2台目以降の駐車スペースを確保しています。
ただし、そのすべてが土地所有者から正式に購入して行われているわけではなく、所有者に連絡が取れない放棄地の草刈りを行う傍ら、駐車場や菜園として無断で使用しているというケースも少なからずあります。
駐車場や菜園のニーズがあるからと言って、直ちに月極駐車場や貸農園での収益が望めるとは限りません(むしろ望めないと考えた方が良いと思います)。
ソーラー用地ブーム
10年ほど前まではこうした住宅地内の空き地も太陽光発電のソーラーパネル用地としてよく取引されましたが、買取価格が下がった現在では、このような小規模なソーラー発電施設が新設されることはほぼなくなりました。
ほとんどの空き地が、十分に活用されることもなく長期間売りに出されたまま、あるいは管理もされず雑草や雑木が生え放題で放��置されているというのが現状ですが、まれにそうした空き地の所有者が変わって新たに生まれ変わるケースも目にします。
よく見るのは車両置き場やガレージとしての利用です。車両置き場は、正直、廃車同然の車が雑然と並べられているだけというケースもあり、このような使い方では景観も悪くなるので一概に良い活用方法とも言えないのですが、立派なシャッターガレージを建てて、趣味の車を保管して、休日になるとそのガレージで愛車を整備している模様を見かけることがあります。
また、トレーラーハウスを設置して利用されるようになった空き地もありますが、しかしトレーラーハウスは高額であり、変な話、周辺で売られている中古住宅よりよほど高価なものもあるので、こちらは本当に趣味の領域といった用途です。
セルフビルド小屋
同じく趣味の延長上にある利用方法に、セルフビルドで小屋を建てて利用する、というものもあります。こちらも、実際に小屋を何かに使用するためというよりは、セルフビルドそのものに強い魅力を感じて挑戦している人が多いという印象です。
変わり種としては、バスケットコートが造られた例がありました。私はそのコートの所有者の方と直接お話ししたことはないのですが、近隣の方によれば、近くに別荘を持っている東京在住の方が、たまの休日にそのコートで息子さんとバスケの練習をしている、とのことでした。
古くなったテニスコートの利活用
空き地の活用という視点とは少し異なりますが、高度成長期に全国各地で造られた別荘地は、往時のテニスブームを反映して、専用のテニ��スコートが備えられているところが多数あります。ところがその後のテニスブームの終焉、別荘利用者の高齢化に伴い、管理が行われず荒れたコートが目立つようになりました。
そうしたテニスコートが近年、近隣定住者のドッグランスペースとして利用されたり、管理組合の主導でRVパークとして再利用されるケースがあります。RVパークは住宅地内の空き地の活用方法としては不適切ですが、ドッグランであれば、あるいは住宅地内の空き地の活用手段のひとつとして良いかもしれません。初期投資もそれほどかからないと思います。
しかしこれら空き地の利用方法はいずれも、拠点となりうる住戸が近隣にあって初めて十分に活用できる副次的な施設です。その地域にまったく縁がない人からの需要を掘り起こすことができるほどの活用手段とは言えず、ターゲットはどうしても近隣在住者、あるいは近隣に別荘を持つようなリピーターに限られます。
山林の「キャンプ用地化」は現実的?
そもそも「負動産」の発生条件のひとつが「事業者が商機を見出すことができない物件」である以上、これは仕方ない話でもあります。活用はあくまで個人レベルの趣味の範囲にとどまっているという印象です。
また余談になりますが、少し前のキャンプブームの際、住宅地の空き地ではなく、人の手がほとんど入っていないような山林が、プライベート用途の「キャンプ用地」として売りに出されているのをたまに見かけたのですが、事業用の大規模なキャンプ場が開設された例は別として、私はこれまで、山林の一角が、個人的なキャンプ用地として活用された事例を見たことがありません。
数メートルにも及ぶ立木が隙間なく並ぶ山林の整備・伐採は素人には極めて困難かつ危険であり、「キャンプ」を山林の現実的な活用方法として提案するのは無理があるでしょう。
マンション
最後にマンションですが、これは空き家、空き地とは比較にならないほど利活用が困難なものです。
マンションが「負動産」と化する背景
需要が高い都市部のマンションであれば、その価格に満足できるかは別として、売買、賃貸ともにそれほど処置が困難になるケースは多くありません。
しかし、人口減に見舞われている小都市の古いマンションや、リゾートマンションなどにおいては、所有するだけでコストが掛かり、賃貸需要もなく、買い手もつかない、しかし活用するにしても、集合住宅という構造上の制約や各マンションの管理規約などもあって好き勝手な利用方法もできない、八方ふさがりの状態にあるマンションも少なからず存在します。
管理費滞納部屋の競売取得とゲストルーム化
筆者がこれまで見聞きしたものでは、リゾートマンションにおいて、管理費を滞納して競売に掛けられた部屋を管理組合名義で取得し、マンション利用者が知人友人を招く際に安価で利用できる「ゲストルーム」として再生した事例があります。
商売としては採算の合うものではありませんが、マンション利用者の満足度を高めるために造られた新しい共有設備です。しかしこれも、利用者の多くがレジャー目的で訪れるリゾートマンションだからこそ成り立つものであって、一般の居住用マンションで広く採用されるような活用方法ではありません。
空き家、空き地と比較すれば、マンションの「負動産」は数としてそれほど事例が多くないので広く語られる機会はまだ少ないですが、居住空間としての用途に特化している分、その他の転用方法が難しくなっているマンションの「負動産」の問題は、今後静かに広がっていくかもしれません。
負動産利活用の実態
すべての負動産の利活用に共通して言えることは、個人レベルの利活用にとどまる範囲での活用以外は難しく、例えば負動産に多額の費用を投じて、ビジネスモデルとして通用する収益物件に変貌させた事例はほとんど見られないこと、そもそもその商機が失われているからこその「負動産」であって、大きなビジネスチャンスを求めるのは禁物であるという点です。
ビジネスチャンスどころか、例えばその負動産の売却価格を高くしようと、費用を投じて改修・整備したところで、儲けが出るどころかその費用を回収できるかどうかも怪しい、というレベルの物件が大半だと思います。
筆者は個人的には、採算面をあまり気にせず、趣味の範囲での活用にとどめるのが無難であると考えています。