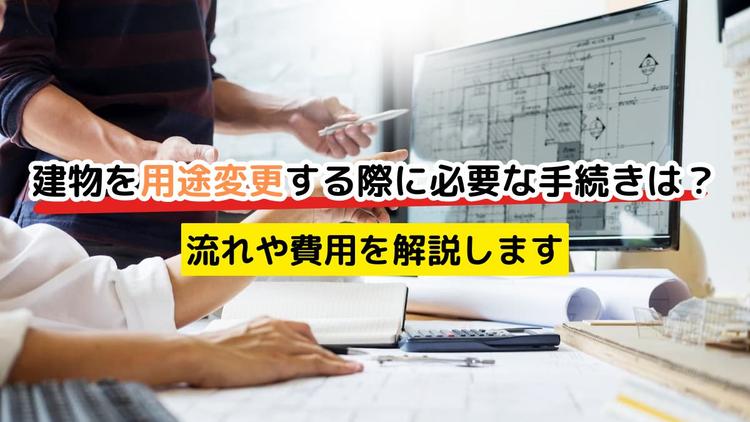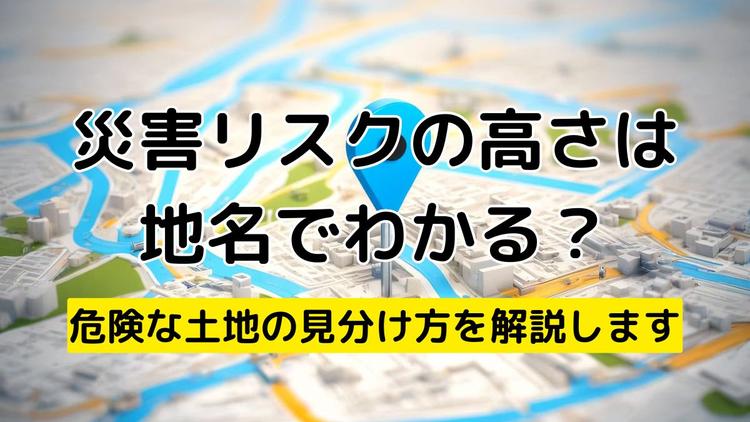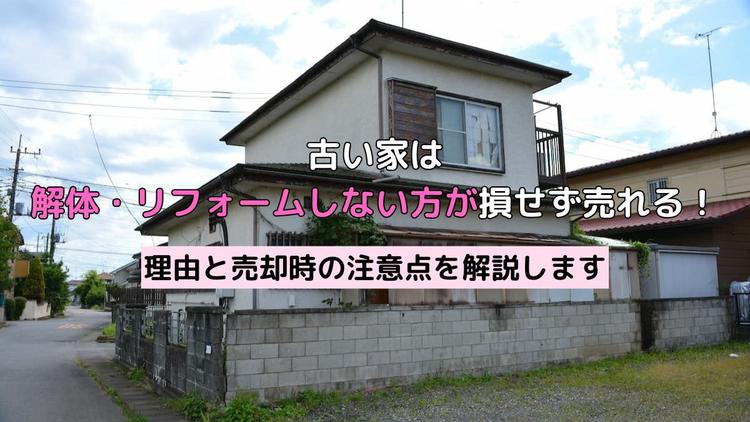建物の用途変更は、不動産を有効活用する上で重要な選択肢のひとつです。
しかし、用途変更には建築基準法などの規制が伴い、適切な手続きを踏む必要があります。
この記事では、建物の用途変更に必要な手続き、流れ、費用について解説します。
用途変更とは
用途変更とは、既存の建物を構造的に変更することなく、特殊建築物の用途に変更することを指します。
単に内装を変更するだけでなく、建物の使用目的そのものを変える行為です。
たとえば、次のような行為が用途変更に該当します。
- 住宅を飲食店に変更する
- 倉庫を展示場に変更する
- 工場を物販店舗に変更する
用途変更は、必ずしも工事が伴うわけではありません。内装工事を一切することなく、家具の搬入などのみで特殊建築物の用途に変更する場合も用途変更になります。
建築確認申請が必要な用途変更とは
用途変更は、変更する用途や規模によって、手続きの要否が決まります。
ここでは、建築確認申請が必要となる用途変更の要件を押えていきましょう。
特殊建築物への用途変更が対象
用途変更の建築確認申請は、特殊建築物に用途を変更する場合に必要になります。
特殊建築物とは、不特定多数の人が利用する建物や、火災発生時に避難が困難となる建物など、特に安全性を確保する必要がある建物を指します。建築基準法では、次の用途を特殊建築物としています。
- 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
- 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等
- 学校、体�育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
- 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗(床面積が十平方メートル以内のものを除く)
- 倉庫
- 自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ
事務所は、広く利用される用途ですが、用途変更をしても建築確認申請は不要です。また工場も対象となるのは、自動車修理工場のみであり、その他の工場は建築確認申請は不要です。
なお、「児童福祉施設等」の中には、助産所、身体障害者社会参加支援施設、保護施設、女性自立支援施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業などが含まれます。
200平方メートル超が対象
特殊建築物へ用途変更する場合、その面積が200平方メートルを超えると、建築確認申請が必要となります。
この200平方メートル超の判断は、ひとつの建物内で行います。
たとえば、商業ビル内の100平方メートルの事務所を飲食店に用途変更する場合で考えてみましょう。
同じビル内ですでに150平方メートルの用途変更をしている区画があれば、合わせて200平方メートルを超えるため、飲食店の用途変更にも建築確認申請が必要となります。
ただし、過去の用途変更を合算するかどうかの判断は、自治体によって異なるため、事前に窓口で相談し、その後の、手続きを進めてください。
類似間の用途は手続き不要
建築基準法で同じグループに属する用途変更は、類似間の用途として、建築確認申請は不要です(建築基準法施行令137条の18)。次に示す番号内であれば、類似間の用途変更になります。
たとえば、④に属する500平方メートルの旅館をホテルに用途変更する場合、建築確認申請は不要です。ただし、③⑥⑦のグループは、付則説明にあるように、一部用途地域において建築確認申請が必要な場合があります。
- 劇場、映画館、演芸場
- 公会堂、集会場
- 診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等……第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域内にある場合を除く
- ホテル、旅館
- 下宿、寄宿舎
- 博物館、美術館、図書館……第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域内にある場合を除く
- 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場……第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、工業専用地域内にある場合を除く
- 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗
- キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー……カフェーは風俗営業の業態を指します。一般的に利用されているカフェは、飲食店に分類されます。
- 待合、料理店……いずれも風俗営業の業態を指します。一般的な料理店は、飲食店に分類されます。
- 映画スタジオ、テレビスタジオ
用途地域の用途制限への適合が求められる
用途変更は、自分のやりたい業種に自由に変更できるわけではありません。建築基準法による用途地域の制限や、他の法令に基づく営業許可、建物の構造や規模など、様々な規制を受けるのです。
用途地域は全部で13種類あり、それぞれの地域で建築できる建物の高さや用途が定められている。
変更後の用途や規模によっては、建築確認申請が必要となり、建物の安全性や防災性能を確保しなければなりません。
用途変更は、不動産の可能性を広げる有効な手段ですが、都市計画法で定められた用途地域により、利用できる建物の用途には制限があります。
そのため、法令遵守と安全性を考慮した上で、慎重な検討が求められるのです。
たとえば、第一種住居専用地域では、専用の店舗や事務所などへの用途変更は認められていません。これを無視して用途変更を強行した場合、建築基準法違反として是正命令や使用禁止命令が出されることがあります。
用途変更の手続きの流れ
建物の用途変更は、法令遵守と安全性を確保するために、適切な手順を踏む必要があります。ここでは、用途変更手続きの一般的な流れを解説します。
事前相談・情報収集
用途変更を行う際は、建築士などの専門家に法規制や手続きについて確認してください。
この際、用途変更を行う建物の建築確認済証、検査済証、およびその建物の図面一式を収集して提示すると、スムーズにアドバイスを得ることができます。
なお、用途変更に関する工事が内装のみのリフォームの場合、建築確認申請が必要なケースでも、建築士の資格は不要です。しかし、建築確認申請が不要だと説明を受けた場合でも、念のため自らその真偽を確認した方が安心でしょう。
計画・設計
変更後の用途、建物の改修内容、必要な設備などを計画します。内装工事のみの場合は、建築士の資格を有していなくて設計することは可能です。
ただし、建築基準法や消防法などの関係法令に適合性が不安な場合は、建築士に依頼した方が安心です。
建築確認申請
建築確認申請書を作成して、自治体の建築審査課、あるいは民間の指定確認検査機関に申請書類を提出します。
審査を通過すると、建築確認済証が交付されます。
工事・完了
建築確認済証の内容に基づいて、適切な工事を進めます。
工事が完成したら、4日以内に自治体の建築主事に工事完了届を提出します。ただし、新築工事の完成後に提出する完了検査申請書ではない点に注意してください。
民間の指定確認検査機関で建築確認済証を交付された場合でも、工事完了届は自治体の建築主事に提出する必要があります。
なお、用途変更の場合、完了検査は実施されないため、検査済証の交付はありません。
用途変更にかかる費用
建物の用途変更には、様々な費用が発生します。これらの費用は、建物の規模、構造、変更後の用途、地域などによって大きく変動するため、事前に詳細な見積りと資金計画が必要です。ここでは、用途変更にかかる主な費用項目と、それぞれの費用相場について解説します。
設計・監理費用
用途変更に必要な設計図の作成や、工事監理を建築士事務所に依頼した場合、一般的な相場としては、工事費の10~20%程度が相場とされています。
ただし、建物の規模や構造、設計の複雑さによって費用が大きく異なります。
建築確認申請�手数料
用途変更の申請手数料は、建築確認申請を提出する自治体や指定確認検査機関ごとに異なります。仮に、200平方メートルから1,000平方メートルの規模の用途変更だとすると、相場は大体6万~10万円です。
ただし、建物の一部を用途変更する場合、用途変更を行う面積に加えて、申請対象外の部分の床面積の1/2を加算した面積が手数料算定面積となる機関もあるので、注意が必要です。
工事費用
建物の用途変更には、建築基準法などの法令上の制限や建物の構造、設備の制約など、さまざまな要因が絡み合うため、工事費は一概に算出できません。
まったく工事費が必要のない用途変更もありますが、一般的な目安としては、次のようになります。
- 小規模な用途変更: 数十万円〜数百万円
- 中規模な用途変更: 数百万円〜数千万円
- 大規模な用途変更: 数千万円〜数億円
用途変更の工事費を抑えるためには、既存の建物を有効活用することが重要です。
また、複数の施工会社から見積もりを取り、比較検討することで、適正な料金で工事を進めることができます。
用途変更での注意点
建物の用途変更は、所有者にとって大きな転換点となり得るものです。しかし、トラブルなく進めるためには、いくつかの注意すべき事項があります。
違法な用途変更のリスク
用途変更は、工事を伴わないことが多いため、必要な手続きや法規制を十分に調査しないまま実行してしまうことがあります。
200平方メートルを超える用途変更には建築確認申請が必要ですが、それ以下の規模でも、指定された��用途地域に適合する用途にしか変更できません。
たとえば、一種低層住居専用地域に建つ空き家住宅を、会社の事務所や倉庫として使うことはできません。
用途地域に適合しない用途変更を行った場合、建築基準法違反となり、工事の中止や建物の使用禁止、罰金などの罰則が科せられる可能性があります。
3階以上に位置する階の用途変更は要注意
3階以上の階に特殊建築物の用途がある場合、より厳しい耐火性能が求められる場合があります。
用途変更によって、建物が特殊建築物になる場合、建物の耐火性能が基準を満たさなくなる可能性があるため、事前に専門家による判断が必要です。
建物に検査済証があるか
基本的に、検査済証がない建物は、用途変更のための建築確認申請をすることができません。もし検査済証を紛失した場合は、管轄の自治体で検査済証明書を取得することで解決できます。
ただし、そもそも検査自体を受けていない場合は、指定確認検査機関に建築基準法適合状況調査を依頼し、その建物が建築基準法に適合していることを証明してもらう必要があります。
参考:「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」
消防法やその他法令にも注意
建築基準法以外にも、消防法や都市計画法、各自治体の条例など、様々な法令によって用途変更が規制される場合があります。
たとえば、飲食店の場合は食品衛生法に基づく営業許可が、ホテルの�場合は旅館業法による営業許可か必要です。これらの手続きを代理申請する場合は、行政書士に依頼します。
必要書類をそろえる
用途変更で建築士に設計を依頼する場合は、次の書類があればスムーズに設計を進めることができます。
- 建築図
- 設備図
- 構造図
- 建築確認済証
- 検査済証
特に、飲食店に用途変更をする場合は、食品衛生法に基づき、衛生的な食品提供と食中毒予防のために、給排水の規定が厳格に定められています。そのため、設備図の存在が非常に重要になります。
まとめ
建物の用途変更は、所有する不動産を有効活用し、新たな収益源を生み出すための有効な手段です。しかし、用途変更は建築基準法や消防法などの複雑な規制を遵守する必要があり、手続きも煩雑になりがちです。
用途変更を検討する際は、次のポイントを参考に、慎重な計画と準備を進めてください。
- 特殊建築物への用途変更で、200平方メートルを超える場合は建築確認申請が必要です。
- 類似用途間の変更は、原則として建築確認申請は不要です。
- 建築確認申請が不要な場合であっても、用途地域による用途制限にも注意が必要です。
手続きの流れは、事前相談・情報収集、計画・設計、建築確認申請、工事・完了の順で進めます。完了時には、工事完了届の提出が必要です。ただし、完了検査はなく、検査済証も交付されません。
費用は、設計・監理費用、建築確認申請手数料、工事費用などがかかり、建物の規模や用途によって大きく変動します。
用途変更は、工事が不要な場合や、簡易�な内装工事のみで完了する場合もあります。その際は、建築士の資格のない、内装専門の施工会社主体で工事を進めることも可能です。
しかしその一方で、専門的な知識と経験が求められる分野であることを念頭に置く必要があります。適法に用途変更を進めるためには、建築士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。