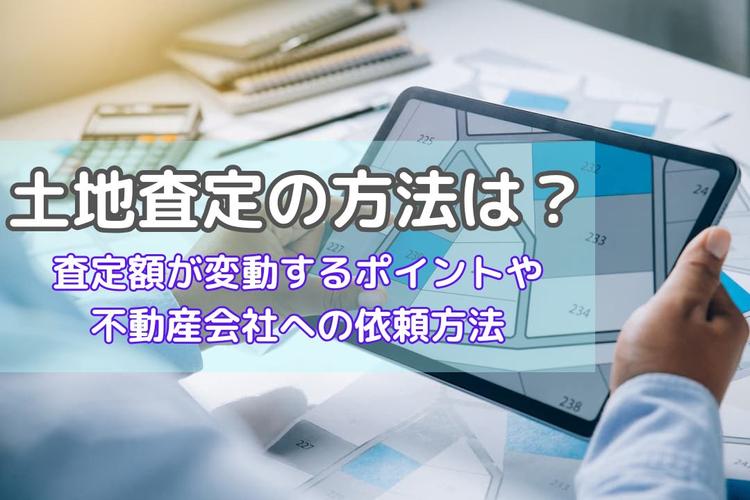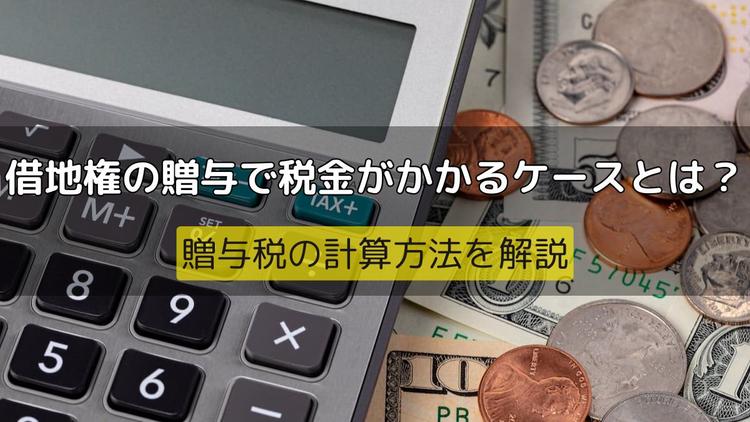土地の境界線を確定させる測量を「確定測量」といいます。
確定測量すれば境界は明確になりますが、登記までしないとトラブルになる恐れがあります。
この記事では、確定測量の基本や、登記しないことでおきるトラブル、確定測量が必要なケース・不要なケースまで分かりやすく解説します。
確定測量とは
確定測量とは、測量士が土地の正確な面積を測るとともに、境界を確定させる作業のことです。
測量時には隣地の所有者にも立ち会ってもらい、承諾を得たうえで境界線を確定させます。
確定測量後には、確定測量図または確定実測図という測量図面と、境界確認書などの書類が作成されます。
境界確定測量と現況測量
不動産の測量には「境界確定測量」と「現況測量」があり、それぞれ目的や調査内容が異なります。
境界確定測量とは
境界確定測量は、境界線を確定させることを目的とした測量です。
その土地の所有者だけでなく隣地の所有者も立ち合い、合意のうえで境界線を明確にします。
現況測量とは
現況測量とは、土地の面積や構築物の状況を把握するための測量です。
設置されている境界標やブロック塀などの構築物を参考に、測量士の目視で測ります。
新築前に土地の状況を把握するために利用されるのが一般的です。
確定測量との大きな違いが、現況測量では境界を確定しない点にあります。
確定測量は隣地の所有者に承諾を得て境界線を確定しますが、現況測量はそもそも境界確定を目的としておらず、測量作業に隣地の所有者は立ち合いません。
大まかな土地の面積や状況を知りたいというケースでは現況測量でよいでしょう。
一方で、売却前に明確に境界線を確定させたいというケースでは確定測量が必要です。
境界確定が取引の条件となっているケースが多い
不動産売却時には、売主が買主に対して境界線を明確に示す「境界明示」が義務付けられています。
境界線の明示方法としては、測量図や境界標を使う方法がありますが、確定測量図を使用するとトラブルを避けやすくなります。
境界が未確定でも売却自体は可能ですが、未確定の境界がある土地はトラブルが起きやすく、買い手から避けられがちです。
そのため、境界が未確定な土地の場合は引き渡しまでに境界確定が条件となっているケースが一般的でしょう。
また、不動産会社は境界が未確定な土地を取り扱わない場�合も多いので、未確定の場合は境界確定が必須となってくるのです。
確定測量後に登記することで誰でも法務局で取得できるようになる
確定測量後に登記まですることで、法務局に地積測量図が備えられるようになります。
地積測量図とは、土地の面積や形状・境界線を示した公的な図面です。
確定測量図と地積測量図は記載内容がほぼ同じですが、入手できる人が異なります。
地積測量図は法務局に申請すれば誰でも入手できる書類です。
一方、確定測量図は土地の所有者が保有しているもので、所有者が紛失すると再度作成が必要となります。
確定測量図の紛失リスクを避けたい場合は、登記までしておくほうがよいでしょう。
また、登記簿上の地積と確定測量した地積が異なる場合は、地積更正登記が必要です。
確定測量したのに登記しないとどうなる?
確定測量後に登記しないと以下のようなトラブルに発展する恐れがあります。
- 取引後にトラブルになる可能性がある
- 第三者に権利を主張できない可能性がある
それぞれ見ていきましょう。
取引後にトラブルになる可能性がある
確定測量を行うことで境界が明確になり、売却後の境界トラブルを避けやすくなります。
しかし、確定測量図は土地の所有者のみが所有するため、紛失のリスクがあるものです。
また、登記簿上の面積と確定測量の結果が異なる場合、登記の地積が修正されていなければ、取引後に面積の違いなどでトラブルになる恐れがあります。
第三者に権利を主張できない可能性がある
登記することで、土地の権利を第三者に公的に主張できます。
一方、登記簿上と実際の地積が異なる場合、登記をしていなければ正式な地積についての権利主張はできません。
地積に関するトラブルが発生した場合、不利な立場になりかねないので注意しましょう。
また、測量の専門家��には測量士と土地家屋調査士がいますが、登記業務ができるのは土地家屋調査士です。
登記手続きまで検討している場合は、土地家屋調査士に依頼するようにしましょう。
境界を確定しないと起こりうるトラブル
登記する・しない以前に、境界が確定しない状態が一番トラブルになりやすいものです。
ここでは、境界を確定しないと起こりうるトラブルを「売却」「相続」「隣地所有者とのトラブル」の3つに分けて解説します。
売却に関するトラブル
境界が未確定な土地を売却する際に起こりうるトラブルとしては、以下が考えられます。
- 契約不適合責任を問われる
- 買主が住宅ローンを組めない
- 分筆できずに売却しにくくなる
境界が未確定でも買主の合意があれば売却できます。
しかし、買主に未確定であることを告げずに売却すると、契約不適合責任を問われる恐れがあるでしょう。
購入後に、契約書に記載されている地積と実際の地積が異なることが判明した場合でも、契約不適合責任に問われる恐れがあるので注意が必要です。
契約不適合責任が問われると、補修費や代金減額を請求されるだけでなく、損害賠償請求・契約解除のリスクもあり、売主の大きな負担となりかねません。
また、境界未確定の不動産は金融機関の担保評価が下がりやすく、買主が住宅ローンを組めない恐れもあります。
そのため、買主の資金面の都合で避けられやすくなる点にも注意しなければなりません。
なお、広すぎる土地は需要が下がるため、売りやすい面積に分筆して売却するケースが多いですが、確定測量していないと分筆できないケースもあるので注意しましょう。
相続に関するトラブル
境界未確定の土地を相続すると以下のようなトラブルになる恐れがあります。
- 相続人で分筆しようとしてもできない
- 相続後に売却しようとしても売れない
- 相続税の物納ができない
- 相続後に近隣所有者とトラブルになる
土地を相続する場合、相続人で共有せずに分筆してそれぞれ相続することで、所有権に関するトラブルが起きにくくなります。
しかし、境界線が未確定の土地は分筆できない場合があり、その結果、相続時の分割がスムーズに進まないことがあります。
また、売却金を相続人で分割する際や、相続人が土地を売却する際にも、未確定であることから売却しにくくなる恐れもあります。
相続財産のうち不動産がほとんどを占めている場合、相続税が発生すると、相続人が現金を用意できないことがあります。
その場合、不動産や株式など現金以外の財産を利用した物納が可能ですが、境界確定していない不動産は物納の対象にはなりません。そのため、自己資金などで相続税に対応する必要があります。
さらに、被相続人(亡くなった人)が生前中に隣地所有者とトラブルを起こしていなくても、相続後に所有者が変わることで隣地所有者とトラブルになるケースもあります。
隣地所有者とのトラブル
境界未確定では、隣地所有者とのトラブルに発展しやすいものです。
隣地所有者とのトラブルとしては、以下のようなケースがあります。
- 境界を巡って双方の意見が対立する
- 隣地の植栽が越境している
- 構築物の越境トラブルになる
- 確定境界に立ち会ってもらえない
- 隣地の所有者が所在不明・死亡している
敷地の利用を巡ってトラブルになった場合、境界が確定していなければ、どちらが正しいかの判断がつかず、トラブルがさらに大きくなる可能性があります。
隣地所有者との関係性が悪くなると、毎日の生活にもストレスを感じる恐れがあるでしょう。
また、関係性が悪いと確定測量しようとしても立ち合いを拒否され、確定できなくなる可能性もあるのです。
さらに、隣地の所有者が死亡している、行方不明になっているなど、立ち合いができない場合もあるので注意しましょう。
もし隣地所有者から立ち合いを拒否されたり、所有者が不明な場合は、法務局に境界線を確定してもらう「筆界特定制度」を利用することができます。
ただし、筆界特定制度では境界確定までに約半年ほどの時間がかかるのため、売却などで早急に境界�確定が必要な場合は、早めに手続きするようにしましょう。
▼関連記事:隣地所有者に確定測量の立会を拒否された場合の対応
確定測量が必要なケース
確定測量は現況測量よりも時間と費用がかかります。
確定測量が不要な場合もあるので、必要なケース・不要なケースを理解しておくことが大切です。
ここでは、確定測量が必要な2つのケースを解説します。
境界が一部不明なケース
境界の一部でも不明瞭な部分があるなら、境界確定をおすすめします。
境界に未確定な部分があると、前述のような売却、相続時のトラブルに発展しやすくなります。
とくに売却を検討する場合は、未確定では売りにくく価格も下がりやすいため、確定測量で境界線を確定させることが大切です。
また、土地の売買では境界に関して「実測売買」と「公簿売買(登記簿売買)」の2つの方法があります。
実測売買は測量で面積を確定し、その面積に応じて金額が変動する方法です。
一方、公簿売買は登記簿上の面積を基準として売却額が決まる方法です。
実測売買では現況測量でも構いませんが、境界確定されないため誤差が生じる恐れがあります。
公簿売買は、実際の土地と公簿に記載された面積に誤差が生じるリスクが高いので、購入後にトラブルになる恐れがあるでしょう。
どちらの売買方法であっても、確定測量しておくことでトラブルのリスクを避けやすくなります。
前回の測量から年月が経っているケース
確定測量し境界線が明確になっている場合でも、前回の測量からかなり年数がたっているなら測量し直したほうがよいでしょう。
一度確定した境界も、災害で地形が変わっているなどで不明瞭になるケースがあります。
また、境界標が経年で破損している、地中に埋まっている、境界標の上にブロック塀を立ててしまったといったケースでも、境界を確定し新たに境界標を設ける必要があります。
▼関連記事:不動産売買時の測量の義務について
確定測量なしでもよいケース
一方、以下のようなケースでは確定測量が必ずしも必要にはなりません。
境界が明確になっているケース
境界が明確になっているなら確定測量は必要ありません。
法務局で地積測量図を取得すれば境界線を確認できます。
相続するだけのケース
相続し売却、分筆、物納を検討する際には確定測量が必要ですが、相続するだけなら確定測量は不要です。
とくに土地が広大になると測量費用も高額になってくるので、費用的な負担が大きくなってしまうでしょう。
ただし、隣地の所有者とトラブルの恐�れがある、いずれ売却の予定があるなら早い段階で確定測量を検討することが大切です。
所有土地の上に建物を建てるケース
すでに持っている自身の土地に建物を建てるケースでも確定測量は不要です。
建物を建てる際に土地の情報提示が必要になる場合がありますが、その際は現況測量を行うことになります。
売買で取引の相手方が納得しているケース
確定測量には隣地所有者の立ち合いが必要になり、通常3ヵ月程度かかります。
隣地所有者が自治体の場合は、さらに時間がかかることが多いため注意が必要です。
売却を急いでいる場合でも、境界確定に時間がかかる場合は、売主が境界未確定であることに合意していれば売却できます。
とはいえ、境界未確定の土地は買主から避けられやすいため、基本的には早めに境界確定しておくことをおすすめします。
また、売買契約後、引き渡しまでに確定測量を行うケースもありますが、引き渡しまでに測量が間に合わない場合や、測量後に契約書と地積が変わる場合があるため、注意が必要です。
基本的には、売り出し前に確定測量を済ませておく方が望ましいので、測量を含めた売却スケジュールを立てるようにしましょう。
まとめ
境界があいまいな土地は、トラブルの懸念から買主に避けられやすくなります。
また、境界未確定は売却時だけでなく、相続トラブルや隣地所有者とのトラブルにも発展しかねません。
境界のトラブル��を避けるためには、確定測量し境界を明確にしておくことが大切です。
また、確定測量後は登記までしておくことで、よりトラブル防止につながりやすくなります。
売却を検討する際には、分譲地など直近で境界が明確になっているケースを除いては、基本的には境界確定が必要になってきます。
確定測定が必要になると3ヵ月ほど時間がかかるので、測量期間も含めて余裕を持った売却スケジュールを立てることが重要です。