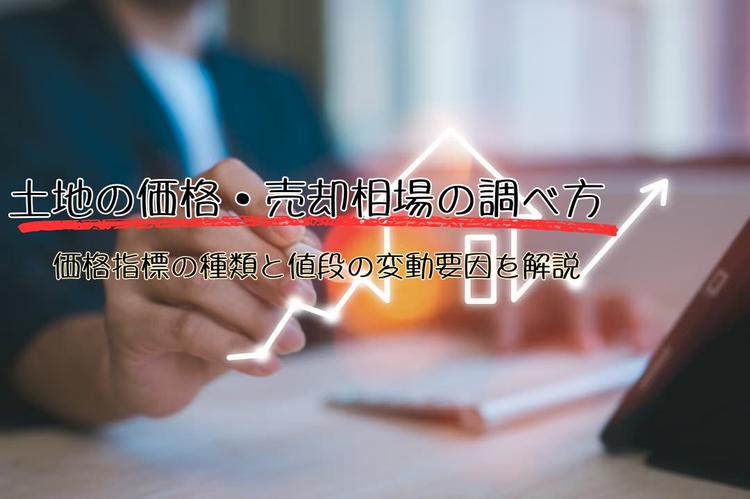「重要土地調査法」は、2022年に新たに施行された法律です。不動産の重要事項説明にも、この法律に基づき、対象の土地や建物が制限を受けるかどうかの記載が追加されました。
不動産の売買にも影響を及ぼす重要土地等調査法とはどのような法律なのでしょうか。
重要土地調査法に関して、不動産の売買時への影響や確認すべきポイントを解説します。
重要土地等調査法の概要
重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)は、2022年9月20日に施行された法律です。
日本の安全保障に関わる土地の利用状況を把握し、有事の際に国の防衛に支障をきたすような事態を防ぐことを目的としています。
不動産売買との関わりを知るために、まず重要土地等調査法の概要を押えておきましょう。
制定の背景
重要土地等調査法は、日本の安全保障に関わる重要な土地の利用状況を調査し、必要に応じて規制を行うための法律です。
近年、防衛施設周辺や国境離島などの土地が、外国資本によって取得される事例が増加しています。
これらの土地が安全保障上の脅威となる可能性が指摘され、政府は対策を講じる必要性に迫られました。
法律の目的
重要土地等調査法は、以下の2つを主な目的としています。
- 安全保障上重要な土地の利用状況を把握すること
- 安全保障上の問題がある場合には、土地の利用を規制すること
具体的には、防衛施設や原子力発電所、国境離島などの周辺区域が「注視区域」として指定され、必要に応じて調査が行われます。特に重要な区域は「特別注視区域」に指定され、より詳細な調査や規制が行えるようにしています。
「注視区域」と「特別注視区域」
重��要土地等調査法では、安全保障上重要な区域を「注視区域」に指定します。その中でも、機能面を重視した際に、機能の阻害が容易で代替が困難な区域を「特別注視区域」に指定します。
内閣府ホームページによると、令和4年12月から令和6年4月にかけて、4回の区域指定により、国境離島等及び重要施設(防衛関係施設、海上保安庁の施設、原子力関係施設、 空港)の周辺の計583カ所の区域(特別注視区域:148カ所、注視区域:435カ所)が指定されています。
それぞれどのような特徴がある区域なのか解説します。
「注視区域」とは
「注視区域」は、重要施設の敷地の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の土地や建物が機能阻害行為に供されることを防止するために指定することができます(法第5条第1項)。
注視区域内では、土地の所有者や利用状況、利用目的などが調査されます。
「特別注視区域」とは
「特別注視区域」は、注視区域に係る重要施設が特定重要施設である場合または注視区域に係る国境離島等が特定国境離島等である場合に指定する区域です(法第12条第1項)。
特別注視区域内にある一定面積以上の土地及び建物の所有権を移転する契約を締結する場合には、売主と買主は、法令に定められた事項を内閣総理大臣に届け出る必要があります(法第13条第1項及び第3項)。
特別注視区域内では、��注視区域よりも詳細な調査が行われます。たとえば、土地の利用履歴や取得経緯、資金の流れなどが調査されることがあります。
特定重要施設とは
特定重要施設とは、特に重要な施設であり、その周辺の土地利用が国の安全保障上重要な意味を持つものを指します。具体的には、以下の施設が該当します。
- 防衛関係施設……防衛省が管理する施設や、日米地位協定に基づき米軍が使用する施設などが含まれます。
- 海上保安庁の施設……巡視船の基地やレーダーサイトなど、領海警備や海上保安活動に関わる施設が対象となります。
- 生活関連施設……国民生活に不可欠な施設であり、その機能が阻害されると国民生活に重大な影響を及ぼすおそれがあるものが指定されます。発電所、変電所、ダム、空港、港湾、鉄道、道路、通信施設、放送施設、病院、政府機関の庁舎などが想定されています。
これらの施設のうち、特に重要なものが特定重要施設として指定されます。特定重要施設の指定は、内閣総理大臣が、関係行政機関の長と協議の上で行います。
調査の実施
内閣府は重要土地等調査法に基づき、指定された注視区域内の土地について調査を行います。
調査の際には、不動産登記簿、住民基本台帳、商業登記簿などの公的記録や、届出に関する情報、地図、航空写真、ウェブサイトなどの公開情報を活用します。
さらに、必要に応じて現地調査を行って実際の状況を確認します。
調査が行われるケース①
防衛施設や原子力発電所などの重要施設の周辺、国境離島等において、安全保障上の観点から特に��土地の利用状況を把握する必要がある場合に、注視区域または特別注視区域が指定されます。
これらの区域内にある土地については、利用状況の調査が行われることがあります。
調査が行われるケース②
個別の事案における調査として、注視区域・特別注視区域以外であっても、土地の利用状況が安全保障上の問題を引き起こす可能性があると判断された場合には、調査が行われることがあります。
調査の内容
調査では、主に以下の事項が確認されます。
- 土地の所有者・利用者……土地の所有者や利用者の情報、利用目的などが確認されます。
- 土地の利用状況:……土地の利用状況(建物が建っているか、耕作されているかなど)や、利用履歴などが確認されます。
- 周辺の状況……土地の周辺の状況(重要施設との位置関係、周辺の土地利用状況など)が確認されます。
重要土地等調査法に基づく調査は、日本の安全保障に関わる重要な情報を取り扱うため、調査対象となった場合には、誠実に対応しましょう。
調査の結果
調査の結果、土地の利用状況が安全保障上の問題を引き起こす可能性があると判断された場合には、土地の利用者に対して、利用状況の改善や利用制限などの措置が取られることがあります。
勧告と命令
注視区域や特別注視区域内にある土地の利用者が、その土地を機能阻害行為のために使用した場合、またはその明確なおそれがあると判断された場合は、土地等利用状況審議会の意見を聴きます。
そのうえで、土地等の利用者に対し、その土地を機能阻害行為のために使用��しないように勧告します。
勧告を受けた者が、正当な理由なく従わなかったときは、必要な措置をとるよう命令が出されます。
機能阻害行為とは
重要土地等調査法における機能阻害行為とは、重要施設や国境離島の機能を阻害する行為を指します。
具体的には、次のような行為です。
【重要施設】
- 妨害電波の発信
- 撮影禁止場所での撮影
- 立ち入り禁止場所への侵入
- 騒音の発生
- 多数の者の集団による示威活動
- 土地の不適切な利用 (例: 土砂崩壊や洪水など)
- 施設への爆発物等の持ち込み
- 施設の破壊
- 職員への暴行・脅迫
- 施設の機能や業務を妨害する行為
- その他、重要施設の正常な機能を阻害する行為
【国境離島】
- 漁業法等関係法令違反 (違法操業、密漁、領海侵犯等)
- 海上保安庁巡視船等への妨害行為
- 密入国・密輸出
- 薬物、武器等の持ち込み
- その他、国境離島の管理・保全を妨げる行為
機能阻害行為に該当するか否かは、個別に具体的な事情に応じて判断されます。
重要事項説明で確認すべきポイント
重要土地等調査法は、不動産の売買においても重要な影響を与えるため、特別注視区域にある土地は、宅地建物取引業法上の重要事項説明書に記載する必要があります(宅建業法法第35条第1項第2号、同施行令第3条第1項第63号)。
重要事項説明で確認すべきポイントとは何か解説をします。
重要事項説明の要点
重要土地等調査法に関して、重要事項として説明が必要なのは、次のような事項です。
- 特別注視区域の��位置……特別注視区域が指定されている位置について説明します。
- 届出対象となる土地・建物……特別注視区域内での届出対象となる土地や建物の情報を提供します。
- 届出対象となる取引……特別注視区域内での取引のうち、届出が必要なものについて説明します。
- 届出に関する手続き……契約締結前に内閣総理大臣に対して行う届出の手続きについて説明します。
- 罰則…… 届出を怠った場合の罰則について説明します。
土地等の取引の事前届出について
特別注視区域内で、土地や建物に関する所有権の移転や設定契約を結ぶ場合は、契約を締結する前に買主に対して、内閣府に届出することを説明する必要があります。
届出の対象となる土地・建物
特別注視区域内の延べ床面積が200平方メートル以上の土地および建物が対象です。
マンションの場合は、専有面積200平方メートル以上が対象になります。
届出の対象となる契約
売買・贈与・交換・形成権(買戻権、予約完結権)の契約をした場合が対象になります。
賃貸借契約や相続は対象外です。
届出の事項
届出には次の内容を記載します。
- 当事者の氏名、住所(法人の場合、代表者の氏名も必要)
- 土地などの所在地・面積
- 土地などに関する権利の種別および内容
- 土地などの利用目的
- 譲受け予定者の国籍など
- 土地などの利用の現況
- 契約予定日
届出の義務があるのは、契約当時者です。売買であれば、売主・買主双方が契約締結前に届け出る必要があります。
届出は、土地や建物の取引を制限するものではありません。期限内に届出を行うことで手続きは完了するので、契約に際して内閣府からの連絡や通知を待つ必要はないです。
ただし、届出をせずに対象となる土地・建物の売買契約などを締結した場合や虚偽の届出をした場合は、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される場合があります(同法第26条)。
オンラインによる届出
届出は郵送もしくはオンラインで行うことができます。届出様式の電子データや記載例などは内閣府のホームページからダウンロードが可能です。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、オンラインによる届出はできません。
- 売主と買主が連名で届出を行う場合
- 届出の対象となる土地または建物が共有の場合(売主または買主が複数の場合)
- 届出の対象となる土地または建物が複数の場合
- 届出の対象となる契約の当事者以外の者が届出を行う場合
この場合は、書面による提出となります。
不動産売買時に確認すべきポイント
重要土地等調査法は、日本の安全保障に関わる土地の利用状況を把握し、有事の際に国の防衛に支障をきたすような事態を防ぐことを目的とした法律です。
不動産の売買を行う際、注視区域や特別注視区域内の土地については、重要土地等調査法に基づく調査が行われる可能性があることを理解しておく必要があります。
売主の確認ポイント
売主は、契約前に次の情報を買主に説明します。
- 重要土地等調査法に基づく調査が行われる可能性があること
- 調査が行われた場合、協力する必要があること
- 特別注視区域内の200平方メートル以上の土地については届出の義務があること
宅建法上、売却する土地が特別注視区域にあるときは、法令名とその制限の概要を重要事項として説明しなければなりません。
その土地が注視区域内でも重要土地等調査法に基づく調査が行われる可能性があるため、調査に協力する義務や、調査結果によっては契約解除となる可能性があることを説明することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
買主の確認ポイント
買主は、購入しようとしている土地が、注視区域や特別注視区域内にあるか否かを確認してください。
該当する場合は、重要土地等調査法に基づく調査が行われる可能性があること、さらには調査が行われた場合、協力する必要があることを納得したうえで購入するようにしましょう。
まとめ
重要土地等調査法では、安全保障上重要な区域を「注視区域」に指定します。そのうち機能が特に重要で、機能阻害が容易であり代替が困難な区域を「特別注視区域」に指定します。
特別注視区域に指定された区域については、宅建業法により重要事項として法令名とその制限の概要を説明する必要があります。
注視区域や特別注視区域の土地の売主は、重要土地等調査法に基づく調査が行われる可能性があることを説明することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
買主は、重要土地等調査法に基づく調査が行われる可能性があることや、調査に協力する必要があることを納得したうえで購入してください。