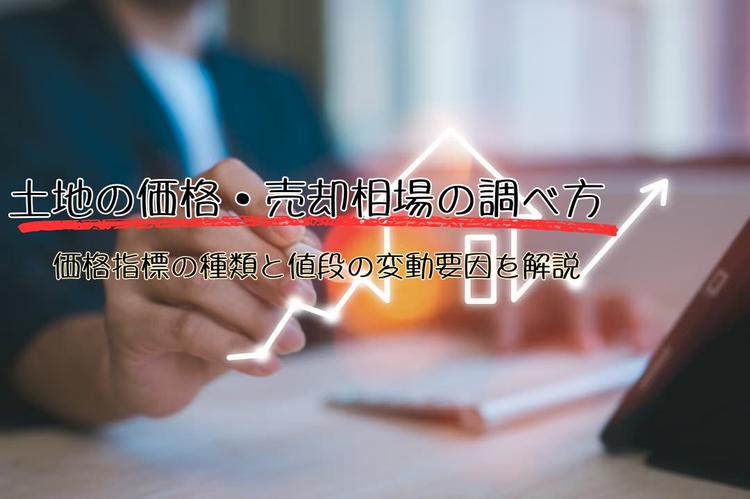土地の価格を調べた時に、公示価格や路線価など何種類かの価格指標の存在に気づいたことはありませんか。
また、昔調べた物件を改めて確認した時、価格が大きく変動していたという経験はないでしょうか。
土地の価格は様々な要因によって決まるため、適正な価格を見極めるのはとても難しいのです。
この記事では、土地の価格や売却相場の調べ方について説明をするとともに、価格指標の種類と値段の変動要因についても解説します。
土地には4種類の価格指標がある
不動産は「一物四価」といって、1つの不動産に対して、次の4種類の価格指標が存在します。
- 公示地価
- 実勢価格
- 固定資産税評価額
- 相続税路線価
4種類もの価格指標があるのは、国や地方自治体、売主、買主などがそれぞれ違った目的で評価をし、視点や基準が異なるためです。
それぞれどのような価格指標なのか解説していきましょう。
公示地価
公示地価とは、国土交通省が毎年1月1日時点の土地を算定した価格です。1地点につき、2人以上の不動産鑑定士が土地の鑑定を行い、評価額を出します。
公示地価は、土地の売買において、適正な土地価格を知るための指標となります。また、道路や河川など、公共事業の用地を取得する際の基準となる役割があります。
公示地価は標準地の価格なので、所有している不動産が基準地の近隣であっても、土地の形状や接道状況といった条件が異なれば価格も異なります。しかし、信憑性の高いデータであることから、比較対象として重要な参考価格です。
- 標準地:国土交通省が設定する地点で、公示地価を算定するための土地
- 基準地:都道府県が調査する土地価格で、主に都市部以外の地域や、国が指定しない地点の価格を補完する役割がある
「一物五価」と呼ばれることもある
不動産の価格指標は「一物四価」と呼ばれるのが一般的ですが、これに「地価調査」を加えて「一物五価」と呼ばれることがあります。地価調査は、国ではなく各都道府県が7月1日時点における基準地の1平方メートル当たりの価格を公表するものです。
基準地の一部は公示地価と同一地点で設定されているため、半年ごとの地価変動を把握することができます。このため、基準地価は公示地価の補完的役割があるとされています。
実勢価格
実勢価格とは、実際に土地が売買された際に取引された価格で「時価」ともいいます。その土地が売れた際の金額であり、売主と買主の合意により決まります。そのため、不動産広告に掲示されている価格とは異なります。
実勢価格は、土地の売買をする際の指標となる価格です。売りたい土地と似ている条件を持つ土地の過去の実勢価格を調べることで、参考値を知ることができるからです。
公示地価と違い公的機関が定めた価格ではなく、売主と買主の需要と供給の兼ね合いで価格が決まります。
売却したい土地に買い手が見つからなかったり、とにかく売却を急いでいたりするケースでは、売主が一般的な相場よりも価格を下げることがあります。反対に買主がすぐに住める家を探しているようなケースでは、相場よりも高い価格で購入することがあります。
売主と買主の事情によって価格が変動するため、絶対的な価格指標ではないことには配慮する必要があります。
固定資産税評価額
固定資産税評価額は、市区町村が固定資産税を算出するために、3年に一度、1月1日時点の土地価格を算定したものです。土地や家を所有した際に発生する、固定資産税の金額を決めるために用います。
固定資産税評価額は公示地価のおおむね70%で設定されていますが、正確な価格を知りたい場合は、固定資産税課税明細書や固定資産評価証明書で確認することができます。
相続税路線価
相続税路線価は、国税庁が毎年発表する土地の価格のことで、相続税や贈与税を計算する際の基準となります。路線(道路)に面している宅地1平方メートル当たりの価額をもとに算出されます。
相続税路線価は毎年更新され、宅地1平方メートル当たりの価額は、売買の実勢価格や公示地価、不動産鑑定士による鑑定評価額などをもとに、その年の1月1日時点の価格が発表されます。
また、固定資産税評価額も路線価を調べますが、こちらは市区町村の管轄のため、相続税路線価とは異なります。調査対象は主要な道路に面した土地なので、調査対象外の土地の路線価は発表されません。
土地価格の調べ方
土地の価格を知るために参考となる4種類の価格指標について、それぞれの調べ方を紹介します。いずれの価格もインターネットや自治体の窓口で確認することができます。
公示地価の調べ方
公示地価は国土交通省が運営するサイト「土地総合情報ライブラリー」で調べることができます。
該当ページを開いたら、目的の土地を地図または地域の名称で検索します。次に「価格情報」のタブから「国土交通省地価公示」をクリックすると、地図上に鑑定地点の1平方メートル当たりの公示地価が表示されます。
過去30年の公示地価も遡って調べることも可能です。
実勢価格の調べ方
土地の売買を目的として土地の値段を調べたい際は、実勢価格を参考にできます。実勢価格も国土交通省が運営するサイト「土地総合情報ライブラリー」で調べることができます。
ページ左下の「不動産価格の情報をご覧になりたい方へ」をクリックすると「データの検索・ダウンロード」が表示されます。ここをクリックして表示された画面に、調べたいエリアの住所を入力することで、過去の取引情報を知ることができます。
注意したいのは「不動産取引価格」は、実際に売買された価格をもとに作成されていますが、同じエリア内でも土地の条件によって価格が異なる点です。
取引価格を参考にする際は、取引時期が最近のもので、できる限り売りたい土地と条件の似ている物件を参考にしてください。
固定資産税評価額の調べ方
固定資産税評価額を土地価格の指標にしたい場合、固定資産税評価額を調べる方法は次のとおりです。
- 固定資産税納税通知書の確認
- 固定資産評価証明書の取得
- 固定資産課税台帳の閲覧
それぞれの方法を紹介します。
固定資産税納税通知書を確認する
固定資産税評価額を最も手軽に調べられるのは、固定資産税納税通知書を確認する方法です。固定資産税納税通知書は、所有する不動産に対してかかる固定資産税について納税を促す通知で、毎年5月頃に納税対象となる物件が所在している市区町村から通知書が送られてきます。
固定資産税評価額は、この通知書に添付されている課税明細書で確認できます。
固定資産評価証明書を取得する
固定資産税について、市区町村から送られてきた納付書だけを保管して、その根拠となる固定資産税納税通知書を廃棄してしまう方もいます。
通常の年であれば、納付書があればほとんど支障はありませんが、土地の価格を調べたい場合や相続登記の際は、固定資産税通知書が必要になります。
もし廃棄や紛失で固定資産税納税通知書が見当たらない場合は、固定資産評価証明書を入手して、評価額を調べることが可能です。
固定資産評価証明書を入手するには、固定資産の所在している市町村の役所へ出向き、申請書、運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類、申請手数料を提出します。
固定資産課税台帳を閲覧する
固定資産税評価額は、固定資産課税台帳を閲覧することで確認することができます。
固定資産課税台帳は、各市区町村長が作成したもので、評価額の根拠として使われる「固定資産評価基準」をもとに算出された固定資産をすべて登録しています。
台帳には固定資産の所有者・所在・価格が記載されているので、価格欄から評価額を知ることができます。
閲覧できるのは、その固定資産に課税される固定資産税の納税義務者、同居の家族、納税義務者からの委任を受けた代理人などで、各役所の開庁時に市町村の担当部署で閲覧することができます。
相続税路線価の調べ方
相続税や贈与税の元となる土地の価格を知りたい場合は、相続税路線価を調べます。相続税路線価は国税庁のサイト「路線価図・評価倍率表」で調べることができます。
「路線価図・評価倍率表」の地図上には、各路線に640B、100Eといった数字が記載されています。これはその路線沿いの1平方メートル当たりの価格を千円単位で示したものです。
たとえば、640Bと書いてあれば、その道路沿いの土地には、1平方メートル当たり64万円の路線価が設定されていることを示しています。
数字の後ろに書かれているアルファベットは借地権割合を示したもので、借地権価格の目安として用います。
借地権とは、その土地を利用できる権利のことで、借地権価格はその評価額のことです。さらに借地権割合は、その土地の更地評価額に対しての借地権価格の割合のことを言います。
- A:90%
- B:80%
- C:70%
- D:60%
- E:50%
- F:40%
- G:30%
これらの借地権割合は、その土地を借りる際の借地権の評価額を算定する際に使われます。
例えば、640Bと書かれている場合、その土地の更地評価額(64万円)に借地権割合80%を掛け合わせて、借地権価格(= 借地権の価値)を計算します。
- 路線価:640(= 64万円)
- 借地権割合:80%(Bの場合)
- 借地権価格:64万円 × 80% = 51万2000円
このようにして借地権価格の目安を知ることができるため、相続税や贈与税の計算において役立ちます。
売買では実勢価格を重視
価格指標について解説しましたが、実際の土地の売買で重視すべきは実勢価格です。
土地を売却する際、相場価格よりも高い設定をしていると、いつまでも売れないおそれがあります。だからといって、相場よりも大幅に安くすると、すぐに売れたとしても金銭的��な損失が生まれます。
土地売却で後悔しないためには、適正な価格で売出すことが重要です。
店舗で売られている商品の価格は、作るのにどれだけ費用がかかったか(費用性)、どの程度の価格で取引されるか(市場性)、どれほどの収益を生み出すか(収益性)で判定します。
土地の売却においても同じで、費用性、市場性、収益性で決まるのが一般的です。これに基づいた実勢価格を割り出すには、次の3つの計算方法があります。
- 取引事例比較法
- 収益還元法
- 原価法
それぞれの計算方法について解説していきましょう。
取引事例比較法
取引事例比較法とは、売却する不動産と同種、同等の土地における取引事例の価格から、補正をして、かつ個別の要因比較を加味しながら土地の価格を求める手法です。
そのため、近隣に類似した物件の取引があった場合に有効な評価手法となります。さらに多数の事例を収集することで、信憑性を高めることができます。
収益還元法
収益還元法は、土地から将来生み出すであろう収益価値を、適正な還元利回りで割り戻して価格を求める計算方法です。
収益還元法は、賃貸用不動産価格を用いる場合に有効です。算定式に表すと、次のようになります。
純収益とは、不動産で得られる家賃収入などの収益から、管理費や固定資産税などの費用を引いたものです。一方で還元利回りとは、不動産の収益性を表した利率です。
たとえば年間の純収益が300万円で還元利回りを5%とした場合、「300万円÷5%」の計算により6千万円になります。
一戸建て住宅においても、それを他人に貸した場合の収益用建物と想定することで、収益還元法を適用することができます。
原価法
「居住用の住宅」の場合、耐用年数は1.5倍にして計算されます(木造住宅の場合は33年)。
原価法は、費用性に着目した評価手法で、建物がある土地に用います。
対象の建物を建てる場合にかかる費用(再調達原価)から、築年数などに基づいた減価額を控除して、対象不動産の資産価格を求めます。
次の計算式によって求めます。
単価や耐用年数は主要構造によって決まっています。
再調達原価は、建物の積算(見積り)をする手法で求めます。土地所有者がその土地に住宅を建てた場合に支払われる標準的な建築代金がこれに相当します。
一戸建ての価格を求める場合には、土地は取引事例比較法を適用し、建物は原価法を適用して、それぞれの価格を算出して合算することで割り出すことができます。
土地価格が上昇する要因とは
不動産価格は、経済的要因や社会的要因の影響を受けて変動することがあります。日本ばかりでなく海外の経済情勢の影響を受けることもあるのです。土地価格は、どのような要因によって上昇するのか解説していきましょう。
資材、人材不足の影響
2011年3月に東日本で大規模な地震が発生しました。この震災によって、多くの建物が倒壊し、未曾有の被害を与えました。この災害は、直接被害を受けた東北地方だけでなく、全国規模で不動産市場への影響を与えたのです。
被災地の復興支援のために、全国各地から建築資材と人材が集中しました。そのため、被災��地以外のエリアにおいて、建築資材不足と人材不足が深刻化したのです。これにより、建築資材の価格や人件費が高騰し、不動産価格の上昇へと繋がりました。
自然災害だけでなく、オリンピックや万博といった大きなイベントが開催される前の時期は、建築資材や人材がイベント会場の建築現場に集中するため、不動産価格が上昇することになります。
海外投資家による影響
現在の日本においては、外国人観光客が大幅に上昇しています。こうした状況を踏まえて、中国や台湾を中心とした海外の投資家が、日本に着目してマンションなどの不動産を積極的に買い求めています。
海外投資家による不動産の買い占めが広がりを見せていることから、不動産価格の上昇へと繋がっていると考えられています。
金融緩和によるマイナス金利政策の影響
日本では、2016年に金融緩和によるマイナス金利政策が開始されました。この施策により、金利の低い状態で住宅ローンを組めるようになり、住宅購入者の増加を招くことになりました。
また、長期間固定金利で住宅ローンを組める「フラット35」が普及したことも、住宅購入者が増加した要因のひとつといえます。
低金利の影響で住宅購入者が増加することによって需要が活発化し、不動産の価格上昇に繋がります。
地方都市における再開発による影響
現在は、地方都市の駅前エリアにおける再開発が活発化しており、大型商業施設やマンションなどの建設が相次いでいます。市街地再開発事業が施行されることで、商業施設や居住施設が充実するため、人が集まり、ブランド価値が付くなどの理由から不動産価格�は上昇します。
都市部の人口増加による影響
現在の日本においては、少子高齢化が顕著になり、その結果人口減少が深刻な社会問題となっています。しかし一方で、東京を中心とした首都圏の人口は増加しています。
そのため東京都内では、土地の著しい価格上昇を招いています。一定のエリアで人口が増加すれば、その地域の不動産価格は上昇することになります。
土地価格が下落する要因とは
反対に土地の価格が下落するときの要因を紹介していきましょう。
地域の核となる商業施設の撤退
人々は魅力ある商業施設に集まる傾向がありますが、近年、全国の百貨店が閉店するニュースをたびだび耳にします。
強力な集客力があった、地域の核となる大型商業施設が撤退すると、その周辺の地域が一気に冷え切った状態になることがあります。
閉店後の跡地利用がどうなるかによって変わってきますが、なかなか活用が決まらないと、地域が衰退して地価に影響が及ぶことがあるのです。
ごみ焼却場や火葬場が近隣に建設された
ごみ収集車で集められたごみを焼却する施設や火葬場がある地域は、敬遠される傾向があります。具体的な悪影響がなくても、先入観による嫌悪感から敬遠する人が多いのです。
この嫌悪施設と呼ばれるごみ焼却場や火葬場などの施設は、人口が密集していないエリアに建てられることが多いのですが、建築が決定するとその周辺の土地価格は下がることになります。
水災害などの影響で土砂崩れが頻発している
近年は地球温暖化の影響により、大規模な水災害が起きています。特に崖地の崩壊による�土砂災害は、人命に関わる甚大な被害を及ぼします。
このため、令和2年の宅地建物取引業法の改正で、不動産の取引時は水害ハザードマップで所在地を説明することが義務づけられました。
ハザードマップで危険とされた地域は、購入を敬遠する人が多いため、土地価格が下落することがあります。
また、既に宅地造成の工事が行われた一団の土地で、地震や大雨によって地盤が崩壊し、多くの居住者に被害が発生する恐れが大きいと判断された場合、都道府県知事等が造成宅地防災区域に指定することがあります。
この造成宅地防災区域は、令和4年に改正された盛土規制法第45条第1項に基づき指定される土地です。
造成宅地防災区域に指定されると、区域内の造成宅地の所有者に、災害防止のため擁壁の設置などの措置をとる責務が生じます。
土砂災害に耐えられる擁壁を設置するには甚大な費用がかかるだけではなく、そもそも地方自治体が危険だと判断したうえで指定した場所に新たに土地を購入する人はほぼいないことが想像できます。
そのため、造成宅地防災区域に指定されたエリアは、土地価格の下落は避けられません。
地盤や地質の状態による影響
違法に有害物資が廃棄されたことで、周辺の土地や水路が汚染されることがあります。こうした有害物質の漏洩や排水管の亀裂によって土壌汚染が認められる場合は、健康被害を懸念して、周辺の不動産価格が下落することがあります。
まとめ
不動産は「一物四価」といって、1つの不動産に対して、地価公示、実勢価格、固定資産税評価額、相続税路線価の4種類の価格指標�が存在します。
それぞれ目的が異なるため、実際の取引でそのまま使用することはありませんが、相場を判断する重要な指標となります。それぞれインターネットや市区町村で調べることができるので、土地の売却を検討している場合は、相場を知る意味でも調べてみる事をおすすめします。
一方で、土地価格は短期間で大きく変動することがあります。一度調べた価格が一年後に大きく下落していたという事態もあるので、できる限り最新の資料を調べることが重要です。