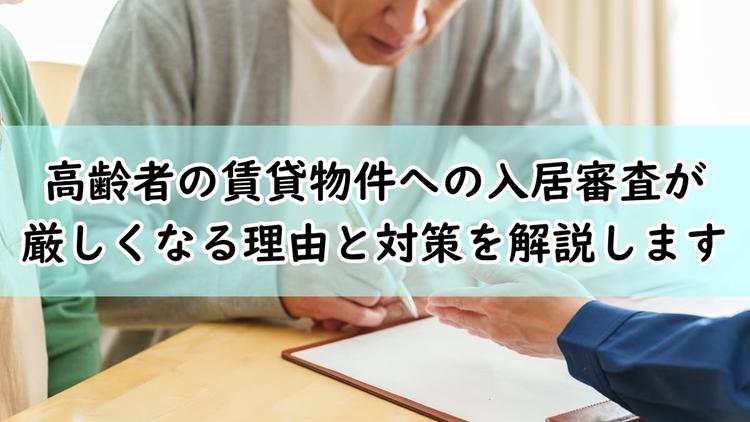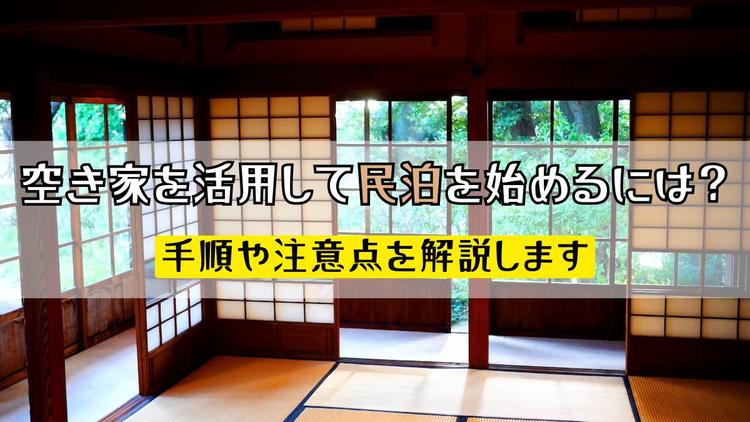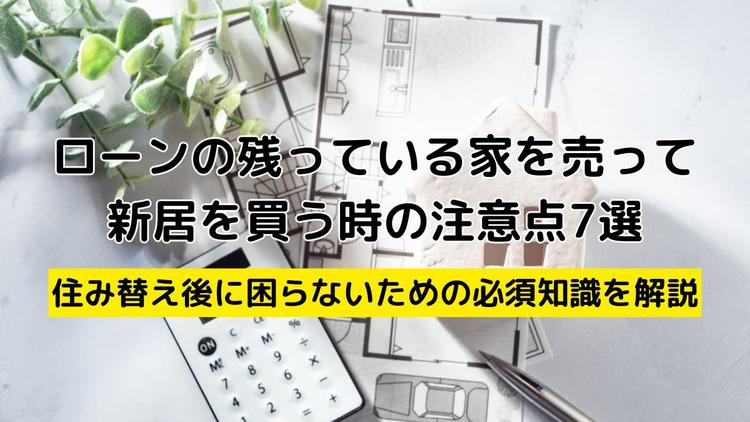「高齢を理由に賃貸の審査で落ちた」そのようなお悩みを抱える人もいます。
高齢になってから賃貸物件に入居しようとしても、収入減少や孤独死のリスクなどを理由に審査が厳しくなりがちです。
とはいえ、賃貸が借りられないと住む場所がないというケースもあるでしょう。
高齢になってから賃貸を探す場合は、対策や賃貸物件を探すポイントを押さえておくことが重要です。
この記事では、高齢者が賃貸の審査で不利になる理由や対策、住みやすい賃貸物件探しのポイントなどを分かりやすく解説します。
高齢者の住居に関する現状
国土交通省の「令和5年住宅・土地統計調査」によると、高齢者(65歳以上)のいる世帯の住宅所有の割合は以下のとおりです1。
| 世帯 | 持ち家 | 借家 | |
| 高齢者のいる世帯 | 81.6% | 18.2% | |
| 高齢者単身世帯 | 67.5% | 32.2% | |
| 高齢者のいる夫婦のみ世帯 | 87.6% | 12.3% |
65歳以上の夫婦での賃貸入居率は18.2%、単身世帯では32.2%と、賃貸利用率はそれほど低くないことが分かります。
高齢になるとそれまでの一戸建では部屋を持て余す、バリアフリー対応でないなどの理由で住み替えを検討するケースは増えています。
住み替え先の選択肢は購入か賃貸になりますが、コンパクトで利便性の高いマンションの賃貸を選ぶケースも珍しくないのです。
ただ、高齢になってから賃貸を探そうとすると、入居審査�がハードルになりやすいです。
日本賃貸住宅管理協会の調査によれば、大家さんの約60%が高齢者の入居に対して拒否感を持っており、実際に60歳以上の単身高齢者の入居制限を設けているのが11.9%に上っています。
そのため、賃貸を検討する場合は、審査が厳しい理由や対策を理解しておくようにしましょう2。
高齢者の賃貸物件への入居審査が厳しくなる理由
高齢者の賃貸物件への入居審査が厳しくなる理由としては、以下の3つが考えられます。
- 収入が低くなりやすい
- 孤独死のリスクがある
- 連帯保証人を見つけられないケースがある
それぞれ見ていきましょう。
収入が低くなりやすい
賃貸に入居している間は毎月家賃の支払いが必要なため、支払い能力が審査で考慮されます。
その点で、年金収入だけに頼る高齢者は審査に不利です。
年金収入だけだとどうしても現役世代よりも年収が下がり、滞納リスクが高くなります。
仮に、賃料を滞納された場合でも、年金収入だけでは後から回収できない恐れがあるため、支払い能力が不安視されて審査に落ちてしまうのです。
孤独死のリスクがある
孤独死が発生すると状況にもよりますが、事故物件扱いされてしまい、その後の賃貸運営に大きなマイナスとなる可能性があります。
孤独死とは直接関係ない居室でも、事故物件となると印象が悪くなり入居者が入らない、家賃を大きく下げる必要があるなどの恐れもあるでしょう。
また、親族と連絡が取れないと、処理を自分でする必要があり、さらには処理費用を払ってもらえないなど大家の負担は大きくなります。
とくに、高齢者単身世帯は、若い世帯よりも孤独死のリスクが高いことから敬遠されがちです。
連帯保証人を見つけられないケースがある
賃貸では、家賃滞納に備えて連帯保証人をつける必要があります。
しかし、高齢者の場合は配偶者が死亡している、親族と疎遠になっているなどで連帯保証人になってく�れる人が少ない傾向があります。
連帯保証人がつけられない場合、家賃保証会社を利用するのが一般的ですが、高齢者は収入の少なさから家賃保証会社が利用できないケースもあり、賃貸審査が不利になってしまうのです。
高齢者が賃貸物件を借りるための対策
審査に不利になりやすい高齢者が賃貸を探す場合は、審査対策しておくことが重要です。
ここでは、高齢者が賃貸物件を借りるための対策として以下の3つを紹介します。
- 夫婦や子供など複数人で入居する
- 家賃債務保証制度を利用する
- 近隣に身内がいてサポートを受けられることをアピールする
それぞれ見ていきましょう。
夫婦や子供など複数人で入居する
高齢者単身での審査は厳しくなりがちですが、夫婦世帯であれば単身よりもハードルは下がります。
夫婦世帯の場合、年金収入が上がるほか、孤独死のリスクも避けられます。
さらに、子供世帯など入居人数が増えるほど審査のハードルが下がるので、親族に相談してみるとよいでしょう。
家賃債務保証制度を利用する
家賃債務保証制度とは、支払い能力が低い高齢者の賃貸入居を支援する制度です。
高齢者住宅財団が、高齢者や障がい者世帯などの住宅確保要配慮者が入居する際に家賃債務を保証し、連帯保証人の役割を担ってくれます。
家賃債務保証制度を利用すれば、万が一、家賃滞納が起きても大家は保証をうけられるのでリスクが軽減でき、入居審査に通りやすくなります。
また、物件によっては国や自治体から高齢者向けの支援や補助��を受けられるケースもあるので、自治体や不動産会社に確認してみるとよいでしょう。
近隣に身内がいてサポートを受けられることをアピールする
同居でなくても近隣にサポートしてくれる親族がいれば、万が一のときも親族が対応できるので大家の安心感につながります。
近隣に住んでいる、すぐに連絡が取れる親族がいるならその旨をしっかりアピールしましょう。
高齢者が住みやすい賃貸物件を見つけるためのポイント
高齢者が賃貸物件を検討する場合は、審査の通りやすさだけでなく自分自身が安心して暮らすためにも、物件選びを慎重に行うことが大切です。
ここでは、賃貸物件を見つける際に押さえておきたいポイントとして以下の4つを紹介します。
- 家賃は収入の3分の1程度に抑える
- できるだけ低階層の物件を選ぶ
- 近隣に知人や友人がいる立地にする
- 高齢者向け公営賃貸住宅を利用する
それぞれ見ていきましょう。
家賃は収入の3分の1程度に抑える
賃貸物件は住み続ける限り家賃の支払いが必要になるため、長期的に支払い続けられる余裕があるかを慎重に計画することが大切です。
高齢になると、収入が減少するだけでなく医療費などの突発的な支出が発生するケースも珍しくありません。
収入に対して家賃が大きすぎると、いざというときに支払いが難しくなるので、注意しましょう。
基本的には収入の3分の1程度に収まる物件が適していますが、貯蓄額や支出状況にも左右されるので、一度長期的なシミュレーションをしたうえで検討するとよいでしょう。
できるだけ低階層の物件を選ぶ
陽当たりや眺望の面で高階層を選びたいという方もいるでしょうが、高齢になってからは低階層がおすすめです。
低階層の方が移動の負担が軽減でき、足腰の負担がかかりにくくなります。
また、高階層は万が一災害が起きた時に、高齢者は避難できないリスクが高まる点にも注意が必要です。
たとえば、普段はエレベーターで移動できるため問題ないとしても、災害時にはエレベーターが停止しま�す。
エレベーターが停止し階段で移動となった場合、足腰が弱ると難しい場合があるでしょう。
災害時や緊急時のリスク軽減のためにも、低階層を選ぶことをおすすめします。
近隣に知人や友人がいる立地にする
近隣に親族や知人・友人がいれば、審査のうえでも考慮してもらいやすくなります。
また、審査に限らず近くにサポートしてくれる知り合いや気の置ける友人がいれば、生活の上で安心感や充実感につながるでしょう。
親族にとってもすぐに確認できる距離は、お互いの不安をなくせるというメリットがあります。
高齢者向け公営賃貸住宅を利用する
近年は、公営賃貸住宅の中でも高齢者向けに提供されている物件も増えています。
高齢者向け公営賃貸住宅であれば、高齢者であっても審査に通りやすいだけでなく、バリアフリーなど高齢者向けの設備が整っている物件も多く生活がしやすくなります。
ただし、高齢者向け公営賃貸住宅は提供数がまだ少なく人気が高いので、見つけたら早めに検討することが大切です。
終の棲家を購入するのもおすすめ
高齢になってからの住み替え先としては、賃貸ではなく購入という選択肢もあります。
購入であれば賃料を支払い続ける不安もないなどメリットもあるので、検討してみるとよいでしょう。
以下では、終の棲家を購入するメリットを解説します。
物件を購入すれば住まいの不安を和らげることができる
賃貸物件に入居すると、住み続ける限り家賃の支払いが必要です。
仮に、65歳で入居して90歳ま�で生きる場合、25年間家賃を支払うことになります。
入居当初は支払いに問題がなくても、貯金の減少や医療費の増加などで支払い続けるのが負担になる恐れもあるものです。
家賃の支払いが難しくなると退去させられる可能性もあるため、住まいへの不安を抱え続けることになります。
その点、購入であれば住宅ローンを完済すれば家が自分のものになるので、退去させられる心配はありません。
住宅ローン完済後は、家にかける支出が大きく減少できるのも大きなメリットでしょう。
とくに、退職金や売却金で現金一括購入すれば、終の棲家を確保しつつ居住費の大きな削減となるので老後の安心感につながります。
住宅ローンの審査が厳しい場合は親子リレーローンを検討できる
老後に家を購入する際、住宅ローンを利用する場合は、完済年齢がネックとなりローンを組めない場合があります。
一般的に、金融機関では完済年齢を80歳などと定めているため、仮に65歳でローンを組むと、返済期間は最大でも15年までしか設定できないのです。
この場合、借入額を下げるか毎月の返済額を多くする必要があり、審査が厳しくなる恐れも出てきます。
しかし、二世帯住宅であれば親子リレーローンを利用できるので、高齢でも住宅ローンを組みやすくなります。
親子リレーローンとは、親子名義で住宅ローンを組み、最初の一定期間を親世代が返済し、その後子世代が返済を引き継ぐローンです。
親子リレーローンであれば、収入が少ない子世代でもローンが組めるというメリットがあり、親子双方にとって有効な�選択肢となります。気になる方は一度相談してみるとよいでしょう。
将来子供に資産を遺すことができる
購入した家は自分の資産として、将来子供や孫に相続させることができます。
立地や状態が良い不動産であれば、相続後に相続人も資産として活用しやすいでしょう。
仮に、不動産を相続させない場合でも、売却して現金化すれば、自分の介護施設の入所資金や老後資金に充てたり、現金として相続させたりと、選択肢は豊富にあります。
購入した家は自分の資産となるのは、賃貸にはない大きなメリットといえるでしょう。
高齢者の賃貸物件への入居審査に関するよくある質問
最後に、高齢者の賃貸物件への入居審査に関するよくある質問をみていきましょう。
老後に賃貸物件を借りられない噂は嘘?
借りられないわけではありませんが、若者世代に比べると入居しにくくなります。
高齢者は収入が年金だけとなり滞納リスクが高い、孤独死のリスクがあるなどで賃貸の入居審査が不利になりがちです。
物件によっては高齢者の入居を制限しているケースもあり、そもそも審査に申し込めない場合もあるので注意しましょう。
年金暮らしでも賃貸物件の入居審査をパスできる?
物件を選び対策しておけば、年金収入だけの高齢者でも入居審査に通る可能性は十分あります。
たとえば、高齢者歓迎の物件を選ぶ、高齢者入居向けの制度や支援を活用する、親族のサポートを受けるなどで審査に通る可能性を上げられるでしょう。
とはいえ、高齢者向け賃貸物件はまだ数が多くはないので、不動産会社に相談しながら慎重に物件を選ぶことが大切です。
高齢者の入居拒否は違法にならないの?
大家には借りる人を選ぶ権利があり、その基準も自由に決めることができるので、高齢者の入居を拒否しても違法には当たりません。
ただ、入居後の賃貸契約更新で高齢を理由に退去を求められても、入居者は拒否することが可能です。
また、高齢者でも賃貸住宅に入居しやすくなるように、「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」に基づいた制度や支援も増えています。
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
- 高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)
- 住宅セーフティネット制度
- 終身建物賃貸借制度
上記は高齢者住まい法に基づいた住宅制度、支援の例です。
まとめ
高齢者は賃貸審査で不利になりやすく、入居できないケースもあります。
賃貸を検討する場合は、家賃債務保証制度を利用する、高齢者向け物件を選ぶ、親族のサポートを受けるなど対策したうえで、物件選びから慎重に行いましょう。
高齢になってからの家の選択肢には、賃貸だけでなく購入という選択肢もあります。
購入であれば退去の心配なく、自分の資産として活用や相続させられるなどのメリットもあるので、賃貸と比較して検討してみるとよいでしょう。