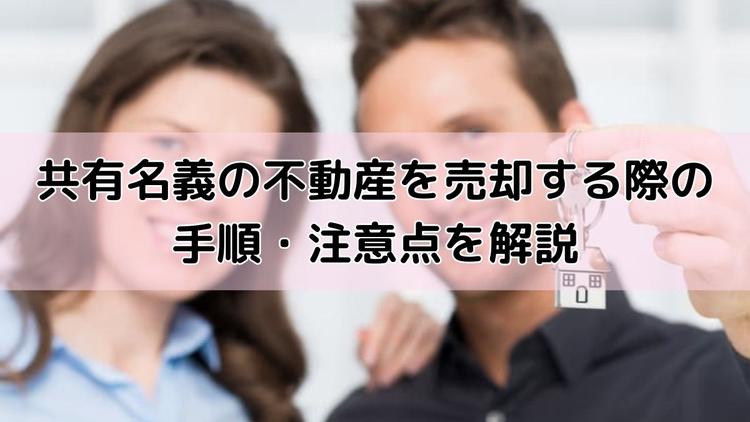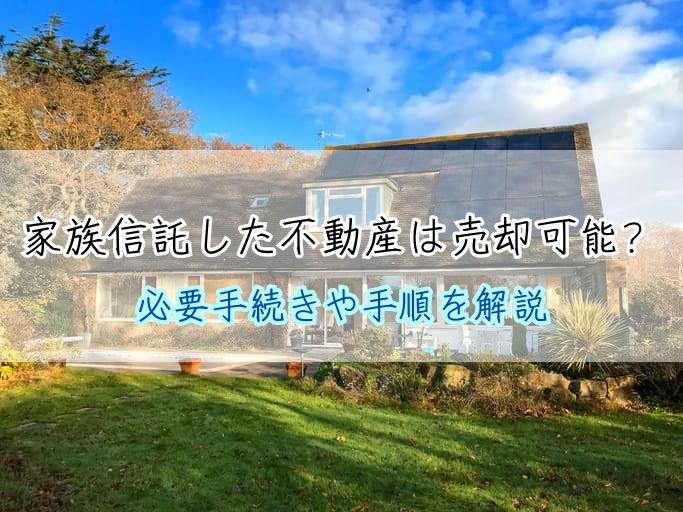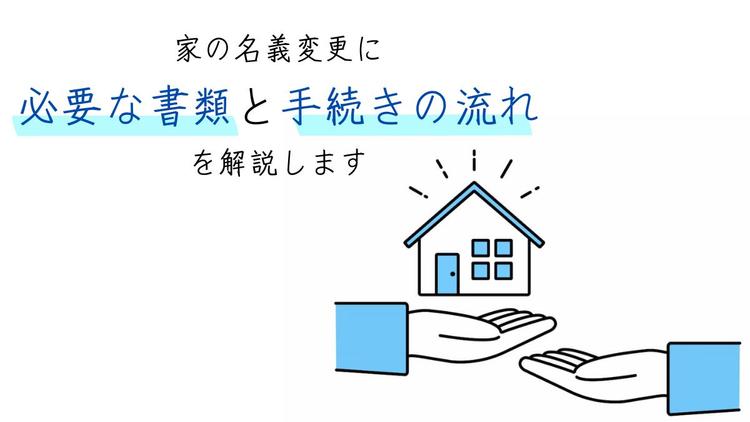不動産の共有名義とは?
不動産の共有名義とは、不動産を複数の人間で所有することを指します。
誰が不動産を所有しているかが記載される登記簿では、共有名義の人全員の氏名と住所が記載されるとともに、その共有持分も記載されます。
共有持分とは、対象の不動産に対してどのくらいの割合、所有するかを示すもので「3分の1」などと記載されます。
共有名義になる3つのパターン
不動産が共有名義なるパターンとして、以下の3つがよく挙げられます。
- 複数人で相続する
- マイホーム購入時に夫婦共有にする
- 二世帯住宅購入時に親子共有にする
以下、それぞれ見ていきましょう。
①複数人で相続する
まず、不動産を複数人で相続するケースです。
相続時には、配偶者と子など以下のように法定相続人が定められています。
例えば、子どもがいる家庭であれば配偶者と子が法定相続人になりますが、子も親もいない家庭であれば配偶者と兄弟姉妹が相続することになります。
また、子がいる家庭で、子どもが複数人いるケースでは、子ども全員が法定相続人となります。
このとき、問題となるのが、誰がどのような割合で財産を相続するかということです。
特に、一般的な家庭であれば相続財産のうち、不動産の占める割合が多く、誰か1人に相続させると他の相続人に対して不公平となってしまいやすいです。
こうしたケースでは、不公平となることを避けるため、子ども3人がそれぞれ3分の1ずつ相続するといった分割が行われます。
②マイホーム購入時に夫婦共有にする
マイホーム購入時、住宅ローンを組んで住宅を取得するのが一般的ですが、住宅ローンは借りる人の年収によって借入限度額が決まります。
最近では夫婦ともに働きに出ており、収入があるのが一般的です。
例えば、ご主人だけでは希望の借入限度額に届かないときに、夫婦が共同で住宅ローンを組むことで、希望の額の融資を受けるといったことがあります。
こうしたときには、その年収割合に応じて、不動産の共有持分も分割することになります。
③二世帯住宅購入時に親子共有にする
二世帯住宅購入時には、親も子も住宅に住むのですから、それぞれがお金を出すことが多いです。
場合によっては、親子リレーローンなど、親子が共同名義で住宅ローンを組むことがあります。
こうしたケ��ースでは、不動産の持分についても親子で共有持分を持つことになります。
共有持分権者ができること
共有持分権者、つまり「共有者のいる不動産の所有者の1人」は、単独で不動産を所有する場合と比べて権利が限定されることになります。
以下、共有持分権者ができることについて見ていきましょう。
単独でできる:保存、使用
共有持分権者が単独でできること、つまり他の共有持分権者の許可なくできることとしては「保存」と「使用」があります。
「保存」とは、不動産の建物を維持したり、不法占拠者を追い出したりすることで不動産の現状を維持することです。
また、「使用」とは不動産を使用することですが、代表例としては不動産に居住することが挙げられるでしょう。
過半数の同意が必要:利用、改良
次に、共有持分権者の過半数の同意を得て初めて実行できることとして「利用」と「改良」が挙げられます。
なお、ここでいう「過半数」とは、「共有持分の過半数」となります。
例えば、共有持分をAさんが2/3、Bさんが1/6、Cさんが1/6持っている場合、BさんやCさんが「利用」や「改良」しようと思えば、Aさんの同意を得る必要があります。
「利用」の代表例としては、不動産を短期的に貸すことが挙げられ、「改良」とは不動産をリフォーム・リノベーションすることだと考えるとよいでしょう。
全員の同意が必要:処分
最後に、全員の同意が必要なことと��して「処分」が挙げられます。
これは、不動産を売却する他、抵当権を設定したり、借地借家法の適用がある賃貸借契約を締結したりすることが該当します。
共有名義の不動産を売却する3つの方法
共有名義の不動産において、共有持分権者は制限を受けることをお伝えしました。
中でも、不動産を売却することを含む「処分」は、他の名義人全員の承諾が必要です。
しかし、仮に承諾を得られなくとも、不動産を売却できる方法はあります。
ここでは、共有名義の不動産を売却する3つの方法をお伝えします。
方法①不動産全体を売却する
まずは不動産全体を売却する方法です。
この方法では、他の共有名義人全員の承諾を得る必要があります。
逆に言えば、承諾を得てしまえば普通の不動産売却と何ら変わりのない状態で売却を進めることができます。
方法②自分の持分を売却する
不動産の共有持分権者は、不動産について共有持分を持ちますが、この共有持分だけ売却することができます。
この場合においては、他の共有持分権者の承諾を得ておく必要はありません。
とはいえ、不動産の持分の一部だけもらっても活用しづらく、実質的には共有持分だけ売却するのは非常に難しくなっています。
どうしても売却したい場合には、共有持分の買取専門会社もあるため、そうした業者を利用することになるでしょう。
しかし、その価格は一般的な相場よりかなり安くなってしまいます。
方法③土地を分筆して売却する
最後に、自分の共有持分割合に応じて、土地を分筆して売却する方法です。
この方法では、分筆後の土地は自分の単独所有となるため誰の承諾を得ることもなく売却できます。
この方法の注意点としては、「建物を建てるには幅4m以上の道路に2m以上接道している必要がある」といった法律に問題を忘れないようにすることです。
また、登記簿謄本には共有持分割合しか記載がありませんが、単に敷地面積×共有持分割合をかけた面積の分筆をするとなると、間口の広さや道路から見て近い場所にあるか遠い場所にあるかといった、分筆後の不動産の価値の問題を考慮することができません。
後々トラブルに発展することを避けるためにも、共有持分権者全員でよく話し合い、公平な分筆を行うことが大切です。
不動産全体を売却する手順と注意点
ここでは、共有持分を持つ不動産について、不動産全体を売却する場合の具体的な手順と注意点を見ていきたいと思います。
手順1:共有持分権者の承諾を取り付ける
不動産全体を売却する場合、まずは共有持分権者の承諾を取り付ける必要があります。
共有持分権者と長く連絡を取っていない場合、相続が発生してさらに権利が細分化している場合もあります。
こうしたケースでは、共有持分権者を特定するのに時間がかかってしまうこともある点に注意が必要です。
手順2:委任状を作成する
共有持分権者を見つけたら、委任状を作成して署名と実印押印、印鑑証明書の提出を受けておきましょう。
これらの書類が揃ったら、不動産の売却を開始できるようになります。
手順3:売却活動を行う
不動産の売却活動を行います。
この辺りは、単独所有の場合の不動産売却と流れは同じです。
ただし、不動産の売り出し価格について共有持分権者に納得してもらってから売却を始めることや、途中で値下げする場合には共有持分権者に相談するなどする必要があるでしょう。
手順4:契約~引き渡し
無事、条件がまとまったら売買契約を締結します。
売買契約時には、委任状があれば共有持分権者の代表となる方が立ち会えば問題ありません。
いつからなら引渡しできるなど、共有持分権者の間でよく話し合っておく必要があるでしょう。
手順5:利益と経費を共有者で分配する
不動産を売却して得られた利益と、不動産を売却するのにかかった経費(仲介手数料や��登記費用など)を相続人全員で配分します。
共有者間で揉めないよう進めよう
上記のように、共有持分を持つ不動産の売却は、代表者の方が他の共有持分権者の委任を受けて進めるのが一般的です。
このとき、他の共有持分権者の中には「もっと高い金額で売れるのではないか」と言い出して揉めることがあります。
また、値下げの度に他の共有持分権者の承諾を得るのは骨の折れることです。
とはいえ、承諾を得なければ値下げができず、いつまでも売れ残ってしまう可能性があります。
このように、共有持分を持つ不動産を売却するときには手間がかかってしまいます。
共有持分の不動産売却では直接買取がおすすめ
このため、手間のかからない、不動産会社による直接買取による方法で不動産を売却する方も少なくありません。
直接買取であれば、売主と不動産会社とで条件がまとまれば、すぐに売買が決まります。
場合によっては、共有持分権者全員で不動産会社に足を運び、その場で話をまとめてしまうことも可能でしょう。
ただし、直接買取では相場より価格が安くなってしまうことが多い点が問題となります。
そこでおすすめなのがイエウリの利用です。
直接買取が持つデメリットを解消できる「イエウリ」買取マッチングサービス
業者買取の場合、不動産会社が直接購入するため、査定から1カ月以内での売却も可能。仲介手数料もかからない。
「イエウリ」買取マッチングサービスであれば、不動産会社の直接買取と同じく、条件がまとまればすぐに売却できます。
また、複数の不動産会社が提示する価格のうち、もっとも高い価格を提示した不動産を選べることから、「相場より価格が安くなってしまう」という問題を解消しやすいのが特徴です。
・仲介でよくある値下げ交渉も無し!
・業者買取なので仲介手数料ゼロ!
・1ヶ月以内のスピード売却も可能!
・サービス利用料は完全無料!
最後に、土地を分筆して売却する手順と注意点について見ていきましょう。
手順1:隣地所有者に連絡する
まず、土地を分筆するためには、隣地所有者と立ち会って「ここが境界で間違いない」という確認をする必要があります。
これを、分筆する予定の土地の周辺の隣地所有者全員に対して行う必要があります。
なお、土地に接する道路が県道や市道の場合、県や市の担当者の立ち会いを受ける必要があります。
全ての境界を確定するまでに2週間~1カ月、場合によっては数カ月かかることもあるため注意が必要です。
手順2:分筆する
境界立ち会いが済んだら、分筆します。
分筆の登記は自分ですることもできなくはないですが、基本的には土地家屋調査士に依頼して代行してもらうようにしましょう。
手順3:売却活動を行う
土地の分筆が済んだら、後は通常の方法で不動産を売却します。
売却の途中で他の共有持分権者の了承を得るといった必要もありません。
手順4:契約~引き渡し
売却活動の結果、買主が見つかったら、買主との間で売買契約を締結します。
この際にも、他の共有持分権者の承諾を得る必要はありません。
土地の形に注意
先ほども少し触れましたが、土地を分筆する際には、分筆後の土地の形について注意する必要があります。
まず、土地と道路面が接している部分の間口について、4m以上の幅を持つ道路に2m以上接していなければ、建物を建てる��ことができなくなります。
建物を建てられなければ、土地の価値は大きく落ちてしまいます。
この点にはしっかり注意するようにしましょう。
なお、上記条件を満たしたとしても実際には間口が2mの土地だと自動車が通ることも難しく、使いづらい土地になってしまいます。
それぞれの共有持分権者が土地をどのように使うか話しあった上で全員が納得できる分筆を行なうのが理想です。
まとめ
共有持分を持つ不動産の売却についてお伝えしました。
共有持分を持つ不動産は、その不動産全体を売却する場合には、他の共有持分権者の承諾を得る必要があります。
承諾を得て、実際に売却活動を始めた後についても、値下げの度に他の共有持分権者に確認するなど、手間が多くなってしまいます。
このため、不動産会社に直接買い取って貰う方法を選択すると手間なく進められて便利です。
特に、「イエウリ」買取マッチングサービスを利用すると直接買取のデメリットである「売却価格が相場より安くなってしまう」といった問題を解消しやすいです。
その他、自分の共有持分割合に応じた部分だけ土地を分筆し、売却する方法もありますが、こちらのケースでは、分筆後の土地が法律の条件をクリアするかどうかや、実際に利用しやすいかどうかをよく考慮したうえで分筆を実行するようにしましょう。