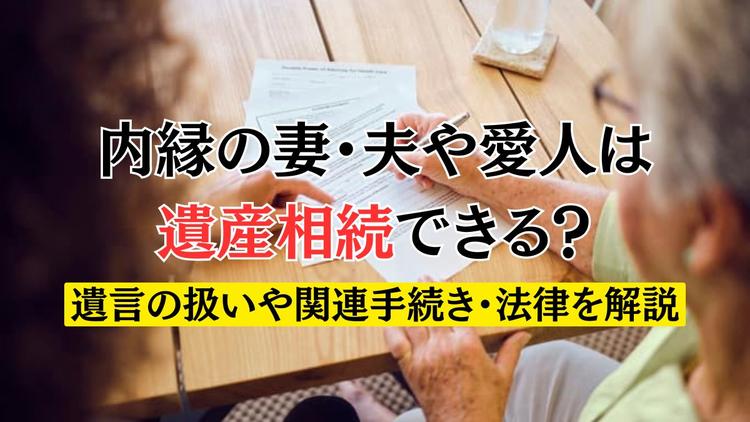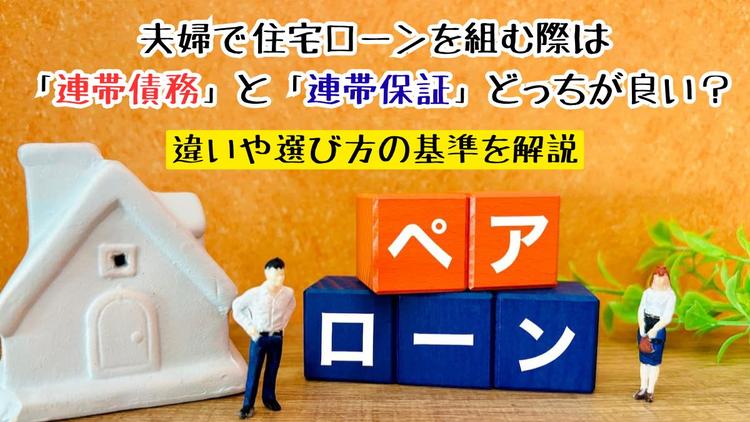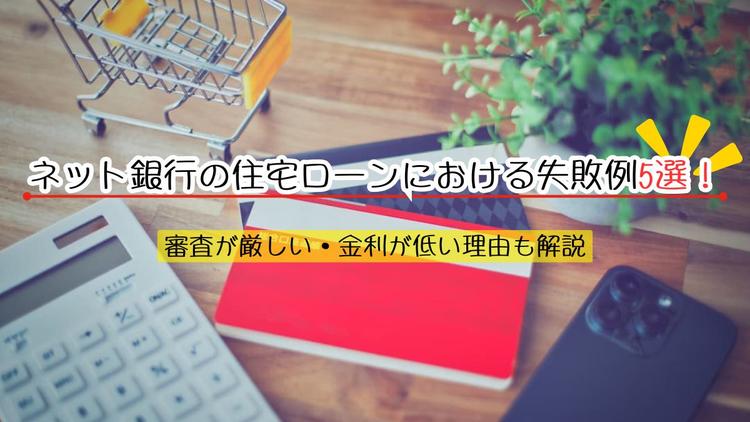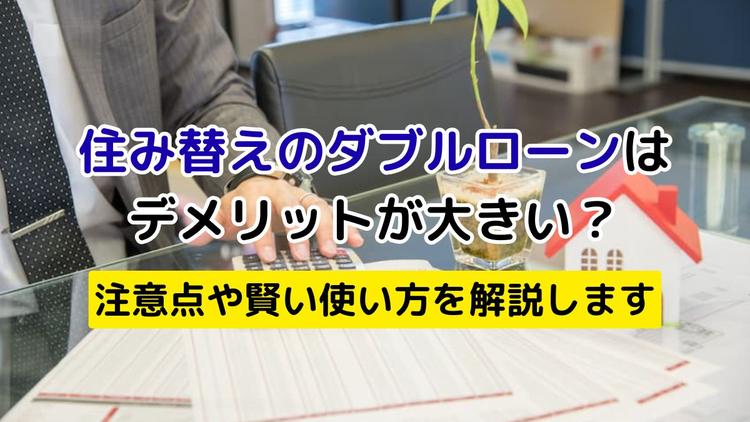内縁関係は、事実婚であると認識されることが多く、社会的にも一般の夫婦と同じ扱いがなされます。ところが、こと相続に関しては、婚姻関係と同列というわけにはいきません。そこには厳格な区別があり、配偶者以外のパートナーは、相続人になることができないのです。
そのため、遺産相続の手法を正しく理解していないと、長年苦労を共にしてきたバートナーが、遺産をいっさい相続できないという事態に直面することになります。適切な相続が実現するよう、この記事では、内縁の妻(夫)に遺産を相続する方法と遺言の扱いについて解説します。
婚姻・内縁の妻(夫)・愛人の違いと判断基準
相続において、婚姻関係と内縁関係では、どのような違いがあるのかを明らかにしていきましょう。さらには、愛人関係との違いについても解説をします。
「婚姻関係」と「内縁関係」の違いと相続の関係
民法では「婚姻は戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生じる(739条)」とされています。婚姻の届出をすることで、相手方は配偶者となります。これが婚姻関係です。
一方、内縁関係とは、婚姻届けは出していないが、婚姻の意思があり、実態上も夫婦として暮らしている状態を指します。
単に同居しているだけでは内縁関係としては認められず、婚姻の意思が前提にあることが重要です。また過去の判例等から、少なくとも3年程度の同居した実績が必要になります。
気をつけたいのは、いわゆる同棲をしているだけでは、内縁関係とはいえないという点です。このため、内縁関係と認めてもらうには、次のような要件に該当していることが求められます。
- 生計を共にしている
- 周囲(友人、知人、近所になど)に紹介して夫婦として認識されている
- 挙式を行った
- 認知した子どもがいる
こうした側面も含めて、内縁関係にあると判断されるのです。
婚姻関係と内縁関係の大きな違いは、婚姻届けを出しているか否かですが、法的には、同等に扱われることが多くあります。�たとえば次のような事項は、内縁関係であっても婚姻関係と同等の義務や責任が伴います。
- 貞操義務(不倫をしない)
- 日常生活に関する連帯責任(民法761条)
- 扶助の義務(民法752条)
- 婚姻費用の分担の義務(民法760条)
- 財産分与(民法768条)
しかし、相続に関しては、相続人になれるパートナーは配偶者に限定されています。
内縁関係では、相続人になれないのです。
「内縁関係」と「愛人関係」の違いと相続の関係
内縁関係と比較される関係に、愛人関係があります。愛人関係とは、配偶者のいる相手と親密な交遊を維持している関係をいいます。
配偶者のいる相手から見れば、いわゆる「愛人」と呼ばれる立場になります。単に親密な男女関係に過ぎないため、法的に保護されることはありません。
ごく希なケースとして、愛人として長年生活を共にしており、被相続人の世話をしていたような実績があれば、内縁関係が認められることがあります。ただしこの場合においても、相続人になることはありません。
内縁関係(事実婚)の妻・夫が「相続」の対象にならない理由
内縁の妻・夫や愛人は相続人になれないだけでなく、相続に関連する様々な権利も認められていません。具体的にどのような権利がないのか解説をしていきましょう。
ポイント①「遺留分」がない
遺留分とは、遺言書によって、ある特定の相続人に集中して相続された場合に、配偶者や子どもなどの近親者が、一定の財産を取得できる権利のことです。ただし、遺留分を主張できるのは、配偶者の他、子ども、孫などの「直系卑属」と親、祖父母などの「直系尊属」に限られます。
被相続人に直系卑属と直系尊属がいない場合、その兄弟姉妹が相続人になることがありますが、遺留分はありません。したがって、そもそも相続人でもない、内縁の妻・夫や愛人に遺留分はありません。
ポイント②「寄与分」がない
寄与分とは、被相続人の生前に、相続人が、被相続人の財産の増加や維持に貢献してきた、あるいは被相続人の療養看護に努めてきたなど、被相続人に貢献をしてきた相続人に対して他の相続人との公平さを図るために設けられた制度です。
寄与分が認められる場合、寄与分の額を差し引いた財産を相続人で分配し、寄与分が認められる相続人は、分配された相続分に寄与分の額が上乗せされます。
この寄与分を主張できるのは相続人のみで、内縁の妻・夫や愛人に寄与分はありません。
ポイント③「特別寄与料」がない
特別寄与料とは、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族が、相続の開始後、相続人に対して支払いを請求することができる金銭のことです。
民法改正により新しくできた制度で、2019年7月1日以降に開始した相続であれば、特別寄与料が請求可能です。特別寄与料の請求ができるのは、相続人以外の被相続人の親族に限られます。ここでいう親族とは、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族を指します。
たとえば、被相続人の長男の妻が、長年にわたり被相続人の介護を無償でしてきた場合などに�特別寄与料を請求することができます。
しかし、たとえ内縁の妻・夫や愛人が、被相続人の療養看護を無償でしていたとしても、親族ではないので、特別寄与料の請求は認められません。
内縁関係(事実婚)の妻・夫が「遺産」を受け取る6つの方法
内縁の妻・夫は相続人になれませんが、必ずしも遺産を受け取れないことを意味するものではありません。内縁関係のパートナーであっても、遺産を受け取れる方法は存在します。
①「遺言書」を作成し遺贈する
法的に有効な遺言書を作成することで、遺贈により内縁の妻・夫に財産を残すことができます。
遺贈とは、遺言によって、自らの財産を相続人以外の人物に無償で譲与することをいいます。遺贈は、誰に対してでもすることができます。また法定相続よりも優先されますから、確実に相続財産を渡すことが可能です。
気をつけたいのは、遺贈は相続の一類型だという点です。つまり、遺言者の死亡によって効力を生じますから、受遺者となるはずであった人が、被相続人よりも先に亡くなった場合には、受遺者となるはずであった人の子が代襲して受遺者にはなれません。
また、たとえ被相続人が「全財産を愛人に譲る」との遺言を残していたとしても、基本的に全額受け取ることはないと考えた方がいいでしょう。全遺産が他人に移ることで、相続人のその後の暮らしが立ちゆかなくなるようでは、相続人の生活の平穏が脅かされることになります。
このため相続人は、全財産が遺贈の対象となっている場合でも、法律で定められた遺留分を受け取る権利が行使できます。遺贈をしたとしても少なくとも遺留分として認められる範囲の遺産は、相続人に渡ることを認識しておきましょう。
②「生前贈与」する
被相続人の生前に贈与を受ければ、内縁の妻・夫や愛人でも確実に財産を受け取ることができます。
しかし��、多くの人が、この生前贈与を躊躇する理由のひとつに、贈与税の存在があります。もともと贈与税は、相続税逃れを防止する目的で創設された税であるとの経緯から、相続税よりも高い税率が設定されています。このため、生前贈与を実施するためには、贈与税に配慮しないと、贈与を受けた側が大きな負担強いられることになります。
贈与税を軽減する方法として、暦年贈与を活用する方法があります。贈与税には、基礎控除があり、毎年110万円までは贈与税がかかりません。たとえば、毎年110万円ずつ20年間にわたって生前贈与をすれば、合計2200万円もの金額を、贈与税をかけずに贈与することができます。このような贈与を暦年贈与といいます。
しかし、毎年の贈与が必ずしも暦年贈与として扱われるわけではありません。たとえば、最初に2,200万円の贈与をする約束をして、毎年110万円ずつ20年間にわたって履行したような場合は、連年贈与と見なされ、約束をした年あるいは最初の履行があった年にまとめて贈与税が課税されることになります。
このため、贈与に際しては、暦年贈与と見なされるよう、次のような対策を行うケースがあります。
- 贈与のつど贈与契約書を作成する(確定日付つき)
- 受贈者が実質的に管理している受贈者名義の口座に振り込む
- 登記や登録の制度のある財産については名義を変更する
- 毎年違う時期に、異なる金額を贈与することで、当初に約束のない単発の贈与であることを示す
- あえて110万円をわずかに超える贈与をして、贈与税申告をすることで納税をした実績を残す
また、贈与額については、自分の財��産のすべてを内縁の妻・夫や愛人に渡すのではなく、相続人の将来の生活設計への配慮も必要です。
なお、相続税や贈与税に関する節税対策をしたい場合は、税理士などの専門家に相談してから実施するのが望ましいでしょう。
③「特別縁故者」の財産分与を受ける
被相続人に相続人が1人もいない場合には、亡くなった被相続人の身の回りの世話をしていた人が特別縁故者として相続財産を受け取れることがあります。
特別縁故者として被相続人の財産を受け継ぐには、相続人の不在が確定してから3カ月以内に「特別縁故者の相続財産分与の請求」を家庭裁判所に申し立てる必要があります。ただし、申立人となれるのは、次の要件に該当する人に限られます。
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人の療養看護に努めた者
- 被相続人と特別の縁故があった者
被相続人に配偶者がいない場合は、愛人でも内縁関係として扱われ、特別縁故者になれる可能性があります。ただし、生計を同じくしていたとか、療養看護に務めていたといった要件があるため、こうした関係が希薄だった愛人の場合には、認められる可能性はほとんどありません。
④「死因贈与」を受けとる
死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が発生する贈与契約のことです。死因贈与は口約束でも成立します。しかし、受贈者が内縁の妻・夫や愛人だった場合、口約束だけでは、相続人とのトラブルは避けられません。契約書などの書面がない限り、死因贈与の口約束があったことを証明することは現実的に困難だからです。
また、書面によらない贈与契約は��、履行が終わっていないかぎり贈与者が自由に解除できることが民法上定められています。
このため、書面がない死因贈与は、履行の完了前であれば、法定相続人による解除が成立する可能性もあります。
⑤「生命保険金」の受取者として指定する
被相続人が加入している生命保険金の受取人に内縁の妻を指定したものがあれば、正当な保険金として受け取ることができます。
ただし、内縁の妻が受取人になれるかは生命保険会社や商品によって異なりますので、加入に際しては、事前に確認しておいた方がいいでしょう。
⑥「遺族年金」を受け取る
年金法においては、「配偶者」に「事実婚関係にある者」を含むとされています。このため、内縁関係と生計維持関係が認められれば、内縁の妻・夫でも受給できる可能性があります。ただし愛人の場合には、同居、生計維持といった要件から外れるため、対象外になります。
内縁関係を証明するために、次のような書類の提出が求められます。
- 健康保険被保険者証の写し
- 結婚式を挙げたことを証明する書類
- 自らが喪主となって葬儀をあげたことを証明する書類
- 住民票……同居していることを証明できる最も有効な書類です
内縁関係(事実婚)の妻・夫に遺産を継承する確実な方法は?
内縁関係は、法的には非常に不安定な関係にあるため、パートナーの財産を継承しようとすれば、相続人から訴訟が起こされる可能性は否定できません。
このため、法的な対抗手段を予め立てておかないと、遺産の継承が無効になってしまうことがあります。パートナー間で確実に財産を継承するには、 生前贈与や遺言書といった、明確な意思表示による財産移転の方法を策定しておく必要があります。
事実婚にある内縁の妻・夫が遺産を受け取った時の注意点
事実婚にある内縁関係の妻(夫)が遺産を受け取れたとしても、税金の面においては、婚姻関係にある場合との違いがあります。思い違いから、想定外の負担を招くことがありますから、注意すべき点について解説をしていきましょう。
注意点①相続税が高くなる
相続または遺贈によって財産を取得した人には相続税が課税されますが、すべての人の税率が同じわけではありません。1親等の血族以外の者が財産を取得した場合は、相続税は2割加算されることになります。
注意点②「配偶者の税額軽減」が適用されない
配偶者は、配偶者の税額軽減が適用されるため、財産を相続した場合、最低でも1億6千万円までは相続税がかかりません。しかし、内縁の妻(夫)や愛人の方が受けた遺贈や特別縁故者としての財産分与には、この特例が適用されませんから、相続税が課せられることがあります。
注意点③ 「基礎控除額」が増えない
内縁の妻(夫)は相続人ではないので、基礎控除額として加算される「相続人の数×600万円」が適用されません。
このため、たとえば相続人が誰もおらず、内縁の妻(夫)が特別縁故者等により財産を取得する場合は、基礎控除の額は最低の3,000万円となります。
注意点④ 「小規模宅地等の特例」が適用されない
小規模宅地等の特例とは、被相続人の住んでいた家を相続して引き続き住み続ける場合、その土地の評価額を最大で80%減額することができる制度です。この特例が適用できるのは、親族のみであるため、法律上は他人である内縁の妻(夫)は適用されません。
したがって、たとえ自分が住んでいた不動産を遺言によって取得したとしても、 小規模宅地等の特例を使うことはできません。
注意点⑤「死亡保険金の非課税枠」を利用できない
被相続人が契約者・被保険者で、受取人が相続人となっている生命保険契約の場合、相続人が受け取った死亡保険金には、1人500万円の非課税枠があります。しかし、内縁の妻(夫)は相続人ではないので、死亡保険金を取得したとしても この非課税枠を利用することはできません 。
注意点⑥「障害者控除」が受けられない
相続人が障害者であり、相続発生時点で85歳未満の場合、相続税の額から次の額を控除することができます。
- 障害者……27万円
- 特別障害者……40万円
- 同居特別障害者……75万円
障害者控除を使えるのは、相続人に限定されているので、内縁の妻(夫)は障害者であったとしても控除の適用はありません。
事実婚にある内縁の妻・夫に住居権はあるのか
借家に居住していた場合、契約者である夫や妻が死亡しても、賃借人としての地位は相続人に相続されるため、賃貸借契約は終了せず、同居していた妻または夫や子どもが引き続き住み続けることができます。
しかし、内縁関係においては、賃借人としての地位を相続できないため、家主から退去を申し渡されたら住み続け�ることはできません。
家主の裁量ひとつで生活が大きく変わるのですから、賃貸で生活している内縁関係は、この点の不安定さは否めません。それでは、せっかく家主が引き続き居住を認めてくれたのに、相続人が賃借権の相続を主張したらどうなるでしょうか。
この場合、多くの判例では、相続人に、この借家を使用させなければならない差し迫った必要がなく、一方で、内縁の妻(夫)側で、この家屋を明け渡すと家計上相当な打撃を受けるおそれがあれば、相続人が内縁の妻(夫)に対して明渡請求をすることは権利の濫用に当たるとして、明渡請求を認めていません。
つまり、家主の了承が得られれば、いくら相続人が明け渡しを請求しても、残された内縁の妻(夫)が、新たに賃貸借契約を締結することで住み続けることができるということです。
内縁関係・愛人関係の間に生まれた「子ども」の相続権は?
父母が内縁関係であっても愛人関係であっても、子どもは血縁上の母の遺産の相続権をもちます。母と子の関係は、分娩の事実によって証明することができるので、認知のような制度はありません。
一方、父と子の関係は、認知の有無が非常に重要になります。認知されていれば相続権を有します。また、平成25年の民法改正によって、非嫡出子であっても嫡出子と同じ相続分を相続できます。しかし、認知されていない子どもは、父の遺産に対する相続権は認められません。
子どもを認知してもらう方法は?
それでは、認知してもらうには、どのような方法をとればいいのでしょうか。
①認知の届出を出す
最も一般的な方法��は、被相続人による認知の届出です。自分もしくは子の本籍地、あるいは自分の居住地のある市区町村役場に、当該非嫡出子が自分の子どもである届を出します。認知の手続にあたっては、子どもの母親の同意を得る必要はありません。
②遺言認知する
遺言認知とは、被相続人が遺言によって非嫡出子を自分の子であると認知する方法です。遺言認知には必ず遺言執行者がいなければなりません。遺言書で遺言執行者が指定されていない場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることになります。
③調停や裁判
父親が自分の子だと認めてくれない場合には、認知調停を申立てることができます。調停で双方の合意が得られ認知の審判が下されれば審判認知となりますが、調停不成立となった際には訴訟を起こすこともできます。
この場合、裁判所により認知の判決が下されると強制認知となります。
認知されていない子ども(非嫡出子)に遺産を残すには?
認知されていない子どもに遺産を残す手段は、その旨を記載した遺言書以外にありません。遺言書には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、確実に非嫡出子に財産を残したいのであれば、公正証書遺言を選択しましょう。
自筆証書遺言は、誰にも知られることなく、手軽に遺言を残せるというメリットがありますが、一方で、内容に不備があると遺言書自体が無効になるという、大きな欠点があります。
一方、公正証書遺言は、原案こそは被相続人が考えますが、遺言書自体は公証役場の公証人が作成しますので、法的に無効になることはありません。また原本は、公証役場に保管されるので、紛失や盗難のリスクがまったくありません。したがって、公正証書遺言を作成することで、確実に非嫡出子に相続することが可能になるのです。
公正証書遺言の作成に際しては、次のような流れで進めていきます。
- 遺言者が公証役場に赴く
- 公証人が本人確認を行う
- 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝え、公証人がこれを筆記する
- 公証人が遺言者及び証人に遺言を読み聞かせる
- 遺言者及び証人が署名押印をする
- 公証人が署名押印をする
- 公証役場で原本を保管する
- 正本と謄本が遺言者に交付される
口頭で遺言内容を説明するのは、非常に煩雑なため、予め弁護士や司法書士、行政書士に相談をしたうえで、原案をまとめた方がスムーズに進められます。
また証人は2名必要になりますが、相続人や直系尊属は証人になることができません。適切な人物が思い当たらない場合は、有償で公証人の紹介による証人に依頼することもできます。
まとめ
どんなに険悪な関係であっても、婚姻関係にある限りは、相続は確実に行われます。一方で、長年献身的に病気看護をしてきた関係であっても、内縁関係だと、いっさいの相続を受けられないことがあります。
相続人となれるパートナーは、配偶者に限られるために、法的な裏付けのない内縁関係は、相続に関しては、極めて不安定な関係になってしまいます。
何らかの事情で、婚姻関係が選択できないのであれば、公正証書遺言による遺贈が、最も確実に遺産を渡せる方法です。苦労を共にしてきた関係であれば、なおさら確実に遺産をパートナーに残したいと考えるのが、通常の心理です。健康なうちに、ぜひ公正証書遺言をはじめとした確実に遺産を残す方法を検討してみてください。
執筆者:切塗よしを