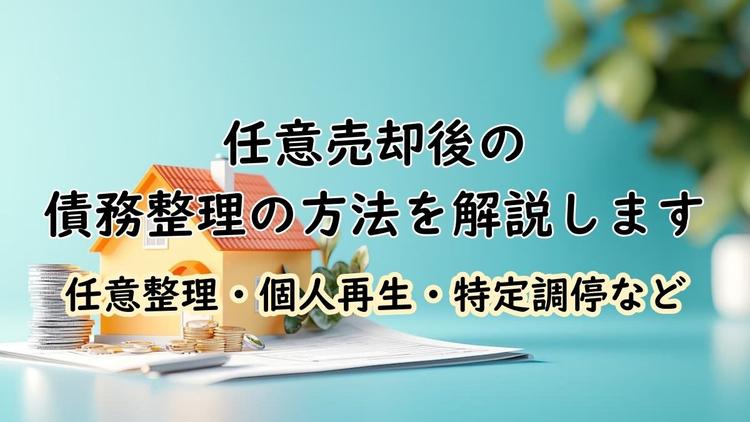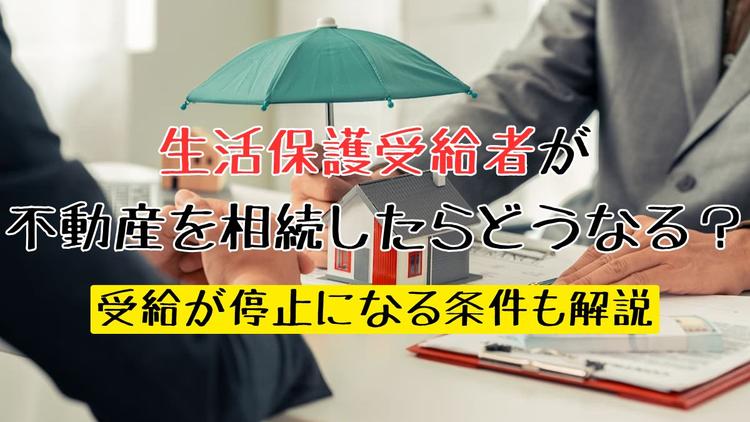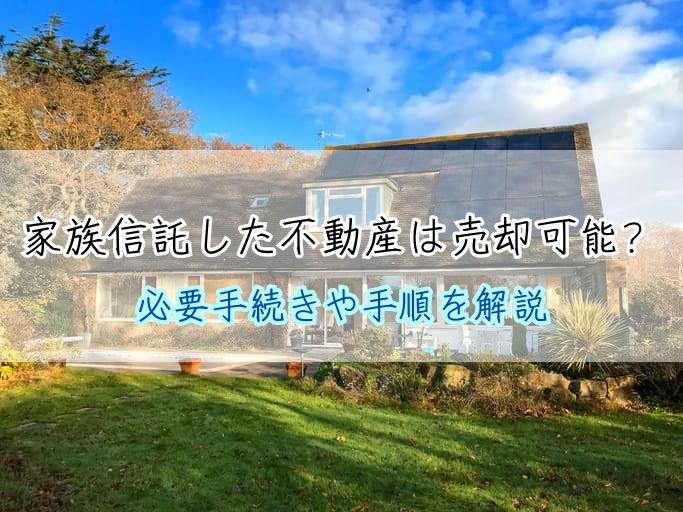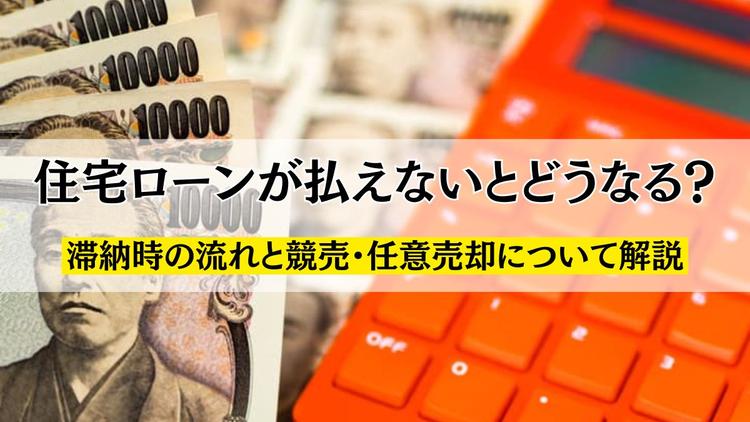「子どもに残す財産は何がいいだろう?」「現金より不動産がお得だろうか?」
そのような疑問をお持ちの方もいるでしょう。
ある程度年齢を重ねると、相続としての資産の残し方を検討する方もいます。
相続させられる資産にはいくつか種類がありますが、それぞれメリット・デメリットがあるので、目的に応じた資産を残すことが大切です。
この記事では、子どもに残すべき資産について種類別のメリット・デメリットや基礎知識、より多く資産を残す方法などを分かりやすく解説します。
子どもに残すべき資産とは?
「自分の死後、子どもが生活に困らないように資産を残してあげたい」という思いは、多くの親が持っているものです。
日本財団の「遺言・遺贈に関する意識・実態把握調査」 では、財産を残したい相手は子どもが54.0%と最も多く、次いで配偶者の42.0%と、ほとんどの方が子ども・配偶者を中心に相続を考えていることが分かります1。
とはいえ、相続が発生した際、子どもが相続できる財産にはさまざまな種類があります。
民法では、相続財産について以下のように明記されています。
(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
相続財産は、形のあるなしに限らずプラスの財産、マイナスの財産すべてが含まれます。
代表的なプラスの財産は以下です。
- 現預金
- 有価証券
- 不動産
- 貴金属・骨とう品・美術品
- ゴルフ会員権や借地権・著作権などの権利
現預金や有価証券・不動産は代表的な相続財産ですが、他にもゴルフ会員権などの形のない権利も相続されます。
また、近年は仮想通貨やFXと言ったデジタル遺産が相続されるケースも増えています。
一方、借金や住宅ローン残債・未払金と言ったマイナスの財産も相続の対象です。
子どもへの相続を考えるなら、マイナスの財産を残さない、もしくはできるだけ小さくすることは前提と言えるでしょう。
そのうえで、プラスの財産として何を残すべきかを検討することが大切です。
「現預金を残しておけば大丈夫」と考える方も多いですが、現金のみの相続が必ずしも適しているとは限りません。
また、単に現金を残すのではなく、自分の死後、子どもの自立を促せるような残し方が理想的でしょう。
なお、自分の死後は葬儀代や相続処理などの費用が発生し、さらに相続のケースによっては相続税も課税され遺族に負担がかかる場合もあります。
死後にかかる費用や税金も考慮して、できるだけ多く子どもの資産を残せるようにしましょう。
子どもに残しておくべき目的別の資産
自分の死後やその直前には、子どもにさまざまな負担がかかります。
ここでは、子どもに残しておくべき資産を目的別にいくつか紹介します。
教育資金
子どもがまだ小さい場合、残された家族は教育資金が大きな課題になります。
日本政策金融公庫の調査によると、幼稚園から大学まですべて公立に通う場合で約822.5万円、すべて私立なら2307.5万円の教育資金が必要です2。
さらに、習い事や塾の費用なども考えると、公立でも1,000万円以上はかかってくると考えられます。
進学先によっては教育資金がかなり大きくなるため、不足が生じると子どもの選択肢は狭まる恐れがあります。
教育資金を子どものために残しておくことで、子どもの将来を守ることにつながるでしょう。
また、子どもがすでに成人している場合でも、子どもの子ども(孫)のための教育資金を残すというのも1つの選択肢です。
介護費用
親が高齢になり介護が必要になると、子どもは金銭的な負担も大きくなります。
生命保険文化センターの調査によると、介護に要した費用は一時的な費用で47.2万円、月々の費用で9.0万円です3。
さらに、施設に入所する場合は、毎月の費用が13.8万円と大きくなります。
同調査では、介護期間の平均が4年7カ月となっているため、毎月9万円かかると月額の費用だけで495万円必要です。
両親二人とも介護が必要になると、子どもの負担は1,000万円以上になる可能性があります。
介護が始まると、子どもは体力的・精神的な負担に加えて金銭的な負担も抱えることになります。
そのため、介護費用については、できる限り子どもに負担をかけないよう準備しておくことが望ましいでしょう。
冠婚葬祭費用
自分の死後の葬儀やお墓に関する費用、子どもの結婚資金も残しておきたいお金に挙げられます。
鎌倉新書「お葬式に関する全国調査」 によると、葬儀費用の総額は118.5万円です4。
最も安い直葬(火葬のみの葬儀)でも42.8万円かかっています。
同社の「お墓の消費者全国実態調査」 では、お��墓の購入平均額は一般墓で155.7万円、納骨堂で79.3万円という結果が出ています5。
葬儀に関する費用をあらかじめ用意しておくことで、子どもの金銭的な負担を軽減できるでしょう。
また、子どもが未婚の場合、これからの結婚資金を用意しておくのもおすすめです。
結婚式や新婚旅行の費用は高額になりやすく、親からの援助がなければ諦めざるを得ないケースも少なくありません。
あらかじめ結婚資金を用意しておくことで、子どもの希望を叶えやすくなり、満足いく新婚生活のスタートを切れるでしょう。
子どもに残す資産の種類別メリット・デメリット
子どもに残す資産は、種類によってメリット・デメリットが異なるので、デメリットまで理解しておくことが重要です。
ここでは、代表的な資産の種類ごとのメリット・デメリットを解説します。
現金
タンス預金や預貯金などの現金資産は、相続財産として代表的です。
現金資産は、相続人がすぐに利用できるだけでなく、子どもが複数人いる場合でも公平に分割できるというメリットがあります。
現金を残すデメリット
しかし、現金資産には以下のようなデメリットもあります。
- 相続税の負��担が大きくなりやすい
- インフレの影響を受けやすい
現金資産は額面どおりの金額が相続税の対象となり、不動産のように評価額を下げる特例がないため、金額が大きくなると相続税の負担も大きくなる恐れがあります。
不動産での相続との違い
不動産で相続した場合は、
- 相続税評価額(相続税路線価の用いた不動産の価値指標)は、時価の70〜80%程度となるのが一般的
- 「小規模宅地等の特例」を適用すれば、条件を満たす自宅の土地であれば最大80%の評価減が可能
といった理由で、時価(実際に売買される価格)よりも相続時の評価額は低くなるのが一般的です。
同じ1億円相当の財産でも、現金で1億円を保有している場合はそのまま1億円が評価額となりますが、不動産であれば評価額が7,000万円前後になり、特例が使えればさらに課税対象額を抑えられる可能性があるのです。
そのため、現金資産が多すぎると、節税の余地が少なく、相続税が高額になりやすいというわけです。
さらに、インフレが進むとお金の価値が下がる点にも注意が必要です。
なお、子どものために預貯金を残す場合、子ども名義の口座を開設するよりも、自分名義の口座で蓄えることをおすすめします。
子ども名義の口座であっても、実際の所有者と名義人が異なる「名義預金」とみなされれば、相続税の対象になるからです。
また、名義預金は子どもがその存在を把握していないと、相続税の申告漏れにつながり、ペナルティが科せられる恐れがあるので注意しましょう。
不動産
実家や投資用物件など、不動産を相続させるケースも多くあります。
不動産であれば、相続後に子どもが住む・賃貸に出して賃料を得る・売却して現金を得るなど、活用の幅が広いというメリットがあります。
また、不動産は時価ではなく「相続税評価額」が相続税の対象となり、相続税評価額は時価の7~8割ほどに下がるので、現金の相続より相続税の負担が抑えられる点もメリットです。
しかし、不動産の相続では以下のようなデメリットも生じやすくなります。
- 分割でトラブルになる
- 活用できるとは限らない
- 維持管理費がかかる
不動産は現金のように公平に分割できないため、子どもが複数人いると分割方法で揉めやすくなります。
さらに、築年数が古い実家などでは、住まないけど売却もできないなどで活用に困る状況になるケースも珍しくありません。
仮に、そのまま所有するにしても、固定資産税や維持管理費などのコストや手間がかかるため、相続させることで子どもの負担となる場合があります。
▼関連記事:小規模宅地等の特例で相続税が抑えられる!適用要件、手続きの流れを解説します
有価証券
株式や債券・小切手などの有価証券で資産を残す方法もあります。
三菱UFJフィナンシャルグループ「親子の居住地・地域による資産承継の傾向」 の調査によると、相続した財産額の内訳として有価証券は12.1%と、不動産(48.1%)・現預金(38.6%)に次いで割合が大きくなります6。
有価証券は不動産よりも流動性が高く、公平な分割もしやすい資産です。
また、銘柄によっては相続後に資産が増える可能性もあるでしょう。
しかし、有価証券の相続には以下のようなデメリットもあります。
- 相続税の計算や相続手続きが複雑になりやすい
- 値下がりにより資産が減少するリスクがある
子どもに有価証券の知識がなければ、名義変更や現金化などの手続きで困る恐れがあります。
さらに、有価証券は日々価格が変動するので、場合によっては資産になるどころか損失が生じるケースもあるでしょう。
相続税の計算も現金より複雑になりやすいので、注意が必要です。
貴金属
金や銀・宝石などの貴金属で相続させる方法もあります。
貴金属で相続させれば、相続時に特別な手続きが必要なく、さらに売却して現金化するのも比較的簡単です。
また、貴金属は時価評価額5万円以下であれば相続税の対象にならない点もメリットでしょう。
一方、貴金属の相続では以下のようなデメリットもあります。
- 分割しにくい
- 現金化しないと活用しにくい
1つの貴金属を複数の子どもで分割はできません。
仮に、複数貴金属がある場合でも、だれが・どれを相続するかで揉める恐れがあるでしょう。
貴金属�を相続してもそのままの状態では、形見としてそのまま使う以外の使い道はありません。
各種費用の支払いなどで活用するには、売却して現金化する必要があるので、活用に手間がかかる点には注意しましょう。
子どもに資産を残すために押さえておきたい基礎知識
ここでは、子どもに資産を残すために押さえておきたい基礎知識として以下の2つを解説します。
- 相続時に財産額に応じて税金がかかる
- 贈与すると贈与額に応じて贈与税がかかる
それぞれ見ていきましょう。
相続時に財産額に応じて税金がかかる
子どもが資産を相続する場合、相続財産によっては相続税が課税されます。
相続税は、以下の基礎控除を超えた部分が税金の対象です。
たとえば、相続人が子ども2人の場合、3,000万円+600万円×2人=4,200万円が基礎控除額です。
この時、相続財産が6,000万円であれば、6,000万円-4,200万円=1,800万円が相続税の対象となります。
また、相続税は原則現金納付となり、納税期限は相続開始から10ヵ月という点にも注意が必要です。
相続財産が不動産、有価証券、貴金属で、現預金がない状態で相続税が課税された場合、期限内に現金化するか相続人の自己資金で対応する必要があります。
相続税が課税されると、受け取れる財産が少なくなるだけでなく、子どもの負担になる恐れがあります。
課税額を確認し、相続税分の現預金を用意する、節税対策を講じるなど、子どもの相続税の負�担を軽減できるようにしておくとよいでしょう。
贈与すると贈与額に応じて贈与税がかかる
子どもへの資産の残し方としては、相続だけでなく生前贈与という方法もあります。
生前贈与とは、生きているうちに財産を子どもなどに無償譲渡する方法です。
生前贈与には以下のメリットがあります。
- 確実に渡したい相手に財産を譲れる
- 相続人以外にも財産を譲れる
- 相続財産が減少でき相続税対策になる
生前中に贈与するので、希望の相手にきちんと贈与できるだけでなく、目的に合った使い方をしているかの確認もできます。
また、生前贈与することで相続時の財産が減少するため、相続税対策としても有効です。
しかし、生前贈与は贈与額が贈与税の対象となる点に注意しなければなりません。
贈与税は、年間の贈与額が基礎控除110万円を超えた部分に課税されます。
さらに、贈与税は相続税の税率よりも高いため、まとまった贈与を行うと贈られた側の税負担が大きくなる恐れがあります。
ただし、贈与税には「相続時精算課税」や「住宅取得等資金の贈与税の非課税特例」「教育資金一括贈与の非課税特例」など、節税が期待できる制度がいくつか用意されています。
制度の活用も検討しつつ、相続税との比較を行い、適切な贈与方法を選択できるようにしましょう。
贈与税と相続税について不安がある場合は、税理士に相談しアドバイスをもらいながら判断することをおすすめします。
子どもにできるだけ多くお金を残す方法
ここでは、子どもにでき��るだけ多くお金を残す方法として以下の5つを紹介します。
- 学資保険を活用する
- NISAを活用する
- 暦年贈与を活用する
- 生命保険の非課税枠を活用する
- 不動産を相続させる
それぞれ見ていきましょう。
学資保険を活用する
学資保険とは、子どもの教育資金の確保を目的とした貯蓄型の保険です。
毎月保険料を支払うことで、入学時などのタイミングでまとまった学資金を受け取れます。
支払った保険料は保険会社が運用するため、支払額よりも多く受け取れる可能性がある点も大きなメリットでしょう。
学資保険であれば、預貯金より利回りが高く、より多くのお金を残せる可能性があります。
また、学資保険は一般的に契約者(親)が死亡すると、以降の保険料の支払いは免除されつつ、満期に学資金を受け取ることが可能です。
教育費目的で資産を残すなら、学資保険も組み合わせることでより安定してお金を残しやすくなるでしょう。
NISAを活用する
NISAとは、国による投資の税制優遇制度です。
通常、上場株式や上場投資信託への投資は利益に対して20.315%の税金がかかりますが、NISAであれば一定額が非課税になります。
NISAであれば、預貯金や学資保険より高い利回りで運用できるため、より多くの資産を残せる可能性があります。
たとえば、ゆうちょ銀行の場合5年の定期貯金で金利は0.400% です7。
仮に、100万円を0.400%で運用すると、1年後には100.4万円になります。
一方、投資信託の利回りは一般的に3~10%となるので、100万円を3%で運用すれば1年後には103万円受け取ることが可能です。
さらに、NISAであれば利益部分の3万円が非課税になります。
NISAで活用し長期で投資することで、より多くの資産を子どもに残せる可能性があるでしょう。
ただし、NISAも投資である以上、景気の悪化などで元本割れのリスクがある点には注意が必要です。
暦年贈与を活用する
暦年贈与とは、贈与税の課税方法の1つです。
暦年贈与では、1月1日から12月31日までの贈与額の合計から基礎控除110万円を引いた部分に贈与税が課税されます。
そのため、贈与額を年間110万円以内に納めれば、受け取った相手は贈与税が課税されません。
子どもに複数年にわけて贈与を行うことで、まとまった資金を残しやすくなるでしょう。
ただし、毎年一定額を贈与すると定期贈与とみなされ、贈与税が課税される恐れがあります。
定期贈与とは、年間100万円を10年間に渡り贈与するといった形式の贈与契約です。
この場合、1,000万円の贈与があったとして最初の年に1,000万円-110万円の890万円が贈与税の対象となる恐れがあります。
定期贈与にならないためには、毎年贈与契約書を作成する、贈与額や時期をずらすなどが検討できますが、税務署によって判断が異なるので税理士に相談することをおすすめします。
なお、贈与であっても相続開始前7年以内の贈与は、相続税の対象です8。
高齢になってから生前贈与すると、相続税が課税される恐れがある点にも注意しましょう。
生命保険の非課税枠を活用する
親が死亡したことで受け取れる生命保険金は、相続税の対象です。
しかし、法定相続人が受けとる生命保険金には、以下の非課税枠が適用されます。
生命保険金の非課税枠:500万円×法定相続人の人数
たとえば、生命保険金が2,000万円で相続人が子ども3名の場合、非課税枠は1,500万円となるので、2,000万円-1,500万円=500万円を相続財産として加算します。
さらに、相続財産に加算後は相続税の基礎控除も適用されるので、相続税を抑えることが可能です。
また、生命保険金は受取人固有の財産とみなさるため、相続税は課税されますが遺産分割の対象とはなりません。
子どもを受取人にしておくことで、相続財産とは別に子どものお金を残しつつ相続税対策にもなるので、活用を検討するとよいでしょう。
不動産を相続させる
不動産は相続税の対象ですが、時価ではなく相続税評価額で判断されます。
相続税評価額は時価の7~8割ほどになるので、現金で相続するよりも相続税を抑えやすくなります。
たとえば、1億円を相続させる場合、現金1億円なら1億円がそのまま相続税の対象です。
一方、時価1億円の不動産では相続税評価額である7,000~8,000万円が相続税の対象となるため、評価額が下がった分課税額も少なくなります。
ただし、相続財産が不動産ばかりになると、課税された際に相続人が自己資金で相続税を支払う必要が出てきます。
また、不動産は分割しにくいことから、子どもが複数人いると分割で揉めやすい点にも注意が必要です。
相続税の納税資金がない、遺産分割でトラブルになりそうな場合は、不動産を事前に売却し、現金化して相続した方がトラブルを避けやすくなるでしょう。
▼関連記事:相続対策で不動産を購入するのはデメリットが多い?相続対策の基礎知識を解説
子どもに残す資産に関するよくある質問
最後に、子どもに残す資産に関するよくある質問をみていきましょう。
子どもに残すお金の平均額は?
三菱UFJフィナンシャルグループの「親子の居住地・地域による資産承継の傾向」によると、子どもが親から相続した財産の平均額は3,273万円です9。
内訳としては、現預金が1,264万円、不動産が1,575万円、有価証券が396万円、その他資産で211万円、借入などマイナスの資産が174万円となります。
なお、相続財産に占める不動産の割合が高いことから、親子共に都市部に居住するケースで相続財産は高くなる傾向があります。
ただし、中央値は1,600万円であることから、個々のケースによって残すお金の額は大きく異なる点には注意しましょう。
子どもに残すお金がない場合はどうすればいい?
子どもにどうしても残したいなら、生命保険や不動産売却を検討するといった方法はありますが、必ずしもお金を残す必要はありません。
金融広告中央委員会に掲載されたデータによると、「将来の遺産をどのようにしたいか」というアンケートが行わ��れました。その中で、「こどもはいるが、自分たちの人生を楽しみたいので、財産を使い切りたい(使い切れずに財産を残すことはある)」と答えたのは18.2%と、少なくありません10。
また、「自分たちの財産をこどもが当てにして働かなくなるといけないので、困ってい
る人や社会・公共の役に立つような使い道を考えていきたい。」も2.2%です。
子どもにお金を残すのが適しているかは、個々のケースや考え方にもよってきます。
まずは、家族で話し合って、将来や相続のお金について家族の認識を統一させていくとよいでしょう。
子どもにお金を残してはいけないといわれる理由とは?
子どもに必要以上のお金を残すと、分割で揉める、お金を充てにして自立しないなどのトラブルが生じるケースがあることから、残してはいけないといわれる場合があります。
お金を残す・残さないに正解はなく、家庭によって適切な方法は異なるものです。
仮に、残す場合でも子どもと話し合い自立を促せるような残し方をすることで、子どものためになる残し方ができるでしょう。
まとめ
子どもに残す資産としては、現預金や不動産・有価証券などがあります。
現預金や有価証券は、不動産に比べ流動性が高く活用しやすい半面、インフレリスクや値下がり、相続税の負担が多くなるなどのデメリットがあります。
一方、不動産は活用の幅が大きく相続税対策として有効ですが、活用しにくい不動産は反対に子どもの負担となる恐れがあるので注意しましょう。
相続の目的やメリット・デメリットを踏まえて、どのように資産を残したらいいかまずは家族と話し合ってみるとよいでしょう。
将来子どもが住む予定がないという場合は、不動産で相続させるより売却して現金化した方が喜ばれる可能性があります。
売却を検討しているなら、相続に詳しい信頼できる不動産会社に相談すると、満足いく相続の仕方が実現しやすくなるでしょう。