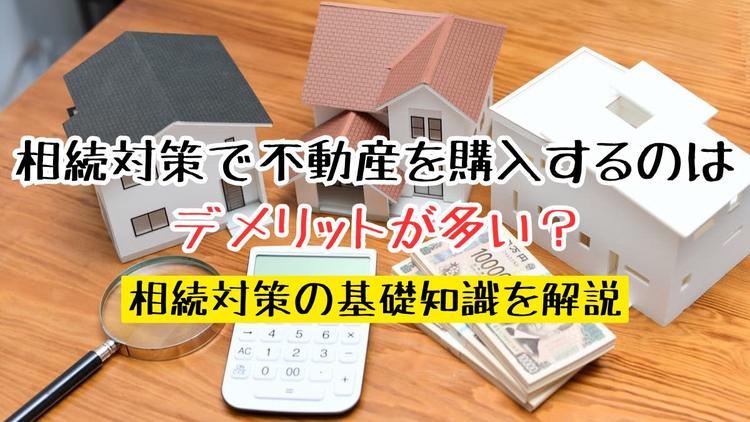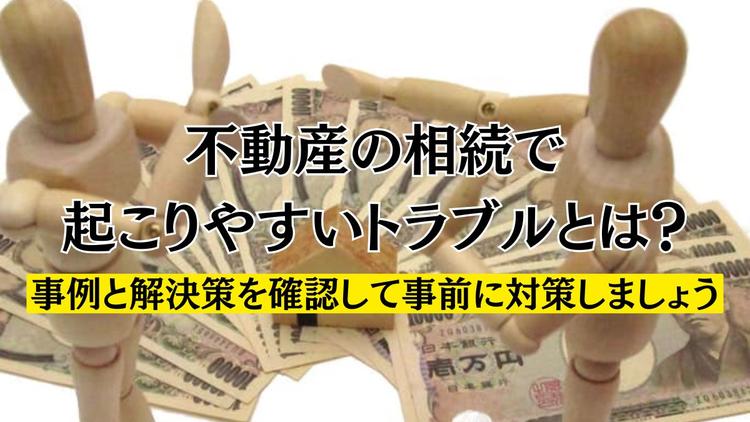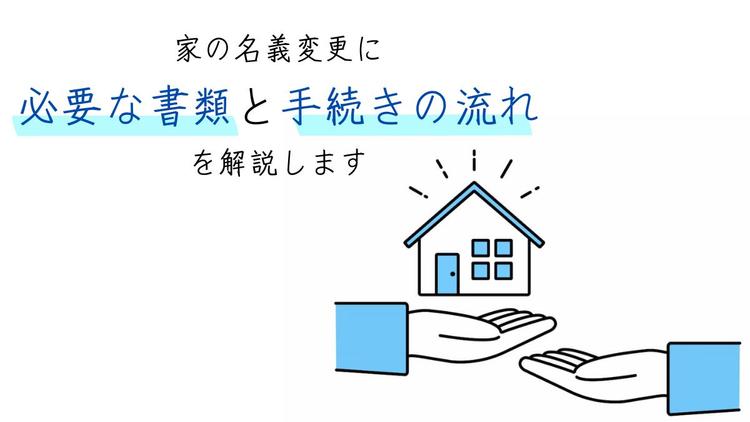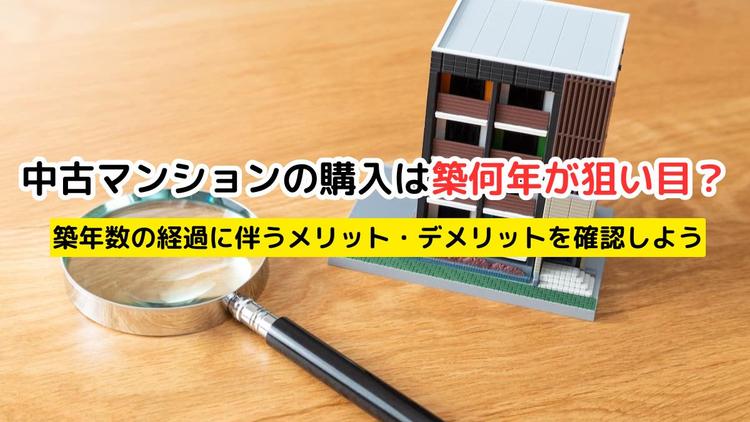「相続対策として不動産を購入するといい」という話を耳にした方もいるでしょう。
確かに、不動産の購入は相続対策として有効な手段です。
しかし、すべての相続で有効なわけではなく、不動産があることでむしろトラブルになるケースもあります。
相続対策として不動産の購入を検討する際には、デメリットまで理解したうえで相続状況に合わせて慎重な判断が重要です。
この記事では、相続対策として不動産を購入する理由やデメリット、不動産のある相続でのトラブルなどを分かりやすく解説します。
不動産で相続対策できる理由
相続財産を現金ではなく不動産にすれば、相続税の節税効果が生じます。
そのことから、不動産はしばしば相続税対策として活用されているのです。
ここでは、不動産が相続税節税につながる理由を見ていきましょう。
相続税評価額は時価より低く算出される
相続税は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた、正味の財産が基礎控除を超えると課税されます。
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
たとえば、相続人が3人のとき基礎控除は4,800万円になります。
このとき、正味の財産が6,000万円であれば6,000万円-4,800万円=1,200万円が相続税の対象となるのです。
プラスの財産には現預金だけでなく、有価証券や貴金属、不動産などが該当します。
これらの財産の評価額を合算した額が、プラスの財産の総額になります。
この際、現金は額面金額が評価額ですが、不動産は時価(市場価格)ではなく相続税評価額が対象です。
不動産の相続税評価額は大まかに以下のように計算します。
- 土地の評価額:相続税路線価×補正率×土地面積 または固定資産税評価額×倍率
- 建物の評価額:固定資産税評価額
計算の際に使用する相続税路線価は公示地価の8割ほど、固定資産税評価額は7割ほどが目安です。
相続税評価額は主に相続税路線価を基に計算される。路線価が無い地域の場合は倍率方式で算出される。
建物部分の相続税評価額は固定資産税評価額で算出される。
ちなみに、実際価格(実際に取引のあった価格)は公示地価の1.1~1.2倍が目安となります。
また、路線価は1年に1回、固定資産税評価額は3年に1回しか評価替えが行われません。
つまり、不動産の相続税評価額は時価よりも7~8割ほど評価額が下がるのです。
そのため、同じ1億円の相続であっても、現金であれば1億円そのままが相続税の対象となるのに対し、時価1億円の不動産なら7,000~8,000万円が相続税の対象というように、対象額が大きく異なってきます。
相続税の対象となる額が大きく異なることから、現金よりも不動産で相続したほうが相続税の節税効果が見込めるのです。
賃貸に出していると評価額が低くなる
賃貸に出している不動産は、自分の不動産であっても自由に活用できません。
活用に制限が出ることから、賃貸していない不動産よりも評価額が下がるという特徴があるのです。
たとえば、土地を貸している場合の評価額は以下の計算で求めます。
借地権割合とは、土地に占める借地権の割合を指し、国税庁によって30~90%で定められています。
仮に、相続税評価額が1,000万円の土地で借地権割合が60%なら、貸宅地としての評価額は1,000万円×(1-60%)=400万円まで下がるのです。
また、土地にアパートやマンションを建築して貸し出している場合も、土地・建物の評価額は以下のように下がります。
- 土地部分:路線価による土地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
- 建物部分:固定資産税評価額×(1-借家権割合)×賃貸割合
借家権割合とは、評価額に占める借家権の割合で全国一律30%に定められています。
賃貸割合は、床面積に対する賃貸部分の割合であり、たとえば10室のうち7室が賃貸中なら賃貸割合は70%です。
以下の条件で計算してみましょう。
- 更地としての土地の相続税評価額:1,500万円
- 建物の固定資産税評価額:2,500万円
- 借地権割合:70%
- 借家権割合:30%
- 賃貸割合:80%
上記から、以下のように計算できます。
- 土地の相続税評価額:1,500万円×(1-70%×30%×80%)=1,248万円
- 建物の相続税評価額:2,500万円×(1-30%)×80%=1,400万円
賃貸していない場合では相続税評価額は1,500万円+2,500万円=4,000万円なのに対して、賃貸としての評価額は2,648万円と大きく下がります。
このように、賃貸している不動産は相続税の対象となる評価額が少なくなるので、相続税軽減効果がより高くなるのです。
条件を満たすと税制優遇を受けられる
相続税の評価額を計算する際、土地は「小規模宅地等の特例」を適用することで、より評価額を下げることが可能です1。
小規模宅地等の特例では、土地の活用法に応じて以下のように評価額が軽減されます。
| 宅地等の利用区分 | 限度面積 | 軽減される割合 |
| 被相続人の居住の用に供されていた宅地等 | 330㎡ | 80% |
| 貸付事業用の宅地等 | 200㎡ | 50% |
| 賃貸事業以外の事業用の宅地等 | 400㎡ | 80% |
被相続人の居住するための宅地であれば、330㎡までの部分で評価額が80%軽減されます。
アパートやマンションなど貸付事業を行っている場合でも、200㎡の部分まで50%の軽減が適用されるため、評価額の大きな軽減ができ節税につながるのです。
ただし、特例を適用するには、居住用宅地の場合は相続人が配偶者か同居している親族であるなど、一定の要件を満たす必要がある点に注意しましょう。
ローンを活用することで節税効果を期待できる
不動産を住宅ローン控除や不動産投資ローンを組んで購入している場合、ローン残債はマイナスの財産として相続財産から控除できます。
たとえば、不動産の相続税評価額が5,000万円でローン残債が4,000万円であれば、相続税の対象額は5,000万円-4,000万円=1,000万円です。
このように、ローン残債があることで、相続税の対象額が少なくなり節税効果が期待できます。
ただし、被相続人が団体信用生命保険(団信)に加入しており、保険金でローン残債が完済される場合は残債が0円となるため、相続財産からローン残債を引けないので注意しましょう。
不動産で相続対策するデメリット
相続税対策として有効な不動産ですが、不動産が相続財産にあることにはデメリットもあるので、デメリットを理解してくことが大切です。
不動産で相続対策するデメリットとしては、以下の4つが挙げられます。
- 相続時に納税資金を現金で用意する必要がある
- 相続後にうまく活用できない可能性がある
- 相続後に売却できない可能性がある
- 活用・売却できないと維持管理の負担が大きい
それぞれ見ていきましょう。
相続時に納税資金を現金で用意する必要がある
相続財産が不動産と現預金わずかというケースで、相続税が課税されると相続財産から相続税を支払えなくなります。
たとえば、相続人が子ども2人で相続財産が不動産6,000万円だけというケースで見てみましょう。
基礎控除は4,200万円なので、基礎控除を超えた部分1,800万円が相続税の対象です。
相続税は、相続人や控除の適用などで額が異なりますが、この場合の相続税は180万円となります。
しかし、相続財産に現預金がないので、相続人は自己資金で相続税を支払う必要があるのです。
相続税に対応できない場合、物納制度を利用することもできますが利用は容易ではなく、基本的に現金が必要になります。
物納とは、相続税を不動産や有価証券などの相続財産で納める制度です。
申請しても必ず認められるわけではなく、管理状況や権利関係が複雑な不動産は、物納不適格と判断されることもあることから、利用が難しいケースもあります。
一般的な家庭の相続では、相続財産が実家と現預金わずかというケースも少なくないので、相続税に対応できるかは事前にチェックしておくことが重要です。
相続後にうまく活用できない可能性がある
相続前に賃貸などの不動産投資として活用していた不動産を、相続人が相続後にも順調に経営できるとは限りません。
不動産投資を成功させるには、あり程度の知識やノウハウが必要となり、生前中に投資に関わっていない相続人がいきなり経営に関わっても失敗するリスクが高くなるでしょう。
賃貸物件を相続させ経営がうまく軌道に乗れば、相続人は賃料収入を得られ被相続人が亡くなった後の収入源を確保できます。
一方、相続人がうまく活用できず経営が赤字になると、相続人の大きな負担となる恐れがあるので注意しましょう。
相続後に売却できない可能性がある
相続した不動産を相続人が売却しようとしても、なかなか売却できずに苦労するケースもあります。
人気エリアで需要の高い不動産ならスムーズな売却も期待できますが、築年数が古く立地が悪いなどの不動産では買い手は見つかりにくいものです��。
とくに、相続税納税は売却金で賄おうと考えていると、売却がスムーズにできずに資金難になる恐れがあります。
活用・売却できないと維持管理の負担が大きい
相続人が不動産を活用する予定がなく、さらに売却も難しいとなると、相続人の負担が大きくなるので注意しましょう。
たとえば、空き家として所有し続けるとしても所有期間中は毎年固定資産税が課税されます。
たとえローンを完済したとしても、火災保険料に加え、マンションの場合は毎月の修繕積立金や管理費などの費用がかかります。
さらに、空き家の管理のための手間や時間・費用も必要です。
これらの維持管理の負担に、相続人が対応できるか考慮しておく必要があります。
不動産は、ただ所有するだけでは費用や手間の負担が大きい財産という点は覚えておきましょう。
不動産で相続対策するメリット
不動産で相続対策するメリットとしては以下の3つが挙げられます。
- 相続税の大幅な節税を期待できる
- 相続後に家賃収入を得られる
- 早めに生前贈与することで家賃収入で相続税のための貯金を貯められる
それぞれ見ていきましょう。
相続税の大幅な節税を期待できる
前述のとおり、不動産は現金を相続させるよりも相続税の節税効果が高くなります。
とくに、立地が良いなど時価の高い不動産ほど節税効果は大きくなるでしょう。
相続財産が高額になり相続税納税資金も確保しているなら、不動産の所有は相続税対策としては有効です。
ただし、節税効果を得られるかどうかは、相続時の状況によって異なるので気になる方は税理士に相談するとよいでしょう。
相続後に家賃収入を得られる
賃貸物件を相続すれば、相続人は相続後に家賃収入を得られます。
一家の大黒柱を亡くした、収入源が年金のみという中で、毎月家賃収入を得られるのは生活費の大きな助けになるでしょう。
自分の死後も残された家族の収入源を確保できるのは、大きなメリットと言えます。
早めに生前贈与することで家賃収入で相続税のための資金を貯められる
不動産を相続させるのではなく、生前贈与して不動産対策することも可能です。
被相続人が賃料を受け取り蓄えていた場合、相続時には賃貸物件だけでなく賃料で蓄えた現金も相続財産に加わります。
一方、賃貸物件を生前贈与させておくことで、相続財産から賃貸物件が除外されるだけでなく、賃料によって現金が増えること�も避けられるのです。
また、生前贈与された人は賃料収入を得られるので、生活費として活用するだけでなく相続税納税の資金にもできます。
ただし、生前贈与は贈与税の対象となるので、相続税だけでなく贈与税も考慮しての検討が大切です。
不動産の相続対策でよくあるトラブル
不動産が相続財産に含まれることで相続トラブルに発展するケースも多くあります。
ここでは、代表的な相続時のトラブルをみていきましょう。
1人に資産の配分が集中してしまう
不動産は、現金のようにきっちり分割できません。
相続人と相続財産の状況によっては、分割方法でトラブルになりやすいので注意が必要です。
たとえば、相続人が子ども2人で相続財産が不動産3,000万円と現金1,000万円の場合、それぞれ2,000万円ずつ相続できます。
このとき、1人が不動産を丸ごと相続すると残りの1人は現預金1,000万円をすべて相続したとしても、分割の偏りが生じるのです。
この場合、不動産を相続した方が相続しなかった方に代償金として1,000万円を支払う方法もありますが、相続人に資金力がなければ難しいでしょう。
不動産を共有持分にして将来活用しにくくなってしまう
不動産の相続方法としては、相続人全員で共有することも可能です。
共有であれば、分割方法でトラブルになることを避けられます。
しかし、不動産の共有は後々トラブルになりやすいのであまりおすすめできません。
共有不動産は売却や増改築するには、共有者全員の合意が必要です。
仮に、将来売却したいとなっても、誰か1人でも反対する人がいると売却できなくなってしまいます。
また、共有のまま次の相続が発生すると、持分が共有者の相続人に相続されます。
相続を数代繰り返すと、共有者が膨れ上がり権利関係が複雑になる恐れがあるので注意しましょう。
不動産の相続対策でトラブルにならないための対処法
不動産の相続対策でトラブルにならないためには、以下の対処法を意識することも大切です。
- 遺言書を作成しておく
- できれば不動産を共有しない
- 不動産を売却して相続人に均等に配分する
それぞれ見ていきましょう。
遺言書を作成しておく
不動産は、だれが相続するかで揉めやすい財産です。
遺言書のない相続では相続人全員で遺産分割協議を行って話し合いで分割方法を決めますが、相続人間で意見の対立が起きるとトラブルになります。
遺言書があれば遺産分割協議は必要なくなるので、無用な相続トラブルを避けやすくなるでしょう。
ただし、遺言書で不公平な内容を残していたり、遺言書の形式を満たさずに無効となると別の相続トラブルに発展しかねません。
遺言書を検討する場合は、弁護士などの専門家に相談しながら作成するとよいでしょう。
できれば不動産を共有しない
先述のとおり、相続人が不動産を共有すると売却や次の相続時などで問��題になりやすいです。
被相続人としては遺言書で共有しないように対策しておく他、不動産以外にも相続できる財産を残すなどが検討できるでしょう。
相続する側も、遺言書がなくても共有にならないように話し合っていくことが大切です。
不動産を売却して相続人に均等に配分する
不動産相続のトラブルを避けるには、売却してしまうのも1つの方法です。
売却すれば売却金を相続人で公平に分割でき、かつ維持管理の負担も解消できるので円満な相続を目指しやすくなるでしょう。
相続税の納税資金がない場合も、売却することで納税資金を用意できます。
ただし、相続税の納税期限は10ヵ月という期限があるので、早めに売却に動くことが大切です。
また、相続前に売却すれば、売却金は被相続人の老後資金などとして活用できます。
現金として相続させると相続税の負担が増える恐れもありますが、生前中に老後資金などで減らしておく、現金を生前贈与するなどで対策も可能です。
まとめ
不動産は現金よりも評価額が下がるため相続税節税効果が期待でき、相続対策として有効です。
しかし、不動産が相続財産に含まれると、相続税納税資金が用意できない・分割方法で揉めるなどのデメリットもあるので注意しましょう。
不動産が相続対策として有効かは相続の状況によっても異なるので、税理士などプロのアドバイスを得ながら適切な方法を検討することが大切です。
また、不動産が相続財産にある場合は売却してしまうのも、1つの方法です。
信頼できる不動産会社と相談しながら適切な売却判断ができるようにしましょう。