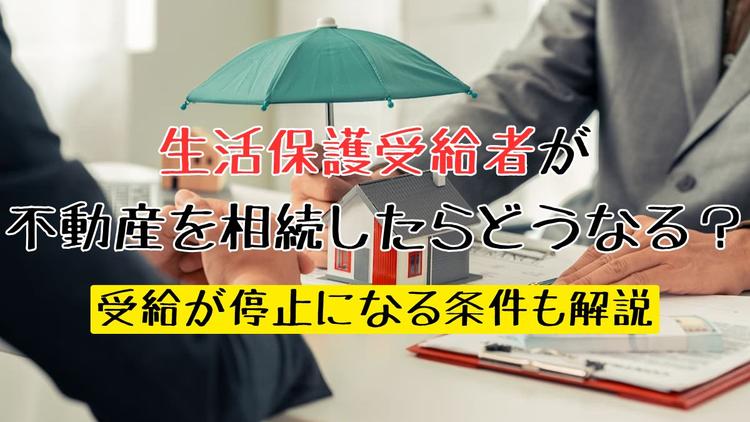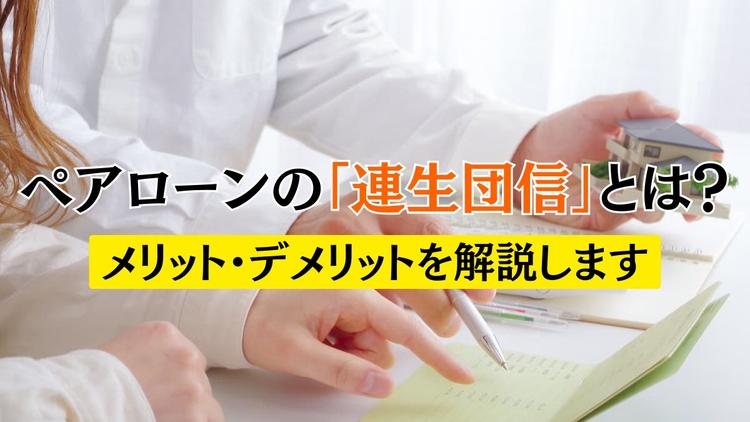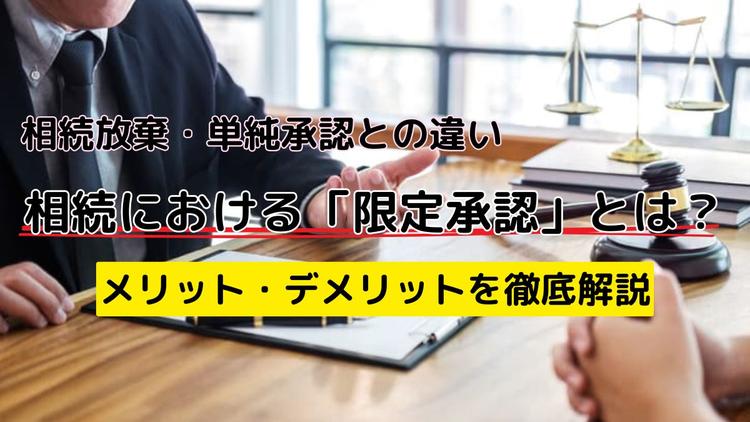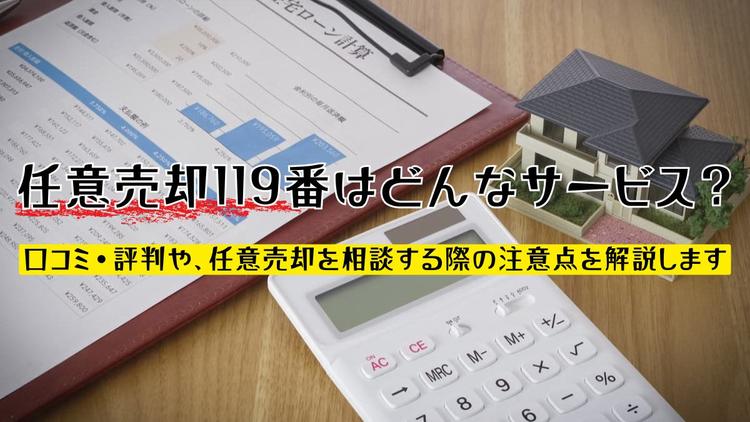生活保護制度は、資産や収入のない人に最低限の生活を保障する制度であり、原則として「資産がある人」は受給できません。
それでは、もし生活保護を受けている方が不動産を相続すると、どのような影響があるのでしょうか?
状況によっては、不動産を相続したことで生活保護の継続が困難になる可能性もあるのです。
この記事では、生活保護受給者が不動産を相続した際の取り扱いや、受給停止になる条件、例外的なケース、そして相続後の対応について解説します。
生活保護における資産の考え方
生活保護制度においては、「資産の有無」が受給可否を左右する、非常に重要な判断基準となります。
ここでいう資産とは、生活費に充てることができる経済的な財産全般のことです。
生活保護法では「資産の活用義務」を基本原則として掲げており、現金・預貯金・不動産・動産を含むあらゆる資産について、まずは生活のために最大限活用することが求められます。
現金・預貯金だけでなく不動産も資産
生活保護法で資産と見なされる対象は多岐にわたりますが、代表的なものとしては以下のようなものが挙げられます。
- 現金や預貯金
- 土地や建物といった不動産
- 自動車や貴金属などの動産
- 有価証券や保険の解約返戻金
特に不動産は、保有しているだけで相応の資産価値があるとされるため、生活保護を受ける際にはその取扱いに注意が必要です。
使用していない土地や建物を所有している場合、売却や賃貸によって生活費を得ることが可能であると判断される可能性があります。
不動産は「活用」が前提となる
生活保護法第4条では「能力、資産その他すべてのものを、その最低限度の生活の維持のために活用しなければならない」と明記されています。
つまり、申請者が資産を有しているにもかかわらず、それを活用せずに保護を申請した場合、制度の趣旨に反するものとされ、却下や受給停止の対象となるのです。
不動産を相続した場合も例外ではなく、たとえ居住していない空き家であっても、売却可能であれば資産と見なされ、生活保護の受給停止・廃止理由となることがあります。
一方で、居住用として実際に使用している不動産については、一定の条件を満たすことで「保有が認められる資産」となることもあるのです。
このように、生活保護における資産の考え方は単なる所有の有無だけでなく、その資産をどのように活用しているか、または活用できるかという視点から判断される点に注意が必要です。
相続した不動産の種類と取り扱い
相続によって取得する不動産と一口に言っても、その種類や状況によって生活保護制度上の取り扱いは大きく異なります。
ここでは、代表的な不動産の種類ごとに、生活保護に与える影響と対応の考え方を整理しておきましょう。
居住用不動産(被相続人と同居していた場合など)
相続した不動産が現在の居住地であり、かつ申請者が引き続きそこで生活している場合、この不動産は「生活の本拠」として保有が認められるケースがあります。
ただし、固定資産税や維持費の負担が過大でないこと、また他に資産性の高い部分が存在しないことが条件です。
「資産性の高い部分」とは、たとえば以下のようなものを指します。
- 建物に併設された貸し駐車場や貸店舗部分
- 敷地内の一部が賃貸可能な土地(アパート用地や月極駐車場など)
- 周辺の地価と比べて著しく広大な宅地や商業地として価値がある土地
- 現在使用していない空き家部分や別棟の建物がある場合
なお、自治体によっては、居住を継続する必要性や合理性について個別に判断されることもあります。
空き家や空き地(使用実態がない場合)
相続した不動産が空き家や空き地であり、生活に利用していない場合は、原則として「売却・処分すべき資産」と判断されます。
すぐに売却が困難な場合でも、売却活動の実績(不動産会社への依頼やチラシ作成など)が求められることがあります。
処分が現実的でないケースでは、一時的な猶予が与えられることもありますが、長期的な保有は認められにくいのが実情です。
賃貸中の不動産(収益を生む資産)
被相続人が他人に賃貸していたアパートや貸地などを相続した場合、それが収益を生んでいる限り、生活保護の「収入認定」対象となります。
収入の規模によっては、保護費が減額されたり、受給停止されたりする場合もあるのです。逆に、空室が多く維持費だけがかかる場合には「活用不能な資産」として判断されることもあります。
他者と共有している不動産
相続不動産が他の相続人との共有状態にある場合、その持分のみでは売却が困難なため、「直ちに活用できない資産」として一時的に保有が認められることがあります。
しかし、共有者間で売却協議が可能かどうか、換価の見込みがあるかどうかは定期的に確認され、状況に応じて対応が求められます。
このように、相続した不動産の種類や利用状況によっては、生活保護を継続することも可能ですが、その判断は自治体の福祉事務所(市区町村の生活保護担当課)ごとに異なる場合があるため、早めの相談と対応が重要です。
不動産相続で受給が停止となる条件
相続した不動産が換金可能と判断された場合や、収入を生む場合は受給が停止される可能性があります。ただ、不動産を相続したからといって、必ずしも生活保護が打ち切られるとは限りません。
一定の条件を満たしたと判断された場合に、福祉事務所が受給の一時的な停止や、生活保護の廃止を決定することになるのです。
ここでは、不動産の相続で、代表的な受給停止・廃止の条件を解説します。
不動産が現金化できると判断された場合
生活保護制度では、相続した不動産が換価可能と判断された場合、まずは売却して生活資金に充てることが求められます。
不動産が実際に売却可能な状態であると福祉事務所が判断した場合に、受給者が不動産の活用義務を果たしていないとして、生活保護の受給停止や廃止につながることがあるのです。
売却手続き中であることが明確であれば猶予が与えられることもありますが、売却の意思や行動が見られない場合は厳しい対応が取られます。
賃貸などで収入が得られる場合
相続した不動産が既に賃貸として利用されている、あるいは簡単に賃貸に回せる状況である場合、その不動産は「収入を生む資産」として認定され、生活保護費が減額または停止される可能性があります。
賃料収入が最低生活費を超えるような場合、生活保護は原則として廃止となります。
居住用であっても資産価値が高いと判断された場合
相続した不動産が居住用であっても、著しく高額な資産と判断される場合は、売却を求められることがあります。
たとえば、都市部の高額な�住宅や広大な土地付きの建物などが該当します。
このような場合、「資産の合理的な活用」が促され、売却の意思がないとみなされると、生活保護の廃止につながる可能性もあるでしょう。
虚偽申告や資産隠しがあった場合
相続した不動産の存在を意図的に申告しなかったり、保有を隠していたりしたことが判明した場合、生活保護法に基づき厳しい処分が科されます。
不正受給と見なされ、保護の即時廃止、過去にさかのぼった返還請求、さらには刑事告発に至る可能性もあるため、相続が発生した際には速やかに福祉事務所へ報告することが不可欠です。
生活保護の受給停止・廃止には複数の要因がありますが、いずれも「資産の保有・活用状況」が根拠となる点が共通しています。相続によって状況が変わった場合は、自身の判断だけで対応せず、必ず福祉事務所に相談するようにしましょう。
不動産相続しても受給が認められるケース
不動産を相続した場合でも、すべてのケースで生活保護が停止・廃止されるわけではありません。
次に挙げるような事情があるケースでは、例外的に生活保護の継続が認められることがあります。
居住の継続が必要なケース
相続した不動産が居住用であり、そこに引き続き住み続けることが生活上合理的と判断された場合、保有が認められる可能性があります。
たとえば、高齢や障がいなどの事情により、引越しが著しく困難な場合や、通院・介護サービス等の生活基盤が整っている地域での居住継続が望ましいとされる場合などがこれに該当します。
売却や賃貸が困難なケース
不動産が極めて流通性の低い土地(過疎地の山林など)であり、当面の換価が事実上不可能な場合には、保有が認められることがあります。
また、他人との共�有状態にある場合や、法的・物理的問題により処分が困難な場合も、一時的な保有が容認されることがあります。
処分努力を継続しているケース
売却や賃貸など、不動産の活用に向けた努力を継続していることが確認できれば、猶予措置が認められることがあります。
たとえば、不動産会社への継続的な依頼や広告掲載など、客観的な行動実績があれば、生活保護の継続が可能になる場合もあるのです。
遺産分割が未了であるケース
相続が発生しても遺産分割が未了であり、まだ不動産の名義変更がなされていない状態では、相続人としての「実質的支配」がないと判断され、保護が維持されることがあります。
ただし、遺産分割協議が成立した後は速やかに報告・対応する必要があるので注意しましょう。
特別な家庭事情があるケース
未成年の子どもと同居していて、転居によって教育や福祉に重大な支障が生じるおそれがあるなど、特別な事情がある場合には、例外的に不動産の保有が認められることもあります。
こうした判断は、個別事情を詳しく検討した上で、自治体ごとに裁量的に決定されます。
このように、生活保護で不動産の相続があった場合でも、状況次第では保護の継続が可能となる道があるのです。
重要なのは、正確な情報開示と早期の相談です。福祉事務所への申告と専門家の助言を受けながら、適切に対応していくことが、生活の安定につながるでしょう。
▼関連記事:生活保護は持ち家があっても受給できる?売却しなきゃいけないのはど��んなとき?
生活保護を継続させるために相続後にすべき対応
不動産を相続した場合でも、生活保護の継続を目指すことは可能です。そのためには、適切な対応と速やかな行動が不可欠です。
ここでは、生活保護の打ち切りを回避するために、相続後に取るべき具体的な対応策を紹介します。
福祉事務所へ早期相談と申告をする
不動産を相続した場合は、速やかに福祉事務所へ報告し、今後の方針について相談することが最も重要です。
報告を怠ると、「申告義務違反」に該当し、保護の返還命令や不正受給と見なされる恐れがあります。正確な情報をもとに、保護継続の可否を自治体と協議しましょう。
相続した不動産の状況を明確にする
不動産の価値や利用状況、売却や賃貸の可能性など、資産の実態を把握する必要があります。
不動産業者への査定依頼や、共有状態の確認、建物の老朽化状況の調査など、可能な限り情報を集めておくことが望ましいでしょう。
活用・処分の意志を示す
生活保護を継続するには、相続した不動産を「生活に活用する意志がある」「処分の努力をしている」ことを示す必要があります。
そのため、売却に向けて不動産会社と媒介契約を結ぶ、賃貸可能かどうかを調査するなど、具体的な行動に移すことで、猶予措置が得られる可能性があるでしょう。
相続放棄や共有解除の検討をする
相続財産が明らかに生活に不利益をもたらす場合、家庭裁判所での相続放棄を検討することも一案です。
また、共有名義である場合には、他の相続人との協議により単独所有に変更することで、資産の処分や活用がしやすくなる場合もあります。
専門家への相談を活用する
相続不動産の取り扱いは法的・実務的に複雑なケースが多いため、行政書士、司法書士、不動産業者などの専門家に早期に相談するのがおすすめです。福祉事務所と連携しながら的確な対応を図ることで、生活保護の継続可能性が高まるでしょう。
相続後に冷静かつ誠実に対応を進めることが、保護の打ち切りを避ける鍵となります。自己判断で動くのではなく、自治体や専門機関と連携しながら、生活の安定を守る行動を取ることが重要です。
まとめ
生活保護受給者が不動産を相続した場合、その影響は決して小さくありません。生活保護制度は、資産を持たない人に最低限の生活を保障する仕組みであり、不動産を取得したことで「資産あり」と判断されれば、生活保護の停止や廃止につながる可能性があります。
特に、相続した不動産が使用されていない空き家や空き地であれば、原則として売却や活用を求められます。売却可能にもかかわらず活用しない場合、資産の活用義務違反として受給停止になる恐れがあるのです。
一方で、居住継続が合理的な場合や、売却・賃貸が困難な事情がある場合には、例外的に保護継続が認められるケースも存在します。
大切なのは、相続が発生した際に、福祉事務所に速やかに正直に申告し、今後の方針を相談することです。不動産の活用可能性を整理し、必要に応じて売却活動や専門家への相談を行うことで、適切な対応が取れるようになります。
生活保護の受給を続けるためには�、自己判断で動かず、自治体や専門家と連携しながら冷静に対応することが何より重要です。相続による変化を正しく理解し、生活の安定を守るための確かな行動を心がけましょう。
なお、相続を隠したり虚偽の申告を行った場合、不正受給とみなされ、保護廃止や返還命令だけでなく刑事罰の対象となる可能性もあります。必ず早期に正直に申告することが重要です。