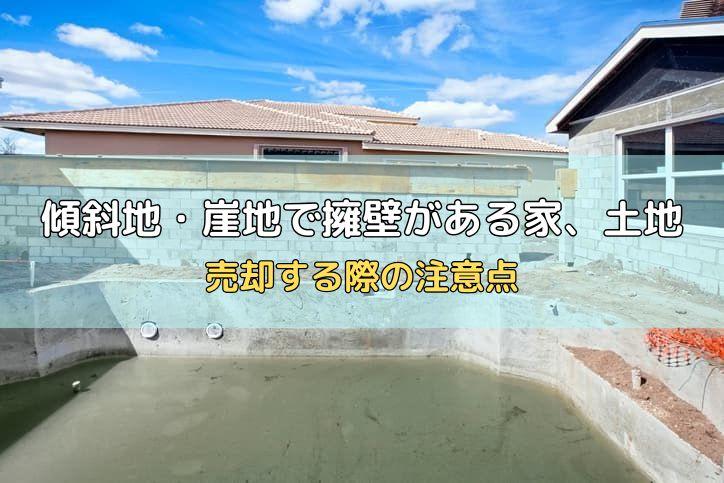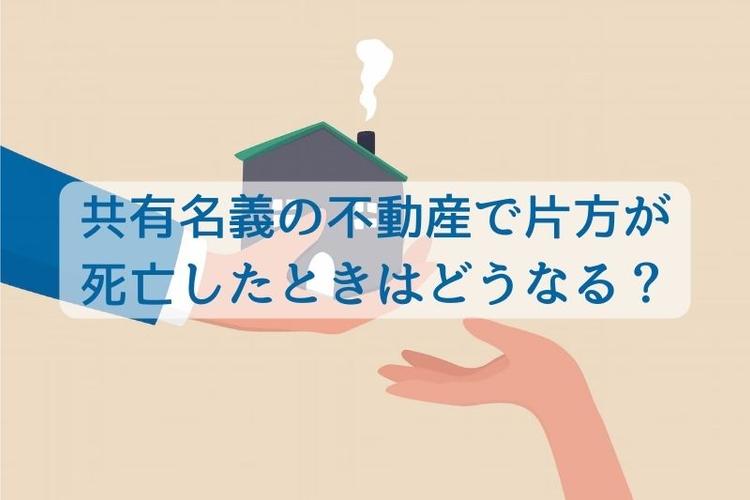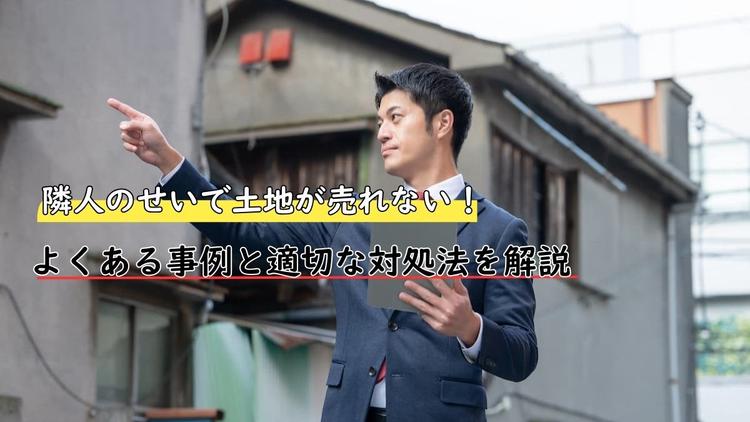「相続土地国庫帰属制度」は、不要な土地を国に引き取ってもらえる制度として注目を集めています。
相続などで取得した土地の管理や処分に困っている人にとって、有効な選択肢となり得るでしょう。
ただし、誰もが簡単に土地を手放せるわけではありません。制度には一定の要件や手続きが定められており、利用には十分な準備と理解が必要です。
この記事では、「相続土地国庫帰属制度」を利用するための主な条件と、申請の流れ、注意すべきポイントについて解説していきます。
相続土地国庫帰属制度とは
近年、全国的に増加している所有者不明土地や管理されない空き地は、公共事業の遅延や景観の悪化など、様々な問題を引き起こしています。
特に、相続後に利用されず放置された土地がその多くを占めており、その解決策のひとつとして、2023年4月に創設されたのが「相続土地国庫帰属制度」です。
この制度は、相続や遺贈により取得した不要な土地を、一定の条件を満たせば国に引き取ってもらえるようにしたものです。
土地問題に悩む相続人の「最後の手段」
長年使用していない山林、接道のない宅地、収益性のない農地といった、いわゆる「負の遺産」は相続人にとって重荷となります。地方移住や家庭菜園ブームの一方で、「手放したくても手放せない土地」を抱えたままの人も多いのが現実です。
「相続土地国庫帰属制度」は、そうした人たちにとっての最後の手段であり、将来世代に不要な土地を残さないための選択肢でもあります。
この制度の創設により、「相続したくない」「相続してしまったが困っている」という人々が、法的な手続きによって土地の所有から解放される道が開かれたのです。
「所有の義務」からの出口
日本では、土地を所有すると、その管理責任や税負担(固定資産税など)が自動的に発生します。たとえ山林や農地であっても、草刈りや境界の管理、災害時の責任など、所有者としての義務は免れません。
この制度は、そうした「所有者の義務を果たすのが難しい」ケースにおいて、一定の審査を経たうえで「土地を手放す=国に帰属させる」ことを可能にする仕組みです。
つま��り、個人が土地の所有権を放棄できる初めての法的ルートといえます。
対象となる土地と取得方法が限定されている
ただし、どんな土地でも国が引き取ってくれるわけではありません。制度の対象となる土地にはいくつかの要件があります。
まず重要なのは、対象となる土地が「相続または遺贈によって取得したもの」に限られるという点です。つまり、土地を売買や贈与で取得した場合は、この制度は利用できません。
また、引き渡せるのは「国が管理可能」と判断した土地に限られます。後述しますが、建物がある土地、崖地、通路、水路など、管理上の支障が大きい土地は制度の対象外です。
なお、相続放棄などと違い、相続土地国庫帰属制度には「相続してから〇年以内に手続きを行わなければならない」などの規定はないため、10年以上前に相続した土地でも申請可能です。
参考:法務省|相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件
制度の利用件数と初期の傾向
「相続土地国庫帰属制度」は施行から日が浅いながらも、全国で確実に関心が高まっています。
法務省によると、制度が開始された2023年4月から2025年4月末までの約2年間で、全国の法務局に約3,700件の申請が寄せられました。
そのうち、正式に「国庫帰属」が認められたのは42%程度にとどまり、残りの多くは「土地の状態が不適格」「書類不備」「申請取り下げ」などにより、却下もしくは審査未了となっています。
特に受理されやすいのは、地方の山林や耕作放棄地で、明確な単独所有かつ境界紛争がない土地です。一方、都市部の住宅地や商業地は、建物の残存や通行権の問題が多いため審査が厳しく、却下されるケースが目立ちます。
たとえ通行権が正式に設定されていなくても、周囲の住民が慣習的にその土地を利用している場合は、現地調査で「第三者の使用実態」が確認されれば、国による引き取りは困難と判断されます。
相続土地国庫帰属制度では、「他人が利用している土地」は原則として引き取りの対象になりません。
つまり、「見た目は空き地でも、誰かがそこを通って日常生活を送っている」ような土地は、国が引き取ると第三者の生活を妨げるリスクがあるため、受け入れが困難なのです。
この制度は、単に「要件を満たしていれば通る」ものではなく、現地調査や書類準備を含む確実な手続きと、現実的な期待値の設定が不可欠であることが、初年度の動向からも明らかになっています。
引き取り可能な土地の条件
相続土地国庫帰属制度を利用するうえで、最も重要かつ最初に確認すべきことは、その土地自体が制度の対象となるかどうかです。
制度は「不要な土地であれば何でも国が引き取ってくれる」というものではなく、土地の性質や状態によって申請そのものが受理されないケースもあります。
ここでは、引き取りが可能な土地の条件について解説していきましょう。
法令上の除外対象となる土地
�相続土地国庫帰属法では、一定のリスクや管理負担が高い土地について、明確に「引き取り不可」と定めています。次のようなケースに該当する土地は、制度の利用ができません。
- 建物がある土地(古家付きも含む)
- 抵当権などの担保権が設定されている土地
- 他人が通行に利用している通路や水路等
- 土壌汚染や産業廃棄物がある土地
- 境界が不明確または紛争中の土地
- 崖地など災害リスクが高い土地
これらの土地については、たとえ相続で取得したものであっても国庫への帰属は認められません。
「現況」に基づいた判断がなされる
土地の引き取り可否は、登記情報だけでなく、実際の現況に基づいて審査されます。
たとえば、登記簿上は「宅地」であっても、現地に建物が存在すれば対象外となります。また、誰かが勝手に通行している私道なども、他人の使用実態があれば申請は却下されます。
「登記情報で判断される」と誤解せず、現地の確認や調査をきちんと行っておくことが重要です。
都市部よりも地方の山林や原野が対象になりやすい
制度の運用実態としては、国が管理しやすい「未利用地」や「再利用の見込みが低い土地」が対象になりやすい傾向があります。たとえば次のような土地は受理されやすいとされています。
- 地方にある管理しやすい山林や原野
- 地目が「雑種地」や「山林」で、他人の利用実態がないもの
- 隣接地との境界が明確で、単独所有である土地
一方で、都市部の宅地や活用が期待される好立地の土地は、国の管理コストや社会的��影響を考慮して、却下されるケースも少なくありません。
境界確定と物理的トラブルの有無が重要
審査において、特に重視されるのが境界の確定状況です。土地の境界線が曖昧なままでは、隣接所有者とのトラブルや管理リスクが生じるため、制度は利用できません。
また、越境物(隣の建物の一部や塀などが自分の土地にはみ出している状態)がないことも重要なポイントになります。
必要に応じて、次のような準備が求められます。
- 測量図や境界確認書
- 隣接地所有者との境界立会
- 土地家屋調査士による現況調査
申請者に対する条件
相続土地国庫帰属制度は、すべての土地所有者が自由に利用できる制度ではありません。
制度の趣旨は、「やむを得ず土地を相続した人」が一定の条件を満たした場合に限って、その負担から解放することにあります。
したがって、申請者側にも明確な要件が設けられており、これらを満たさない場合は制度の対象外となります。
ここでは、制度を利用できる「人の条件」について見ていきましょう。
相続または遺贈によって取得した人
相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、土地を「相続」または「遺贈」によって取得した個人に限られます。売買や贈与で取得した土地は対象外です。
また、制度の名称に「相続」とありますが、相続人に限らず、包括遺贈や特定遺贈で土地を受け取った人も対象となります。ただし、その所有者が法人である場合は制度を利用できません。
さらに、所有権の明確化が前提となるので、登記が完了している必要があ��ります。
たとえば「全財産の3分の1をAに遺贈する」といった内容です。この場合、土地を含めたすべての財産から自動的にその割合が割り当てられます。特定遺贈とは、「〇〇市の土地」など、特定の財産を指名して受け取る遺贈方法です。
たとえば「〇〇町の畑をBに遺贈する」といった形です。
所有者が単独であること(共有名義は不可)
申請者が単独でその土地を所有していなければ、申請することはできません。
つまり、複数人の共有名義になっている場合は、共有者全員の同意を得て、名義を単独にした上でなければ申請が受け付けられないのです。
共有状態のままでは、たとえ相続で取得した土地であっても、制度を利用することはできないという点に注意しましょう。
管理義務を誠実に果たしていたこと
制度の審査では、申請者がこれまでその土地に対して適切に管理義務を果たしていたかどうかも重要な判断材料となります。草刈りや境界管理、近隣とのトラブル対応などを放置していた場合には、申請が認められないこともあります。
「困っているから国に引き取ってほしい」という事情があっても、一定の管理義務を怠っていたと判断されれば、申請が却下される可能性もあるのです。
申請の流れ
制度の対象となる土地や利用者の条件を満たしていることが確認できたら、次は実際の申請手続きに進むことになります。
相続土地国庫帰属制度の申請は、単に書類を出せば完了するような簡易な手続きではなく、土地の現況確認や専門的な書類の準備、実地調査など、いくつかの段階を経ることになります。
申請から国庫への正式帰属までは、数ヶ月から1年以上かかる場合も少なくありません。
ここでは、制度を利用する際に踏むべき基本的な流れを、ステップごとにみていきましょう。
ステップ1:法務局への事前相談
申請を始める前に、まずは土地を管轄する法務局に事前相談を行います。ここで土地の状況や申請の可否、必要書類などについて具体的なアドバイスを得ることができます。
事前相談は任意ですが、制度の対象かどうかを判断する重要な機会であり、特に不安がある場合には積極的に活用すべきです。なお、予約が必要な場合もあるため、事前に電話等で確認しましょう。
ステップ2:必要書類の準備
申請には次のような書類が必要となります:
- 申請書(法務局様式)
- 登記事項証明書……土地の所有者を証明するため
- 公図および地積測量図……土地の形状や位置関係を示すため
- 相続関係説明図や遺言書など、取得を証明する書類
- 境界確認書や近隣関係の説明資料(必要に応じて)
これらの書類は、土地の所有状況や現況を正確に示すものとして非常に重要です。
場合によっては、土地家屋調査士や司法書士への依頼が必要になることもあります。専門家のサポート�を受けることで、誤記や不備を防ぎ、スムーズな申請ができるようにしましょう。
ステップ3:申請書の提出と受付
必要書類を揃えて法務局へ申請します。申請が受理されると、法務局により形式的な審査が行われ、必要に応じて補足資料の提出が求められることもあります。
提出は窓口で行うのが基本ですが、郵送での対応も一部可能です。提出時には、申請内容の控えを取っておくと安心です。
ステップ4:実体審査と現地調査
申請内容に基づき、土地の状態や境界、周辺の状況について実地調査が行われます。
調査の結果、管理が困難と判断されたり、他人の通行権や使用実態が確認されたりすると、申請が却下されることもあるので、事前に状況をよく確認しておくことが大切です。
なお、調査は事前連絡のうえで実施され、申請者が立ち会うこともあります。
ステップ5:負担金の納付
申請が認められた場合、10年分の管理費相当額として「負担金」の納付が必要となります。
一般的な金額は1筆あたり20万円程度(10年分の管理費相当額)とされていますが、地目、面積に加えて、市街化区域かどうかなども影響する可能性があります。
負担金は承認通知とともに納付案内が届き、期限内に支払わなければ帰属は無効となるため注意が必要です(通常、30日以内の納付が求められる)。
ステップ6:国庫への帰属決定
負担金の納付が確認されると、土地は正式に国庫に帰属され、所有権が国へ移転します。
その後、固定資産税の課税も止まり、所有者としての義務から解放されます。所有��権の移転登記は法務局が進めるため、自分での手続きは不要です。
制度を利用するための注意点
相続土地国庫帰属制度は「土地を手放したい人が簡単に処分できる制度」ではなく、「国が管理できると判断した土地のみを条件付きで引き取る制度」です。
制度の仕組みや目的を誤解したまま申請を進めると、審査で却下されたり、余計な費用や労力がかかってしまったりすることもあります。
ここでは、制度利用にあたって特に注意が必要な事項を示します。
無条件では引き取られないという前提を理解する
「相続土地国庫帰属制度」は、あくまでも一定の条件を満たすことを前提に、国が土地の引き取りを認める制度です。「相続したから困っているので手放したい」という感情だけでは認められません。
特に、建物が残っていたり、他人の通行に使われていたり、管理コストが高い土地については、制度の対象外となります。まずは、客観的に自分の土地が制度の適用対象となるかを冷静に判断する必要があるでしょう。
専門家への相談を積極的に行う
土地の現況確認、境界の明示、必要書類の準備など、専門的な判断や手続きが求められる場面が多くあります。
土地家屋調査士や司法書士、行政書士、不動産専門の弁護士など、信頼できる専門家に相談することで、無駄な手戻りや時間の浪費を防ぐことができるでしょう。
専門家は、それぞれ次のような分野を扱っています。
- 土地家屋調査士……土地の測量や境界確定、現況調査
- 司法書士……登記手続き、書類作成のサポート
- 行政書士……申請書類の作成補助(登記申請手続きを除く)
- 弁護士……隣地との境界紛争や権利関係の調整など
また、法務局の事前相談は義務ではありませんが、ほぼすべてのケースで相談しておいたほうがスムーズです。
地元の法務局には、制度の詳細を熟知した担当者が配置されており、申請者の立場に立ったアドバイスが期待できます。
書類不備や審査中の追加資料に備える
書類の不備や追加資料の提出を求められることは少なくありません。
「申請したらあとは結果を待つだけ」と油断せず、審査期間中も電話や郵送での連絡にしっかり対応できるよう、日常的に情報を確認できる状態を保つことが重要です。
時間と費用に余裕をもって取り組む
申請から国庫帰属までには、通常でも数ヶ月、場合によっては1年以上かかることもあります。これは、土地の状況や法務局の混雑具合、審査内容によって大きく異なります。
また、調査費用、専門家報酬、境界確定費用、負担金など、制度利用にはそれなりの費用がかかることを念頭に置いておくべきです。
「手間をかけずに土地を手放せる制度」と期待しすぎず、現実的なスケジュールと予算の中で進める心構えが大切です。
▼関連記事:親の土地がいらない時はどうすべき?
まとめ
相続土地国庫帰属制度は、相続によって不要な土地を取得した人にとって、所有の義務から法的に解放される重要な選択肢です。制度の導入によって、従来は放置されがちだった「負の遺産」ともいえる土地の管理・処分問題に、新たな出口が示されました。
しかし、本制度は誰でも簡単に利用できるわけではなく、土地の状態、取得方法、申請者の属性など、細かく定められた条件をすべてクリアする必要があります。また、申請手続きにも手間と費用、そして時間がかかることから、軽い気持ちで申し込むことはおすすめできません。
制度の利用を検討する際は、まず土地の現況を把握し、法務局への事前相談を通じて制度の適用可能性を確認することが出発点となります。そのうえで、境界の確定や必要書類の整備、そして専門家との連携など、丁寧な準備を重ねることが成功の鍵です。
不要な土地に悩んでいる方にとって、相続土地国庫帰属制度は確かに救いとなる制度です。とはいえ、それは「制度の条件に合致し、適正に手続きを行った人にのみ開かれる道」であることを忘れてはなりません。
制度を正しく理解し、計画的に取り組むことで、自身や家族の将来にとって最善の土地整理を実現することができるでしょう。