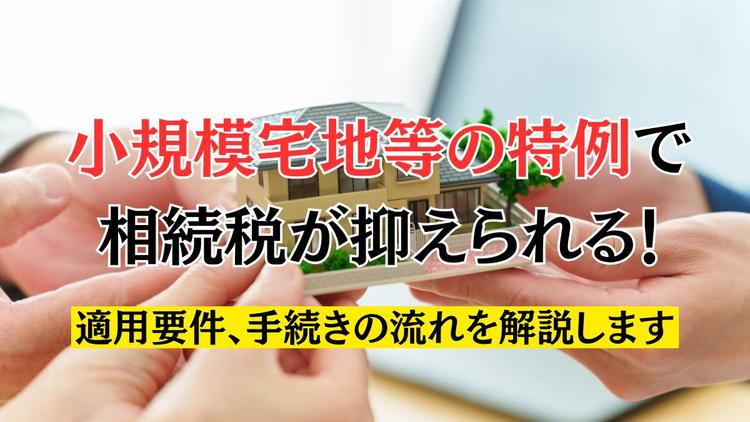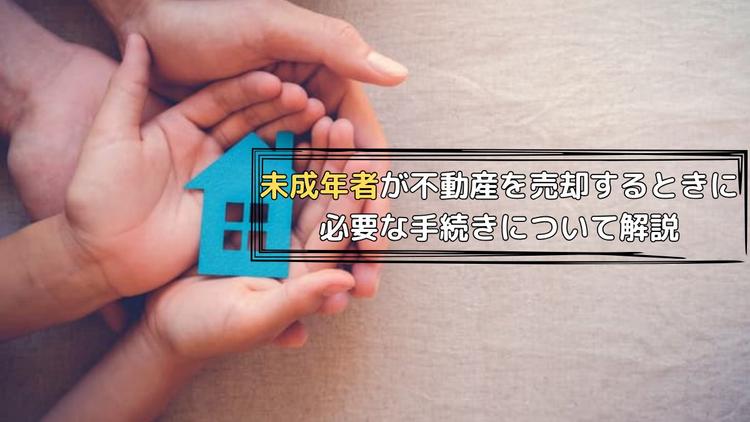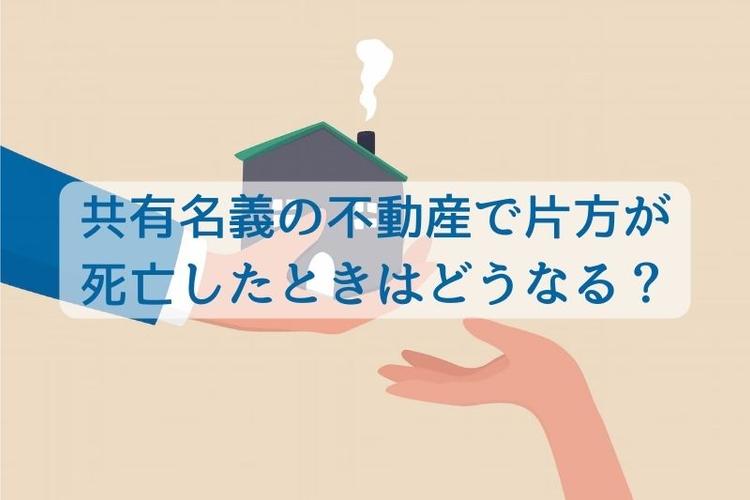相続税の課税対象となる財産の中でも、不動産は評価額が高額になりやすく、相続税負担が大きくなる原因のひとつです。
そこで節税対策として活用したいのが、「小規模宅地等の特例」です。一定の要件を満たせば、相続税の課税価格を大幅に減額できる制度であり、相続人の負担軽減に大きく貢献します。
この記事では、小規模宅地等の特例について、制度の概要から適用要件、申告手続きの流れを解説します。
小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例とは、相続または遺贈により取得した土地のうち、被相続人が居住や事業に使用していた宅地について、一定面積を限度として相続税評価額を大幅に減額できる制度です。
これは、相続人が相続後も引き続きその土地での居住や事業を継続しやすくすることを目的としています。
たとえば、被相続人が住んでいた自宅の敷地(居住用宅地)であれば、330平方メートルを限度に評価額を80%減額できます。
また、事業用の宅地についても400平方メートルを限度に80%、貸付事業用宅地については200平方メートルを限度に50%の減額が認められます。
この特例を活用することで、土地の評価額を数千万円単位で圧縮することも可能であり、相続税の大幅な軽減につながります。
土地の利用状況と相続人の立場で分類
小規模宅地等の特例を適用するには、宅地の「利用状況」と「相続人の立場」が密接に関係します。
単に宅地の種類を見分けるだけでなく、相続人が誰で、どのような利用目的で宅地を取得するのかが非常に重要です。
小規模宅地等の特例が適用されるのは、次の3種類の宅地です。
- 特定居住用宅地等
- 特定事業用宅地等
- 貸付事業用宅地等
小規模宅地等の特例は、被相続人の生活拠点や家業の継続性を支援する観点から設けられており、土地の売却や賃貸を前提とした節税策としての利用には厳格な審査が行われる点も注意が必要です。
特定居住用宅地等
特定居住用宅地等とは、被相続人が亡くなるまで居住していた宅地のことを指します。相続人が�その宅地を取得し、相続税の申告期限まで引き続き居住を続ける意思と実態がある場合に適用されます。
同居していた配偶者や子がそのまま相続して居住を続けるケースが代表的です。また、いわゆる「家なき子特例」(別居していた相続人が自宅を所有していないなどの要件を満たす場合)も、条件付きでこの区分に該当します。
- 減額割合:80%
- 限度面積:330平方メートル
- 主な該当者:配偶者、同居親族、家なき子
特定事業用宅地等
特定事業用宅地等とは、被相続人(またはその親族)が相続開始直前に、事業のために使用していた宅地で、相続人がその事業を引き継いで使用を継続する場合に該当します。
この場合の事業とは、製造業・小売業・サービス業などの営利を目的とした事業を指し、不動産貸付業は除かれます。
相続人がその事業を相続開始時点から継続し、申告期限まで維持していることが条件です。
- 減額割合:80%
- 限度面積:400平方メートル
- 主な該当者:事業継承者、生計一親族
貸付事業用宅地等
貸付事業用宅地等とは、被相続人が不動産貸付(アパート・駐車場など)をしていた宅地で、相続人がその賃貸事業を継続して行う場合に適用されます。
ただし、相続開始前3年以内に新たに開始した貸付事業については、節税目的とみなされて除外される可能性があり、事業の実態が形式的である場合にも、適用が認められないことがあります。
特例の適用が認められるかどうかは、継続的かつ実質的に収益事業として運用されていたかどうかが判断の分かれ目です。
- 減額割合:50%
- 限度面積:200平方メートル
- 主な該当者:賃貸事業の後継者(配偶者や子など)
家なき子特例とは
小規模宅地等の特例は、相続人が相続後も引き続き居住や事業を継続しやすくすることを目的とした制度です。
しかし、相続人が被相続人と同居していなかった場合でも、「家なき子特例」と呼ばれる要件を満たせば、特定居住用宅地としての適用が可能です。
この「家なき子」とは、相続開始前3年以内に、自分または配偶者が所有する家屋に居住しておらず、かつ、相続後にその宅地に居住する意思と実態がある相続人を指します。
持ち家に住んでいなかったことや、一定期間にわたる借家暮らしをしていた実態などを証明する必要があり、慎重な判断と適切な証明書類の整備が求められます。
小規模宅地等の特例の適用要件
小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、「土地の利用実態」と「相続人の立場」の両面が重要です。
ここでは、それぞれの宅地区分に応じて、相続人がどのような立場にあれば特例が適用されるのかを解説します。
特定居住用宅地等の場合
被相続人が居住していた自宅の敷地が対象となるのが「特定居住用宅地等」です。適用を受けるには、以下の条件が必要です。
- 被相続人が死亡時に居住していた宅地であること
- 相続人が相続税の申告期限までその宅地を保有していること
そのうえで、相続人の立場ごとに次のような要件があります。
被相続人と同居していた
同居していた親族が相続人であれば、原則としてそのまま土地を相続し、引き続き居住を継続することで特例の適用が可能です。この場合、配偶者であれば無条件で適用�され、同居していた子や兄弟姉妹も申告期限まで居住を継続していれば、適用を受けられます。
被相続人と別居していた(家なき子特例)
別居していた子などでも、次のすべての要件を満たす場合は特例の適用対象となります。
- 被相続人に配偶者がいないこと
- 相続人が、相続開始前3年以内に自己または配偶者が所有する家屋に居住していないこと(相続開始日を起点に判定)
- 相続人自身に持ち家がなく、相続した宅地に居住する意思と実態があること
この特例は「家なき子特例」と呼ばれ、住民票、賃貸契約書などで実態を証明する必要があります。
被相続人が老人ホームに入居していた
被相続人が生前に老人ホームなどに入所していた場合でも、次の条件を満たせば特例の適用対象となります。
- 自宅に居住していなかったのが、身体上または精神上の理由によること
- 被相続人の居住用宅地が空き家として維持され、他人に賃貸されていないこと
医師の診断書や老人ホームの入所契約書等で、事情の正当性を証明することが求められます。
特定事業用宅地等の場合
特定事業用宅地等の場合で小規模宅地等の特例を適用されるためには、次の条件があります。
- 被相続人の事業(不動産貸付業を除く)用に使用されていた宅地等であること
- 相続人または被相続人の生計を一にしていた親族が、その事業を相続開始時点において現に行っており、かつ申告期限まで継続していること
- 相続人がその土地を相続して保有し続けていること
相続開始前3年以内に新たに事業�のために使用され始めた土地は、特例の対象外となります。
ただし、例外として、その宅地上で使用されている減価償却資産の価額が、相続時点における当該宅地の評価額の15%以上である場合には、特例の適用対象となります。
この15%基準は、単なる名目的な利用や形式的な事業開始ではなく、実質的に事業用資産が投入されていることを示す客観的な指標として設けられたものです。
例えば、機械設備など事業用のの減価償却資産がある程度の金額で設置されていれば、土地が真に事業に使用されていると判断できます。
つまりこのルールは、節税目的の不自然な事業開始と、実際の事業継続との線引きを明確にするために設けられているのです。
貸付事業用宅地等の場合
貸付事業用宅地等の場合で小規模宅地等の特例を適用されるためには、次の条件があります。
- 被相続人が相続開始前から不動産賃貸業などの貸付事業を営んでいた土地であること
- 相続人がその貸付事業を相続後も継続していること
相続開始前3年以内に新たに始めた貸付事業は原則として適用除外となります。ただし、相続開始の3年以上前から継続して貸付事業を行っている場合は適用可能です。
これらの要件は、申告時点における「事実」として証明される必要があります。したがって、相続人の立場や使用実態、生活状況などに基づいて慎重に判断して、申告書類を作成することが重要です。
小規模宅地等の特例の手続きの流��れ
小規模宅地等の特例を受けるためには、相続税の申告書を税務署に提出する際に、所定の「小規模宅地等の特例に関する明細書」などの必要書類を添付する必要があります。
小規模宅地等の特例の基本的な手続きの流れを紹介していきましょう。
手続きの主な流れ
- 相続発生……被相続人が亡くなった日(その事実を知った日)をもって相続が開始します。
- 遺産分割協議……法定相続人で財産の分割方法を決定します。遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って分割が行われます。
- 相続税評価……相続財産(不動産を含む)の評価額を算出します。
- 適用要件の確認……対象宅地の種類・面積・取得者の要件などを確認します。
- 申告書の作成・提出……相続開始から10か月以内に相続税申告書を提出します。提出期限に遅れると特例の適用が認められません。
条件を満たしていても、自動的に特例が適用されるわけではありません。そのため、手続きは慎重に行う必要があります。記載漏れや形式的なミスが命取りになることもあるため、税理士に依頼した方が安心でしょう。
必要書類
小規模宅地等の特例を適用されるためには、次の書類を相続税申告書(第1表、第11表、第15表など)に添付して提出します。
- 小規模宅地等についての明細書
- 登記事項証明書(相続財産である宅地の登記内容)
- 相続人の住民票や戸籍謄本(居住や同居の事実を証明するため)
- 被相続人の住民票除票
- 相続関係説明図
- 遺産分割協議書
- 事業の継続を証する書類(青色申告書の控え、営業許可証など)
- 貸付事業であれば、賃貸借契約書や賃料収入の帳簿など
被相続人が老人ホームに入居していた場合は、入所契約書や医師の診断書など、「身体上の理由による入居」であることを証明する書類が必要です。
また、被相続人と同居していたかどうかで要件が異なるため、居住実態を証明する住民票や公共料金の明細等も役立ちます。
これらは一般的な必要書類であり、個別の相続状況によって追加の書類が必要となる場合もあります。
小規模宅地等の特例の注意点
小規模宅地等の特例は大変有益な制度ですが、制度の誤解や適用要件の見落としによって、期待した節税効果が得られないケースや、後から適用が否認されるリスクもあります。
ここでは、小規模宅地等の特例を適用する際の注意点を解説します。
要件を満たしていないと適用できない
同居していない親族が被相続人の自宅を相続する場合、3年以内に持ち家に居住していたことがあると、小規模宅地等の特例が適用されないなど、要件は細かく定められています。
これらの要件を満たしていない場合、適用されないばかりか、見落としや誤認があると税務調査で否認され、追徴課税が発生する可能性もあるため注意が必要です。
適用条件を満たしていても分割未了だと適用されない
相続税の申告期限(相続開始から10か月)までに遺産分割が完了していない場合、原則として小規模宅地等の特例を適用することはできません。
この場合、いったん特例を適用せずに相続税の申告を行い、その際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出します。これを提出することで、遺産分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求を行えば、特例の適用を受けることが可能です。
なお、申告時に分割見込書を提出していなかった場合でも、申告期限から5年以内であれば更正の請求を行うことはできますが、単に遺産分割成立による特例適用の後出しは不可とされるのが一般的な解釈です 。
用途や使用状況の変更に注意
相続開始時点で事業に使用していた土地であっても、相続後すぐに用途を変更してしまうと、特例の適用が取り消されるおそれがあります。
たとえば、賃貸用の土地を居住用に変更したり、空き地のまま放置したりするなどの行為は注意が必要です。
二次相続への影響も考慮を
一次相続で小規模宅地等の特例を最大限使った結果、次の相続(二次相続)で適用可能な宅地が残らないという事態もありえます。
特に、配偶者がすべての土地を相続し、その後の相続で他の相続人が宅地を取得した場合、再度特例を使えない可能性が高まるのです1。
このようなケースでは、配偶者がそもそも相続税を軽減できる制度(配偶者の税額軽減)を活用しつつ、あえて小規模宅地等の特例を使用しないという選択肢も検討すべきでしょう。
特例には評価減の面積上限があるため、一次相続でのフル活用が、次世代の負担増に直結する場合もあるためです。
二次相続までを見据えた分割や利用計画が、トータルの相続税対策として重要です。
▼関連記事:不動産の二次相続は対策すべき?よくある事例を基に対処法を解説します
まとめ
小規模宅地等の特例は、相続税対策として極めて有効な制度であり、特に不動産を含む遺産を相続する場合には、その恩恵は非常に大きいといえます。
特例の適用によって数千万円単位で評価額を減額できるケースもあり、自宅や事業用の土地を維持しながら、現金納税の負担を抑えることが可能になります。
しかしその一方で、特例の適用には複雑な要件や手続きが伴い、特に「被相続人との関係性」や「居住実態」、「事業継続の有無」などについて詳細に確認されるため、事前の準備と慎重な対応が求められます。
また、期限内に遺産分割協議を終えていない場合や、必要書類に不備がある場合には、特例の適用が認められないリスクもあるため注意が必要です。
さらに、節税だけを目的にした形式的な利用は否認されるおそれがあり、将来の土地利用や二次相続への影響も視野に入れた総合的な相続�設計が重要となります。
特例の内容や税務署の判断は年度ごとに見直されることもあるため、常に最新の情報を確認しつつ、相続税に精通した税理士や専門家と連携して進めることが、トラブルを防ぎ、スムーズな手続きにつながります。
適切な知識と手続きをもって小規模宅地等の特例を正しく活用すれば、相続税の大幅な軽減が可能となり、大切な資産を次世代へと安心して引き継ぐことができるでしょう。