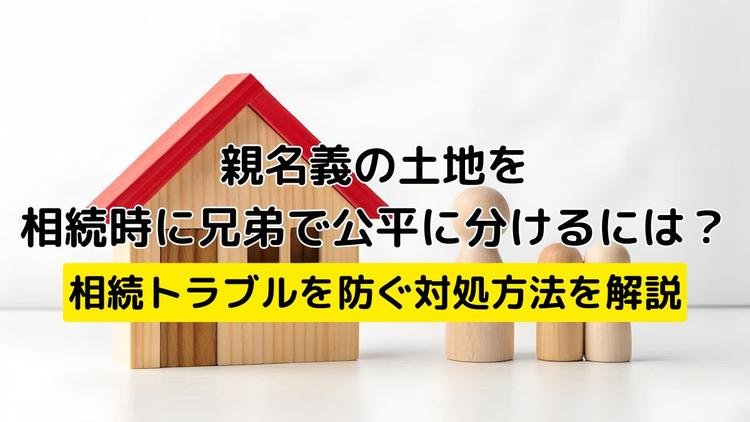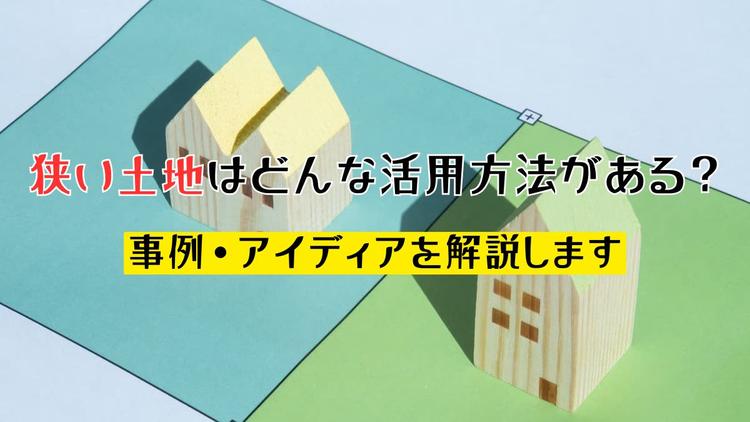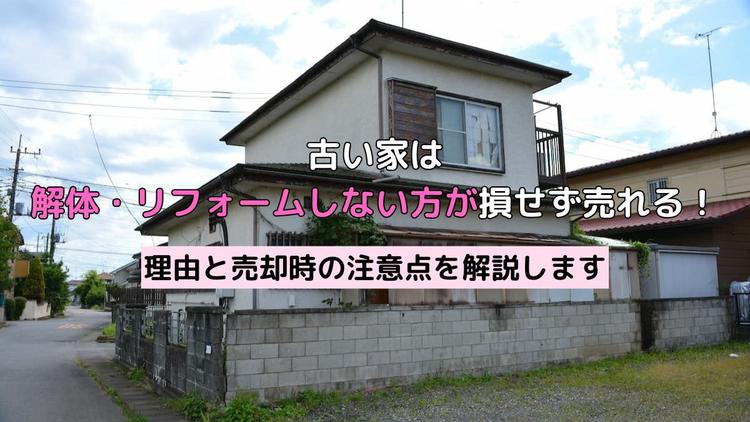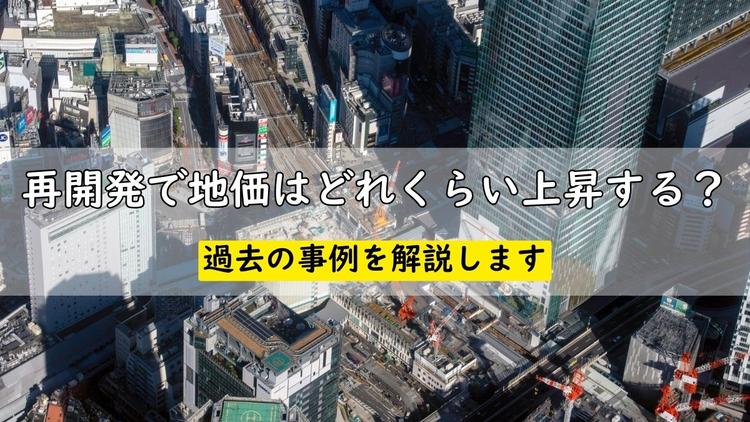不動産は分割しにくいことから、相続で揉めやすい財産です。
親名義の土地も兄弟で相続となると、分け方や相続税を巡ってトラブルになるケースがあります。
相続トラブルが起きると相続がストップするだけでなく、その後の関係性も悪化しやすいのでトラブルを起こさないことが大切です。
この記事では、親名義の土地を兄弟で相続する際によくあるトラブルや、相続の流れ、具体的な分け方などを分かりやすく解説します。
親名義の土地を兄弟で相続する際によくあるトラブル
親名義の土地を兄弟で相続する際、どのようなトラブルになりやすいのでしょうか。
ここでは、よくあるトラブルとして以下の3つを見ていきましょう。
- 親が遺言書を遺しておらず遺産分割割合で揉めるケース
- 兄弟のうちの一人が親の介護をしており多めの分配を望むケース
- 相続税の納税資金を準備していないケース
それぞれ見ていきましょう。
親が遺言書を遺しておらず遺産分割割合で揉めるケース
遺言書のある相続は、原則として遺言書に記されたとおりに遺産を分割します。
そのため、相続人間で意見の対立が起きにくく、スムーズな相続が可能です。
一方、遺言書がない相続では、相続財産の分け方は相続人全員で話し合って決めることになります。
しかし、相続人同士で話し合うと、互いの意見が対立しトラブルになるケースも珍しくないのです。
仲の良い兄弟だから大丈夫だと思っていても、相続財産が絡むとどうなるかは分かりません。
なかには、兄がすべて相続するものと考えている人もいるでしょう。
遺言書がないことで兄弟それぞれの主張がぶつかると、トラブルになりやすいので注意しましょう。
なお、遺言書がある場合でも、相続人全員の話し合いによって、遺言書とは異なる相続内容に変更することも可能です。
遺言書の内容が偏っている�、指定された以外の相続財産が欲しい場合などには、話し合いで決めることも検討するとよいでしょう。
兄弟のうちの一人が親の介護をしており多めの分配を望むケース
親の生前中の介護の負担が偏っているケースでも、相続時に寄与分を主張し揉めやすくなります。
寄与分とは、介護など被相続人(亡くなった人)への貢献に対して、貢献した人が相続財産を多く取得できる制度です。
よくあるケースが、どちらかがすべての介護を行っていたことを理由に相続財産を多く主張するといったケースです。
寄与分を認めるかどうかは相続人の話し合いで決めるため、他の相続人が貢献を認めて寄与分として土地を譲るというなら相続をスムーズに進められるでしょう。
寄与分をどちらかが主張すると、もう片方が自分の寄与分や相手の寄与分の無効を主張するなどでトラブルになりがちです。
話し合いで寄与分が決めらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てて判断してもらうことになります。
しかし、家庭裁判所で寄与分が認められるハードルはかなり高くなります。
寄与分を認められるには通常を超える貢献が必要となるので、たとえば介護であれば仕事をやめて24時間365日つきっきりの介護を長年行ったといったレベルが必要です。
病院に付き添った、仕事の合間で介護した位では認められないので注意しましょう。
なお、寄与分が認められるのは相続人自身が行った寄与に対してです。
たとえば、兄の妻など相続人の配偶者が介護した場合、妻は相続人ではないため寄与分は認められません。
ただし、配偶者は特別寄与料を相続人に対して請求できます。
相続税の納税資金を準備していないケース
相続財産に対して不動産が占める割合が多いと、納税トラブルになる恐れがあります。
たとえば、相続財産が土地とわずかな現預金しかないケースです。
この場合、相続税が課税されると、現預金だけでは納税に対応できず、相続人が自己資金を用意するか、土地を売却して納税しなければならない可能性があります。
そのため、以下のようなケースで相続税を巡って兄弟間でトラブルになる恐れがあります。
- どちらかが現預金を多く相続する
- 土地の売却にどちらかが反対する
相続税には基礎控除があるので、課税されるケースはそれほど多くはありません。
とはいえ、一般的な相続では相続財産が現預金と実家というケースも多いため、相続税についても事前に把握しておくことが大切です。
相続トラブルを避けるために知っておきたい相続の流れ
相続が発生すれば、自動的に土地などの相続財産が相続人に引き継がれるわけではありません。
相続には手順があるので、トラブルにならないためにも相続の流れを押さえておくようにしましょう。
相続発生から土地を相続するまでの大まかな流れは、以下のとおりです。
- 遺言書の確認
- 遺言書がない場合は遺産分割協議を行う
- 相続登記を行う
- 相続税を支払う
それぞれ見ていきましょう。
遺言書の確認
相続では遺言書が優先されるため、まずは遺言書の有無を確認する必要があります。
遺言書には�「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があり、公正証書遺言であれば公証役場で保管されています。
自筆証書遺言・秘密証書遺言は自宅などで保管されているため、被相続人から場所を聞いていない場合は書斎など思いあたる場所を探してみましょう。
なお、公正証書遺言と、保管制度を利用した自筆証書遺言以外は、見つけても勝手に開封してはいけません。
開封には家庭裁判所の検認手続きが必要なので注意しましょう。
遺言書がない場合は遺産分割協議を行う
遺産分割協議とは、相続人全員で相続財産の分け方を話し合うことです。
遺言書がない場合、遺産分割協議または法定相続割合で相続することになります。
また、遺言書があるケースでも、遺言書に記載のない財産があった場合と、遺言書とは異なる割合で相続する場合では遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議では、相続人全員の合意がなければ成立しません。
誰か1人でも話し合いに合意しない・参加しない人がいると、遺産分割協議が無効になるので注意しましょう。
遺産分割協議後に新たに相続人が判明すると、再度協議をやり直すことになります。
そのため、遺産分割協議前に相続人と相続財産をしっかり調べて確定させておくようにしましょう。
相続登記を行う
相続登記とは、不動産の名義を被相続人から相続人に変更する登記手続きです。
遺産分割協議で土地の相続の仕方が決まれば、速やかに相続登記を行いましょう。
相続登記は、必要書類を揃えて不動産を管轄する法務局で手続きします。
主な必要書類は以下のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書または遺言書
- 固定資産評価証明書
- 相続登記の申請書 など
なお、遺言書や遺産分割協議など相続の仕方によっても書類が異なるので、事前に法務局のホームページで確認しましょう。
相続登記は自分で行う他、司法書士への依頼も可能です。
手続きに不安がある、時間が取れない、法務局が遠方などの場合は依頼を検討するとよいでしょう。
相続税を支払う
相続税は、現預金などのプラスの財産から、借金などのマイナスの財産を差し引いた正味の財産が基礎控除を超えた場合に、その超えた分に課税されます。
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」です。
たとえば、法定相続人が配偶者と子ども(兄弟2人)であれば、3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除となり、この額を超えたときに相続税が課税されます。
相続税が課税される場合、納税期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
死亡したことを知った日とは、一般的には被相続人の死亡日になります。
土地を売却して相続税の納税を検討しているなら、10ヵ月以内に相続手続きと売却を進める必要があるので、早めに行動するようにしましょう。
相続税のための売却なら、短期間で売却できる買取を視野に入れるのも1つの方法です。
相続トラブルを避けるために知っておきたい遺産分割の方法
土地を兄弟で相続する場合、どのように分割すればよいのでしょう。
遺産分割の方法には以下の4つがあり、その中から状況に合わせて選ぶことになります。
- 現物分割
- 換価分割
- 代償分割
- 共有分割
それぞれ見ていきましょう。
現物分割
現物分割とは、遺産をそのまま相続する方法です。
たとえば、兄が土地・弟が現金というように相続します。
また、土地であれば、分筆してそれぞれで相続するケースも現物分割にあたります。
現物分割はシンプルな相続方法ですが、種類が異なる遺産で分けると不公平が生まれやすくなります。
土地を分筆するケースでも、どのように切り分けるかで揉める恐れがあるので注意しましょう。
そもそも分筆しても十分な広さが取れる広大な土地でないと、分筆後にデメリットが生じやすい点にも注意が必要です。
換価分割
換価分割とは、遺産を売却して現金を分ける方法です。
現金であれば、相続人で公平に分割できトラブルになりにくいというメリットがあります。
土地に活用予定がないなら、換価分割が現実的な方法でしょう
しかし、換価分割には売却の手間や時間がかかるため、早めに売却を進めることが大切です。
代償分割
代償分割とは、遺産を相続した人が、他の相続人に対して代償金を支払う方法です。
たとえば、相続財産が土地2,000万円で兄弟2人が相続人の場合、本来なら兄弟がそれぞれ1,000万円ずつ相続します。
このとき、兄が土地をすべて相続する代わりに、弟に1,000万円を支払う方法が代償分割です。
代償分割であれば平等な相続をしやすいですが、相続人に代償金を支払うだけの資金力が必要です。
そのため、現実的には用いるのが難しい方法ともいえるでしょう。
共有分割
共有分割とは、特定の相続人が相続するのではなく、相続人同士で共有する方法です。
土地を兄弟で相続するのであれば、兄弟の共有名義にして相続します。
この際、共有持分は法定相続分か遺産分割協議で決めた割合になるのが一般的です。
共有名義であれば、土地を分割する必要がなく平等に相続しやすくなります。
しかし、不動産を共有名義にするとトラブルが起きやすいので、あまりおすすめできません。
共有名義のトラブルについては後ほど解説するので参考にしてください。
親名義の土地を兄弟で相続する際にトラブルを避けるためのポイント
相続時に兄弟でトラブルになると、相続手続きがストップする・関係性が悪化するなどの恐れがあります。
親としても兄弟が相続でトラブルになるのは望まないところでしょう。
トラブルを避けるためには、以下のようなポイントを押さえておくことが大切です。
- 土地を兄弟で共有名義にしない
- 親に遺言書を用意してもらう
- 土地を相続する人を決めて生前から相続資金の準備を進める
- 土地を売却するのも一つの方法
それぞれ見ていきましょう。
土地を兄弟で共有名義にしない
共有名義の不動産は、共有者の合意がなければ売却できません。
自分の持分だけであれば単独で売却できますが、共有持分のみを購入する買主はほとんどいないため、安値での売却になるか、そもそも売却できない恐れがあります。
また、共有名義のまま次の相続が発生すると、より権利関係が複雑になる点にも注意が必要です。
たとえば、兄弟で土地を共有しているとき、兄に相続が発生すると、兄の持分は兄の相続人が相続することになります。
仮に、兄の相続人が妻と子ども2人でさらに土地を共有することにしたら、この時点で共有者は弟と兄の妻・兄の子ども2人の4人ということになるのです。
さらに、そのような相続が続けば、共有者は膨れ上がり、権利関係がより複雑になるでしょう。
共有名義の土地は利用しにくいうえにトラブルになりやすいため、できるだけ共有にならないように相続の仕方を決めることをおすすめします。
親に遺言書を用意してもらう
遺言書があれば兄弟で意見を主張する必要はなく、トラブルを避けやすくなります。
家族全員で相続について話し合い、遺言書を作成してもらうように進めましょう。
ただし、遺言書があっても以下のようなケースでは別のトラブルに発展しかねないので注意が必要です。
- 遺言書の内容が偏っている
- 遺言書の形式に不備がある
「兄にすべて相続させる」というように、偏った遺言を作成すると兄弟間でトラブルになりがちです。
一定の相続人には最低限の財産を取得する遺留分が認められており、遺言書でも遺留分の侵害はできません。
そのため、遺留分を侵害された相続人が、侵害した相続人に対して侵害分の請求を行う可能性があります。
また、遺言書には厳格なルールが設けられており、日付がないなど形式不備で無効になる恐れもあるので注意が必要です。
遺言書は遺留分や形式など考慮すべき点も多いので、不安がある方は弁護士などの専門家への相談をおすすめします。
土地を相続する人を決めて生前から相続資金の準備を進める
兄弟のうちどちらかが土地を相続すると、もう片方にはそれに見合った別の相続財産を用意しておく必要があります。
また、土地だけ相続した方も、相続税に対応できない可能性があるでしょう。
相続財産として現預金を貯えておく、生命保険を活用するなど、相続時に相続人が困らないような対策をしておくことも大切です。
土地を売却するのも一つの方法
相続財産に不動産があるとトラブルが起きやすい為、売却するのも一つの方法です。
生前中に被相続人が売却しておけば、売却金は被相続人の老後資金にでき、余ったら現金として相続させることができます。
相続後であっても売却することで、現金で分割できトラブルを避けやすくなるでしょう。
将来活用予定がない土地は、相続しても管理の費用や手間がかかります。
早い段階で売却することで、相続対策や管理の手間・費用の削減ができるでしょう。
親名義の土地の相続に関するよくある質問
最後に、親名義の土地の相続に関するよくある質問をみていきましょう。
親が生きているうちに土地の名義を兄弟に変更することはできる?
名義の変更は可能ですが、名義変更は贈与に該当し、贈与税がかかる可能性が�あります。
贈与税は、年間の贈与額から110万円の基礎控除を控除した額に課税されます。
贈与額は土地の評価額で判断されるので、評価額(主に固定資産税評価額が参照される)が110万円を超えると贈与税の対象です。
贈与税は相続税よりも税額が高くなりやすいので、事前に税額を確認して判断するようにしましょう。
ただし、相続時精算課税制度を利用する、または売買で名義を変更することで贈与税対策も可能です。
生前中に名義を変えておくと相続トラブルを避けやすいというメリットもあるので、贈与税対策を視野に入れながら検討するとよいでしょう。
相続時に土地を兄弟で分割することはできる?
土地が広いのであれば、分筆してそれぞれの名義で相続することが可能です。
それぞれの土地の名義人は1人ずつになるので、活用や売却もしやすくなります。
しかし、分筆後に活用しやすい広さの土地が確保できるかも重要になってきます。
分筆後の土地が狭かったり形状が悪かったりすると、活用や売却が難しくなるので注意しましょう。
死亡した兄弟がいる場合の土地の相続はどうなる?
相続人である兄弟のどちらかが死亡している場合、死亡した相続人については代襲相続が発生します。
代襲相続とは、本来相続人となるはずの人が亡くなっている場合で、その子どもなどが変わって相続する制度です。
たとえば、父親が死亡し相続人が子どもである兄弟2人のケースで、兄が死亡しているとします。
この場合で、兄に子ども(被相続人の孫)が2人いるなら、兄の相続��分はその子どもが相続することになるのです。
なお、被相続人の相続人が子どもである場合は、その人が亡くなっていれば孫が代襲相続人となり、さらに孫も亡くなっていると孫の子どもというように、順次代襲相続人が引き継がれます。
しかし、被相続人の相続人が子どもではなく被相続人の兄弟姉妹の場合、代襲相続は甥姪までしか認められておらず、甥姪の子どもは代襲相続できないので注意しましょう。
まとめ
親名義の土地を兄弟で相続するケースでは、分割方法や相続税を巡ってトラブルになりがちです。
また、分割でのトラブルを避けようととりあえず土地を共有名義にしてしまうと、土地の活用や売却に制限がかかり将来困った事態にもなりかねません。
土地を含め不動産の相続は、トラブルになりやすいので遺言書など事前の相続対策を行うようにしましょう。
相続後に活用する予定がないなら、事前に売却しておくのも一つの方法です。
売却金であれば自分が活用できる他、相続人で公平に分割でき相続税にも対応できるので、スムーズな相続を目指しやすくなるでしょう。