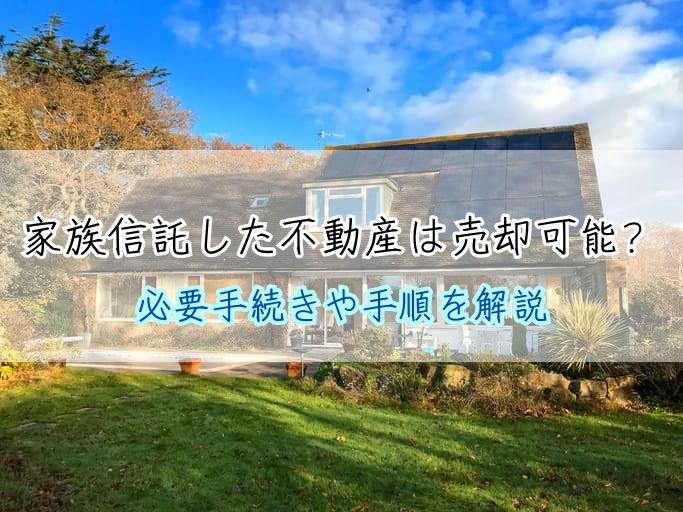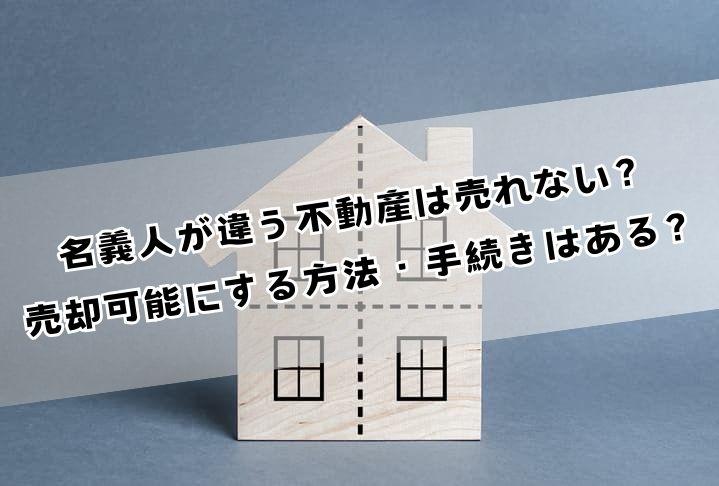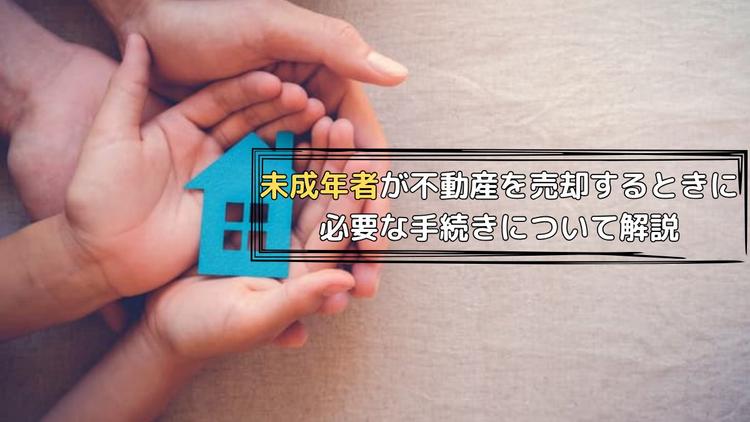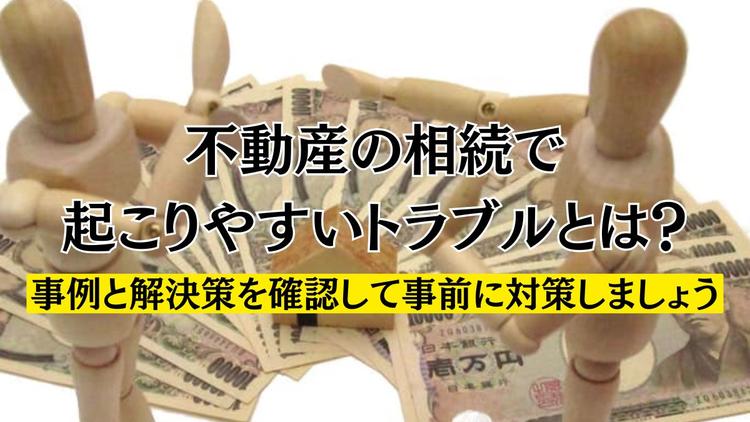違反建築物を相続する事態になれば、多くの方が戸惑い、不安を感じるのではないでしょうか。
しかし、適切な手順を踏めば、問題を解決して不動産を有効活用することも可能です。
この記事では、違反建築物を相続した際に必要な手続きと、売却時の注意点を解説します。
違反建築物とは
違反建築物とは、建築基準法やその他の法令に違反して建てられた建築物のことを指します。
違反建築物を相続したときの対策を考えるために、まずは違反建築物について押さえておきましょう。
手続き違反
建物を新築する際には、建築確認申請が必要です。しかし、この手続きを行わずに建築された「違反建築物」も存在します。
近年では、建築確認済証のない建築物に対して住宅ローンの融資が受けられないことが一般的なため、無確認で新築されるケースはほとんどありません。
しかし、相続対象となるような古い建物の場合、当時の時代背景によっては建築確認申請を無視して建てられたものもあります。
また、建築確認申請を行わない理由として、違反建築物を建てることを前提にして、あえて申請をしないというケースもあります。
そのため、多くの場合、単なる手続き違反にとどまらず、建物そのものが法規制に違反している可能性が高いです。
建ぺい率・容積率オーバー違反
市街化区域内は、都市計画により建ぺい率や容積率が定められています。
建ぺい率
容積率
新築時には、指定の建ぺい率・容積率の範囲内で建築していても、その後の増築でこれをオーバーしてしまうことがあります。
また、相続する古い住宅の中には、当時の住宅金融公庫(現・独立行政法人住宅金融支援機構)の住宅ローンを利用して建築された建物を除き、完了検査の受検率が極端に低かった時代のものもあります。
そのため、完了検査を受けないことを前提に工事が進められ、建築確認申請書に記載された内容とは異なる規模の建物が建てられているというケースも少なくありません。
用途地域制限違反
用途地域は全部で13種類あり、それぞれの地域で建築できる建物の高さや用途が定められている。
都市計画法で定められた用途地域(第一種住居地域、商業地域など)では、営業が制限される用途の建物が建てられているケースがあります。
当初は適法でも、業種を変更することで用途地域制限違反になることがあります。
たとえば、第一種低層住宅専用地域において、店舗兼用住宅として豆腐屋を営んでいた人が、ペット美容室に業種変更をした場合は、用途制限違反となる可能性があります。
接道義務違反
建築物の敷地は、建築基準法により、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接している必要があります。
しかし、この基準を満たしていない敷地に建物が建てられている場合、接道義務違反となります。
違反建築物を所有する問題点とは
相続をして違反建築物の所有者になると、数々の問題点を抱えることになります。
そもそも違反建築物は、法令で定められた基準を満たしていない可能性があり、地震や台風による倒壊、火災による延焼などのリスクが高まります。
また、違反建築物の建築に直接関わっていなくても、相続により所有者になった場合は、行政からの是正指導や命令を受ける可能性があるでしょう。
さらに、再三の命令を無視し続けた場合、行政代執行の対象になることがあり、その費用は基本的に建物所有者の負担になります。
問題の多い違反建築物は、購入しても買主にほとんどメリットがなく、資産価値の面でも適法な建築物に比べて評価が低くなる傾向があることを覚えておきましょう。
既存不適格は違反建築物ではない
現行の建築基準法に適合していない建物として「既存不適格」というものがあります。しかし、既存不適格は違反建築物ではなく、適法な建築物です。
既存不適格とは、建築時には適法に建てられたものの、その後の法改正や都市計画の変更などによって、現行の基準に適合しなくなった建築物を指します。
そのため、現行の基準に適合しない建築物を相続した場合でも、すぐに違反建築物だと判断するのではなく、まず既存不適格に該当するかを確認することが重要です。
既存不適格と違反建築物では、資産価値やその後の対応策が大きく異なるため、適切な判断を行いましょう。
なぜ既存不適格になるのか
相続した建築物が既存不適格になった原因として、次のようなケースが想定できます。
- 家を建てた後で、建ぺい率や容積率が都市計画によって指定された。
- 何代も前から機械製造業を営んでいたが、都市計画で住居系用途地域に指定された。
- 古くから建つ家の前の通路が、建築基準法の道路規定に適合しない。
これらの建物は、既存不適格建築物として扱われ、基本的にはそのまま使用することができます。
なぜ既存不適格は違反建築物ではないのか
現行の建築基準法に適合しないことから、既存不適格は違反建築物のひとつであると考える人もいるかもしれません。しかし、違反建築物でないことは、建築基準法の次の条文(要約)を読めば一目瞭然です。
「この法律の施行前の建築物もしくはその敷地がこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地に対しては、当該規定は、適用しない。(第3条2項)」
つまり、法律が施行される前に建てられた建築物に対しては、新たに適用された基準に適合していなくても、違反とはみなさないという考え方です。
そのため、既存不適格建築物には、建築基準法に違反している条項は一切ないということになります。
既存不適格は��増築等ができない
既存不適格建築物は、建物に手を加えなければ、現行法令は適用されませんが、反対に増築や大規模の修繕・模様替を実施した際には、たちまちこの適用除外が解除されます(同法3条3項)。
大規模な修繕や模様替は、一定の規模以下であれば建築確認申請が不要な場合もあります。
しかし、その場合でも現行の建築基準法が適用されるため、既存不適格の状態が解消されない限り、その工事を行うことはできません。
用途不適格は例外的に増築が可
既存不適格建築物は、増築をすると現行法令が適用されるため、不適合部分を解消しない限り増築等はできません。しかし、用途不適格に関しては、一定の増築が認められています(同法第86条の7、同法施行令137条の7)。
たとえば、何代も前から続く精密機械工場の敷地が、後に第一種住居地域に指定された場合、その建物は用途が適合しないため、用途不適格建築物として扱われます。その工場の機能を充実させるために増築を計画した場合、1.2倍までの増築が認められるのです。
つまり、100平方メートルの工場であれば、20平方メートルを増築して、120平方メートルの工場にすることが可能です。
ただし、工場が営業を継続していることが要件となります。たとえば、経営者の親が死亡し、いったん工場を閉鎖してしまうと、その時点で適法建築物ではなくなるため、既存不適格建築物としての扱いは受けられなくなります。
そのため、たとえ同種の工場であっても再開することはできず、指定された用途地域に適合する用途の建築物として使うことしかできなくなるのです。
違反建築物を相続したときの必要な手続き
相続した建物が違反建築物だった場合、放置すれば行政からの指導や命令を受けるだけでなく、安全性を確保できないリスクも生じます。また、売却時にもトラブルの原因となりかねません。
違反建築物を相続した際に、どのような手続きや対策をすればいいのか、解説をしていきましょう。
現状を把握する
相続した家が違反建築物の可能性が高い場合は、建築士などの専門家に依頼して、建物のどこにどのような違反があるかを詳しく調査してもらいます。
この違反の内容(建ぺい率オーバー、容積率オーバー、用途地域違反、防火規定違反など)により、対処方法や費用が大きく異なります。
また、建築確認済証や検査済証などの書類を確認し、違反に至った経緯を把握することも重要です。
そのうえで、相続した建物が適法であるのか、違反建築物であるのか、あるいは既存不適格であるのかを把握しましょう。
是正を検討する
相続した建物が違反建築物の場合は、是正方法を検討します。
たとえば、建ぺい率オーバーによる違反であれば、建物の一部を解体することで適法にすることが可能です。しかし、解体場所の選定は、使い勝手よりも、安全性や適法性を優先して判断する必要があります。
そのため、建築士や施工会社などの専門家に相談し、解決策を見つけることが重要です。
用途違反の場合は、違反とされている業務を廃業することになります。接道違反がある場合は、最悪のケースとして、建物の全撤去を検討することになるでしょう。
相続前から違反指導を受けている場合は、自治体��の建築指導課などの担当部署に相談し、違反内容と是正方法を確認した上で、行政の指導に従って是正計画を立てる必要があります。
違反の程度によっては、相続人が新たに是正命令や使用禁止命令を受ける可能性もあります。
なお、建築確認申請は、将来建築予定の建築に対する手続きです。そのため、是正して適法になったとしても、すでに完成した建物に対して建築確認申請はできません。
ただし、建築確認済証がない建築物であっても、現行法に適合している建築物であれば、完了検査を受けられる場合があります。詳しくは、管轄の自治体に問い合わせてみましょう。
▼関連記事:違反建築物の是正勧告を受けたらどうする?
相続放棄を検討する
状況によっては、相続放棄も検討した方がいい場合があります。特に次のようなケースでは、相続放棄も選択肢のひとつとなり得ます。
- 違反建築物の是正費用が、相続財産を上回る場合
- 違反建築物以外にも、多額の借金などの負債がある場合
- 違反建築物の扱いに困り、管理する意思がない場合
相続放棄は、相続開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申告する必要があります。ただし、相続放棄をすると、預貯金や不動産などのプラスの財産も一切相続できなくなる点に注意が必要です。
既存不適格は活用方法を検討する
相続した建物が既存不適格だった場合、新たな工事をしない限り、行政から指導を受けることはありません。そのため、慌てることなく、将来の活用方法をじっくりと検討することが��できます。
建物を使用する場合、構造材を大きく変更しないリフォームであれば施工が可能です。また、通常の方法で売却することもできます。専門家(建築士、不動産会社)に相談し、有効な活用方法を検討してください。
違反建築物を売却するときの注意点
違反建築物を売却する際には、通常の不動産売却とは異なる注意点があります。買主とのトラブルを避けるため、どのような点に注意をして進めればいいのか紹介していきましょう。
違反内容を買主に告知する
売主は、買主に対して違反建築物であることを告知する義務があります。違反内容を隠して売却すると、契約不適合責任を問われ、契約解除や損害賠償請求を受ける可能性があります。
告知は、口頭だけでなく、重要事項説明書などの書面で行うことが重要です。違反箇所や是正の必要性、費用などを正確に伝えましょう。
また、売買契約書には、違反建築物に関する事項を明確に記載しましょう。契約不適合責任の範囲や、売主・買主それぞれの責任などを明確にしておくことで、トラブルを防止できます。
住宅ローン利用の制限がある
違反建築物は、住宅ローンの審査が通りにくい、または通らない可能性があります。
買主が住宅ローンを利用できない場合、購入を見送る可能性も考慮しておく必要があります。
現金で購入できる買主をターゲットにするか、買主がローンを利用しやすいように、違反箇所を是正しておくなどの対策を検討しましょう。
売却価格を調整する
違反建築物は、通常の物件よりも売却価格が低くなる傾向があります。是正費用や住宅ローン利用の制限などを考慮し、適切な売却価格を設定することが重要です。
価格設定は、違反建築物の売却に慣れた不動産会社に依頼する方法が有効です。違反内容の調査や買主への説明、価格交渉などをスムーズに進めてくれます。
▼関連記事:違反建築物は売却できる?
まとめ
違反建築物を相続してしまった場合、適切な手順を踏めば問題を解決し、不動産を有効活用できます。
違反建築物とは、建築基準法などの法令に違反して建てられた建築物のことです。違反建築物には、手続き違反、建ぺい率・容積率オーバー、用途地域制限違反、接道義務違反などがあります。
違反建築物の問題点は、安全性や資産価値の低下、行政からの是正指導などが挙げられます。
同じ法律に適合しないものに既存不適格があります。既存不適格建築物は、建築時には適法に建てられたものの、その後の法改正などによって現行法に適合しなくなった建築物のことで、違反建築物とは異なります。既存不適格建築物は、増築等の制限がありますが、基本的にはそのまま使用できます。
違反建築物を相続した場合は、まず現状を把握し、違反内容に応じて是正、相続放棄などを検討する必要があります。
違反建築物を売却する場合は、違反内容を告知し、売却価格を調整する必要があります。また、住宅ローン利用の制限があることにも注意が必要です。
違反建築物の相続は、複雑で専門的な知識が必要です。そのため、建築士や不動産会社などの専門家に相談しましょう。