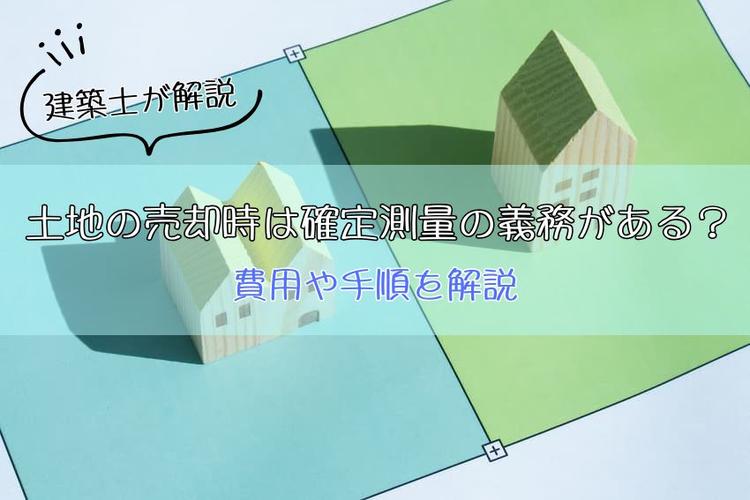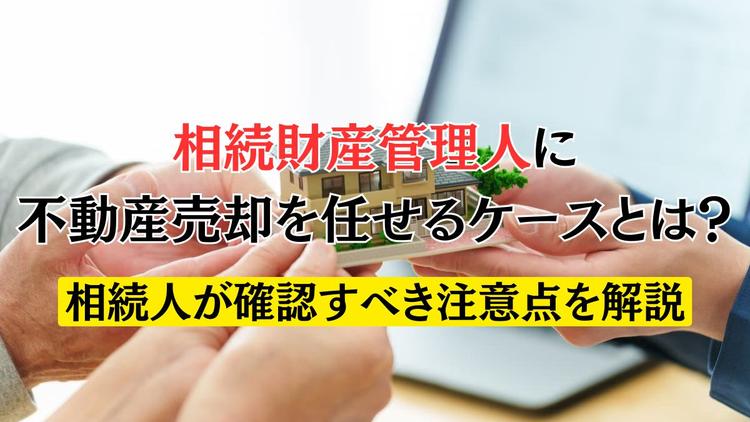相続財産の中に農地が含まれていたら、「自分は農業を営むつもりはない」と対処に迷う方もいるのではないでしょうか。
農地は農地法の規制があり、一般的な土地のようにすぐに売却できるわけではありません。
この記事では、相続した農地の売却方法と注意点、さらには相続放棄をする方法について解説をします。
農地を相続したらどうする?
田んぼや畑などの農地を相続するとき、相続人が農業従事者であれば、引き続き自身が農業を営むことで農地を維持できるので、大きな問題は生じません。
しかし、相続人が被相続人とは別の都市に住んでいる場合や、農業をする意思がない場合には、農地の扱いを検討しなくてはなりません。
農地の売却には農業委員会の許可が必要
一般的な土地を売却する場合、不動産会社に売却の仲介を依頼しますが、農地は農地法の規制があるため扱いが異なります。農地法とは農地の保護を目的に、転用や売買について規制する法律のことです。
農地を農地以外の用途に転用する場合は、農地法に基づき農業委員会への許可申請や届出が必要になります。
農地転用の手続きをしなければ所有権が移転できない(売却できない)
特に許可申請を要する農地を売却する場合、農地法の手続きを踏まなければ、法務局で所有権移転の登記ができないのです。
農地をいったん宅地にしてしまうと、再び農地に戻そうとしても、物理的にも法律的にも大きな困難が立ちはだかります。それだけに農地を転用することには慎重な判断を要するのです。
こうした状況を踏まえながら、相続人としては農地のまま維持するのか、あるいは転用するのかという選択を迫られることになります。
農地を継続する場合の対応
相続した農地をその��まま農地として維持したい場合、次のような選択肢があります。
- 自ら農業を営む
- 農地を貸し出す
- 農地を農地として売却する
それぞれどのような対応になるのか解説していきましょう。
自ら農業を営む
相続による農地の名義変更は農地法の許可は不要とされています(農地法第3条第12項)。
ただし、相続の発生から10カ月以内に農業委員会への届出を行わなければなりません。
一般の人が農地を取得する場合、市町村の農業委員会に農家として登録される農家資格が必要です。
しかし、被相続人が主たる従事者として農家資格を有していれば、相続人はその農家資格を引き継ぐことができるのです。
そのため、自ら農業を営む決断をした場合、法律的に大きな障害はありません。
課題となるのは、農業経営や農作物を育てるノウハウを取得するという点に絞られます。
農業は、知識もなくできるものではありません。相続するまで一切農業に関わっていなかった場合、当面の間、採算が取れないリスクがあります。
農地を貸し出す
相続した農地を近隣の農家に貸し出す方法もあります。
貸し出す場合、所有する農地が属する市町村の農業委員会から農地法第3条の許可を受けなければなりません。
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可(これらの権利を取得する者(政令で定��める者を除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合その他政令で定める場合には、都道府県知事の許可)を受けなければならない。
借手を探すのが難しい場合、自治体の農業関係部署やJAに相談すれば、仲介してくれる制度があります。
一定の手数料が差し引かれますが、賃料を得ることができます。
農地のまま売却する
農地を農地のままで売却する方法もあります。
農地のままで売却するには、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要になります。
この場合、売却先は農業を営んでいる者(個人または法人)でなければなりません。
また、継続的に農業を営んでいるかという厳格な要件もあります。
そのため、購入希望者がほとんど現れないのが実情です。
また、宅地化前提の売却とは異なり高額で売却されることはほとんどありません。
農地をやめる場合の対応
相続した農地を農地以外の用途で活用したい場合は、次のような対応を選択することになります。
- 農地転用して自ら活用する
- 農地転用を前提にして売却する
- 相続放棄する
それぞれ、具体的な対応について解説していきましょう。
農地転用して自ら活用する
農地転用とは、農地を農地以外の土地に変えることをいいます。たとえば、「宅地」に変えて家を建てることや、「雑種地」に変えて駐車場にするといったことです。
農地を相続人自らが農地以外に転用する場合、その農地を管轄する市町村の農業委員会の許可が必要です。
この場合、農地法第4条の許可を取得します(市街化区域内の農地は届出)。
農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。
ただし、次の区分に分類される農地は、原則として農地転用が認められません。
- 農用地区域内農地
- 甲種農地
- 第1種農地
これらの地域は、生産性の高い農地や、農地としての保護優先度が高い土地であり、そもそも都市計画法上の制限で一般的な住宅や賃貸住宅を建てることができない地域です。
一方で、次の区分に分類される農地であれば、原則として農地転用が認められます。
- 第2種農地
- 第3種農地
第2種農地を転用する際は、他に代替できる土地がないことが審査されます。
そのため農地転用をするのが当該農地でなければならない理由が求められます。
第3種農地は、基本的に農地転用が可能です。
農地転用を前提にして売却する
相続した農地を農地転用することを前提にして売却する選択肢もあります。
買主が農地転用をする場合、その農地を管轄する市町村の農業委員会の許可が必要です。
この場合は、農地法第5条の許可を取得します。
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。
市街化区域であれば、建築用地として売却できる可能性がありますが、市街化調整区域だと建築できる用途が限定されるので、売却できない可能性があります。
相続放棄をする
農地に関わることが煩わしい場合などには、相続放棄としいう選択肢があります。
相続が始まってから3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行うことで、農地を含む財産の相続を放棄できます。
ただし、農地だけに限定して相続放棄をすることはできません。相続放棄はすべての財産を放棄することを意味しているからです。
たとえば、預貯金や自宅などの相続財産も合わせて相続放棄することになります。
したがって、農地以外に高額の遺産が存在する場合には、相続財産の全体を見渡して、相続するのか放棄するのかの判断をする必要があります。
ここで気をつけたいのは、相続放棄をしても管理責任は残るということです。
相続放棄をしても、新たに相続人となった人が相続財産の管理を始めるまでは、自分の財産と同じように注意を払ってその財産の管理をしなければならないと民法第940条�で定められています。
そのため、相続人全員が相続放棄をしても、相続財産管理人が選定されるまでは、法定相続人全員に土地の管理責任が残ります。
農地を相続したときの手続き
農地を相続した場合、法定相続人であれば、まず法務局で相続登記をしてから、農業委員会に相続の届出をするという流れになります。
ただし、法定相続人以外の人が相続(受遺)した場合は、最初に農業委員会で農地法第3条の許可を受ける必要があり、その後に法務局で登記をする流れになります。
法務局で相続登記をする
管轄の法務局で、農地の相続登記を行います。一般的な農地の取得では、農業委員会の許可がないと登記ができませんが、相続登記は書類に不備がなければ登記ができます。
申請に際しては、次の書類を添付します。
- 被相続人の連続した戸籍謄本類
- 相続人の戸籍謄本
- 該当する農地を相続する相続人の住民票
- 遺産分割協議書もしくは遺言書
農業委員会へ相続の届出をする
農地を管轄する市町村の農業委員会へ相続の届出を行います。届出の際には、農地法の規定による届出書と登記事項証明書を提出します。
農業委員会への届出は、相続開始を知った日から10カ月以内に行わなければいけません。
期限を過ぎて届出がされていない場合は、10万円以下の過料を求められることがあります。
相続放棄の方法
相続放棄は、相続が始まってから3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行う必要があります。
相続放棄はすべての相続財産を放棄することを意味します。預貯金や自宅などの不動産だけ相続して、農地を相続放棄するといった選別はできません。
そのため、農地以外に高額の相続財産がある場合は、慎重な判断が求められます。
相続��放棄をする手続きの流れを解説していきましょう。
書類を準備する
相続放棄には、次の書類が必要になります。
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人の戸籍謄本
相続放棄の申述書には、申述人と被相続人との関係や、相続放棄をする理由、相続財産の概略などを記載する欄があります。申述人1人につき収入印紙800円の納付が必要です。
書式は、裁判所のホームページからダウンロードできます。
上記の書類の他に、申述人と被相続人との関係性に応じて別途書類を用意します。たとえば申述人が被相続人の配偶者だと、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)が必要です。
家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
書類の申述先は、被相続人が亡くなる前に在籍していた住所地を管轄する家庭裁判所です。必要書類を、申述先に郵送します。
連絡用の郵便切手の同封が必要な場合がありますので、事前に申述先の家庭裁判所に確認してください。
申告期限は、相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内です。確実に期限内に手続きをするようにしましょう。
相続放棄照会書を送る
相続放棄を申し立てると、家庭裁判所から相続放棄照会書が届きます。
相続放棄照会書とは、相続放棄が申述人の意思によるものかを確認するため、家庭裁判所から送付される書類です。真に本人の意思による申述か、申述後の意思に変わりがないかが、照会書によって確認さ��れます。
内容に問題がなければ、必要事項を記入して照会書を送り返します。
照会書を送った後、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。これが正式に相続放棄したことを証明する書類です。
農業委員会に届出をする
相続放棄を行い、他の相続人が農地を相続することになった場合には、その相続人が農業委員会へ名義変更の手続きを行います。
届出は相続開始から10カ月以内に行う必要があり、怠ると10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
農地を売却する際の注意点
農地の売却は、農地法の規制があるため、一般の土地の売却と扱いが異なります。農地特有のルールに戸惑うことのないよう、農地を売却する際の注意点について解説していきましょう。
農地法3条許可が認められないことがある
農地の売却は、原則として農業委員会の許可が必要です。農地を農地のまま売却する際の許可は農地法の第3条許可になります。
3条許可は、農地として利用することが前提となっているため、農地所有適格法人(農地等の権利を取得し、農業を行うことのできる法人のこと1)以外の一般的な会社や信託会社、信託銀行などは農地の権利を取得することができません。
また、個人の場合であっても、所有権を取得しようとする者やその世帯員が農地の取得後に、農作業に常時従事すると認められない場合は、許可を受けることができません。常時従事とは年間150日が目安とされています。
その他農地の面積要件や効率的な農作業ができないなどの要件によって、許可が認められないことがあります。
第3条許可が受けられない場合、法務局で所有権移転の登記を行うことができません。
農地転用許可が認められないことがある
農地を転用して他人が所有する場合は、農地法の第5条許可が必要です。ただし、要件によっては、第5条許可が受けられないことがあります。
そもそも「農用地区域内農地」「甲種農地」「第1種農地」にある農地は転用が認められません。
転用が認められる「第2種農地」「第3種農地」であっても、農地転用の確実性や、周辺農地への被害を防ぐための措置の妥当性などについて審査があります。
そのうえで、次に該当すると判断されたものは許可を受けることができません。
- 他法令の許認可の見込みがない
- 関係権利者の同意がない
- 周辺農地への被害防除措置が適切でない
- 一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められない
なお、市街化区域にある農地については許可申請は不要で届出が必要となります。
譲渡所得税の納付が必要になる
農地売却は、通常の土地売却と同じように次の税金が課せられます。
- 登録免許税
- 印紙税
- 譲渡所得税
このうち、最も負担が大きくなるのが、譲渡所得税です。ただし、農地として売却した場合は、特別控除が設けられているため税負担は軽減されます。
譲渡所得税の計算式は次のとおりです。
- 譲渡所得 = 収入金額 – 取得費 – 譲渡費用
- 税額 = 譲渡所得 × 税率
譲渡所得に乗じる税率は、次のとおりです。
- 短期譲渡所得(5年以下)……39.63%
- 長期譲渡所得(5年超)……20.315%
税率には、所得税、住民税、復興特別所得税が含まれています。税率は、農地の所有期間が5年を超えるかどうかで変わります。
相続で得た農地は、被相続人が取得した時期が相続人に引き継がれます。このため、多くのケースは長期譲渡所得にな�ると考えられます。
譲渡所得は農地を売却した翌年の確定申告後に納付します。
確定測量図が必要になる
農地の場合、慣習的な使い勝手だけで大きなトラブルになることはありませんが、宅地として売却する場合には、境界確定が必要になることがあります。
この場合、農地の全周を測量して、隣接所有者立ち会いのもと、境界画定図を作成することになります。
確定測量図は土地家屋調査士に依頼して作成します。費用は農地の大きさや形状によって異なりますが、概ね40~80万円です。
農地転用しても建築できないことがある
農地転用をして、自宅や賃貸住宅の建築を計画しても、都市計画法の規定により、建築ができないことがあるので注意が必要です。
都市計画区域には、市街化区域と市街化調整区域があります。
このうち市街化調整区域は、原則として市街化を抑制する区域なので、一般的な住宅や賃貸住宅の建築は認められません。
自宅の建築が認められるのは、建築主が農業従事者であるいわゆる「農家用住宅」であるケースです。
農地転用して売却するにはどれぐらいの時間がかかる?
農地転用は必要な許可申請を行えば市街化調整区域であっても2~3カ月で完了することが多いですが、過去に「イエウリ」を通じて「農地を宅地に転用して売却した」というケースでは、査定依頼から約2年の時間がかかったケースがあります。
【成約実績 No.0485】
石川県 河北郡津幡町
農地転用の必要があり、登録から約2年を経て
買取成立となった。時間がかかると分かれば見限る会社様も多い中、
イエウリの会社様が辛抱強く待っていただいたおかげで
成立となっています。#企業公式相互フォロー#イエウリ#石川県#河北郡津幡町pic.twitter.com/PY2MfOkjUd— イエウリ【公式】 (@ieuri_ieuri) December 18, 2024
一方で、既に宅地転用の手続きを終えていれば、仲介で2カ月程度の期間を経てスムーズに売却できたケースもあります。
【成約実績 No.0336】
茨城県 坂東市
元々農地だった本物件を転用し宅地に。
その後居住をするものの、約1年で転勤になったため、
空き家となっている��本物件を売却したい。急ぎではなかったため、仲介で売り出し、
約2か月で売却となった。#企業公式相互フォロー#イエウリ#茨城県#坂東市pic.twitter.com/xfkb8ZmlrU— イエウリ【公式】 (@ieuri_ieuri) July 19, 2024
農地転用の申請に必要な手続きに時間がかかることもあるため、自身で活用しない農地を相続等で取得した場合は、不動産会社や行政書士に早めに相談することをおすすめします。
▼関連記事

まとめ
農地を相続した場合、まず農地として持続させるのか、あるいは別の用途に転用するのかという選択をする必要があります。
農地として持続させる場合は、さらに次の選択肢を選びます。
- 自ら農業を営む
- 農地を貸し出す
- 農地を農地として売却する
貸し出しや売却には、農業委員会の許可が必要になります。また相手先には、農業従事者に限定されます。
農地以外の用途に転用する場合は、次の選択肢を選びます。
- 農地転用して自ら活用する
- 農地転用を前提にして売却する
- 相続放棄する
農地転用をして建築用地とするには、農地が市街化区域に属していなければなりません。市街化調整区域では、建築できる建築物の用途が限定されているので要注意です。
相続放棄は、相続が始まってから3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行う必要があります。相続放棄をする場合は、相続財産のすべてを放棄することになるので、農地以外の相続財産をしっかり把握した上で判断することが重要です。