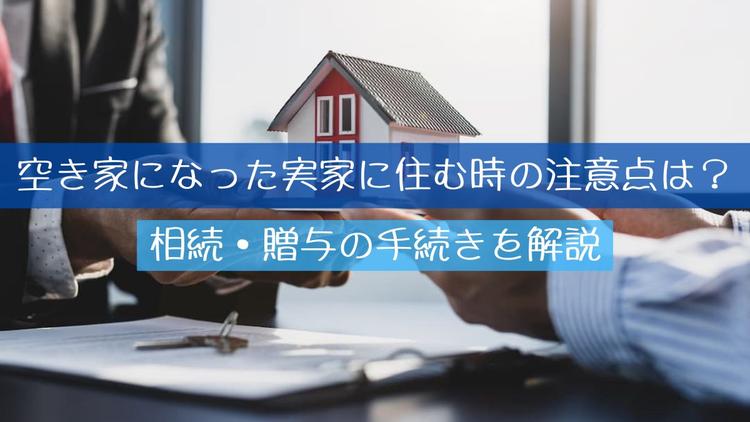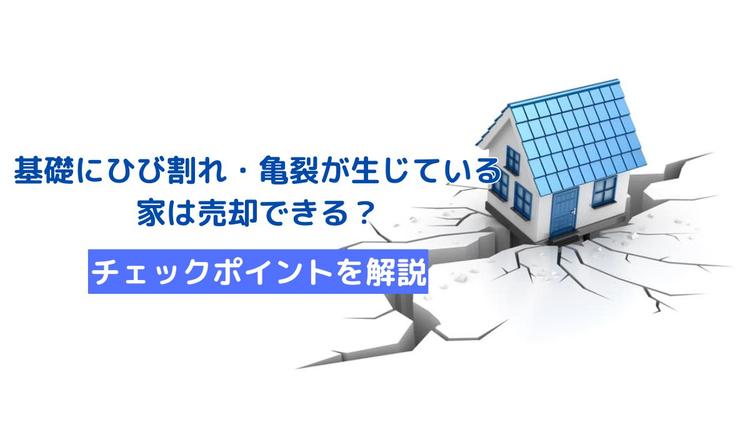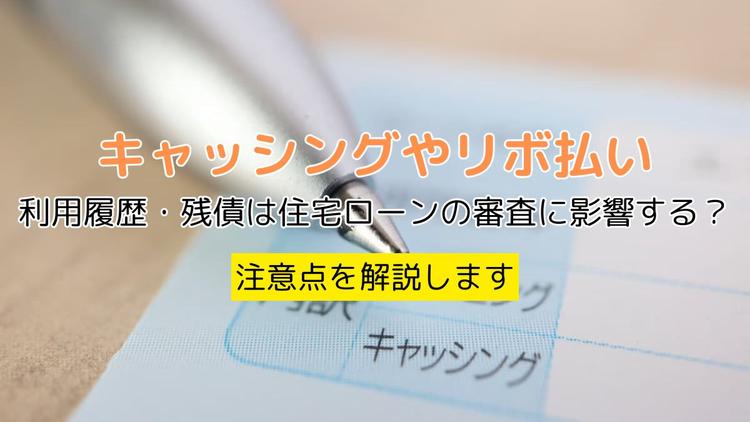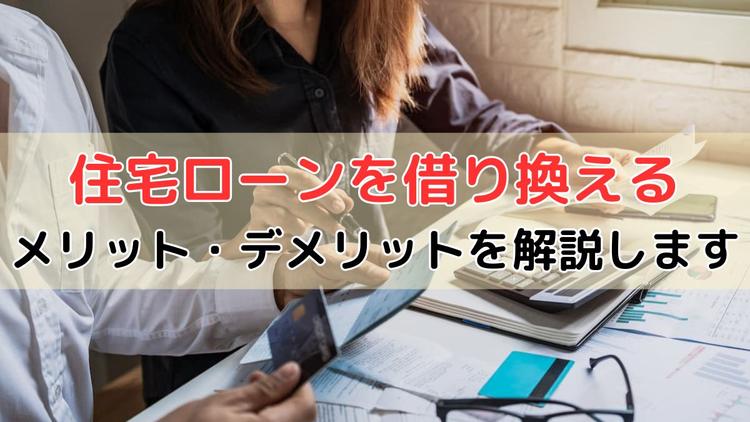実家が空き家になった際の選択肢の1つに「住む」ことが挙げられます。
実家に住むのであれば、家賃の支払いが必要なく家を自分で管理できるといったメリットがあります。
しかし、実家に住む場合でも相続税や贈与税、相続人間トラブルなどデメリットも生じやすい点には注意が必要です。
この記事では空き家になった実家に住むデメリットや注意点、贈与税や相続税について詳しく解説します。
空き家になった実家に住むデメリット・注意点
相続により実家が空き家になったり、親が施設に入居したことによって実家が空き家になったりするケースは、多くの人が経験するものです。
空き家になった実家の選択肢としては、「誰かが住む」「売却する」「賃貸に出す」などが検討できます。
なかでもシンプルに手間なく解決できる方法が「誰かが住む」ことでしょう。
しかし、実家に住む場合でも他の兄弟姉妹とトラブルになったり、税金が発生するなどデメリットや注意点があるので、慎重に検討することが大切です。
空き家になった実家に住むデメリット・注意点としては、以下の4つが挙げられます。
- 兄弟間でトラブルになる可能性がある
- 維持管理費がかかる
- 贈与税や相続税を納税する必要がある
- 相続の手続きを済ませておかないとペナルティを受ける可能性がある
それぞれ見ていきましょう。
兄弟間でトラブルになる可能性がある
空き家になった実家を相続して住むことになった場合、将来的に兄弟とトラブルになる可能性があります。
親が亡くなって相続が発生した場合、兄弟は基本的に親の資産を引き継ぐ権利のある法定相続人だからです。
一般的な家庭の相続では、家が相続財産の中で最も価値が大きくなりやすいものです。
家の価値が大きい場合、誰が相続するか、遺産分割をどうするかで揉��めやすくなります。
例えば、家の資産価値が2,000万円、その他の相続財産が600万円というケースで、相続人が子ども2人の場合を考えてみましょう。
この場合、それぞれの子どもは1,300万円ずつの法定相続分を持つことになりますが、片方が家を相続する(住む)となると、もう片方がその他の財産をすべて相続しても相続に不平等がおきます。
- 子A:家(2,000万円)
- 子B:その他の相続財産(600万円)
このケースでトラブルになるようであれば、子Aは子Bに対して差額分の700万円を現金で支払うといった対策が必要になるでしょう。
相続した家に相続人の一部が住む場合、他の相続人に不動産の評価額に応じた金銭を分配することで公平に相続財産が分配できる。
空き家になった実家に住むことで、兄弟間で相続絡みのトラブルに発展しそうであれば、早い段階で弁護士などの専門家に相談することが大切です。
維持管理費がかかる
空き家になった実家に住む場合、家の維持管理費を負担しなければなりません。
一般的な戸建ての維持管理費としては、以下のような費用が挙げられます。
- 固定資産税・都市計画税
- 修繕費やメンテナンスの費用
固定資産税や都市計画税は毎年負担する必要があるので、事前に額を確認しておく必要があります。
突発的な故障や劣化による修繕も自分で費用を負担して行わなければなりません。
空き家になった実家に住むのにも、上記のようなランニングコストがかかるので、事前に資金計画を立てておくようにしましょう。
贈与税や相続税を納税する必要がある
家は相続税・贈与税の対象となる資産です。
親が亡くなり、実家を相続して住む場合には、親の相続財産の額に応じた相続税を支払わなければなりません。
また、高齢の親が老人ホームに入居するなどして、親が生きている間に生前贈与で実家の贈与を受ける場合、家の価値に応じた贈与税を納める必要があります。
それぞれの税金の計算方法や手続きは後ほど詳しく解説します。
相続の手続きを済ませておかないとペナルティを受ける可能性がある
家を相続した場合は、相続登記が必要になります。
相続登記とは、家の所有者を被相続人(亡くなった人)から相続人に移す登記手続きです。
相続登記は2024年4月から義務化されており、相続開始後3年以内に登記しないと過料のペナルティが科せられる恐れがあります。
そのため、家に住む、売却するにかかわらず、相続後は速やかに相続登記手続きするようにしましょう。
なお、相続登記の義務化に伴い2024年4月以前の相続も義務化の対象となっています。
すでに相続したけど登記していないという人も早めに手続きしましょう。
空き家になった実家に住むメリット
空き家になった実家に住めば、家賃不要で家に住めるなどもメリットもあります。
ここでは、空き家になった実家に住むメリットとして以下の3つを解説します。
- 家賃を負担する必要がなくなる
- 慣れ親しんだ家に住むことができる
- 空き家のまま放置するより自分で維持管理できる
それぞれ見ていきましょう。
家賃を負担する必要がなくなる
実家に住んでしまえば、家賃を負担する必要はなくなり、これまで賃貸に住んでいたという方であれば生活費を大きく削減できるでしょう。
ただし、実家に住宅ローン残債がある場合は、残債を引き継がなければならないケースがあるので注意が必要です。
また、家賃の負担はなくても固定資産税や修繕費などの負担はあります。
とくに実家が古いケースでは、住むにあたって大規模なリフォームが必要になる場合もあります。
実家に住む場合でも、住宅ローンの残債がどうなるか、維持管理費はどれくらいかかるかは事前にシミュレーションしておくことをおすすめします。
慣れ親しんだ家に住むことができる
子どもの頃に生活していた実家は愛着もあり慣れ親しんだ家です。
地域への慣れもあるので、まったく新しい土地・家で生活をスタートするよりも負担は少ないでしょう。
また、愛着のある家を手放さずに済むので精神的な満足感を得られる点もメリットだといえます。
空き家のまま放置するより自分で住んだ方が維持管理できる
実家を空き家のまま誰も住まずに放置するというケースでも、実家の維持管理は必要です。
特に誰も住まない家は劣化が早く、定期的な維持管理は手間もコストもかさんでしまいやすいものです。
一方、実家に住めば、住みながら維持管理できます。
家賃の負担を抑えながら、自分で維持管理することで、住まない場合にはかかっていた維持管理コストを抑えることにもつなげられます。
実家の贈与を受ける際の手続きや贈与税の計算方法
生前に、親からの贈与によって家の所有権を得る場合は、贈与税の対象となります。
ここでは、贈与税について理解を深めていきましょう。
生前贈与で実家の贈与を受ける際の手続きの流れ
生前贈与とは、贈与者の生前中に行われる財産の継承です。
それに対して、死亡してから行われる財産の継承が相続や遺贈になります。
生前贈与で実家を取得する大まかな流れは以下のとおりです。
- 必要書類を揃える
- 贈与契約書を作成する
- 登記申請書を作成し登記��する
- 贈与税の申告・納税
たとえ親子間の贈与であっても、口頭のみで贈与すると後々トラブルに発展しやすくなります。
また、登記申請の際には贈与で取得したことが分かる書類が必要になるので、贈与契約書を作成する必要があります。
贈与契約書はインターネット上でテンプレートを取得して作成できますが、必要な記載がないとトラブルになる恐れもあるので、司法書士などへの相談も検討するとよいでしょう。
贈与後は、実家を管轄する法務局で所有者を変更する登記を行います。
さらに、贈与税が発生するケースでは、贈与税の申告・納税が必要になるので、忘れずに手続きするようにしましょう。
贈与税の計算方法
贈与税の課税方法には、以下の2種類があります。
- 暦年贈与
- 相続時精算課税
暦年贈与
暦年贈与では、1月1日から12月31日までの贈与額合計が贈与者ごとに110万円の基礎控除額を超えた場合、贈与税が課税されます。
贈与額が年間110万円以下であれば贈与税はかからず、申告も不要です。
相続時精算課税
一方、相続時精算課税では、累計2,500万円までの贈与額を非課税にすることができます。
ただし、相続時精算課税では110万円の基礎控除は適用されません。
また、贈与税が課税されなくても、将来相続が発生した際には、贈与額が相続財産に加算されるため、相続税が発生する可能性があります。
なお、この制度を利用できるのは、贈与者が60歳以上の親または祖父母、受贈者が20歳以上の子または孫の場合に限られます。
相続時精算課税は、一度選択��すると同じ贈与者では暦年贈与が選択できなくなるので、慎重に利用を検討するようにしましょう。
贈与税のシミュレーション
ここでは、前提として3,000万円の実家の贈与を受ける場合でシミュレーションします。
暦年贈与の場合
暦年贈与の場合、3,000万円-110万円(基礎控除)=2,890万円が贈与税の対象です。
贈与税は贈与額に応じて税率が異なり、2890万円の場合の贈与税は以下のようになります。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | - |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3000万円超 | 55% | 400万円 |
相続時精算課税制度の場合
一方、相続時精算課税では、2,610万円が非課税となるので3,000万円-2,610万円=390万円が税金の対象です。
相続時精算課税では、非課税を超えた額に一律で20%の税率で贈与税が課税されるので、この場合の贈与税は以下のようになります。
この場合3,000万円-110万円=2,890万円は相続財産に加算され、相続税の対象となる点には注意しましょう。
なお、相続税が発生するケースでも、すでに支払った贈与税78万円は相続税から控除されます。
贈与税の確定申告と納付方法
贈与税は、申告時期に管轄の税務署に申告し納税します。
贈与税の申告時期は、贈与のあった年の翌年2月1日~3月15日までです。
この時期に、申告書と必要書類を税務署窓口へ持参や郵送するか、e-tax(電子申請)にて申請します。
また、納税時期も申告時期同様の2月1日~3月15日となります。
納付書・e-tax・インターネットバンキングなどの納付方法があるので、都合の良い方法で納付しましょう。
実家の相続を受ける際の手続きや相続税の計算方法
実家を相続する場合は、相続税の対象です。
ここでは、実家を相続する流れや相続税の計算についてみていきましょう。
実家を相続する際の手続きの流れ
実家を相続する流れは以下のとおりです。
- 遺言書の有無の確認
- 財産調査
- 相続放棄の検討
- 遺産分割協議
- 相続登記
- 相続税の申告・納税
遺言書の有無の確認
相続には以下の3つの方法があります。
- 遺言書の内容に沿って相続する
- 法定相続分で相続する
- 遺産分割協議を行って相続する
遺言書は基本的に、どの方法よりも優先されるため、まずは遺言書の有無を確認する必要があります。
なお、公正証書遺言以外の遺言書は勝手に開封できないので、見つけたら家庭裁判所での検認手続きが必要です。
遺言書がない場合は、民法で規定されている法定相続分で相続するか、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)で相続方法を決めることになります。
遺産分割協議する場合は、相続財産と相続人を明らかにしておく必要があるので、協議前にしっかり調査を行います。
財産調査~相続放棄の検討
財産調査の結果、マイナスの財産が多いなどでは相続放棄を検討するとよいでしょう。
なお、相続放棄は相続の開始を知った日の翌日から3ヶ月以内に行う必要があります。
遺産分割協議
遺産分割協議で相続人全員の合意を得られれば、それぞれの相続人で相続手続きを行っていきます。
相続登記
実家を相続する相続人は相続登記を行いましょう。
相続税の申告・納税
相続税が発生する場合は、相続を知った日の翌日から10ヵ月以内の申告・納税が必要です。
期限内に申告・納税できるように、早めにすべての手続きを進めていく必要があります。
相続税の計算方法
相続税は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた「正味の相続財産」が基礎控除を超えた場��合に、超えた部分に課税されます。
相続税の基礎控除は以下のとおりです。
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人の場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
この場合、実家を含めた相続財産の合計が4,800万円を超えた時点で、相続税が課税されるのです。
なお、相続税はいったん法定相続で相続したとして税金を計算・合算し、実際の相続割合で按分するというステップを踏みます。
この時、相続財産の合計が6,000万円だった場合の相続税は以下のようになります。
- 配偶者の相続税:2,400万円×15%-50万円=310万円
- 子どもの相続税:1,200万円×15%-50万円=130万円ずつ
- 相続税合計:310万円+130万円+130万円=570万円
相続税合計の570万円を実際の相続財産の取得割合に応じて按分して、それぞれの相続税を算出します。
また、実際の相続では配偶者は配偶者控除を利用すれば課税されません。
このように、相続税の計算は複雑になりがちなので、相続税の詳しい計算は税理士などに相談するとよいでしょう。
相続税の確定申告と納付方法
相続税の申告期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
10ヵ月は長いように感じますが、被相続人の死亡後に遺産分割協議や相続手続きなどをしているとあっという間に期限が来ます。
とくに、不動産を売却して相続税に備えたいという場合は、速やかに相続手続き売却が必要になるので注意しましょう。
実家の贈与・相続を受けたけど住まない場合の選択肢
実家を贈与・相続したけど、すでに家を持っている・遠方などの理由で住まないケースも少なくありません。
この場合、実家の処分方法としては放棄するか売却するかを検討できます。
放棄する
相続した実家を放棄する方法としては、「相続放棄」または「相続土地国庫帰属制度」の2つがあります。
相続放棄すれば家を相続しなくて済みますが、他の財産も相続できなくなるので慎重に検討するようにしましょう。
また、相続放棄には相続開始から3ヵ月以内という期限もあるので、相続放棄する場合は早めに手続きすることが大切です。
相続土地国庫帰属制度とは、活用しない土地を国に引き渡せる制度です。
建物は引き渡せないため解体して更地にする必要がありますが、一定の条件を満たした土地であれば相続放棄しなくても土地を手放せられます。
ただし、管理や処分にコストや手間のかかる土地は対象外となるため、要件などをしっかり調べて検討するようにしましょう。
売却する
活用予定のない家であれば売却して手放す方法があります。
売却であれば、売却金を得られるので相続時に現金で分割・相続税に対応などもしやすくなります。
しかし、築年数の古い家など条件が悪いと売却が難しいケースもあるので注意が必要です。
相続税や遺産分割を検討しているなら、少しでも高値で売却することも大切になってきます。
そのため、相続した家の売却が得意で信頼できる不動産会社を見つけることが大切です。
で��きるだけ多くの不動産会社の査定を受け、比較しながら不動産会社を見つけていくとよいでしょう。
不動産会社の査定を比較するなら「イエウリ」の一括査定がおすすめです。
イエウリの一括査定では、他の一括査定サイトとは異なり入札形式となるので、査定数の上限がなく、より多くの不動産会社の査定を比較できます。
入札形式であるため自然と査定も高くなるのも大きな魅力です。
イエウリでは、中立の立場で売却をサポートする窓口もあり、はじめての不動産売却でも安心して進められます。
相続後の家の売却を検討しているなら、まずはイエウリにお気軽にご相談ください。
空き家になった実家に住むことに関するよくある質問
最後に、空き家になった実家に住むことに関するよくある質問をみていきましょう。
住まない実家は相続してはいけないといわれる理由は?
住まない実家を相続すると、固定資産税や維持管理費などの負担がかかります。
また、倒壊などで損害賠償請求されるリスクもあるため、手放したほうがコストやリスクから解放されます。
相続してしまうと、簡単に売却や放棄もできなくなるので、相続する前に相続放棄などを検討するのも1つの方法です。
実家に住むと固定資産税はどのくらいかかる?
固定資産税の額は不動産によっても異なりますが、一般的な戸建ての場合年間10~15万円程が目安です。
固定資産税は「不動産評価額×1.4%」で計算できます。
不動産評価額は、毎年送付される固定資産税納税通知書や自治体の窓口で確認できま�す。
築年数の古い家の場合、家の評価額が少なく土地のみの固定資産税となるケースも多いでしょう。
ただし、税率は自治体によっては1.4%以外に設定しているケースもあるので、お住まいの自治体のホームページなどで確認してください。
まとめ
空き家になった家に住むと、兄弟間で相続トラブルになる、維持管理費がかかるなどのデメリットがあります。
また、実家を相続・生前贈与で取得する際には、相続税・贈与税の対象となるので計算方法や取得手続きなどを押さえておくことが大切です。
相続した実家は住む以外にも、相続放棄や売却という選択肢もあります。
売却であれば、まとまった資金を得られるので相続税などにも対応できるでしょう。
相続した家を売却するなら、相続した家に強い信頼できる不動産会社を見つけることが大切です。
まずは、イエウリの一括査定を利用して不動産会社の比較からスタートするとよいでしょう。