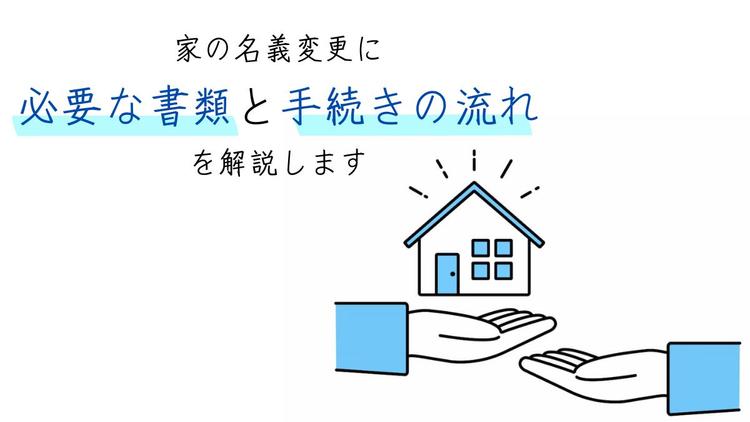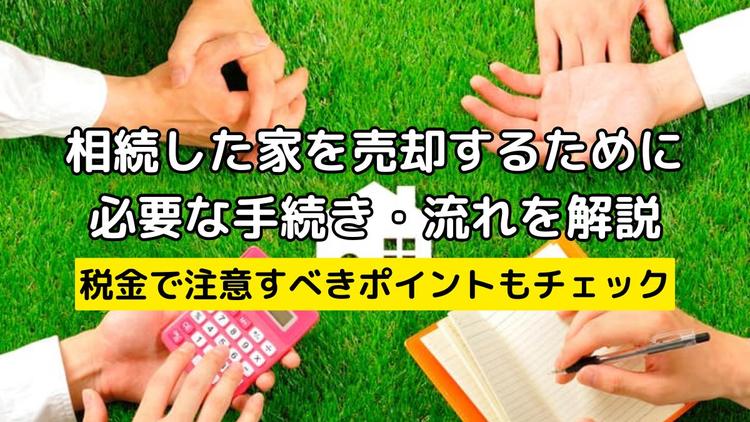借地権とは、土地を借りる権利のことですが、ご両親が借りている土地がある場合、その借地権も相続することができます。
ところで、借地権を相続した場合、どのように手続きを進める必要があり、またどのような点に注意する必要があるのでしょうか。本記事では、借地権の相続について、概要や必要な手続き、注意点など解説していきます。
借地権の相続に地主の許可は不要
借地権の取扱いには何かと地主の許可が必要なことが多いです。
例えば、借地権を第三者に売却する場合、借地権の譲渡や抵当権の設定・建物建て替え等について地主の承諾を得た上で、承諾料を支払う必要があります。
仮にこれらの承諾を得られない場合、裁判所の許可を得なければ手続きを進めることができません。
一方、借地権の相続の場合、地主の許可を得る必要はありません。
地主に通知すればOK
借地権を相続する場合地主の許可は要らず、相続した後、地主に「借地権を相続しました」と通知すればよいことになっています。もちろん、承諾料も不要です。
相続することで、賃貸借契約書と借主が相違することになりますが、必ずしも書き換える必要はありません。ただし、場合によっては、地主から賃貸借契約書について打診があることがあります。
もちろん、書き換えした方が分かりやすくなりますが、同時に名義書換料や更新料を請求されるようであれば、拒んでも問題ありません。
建物の所有権移転登記は必要
土地の借地権の相続については借地人の許可を得る必要はありませんが、土地の上に建っている建物については被相続人(亡くなった方)の所有権となっています。
このため、建物については被相続人から相続人へ所有権を移す登記、いわゆる相続登記をする必要があります。
遺贈の場合は地主の許可が必要
また、相続の場合地主の承諾は不要ですが「遺贈」となった場合売却と同じく地主の承諾を得る必要があります。
「相続」とは法律で�定められた法定相続人が被相続人の財産を受け継ぐことを指します。
一方、「遺贈」とは遺言によって被相続人の財産を受け継ぐことを指します。
遺贈は相続に際し「無償で第三者に財産を譲り渡す」ことであり、売却と同じように承諾が必要ですし、承諾料も支払わなければなりません。単に相続するのと比べるとかなりの手間がかかるといえるでしょう。
借地権の遺贈に必要な手続き
ここでは、借地権の遺贈に必要な手続きを見ていきましょう。具体的には、以下のように手続きを進める必要があります。
- 承諾請求
- 地主の承諾を得る
- 移転手続き
承諾請求
まずは地主に対して「遺言によって借地権を遺贈する人」と、「遺贈を受ける人」が連署の上、地主に対して承諾請求する必要があります。
地主の承諾を得る
地主は、借地権の遺贈について承諾請求を受けたら、「遺贈する人」と「遺贈を受ける人」のどちらかに対して承諾する旨を伝えます。これは口頭でもよいこととされていますが、後々言った言わないのトラブルになることを避けるためにも、内容証明郵便や配達証明郵便を使うようにしましょう。
移転手続き
建物についての所有権移転登記を行います。通常、借地権が登記されていることは稀です。これは、借地上にある建物を登記すれば第三者に借地権を主張できるからです。
このため、借地権についての登記はほとんどのケースで不要ですが、建物に関する所有権は移転登記を済ませておく必要があります。
承諾料
借地権の遺贈を受けた場合、売却や譲渡と同じく、慣習として承諾料を支払うことになっています。承諾料の相場は借地権価格の10%程度が目安とされています。
地域や地主の意向により異なりますが、上記相場より大きくかけ離れた金額を提示されたようなケースでは注意が必要です。
例えば、地主が承諾料について借地権価格の10%ではなく、「土地の価格の10%」を要求するようなケースもあります。もちろん、それ�が違法ということではありませんが、不当に高いお金を払いたくないかと思いますので、相場を頭に入れておきましょう。
地主の承諾を得られない場合(提示された承諾料が高すぎる)
交渉してもどうにもならず、それでも提示された額の承諾料を支払いたくない場合には、地主の承諾に代わり、裁判所の許可を得る必要があります。裁判所の許可を得られれば、借地権を遺贈することが可能になります。
ただし、地主との関係が悪化する可能性が高いため、その後長くその土地を利用していくことを考えると、あくまでも最終手段として考えておきましょう。
借地権の相続税評価
借地権の相続も所有権の相続と同様に、その評価額に応じて相続税が課されます。では、借地権の相続税評価はどのように算出されるのでしょうか。
借地権の種類
借地権には大きく分けて普通借地権と定期借地権がありますが、それぞれ計算方法が異なります。
普通借地権とは、一般的な借地権のことで、契約期間の更新や延長を借主から申し出ることができ、断られた場合には土地を買い取ることも可能など、借主の権利が強い借地権です。
一方、定期借地権とは、50年など最初に定めた期間が経過すれば、契約期間の延長や更新なしで契約が終了するもので、借主は契約終了後に建物を解体して更地にして返す必要があります。
定期借地権は、普通借地権と比べて地主の権利が強い契約です。
普通借地権の評価方法
それでは、借地権の評価額の計算方法を見ていきましょう。
まず、普通借地権の評価額は以下のように計算できます。
土地の価格とは相続税路線価や倍率方式で求めるもので、国税庁のWebサイトで確認することができます。
参考:国税庁|路線価図
路線価図では、土地の前の道路につけられた価格に対して、面積を掛け合わせて算出します。例えば、路線価が150,000円/㎡で土地の面積が200㎡の場合、3,000万円と計算できます。
また、借地権割合は国税庁が地域ごとに30%~90%の間で定めるもので、住宅地は60~70%の間で定められることが多いです。
借地権割合も、路線価図で確認することができ、例えば「150C」と書かれており、Cの借地権割合が70%、敷地面積が200㎡だった場合、150,000円×200㎡×70%=2,100万円となります。
参考:国税庁|路線価図の説明
定期借地権の評価方法
定期借地権の評価額の計算方法は、普通借地権と比べるとやや複雑です。
具体的には、以下のように計算します。
- A=設定時の借主の権利金や保証金などの総額
- B=設定時の宅地の通常の取引相場
- C=課税時期の残存期間年数に応じた基準年利率による複利年金現価率
- D=借地設定期間に応じた基準年利率による複利年金現価率
定期借地権は、毎月の地代の他、設定時に権利金や保証金などを支払うのが一般的で、Aはその総額となります。また、CやDに用いる基準年利率と複利年金現価率は以下の国税庁のWebサイトで確認することができます。
参考(基準年利率):国税庁 令和元年分の基準年利率について
参考(複利年金現価率):国税庁 複利表
例えば、土地価格2,500万円、設定時の取引相場3,000万円、保証金として300万円、設定期間50年、残存期間20年の場合、以下のように計算します。
相続税の確定申告
相続財産を受け継ぐことになった場合、遺産分割協議などを済ませ、相続財産を計算し、期日までに確定申告する必要があります。
ここでは、相続税に関する各種期日をお伝えしていきます。
単純承認や相続放棄などの期日
相続財産にはプラスの財産もマイナスの財産もありますが、それらの財産について、引き継ぐか放棄するかを決める必要があります。
これらの判断の期日は、被相続人が亡くなったことを知ってから3カ月以内となっており、期日までに相続放棄しなかった場合には単純承認したこととみなされます。
なお、限定承認といって、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法もありますが、こちらの期日も被相続人が亡くなったことを知ってから3カ月以内となっています。
▼関連記事


準確定申告の期日
亡くなった方に所得があった場合、1月1日から亡くなった日までの所得を相続人が行う必要があります。このことを、準確定申告と呼びます。
準確定申告は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から4カ月以内に手続きしなければなりません。
相続税の確定申告の期日
相続税の確定申告の期日は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内となっています。この期日の日までに、遺産分割協議や相続税評価額の計算など全て済ませておく必要があります。
例えば、1月15日に亡くなった場合、4月15日までに限定承認や相続放棄するかの手続きをするとともに、5月15日までに準確定申告し、11月15日までに相続税の確定申告をする必要があります。
借地権は売却しづらい
借地権を相続したものの、住んでいる場所から離れている等の理由で上手に活用できないこともあるでしょう。その場合、売却等も含めて検討することになるかと思いますが、借地権は売却しづらい点に注意が必要です。
借地権の売却については、以下のページで詳しく解説しています。
▼関連記事

借地権を活用できない場合は相続放棄するのも手
借地権は初期費用を安く抑えられるといったメリットがありますが、定期借地権の場合、借地期間終了後に建物を解体して土地を返還しないといけないといったことや、借地権の取引自体が一般的でないといった理由から、売却しづらいのが一般的です。
借地権を相続すると毎月地代を支払う必要があるため、相続したのに活用できていなければ、もったいないどころか毎月マイナスとなってしまいます。
借地権を相続しても活用できないことが想定されるのであれば、相続の段階で相続放棄を検討してみるのも一つの方法です。
まとめ
借地権の相続について、取り扱いや評価額の計算方法、確定申告の期日などお伝えしました。
相続自体ややこしい手続きなのに加え、借地権は借地権の種類や残存期間なども考慮しなければならず、大変なことも多いです。必要に応じて税理士など専門家の手を借りるようにすることをおすすめします。