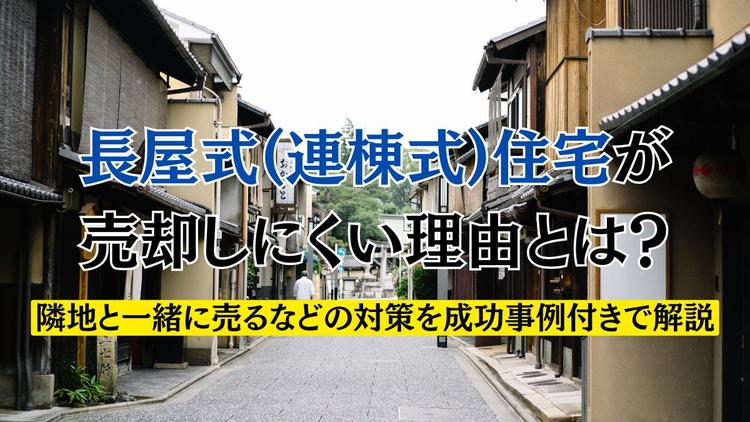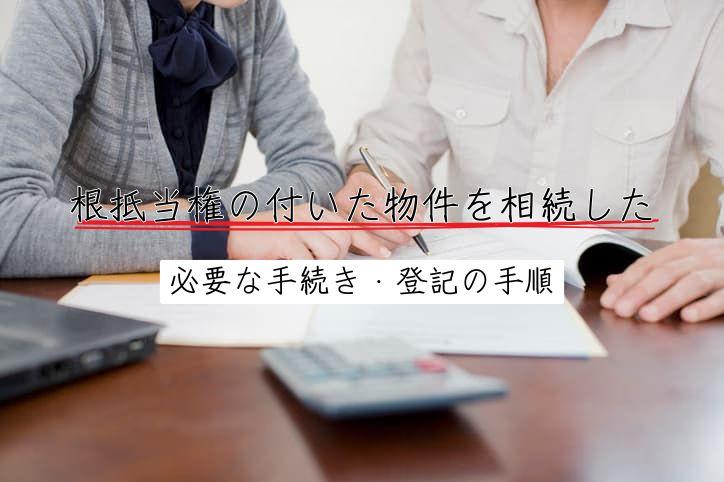長屋(連棟)式住宅は、最近ではテラスハウスやタウンハウスと呼ばれています。
物件によってはそうでもないこともありますが、一般的には通常の戸建て住宅やマンションよりも売却しづらいケースが多いです。
本記事では、長屋式住宅の売却を検討されている方に、売りにくい理由や、売れない場合の対処法を解説します。
【成約実績 No.0209】
大阪府 大阪市鶴見区
連棟式建物につき隣地と同タイミングで売却をしたい。
加えて、名義人が後見人をたてているため、
売却は少し長期化したが、
全18社から金額提示を受け、
売却完了。難しい案件もお任せを。#企業公式相互フォロー#イエウリ#大阪府#大阪市鶴見区pic.twitter.com/aPXgdCprMO
— イエウリ【公式】 (@ieuri_ieuri) March 14, 2024
なお、長屋式住宅の売却を検討している方は、実績豊富な「イエウリ」にご相談ください。
長屋式住宅とは
長屋というと時代劇に登場する住宅をイメージされる方が多いでしょう。
現代の長屋も基本的には同じもので、壁がつながった状態で住宅が連続しているものを長屋と呼び、横に連なっているものの他、上部下部で連なっているものもあります。
ただし、最近では長屋という呼び名ではなくテラスハウスやタウンハウスといったおしゃれな呼び名で呼ばれることもあります。
長屋式住宅にはいくつかメリットがあることもあり、業者がブランディングして商品化しているケースもありますが、基本的には昭和に建てられた古い建物が多いといえるでしょう。
基本的にはアパートやマンションと似たもの
長屋式住宅は屋根が連なった1つの建物に複数の居室が並び、それぞれに異なる世帯が暮らす形態の住宅です。
1つの建物を壁で隔ててそれぞれ違う世帯が暮らすということもあり、基本的にはアパートやマンションと似たものと考えて問題ありません。
しかし、アパートやマンションと長屋式住宅とは異なる点もあります。
共同住宅と長屋の違い
法律上、アパートやマンションのことを共同住宅と呼びますが、共同住宅と長屋の違いには以下のようなものがあります。
- 長屋は外部から直接出入りする
- 敷地が道路に2m以上接していればよい
- 建築基準法上特殊建築物に該当しない
通常、共同住宅は廊下など共用部を通じて各居室に出入りするようになっていますが、長屋式住宅の場合は各戸が独立した玄関を持ち、直接外部と出入りするようになっています。
また、共同住宅は通常、敷地が道路に4m以上接していないといけませんが、長屋式住宅であれば2m接していれば問題ありません。
このため、特に入口の狭い旗竿地のような敷地で建てやすく、土地代を含めて安価で建てやすいという特徴があります。
最後に、共同住宅は特殊建築物扱いとなるため、設計時にさまざまな制約を受けることになりますが、長屋式住宅の場合は特殊建築物になりません。
このため、アパートやマンションなど共同住宅と同じような性質を持ちながら、制約の少ない建物を建てることが可能です。
長屋式住宅のメリット・デメリット
ここでは、長屋式住宅のメリット・デメリットを見ていきます。
売却活動を進める上での販売戦略にも関係する要素ですので、チェックしておきましょう。
長屋式住宅のメリット
長屋式住宅には以下のようなメリットがあります。
- 購入時に安い
- 規制が緩い分リフォームのコストを抑えられる
- 建築の自由度が高い
購入時に安い
冒頭でお伝えした通り、共同住宅は法規制上、共同住宅の扱いを受けますが、長屋式住宅は特殊建築物ではありません。
接道義務についても(具体�的な規制は自治体によって異なりますが)、敷地が道路に2m以上接道していればよく、土地代も安く抑えられる可能性があるでしょう。
このため、同じ地域のアパートやマンションより安く購入しやすいというメリットがあります。
規制が緩い分リフォームのコストを抑えられる
また、購入した長屋式住宅を購入後すぐにリフォームするケース、さらに住んで数十年後にリフォームするようなケースでも防火上や衛生上の規制が緩いことから、コストを抑えて実施できます。
このため、購入時のイニシャルコストはもちろん、住みながら負担しなければならないランニングコストについても安く抑えられるという点でメリットがあるといえるでしょう。
建築の自由度が高い
長屋式住宅を通常の戸建て住宅と比べた場合、長屋式住宅は登記上1つの建物と見なされることから建築の自由度が高くなるというメリットがあります。
通常の戸建て住宅で長屋住宅のように複数の建物を建てようとすると、1つ1つの建物を登記する必要があるため、それぞれについて接道義務を満たさなければなりません。
一方、長屋式住宅は1つの建物で敷地が道路に2m以上接していればよく、自由度の高い建築ができるのです。
長屋式住宅のデメリット
一方、長屋式住宅には以下のようなデメリットがあります。
- リフォームが自由にできない
- 切り離しができない場合がある
- 火災に弱い可能性がある
リフォームが自由にできない
長屋式住宅は屋根で隣家とつながっているため、居室内のリフォームであれば問題ありませんが、建物の外側部分のリフォームについては自分一人で自由に実施できません。
他の所有者や居住者の方と相談したうえで実施しなければならず、手間がかかってしまうでしょう。
切り離しができない場合がある
長屋式住宅では建て替えや売却のために、自身の所有している不動産と隣家を切り離しをしたいと考えても、住宅の安全性や接道義務などの観点からできない場合があります。
また、仮に可能であっても当然隣家の許可が必要になる点に注意が必要です。
火災に弱い可能性がある
長屋式住宅は隣家と壁で隔てられているだけなので、1つの居室内で火災が発生したときに同じ建物内の居室にどんどん燃え広がっていく可能性が高いといえます。
戸建を個別に建てる場合はもちろん、アパートやマンションなど共同住宅と比べても火災に弱い造りになっていることが多いといえるでしょう。
そもそも、アパートやマンションなど共同住宅が特殊建築物扱いである理由の一つに、防火上の対策をすべきであるから、ということがありますが長屋住宅にはこうした法的規制が適用されません。
法的規制が適用されないからといって、防火対策をしないでいると、いざ火災が発生したときに大きな損害を負ってしまうことになります。
法律で定められた最低限の対策をするだけではなく、自己判断で必�要な防火対策をしていくことも検討する必要があるでしょう。
長屋式住宅が売却しにくい理由
長屋式住宅にはメリットもあればデメリットもありますが、一般的には、通常の住宅と比べて売却しづらい傾向にあります。
これには、以下のような理由があります。
- ローン審査に通りにくい
- 再建築や切り離しが困難
以下、それぞれについて見ていきましょう。
ローン審査に通りにくい
長屋式住宅は以下のようなことを理由に、ローン審査に通りにくい傾向にあります。
- 既存不適格建築物の可能性がある
- 再建築不可物件で可能性がある
- そもそも古い建物が多い
まず、長屋式住宅は古い建物が多く、また建物がひしめくエリアに建てられていることが多いことから、当時の法律には適合していても現在の法律に適合していないケースが多くなっています(既存不適格)。
また、市街化区域の第一種・第二種低層住居専用地域では、建築物の敷地面積を一定以上としなければならない場合があり、これを満たしていない長屋式住宅は再建築ができません。
こうした既存不適格建築物や再建築不可物件については、ローンの審査で厳しく見られることが多いです。
さらに、単純に古い建物が多く「旧耐震基準であり担保価値が低い」といった条件であれば、これもローンの審査に通りにくい�理由となるでしょう。
再建築や切り離しが困難
先述の通り、長屋式住宅は法的に再建築不可であることも多いですが、また物理的にも売却に苦戦する要素を多く抱えています。
例えば、長屋式住宅の切り離しは可能ですが、切り離した後の安全性に考慮しなければなりません。また、切り離した住宅のどちらともが建築基準法を満たす必要があり、満たせない場合は切り離せないという問題もあります。
具体的には、長屋住宅にすることによって接道要件を満たしていた場合などは、切り離した後にどちらかの住宅が接道要件を満たせなくなることがあり再建築ができません。
冒頭でお伝えした通り、長屋式住宅は1戸の建物として見ることができるため、道路に敷地が2m以上接道していればよいのですが、切り離しするとなると2つの建物が接道義務を満たさなければならず、少なくとも4mは接道する必要があります。
そもそも、切り離しには隣家に大きな影響が及ぶ工事になるため個人の独断で行うことができません。
こうしたことが長屋式住宅が売却しづらい原因となっているといえるでしょう。
売却しやすい長屋式住宅もある
長屋式住宅が売却しづらい理由についてお伝えしましたが、必ずしも全ての長屋式住宅がその条件を満たしているわけではありません。
各戸で接道を取れる物件や比較的最近建てられた物件などは売却しやすいケースも多いです。
逆に、一般の住宅であっても古い建物や接道のための道路が狭い物件などは売却しづらい傾向にあります。
実際に売却を進める場合には、長屋�式住宅だから売却しづらいというわけではなく、個別に条件を見ていく必要があるといえます。
長屋式住宅を売却する方法
とはいえ、長屋式住宅が売却しづらい条件を満たしていることは少なくありません。
通常の方法で売却できれば問題ありませんが、ここではそれ以外の、長屋式住宅を売却する方法についてお伝えしていきたいと思います。
具体的には、以下のような方法があります。
- 買取業者に売る
- 隣家を買い取って売却する
- 隣家に買い取ってもらう
- リノベーションする
買取業者に売る
仲介による方法だと一般の個人の方が相手となるため、リスクのある物件は買い手がつきづらいものです。
しかし、買取業者であれば、リスクを踏まえたうえで効果的な活用法を考えてくれる可能性が高く、買い取ってもらえる可能性は高くなるといえるでしょう。
ただし、買取は仲介による方法と比べると6~7割程度の価格での売却となる点には注意が必要です。
とはいえ、仲介による方法だとリスクのある物件は長期間売却できない可能性が高く、最終的に値下げや値引きすることを考えると最初から買取業者に買い取ってもらった方がよかったということも少なくありません。
なお、不動産会社による買取でできるだけ高く売却したい場合は「イエウリ」が便利です。
【成約実績 No.0082】
大阪府 東大阪市
賃借人様の退去に伴い、
資産処分として売却。建物が連棟式のため、個人の買い手が付きづらく、
買取にて登録後26日で売買契約成立。売りづらい物件もイエウリにお任せください。#企業公式相互フォロー#イエウリ#大阪府#東大阪市
— イエウリ【公式】 (@ieuri_ieuri) November 9, 2023
隣家を買い取って売却する
長屋式住宅であっても、隣家や周辺の土地を買い取って売却する形式であればデメリットが解消する可能性があります。
隣家も長屋式住宅の売却を検討している場合があり、長屋式住宅全体を所有できれば買いたいという人も出てくるでしょう。
隣家に買い取ってもらう
逆に隣家も長屋式住宅の活用など検討している場合があります。
いずれにせよ、長屋式住宅の売却を検討しているのであれば、一度隣家の所有者と話をしてみるとよいでしょう。
単独で売却するより、まとめて売却したり活用したりした方が価値を高められるのは、長屋式住宅に限りません。
▼関連記事


リノベーションをする
リノベーションをすることで「昭和レトロ」な雰囲気が出て、ニーズにあった買い手を捕まえられる可能性もあります。
リノベーションを依頼する業者次第ではありますが、検討してみる価値はあるでしょう。
ただし、リノベーションに掛かった費用を確実に回収できるとは限らないため、慎重に判断することが大切だといえます。
また、長屋式住宅だと単独ではできることとできないことがあるため、この場合も隣家の所有者と話し合いながら進めることも検討することをおすすめします。
まとめ
長屋式住宅の特徴や売却する際のメリット・デメリット、問題点などお伝えしました。
長屋式住宅は売却しづらい物件であることが多いですが、その際には本記事でお伝えした内容を参考に売却を進めてみるとよいでしょう。
特におすすめなのは買取業者を利用する方法です。
ただし、いずれの場合を取るにしても、隣家�と併せて売却することでより価値が高まることも多いため、まずは隣家の所有者と話し合ってみることをおすすめします。