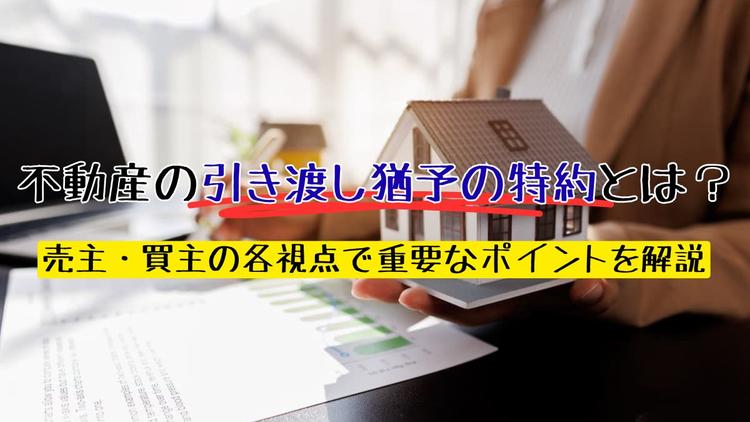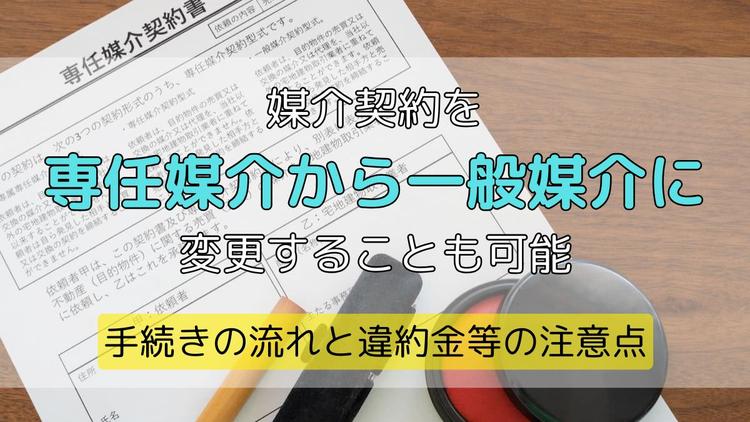不動産売買で、決済までに引っ越しが間に合わないといった場面で役に立つのが、引き渡し猶予の特約です。
引き渡し猶予の特約を設けることで、売主は決済後でも一定期間引き渡しを待ってもらうことができます。
しかし、決済と引き渡し日がズレるとトラブルも生じやすいため、特約を設ける際にはポイントを押さえておくことが重要です。
この記事では、不動産売買の引き渡し猶予の基本や利用するケース、特約を設ける際の売主・買主それぞれの注意点について分かりやすく解説します。
不動産の引き渡し猶予の特約とは
まずは、引き渡し猶予の特約とはどのようなものかを確認していきましょう。
決済日から遅れて引き渡しをすることを約束する特約
通常、不動産売買では、決済と引き渡しは同日に行われます。
大まかな流れとしては、決済で代金の受け取りを確認した後、所有権移転登記の手続きを行い、売主から買主に鍵などを引き渡すという流れが同じ日に行われます。
そのため、売主は引き渡し日までに引っ越しなどを済ませて、物件を空き家の状態にする必要があるのです。
しかし、状況によっては売主の引越しが決済日までに間に合わないケースがあります。
そのような場合に利用されるのが、引き渡し猶予の特約です。
引き渡し猶予の特約を設けることで、売主は決済日から一定期間引き渡しの日を待ってもらうことができます。
ただし、決済日に所有権移転登記は完了しているので、家の権利は買主にあります。
つまり、売主は家の権限を持たない状態で一定期間家に住まわせてもらっているという形になるのです。
なお、引き渡し猶予はあくまで買主の厚意によるものであり、買主にもリスクはあるので、猶予期間は3日~10日ほどと短いのが一般的です。
決済から引き渡しまでは使用貸借の状態
引き渡しまでの猶予期間は、買主の家に売主が住まわせてもらっている形です。
賃貸借の形態に似ていますが、この期間はあえて賃料は発生させないのが一般的です。
これは、賃貸借契約ではなく使用貸借契約にすることが目的でもあります。
賃料をもらう賃貸借契約では、基本的に入居者の権利が強く、大家は入居者の退去を求めることが難しくなります。
一方、無償で家を借りる契約である使用貸借では、入居者の権利は弱く、いざとなれば大家は簡単に入居者を退去させることが可能です。
引き渡し猶予期間は、あくまで売主のお願いで少しの間住めるようにしてもらっているだけという点は覚えておきましょう。
引渡し猶予特約の文言・記載例
特約の内容によっても記載は異なりますが、以下の項目の文言を盛り込むのが一般的です。
- 引渡しを猶予する期間
- 猶予期間中の物件の管理責任が売主にあること
- 猶予期間中に物件が毀損した場合の損害賠償責任は売主にあること
- 固定資産税などの清算日は引き渡し日が起算日となること
たとえば、以下のように特約を記載します。
買主は売主に対して、残代金の支払い・所有権移転登記完了後の翌日から5日間にかぎり本物件の引き渡しを猶予するものとする。
また、猶予期間中、売主は本物件の管理責任を負い、猶予期間中に天災地変等の不可抗力によって本物件の全部又は一部が滅失もしくは毀損したときは、その損失は売主負担とする。
なお、固定資産税等の清算は上記引渡日を基準日として算出し、引き渡し日が�早まった場合でも再清算は行わないものとする。
記載する文言によってはトラブルになる恐れもあるので、内容をしっかり確認したうえで契約書にサインすることが大切です。
売主が引き渡し猶予の特約を利用する代表的なケース
引き渡し猶予の特約は、基本的に売主が決済日までに引っ越しが間に合わないケースで利用されます。
引っ越しが間に合わない理由もさまざまですが、代表的なケースが以下の2つです。
- 家の売却代金を新居の購入費用に充てる
- 学校や勤務先の都合で引っ越し時期を調整する
それぞれ見ていきましょう。
家の売却代金を新居の購入費用に充てる
引き渡し猶予は、住み替えを「売り先行」または「同時決済」で行う際に利用されることがあります。
売り先行とは、今住んでいる家を売却してから新居を購入する住み替え方法です。
この場合、新居の契約は今の家の売買契約後になるため、新居探しに時間がかかると、決済日までに新居を用意できない恐れがあります。
もし決済日までに新居を用意できない場合、仮住まいを用意するのが一般的です。
しかし、「新居は見つかっており仮住まいは必要ないけど、新居の購入費用を売却金で賄う」というケースでは、決済後でなければ新居の契約ができない為、引き渡し猶予が必要になってくるのです。
また、同時決済とは、今の家の売却と新居の購入の決済日を同日、または少し猶予をもって行う住み替え方法です。
この場合でも、新居の用意が間に合わずに引越し時期をずらす必要が出てくる可能性が�あります。
学校や勤務先の都合で引っ越し時期を調整する
転勤による住み替えや、住み替えで転校が必要になるケースでは、新居を用意していても学校や勤務先の事情で引っ越しが間に合わない場合があります。
このような場合でも、引き渡し猶予の特約を利用することで、事情に合わせて引越し時期を調整できます。
売主が不動産売買契約で引き渡し猶予の特約を設ける際のポイント
売主が引き渡し猶予の特約を設ける際のポイントには、以下の3つが挙げられます。
- 買主の不都合が多い特約のためしっかり合意を得る
- 引き渡しの時期など売買契約書に明記する
- 猶予期間中の自然災害などによる損害は売主が負担する可能性がある
それぞれ見ていきましょう。
買主に不都合が多い特約のためしっかり合意を得る
引き渡し猶予は売主にとってはメリットがありますが、買主には何もメリットがありません。
むしろ、代金を支払っているのに家に住めない状態です。
さらに、売主が契約を守らず、引き渡し期限を過ぎても居座り続ける可能性もあるため、買主にとってはリスクの大きい特約と言えるでしょう。
特約を設ける際には、買主にその内容をしっかりと説明し、十分な理解と合意を得ることが大前提です。
買主の理解が浅いまま話を進めてしまうと、後々トラブルにつながりかねません。
また、買主に不利な引き渡し猶予の特約を設けることで、買主から値引き交渉を受ける恐れがある点にも注意が必要です。
引き渡しの時期な�ど売買契約書に明確に記載する
引き渡し猶予の特約があると、引き渡しされないのではと買主も不安になり、売却にも影響が出かねません。
買主が安心して売買を進められるように、引き渡し時期などは契約書にしっかり明記するようにしましょう。
猶予期間中の自然災害などによる損害は売主が負担する可能性がある
猶予期間の賃料は発生しませんが、期間中の物件の管理責任は売主にあります。
猶予期間中に物件を破損した、自然災害が起きて物件が損傷したといった場合の修繕責任は売主が負います。
仮に、修繕できずに引き渡しできない状態になれば、買主のペナルティなしで契約解除になる恐れもあるでしょう。
引き渡し猶予期間が長いほど売主は余裕をもって引っ越しを進められますが、売主にもリスクがある点には注意が必要です。
買主が不動産売買契約で引き渡し猶予の特約を設ける際のポイント
買主が引き渡し猶予特約を設ける際に注意したいポイントは以下の3つです。
買主は引き渡し猶予の特約のリスクが大きくなるので、以下の点を踏まえて慎重に判断するようにしましょう。
- 住宅ローン審査に影響を及ぼす可能性があるため事前に金融機関に相談する
- 猶予期間中の管理責任を明確にする
- 租税公課や水道光熱費を誰が負担するか明確にする
それぞれ見ていきましょう。
住宅ローン審査に影響を及ぼす可能性があるため事前に金融機関に相談する
引き渡し猶予特約を設けた売買契約は、引き渡しされないリスクを負うため、金融機関も住宅ローン審査�で慎重になる可能性があります。
金融機関によっては、引き渡し猶予の特約が付加された売買契約では住宅ローンが利用できないケースもあるので注意が必要です。
事前に引き渡し猶予特約が住宅ローン審査に影響しないかは、金融機関に確認することをおすすめします。
猶予期間中の管理責任を明確にする
猶予期間中は売主が住んでいる状態ですが、家の所有権は買主にあります。
家に何かあった際の責任の所在でトラブルになる恐れがあるため、管理責任を明確にしておくことが大切です。
猶予期間中のトラブルになりやすい項目としては以下が挙げられます。
- 物件にできたキズや汚れ
- 設備の故障
- 自然災害による物件の損傷
- 火災
基本的にはこれらの物件の修繕費などは売主が負担します。
しかし、契約書に明記がなければ責任を問えない恐れがあるので、どちらが責任を負うのかを明確にしたうえで契約書にもしっかり記載するようにしましょう。
租税公課や水道光熱費を誰が負担するか明確にする
不動産の売買では、売却した年の固定資産税・都市計画税は売主・買主の所有期間に応じて按分するのが一般的です。
特約を設けていない売買契約なら、起算日は決済・引き渡し日となります。
しかし、特約を設けると決済日(所有権移転日)と引き渡し日がずれ、どちらを起算日にするかでそれぞれの負担が変わってくるためトラブルになりやすくなります。
同様に、猶予期間中に使用した水道光熱費もどちらが負担するかでトラブルになりがちです。
一般的には、租税公課は引き渡し日が起算日となり、猶予期間中の水道光熱費は売主が負担します。
事前に負担する人が誰かを明確にし、契約書に反映するようにしましょう。
▼関連記事:不動産売買時の契約から残代金決済までの流れを売主・買主の各視点で解説
不動産の引き渡し猶予特約に関するよくある質問
最後に、不動産の引き渡し猶予に関するよくある質問をみていきましょう。
引き渡し猶予特約の一般的な期間は?
猶予期間の目安は3~10日ほどです。
しかし、売主と買主の合意で期間は決まってくるので、それぞれの事情に合わせて話し合って決めるようにしましょう。
ただし、猶予期間が長いほど買主からは避けられやすくなるので注意が必要です。
また、猶予期間中は売主も物件を管理する責任が生じ、万が一損傷すると損害賠償請求などのリスクがあります。
期間が長いほど売主にとってもリスクになることは覚えておきましょう。
引き渡し猶予特約で2ヶ月や半年の猶予を設けることはできる?
買主が合意すれば、2ヵ月や半年の期間で設けることも可能です。
しかし、その期間買主は自分の物件に住めないうえに賃料を得られる�わけでもありません。
さらに、期間が長くなるほど売主が居座る心配も出てくるでしょう。
そのため、長期の猶予期間に買主が合意してくれる可能性は高くはありません。
ただし、不動産会社が買主となる買取であれば、交渉次第で長期間の引き渡し猶予を設けられるケースは多くあります。
引き渡し猶予を長期間設定したい場合は、買取を視野に入れるとよいでしょう。
引渡し猶予特約でよくあるトラブルとは?
引き渡し猶予特約では、猶予期間中の物件の損壊でトラブルになる恐れがあります。
たとえば、キズや汚れをつけた、設備が故障したなどです。
また、可能性は低いですが、自然災害や火災で物件が損壊・消滅するリスクもあるでしょう。
そのような物件の損壊について誰が責任を負うのかを明確にし、契約書に記載しておくことでトラブルを防ぎやすくなります。
まとめ
決済日から引き渡しまでに一定の猶予を設ける引き渡し猶予の特約があれば、売主が決済日に引っ越しが間に合わない状況でも対応できます。
しかし、引き渡し猶予の特約は買主のリスクが大きいことから、売りにくくなったり、値引き交渉を受けたりする恐れがある点には注意が必要です。
引き渡し猶予の特約を設けたい場合は、信頼できる不動産会社のサポートを受けながら売却活動を進めるようにしましょう。