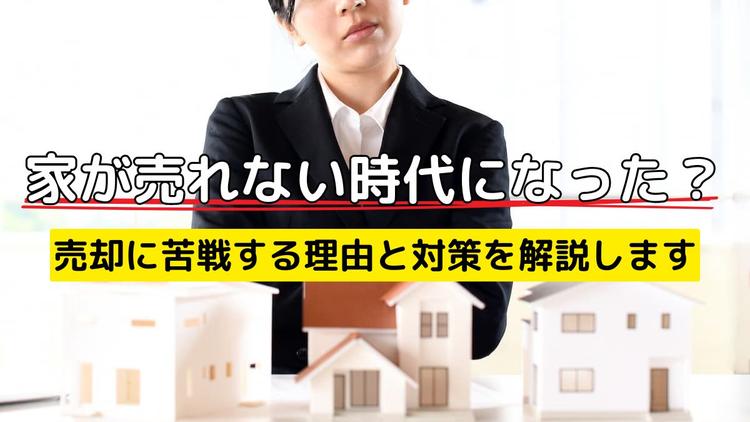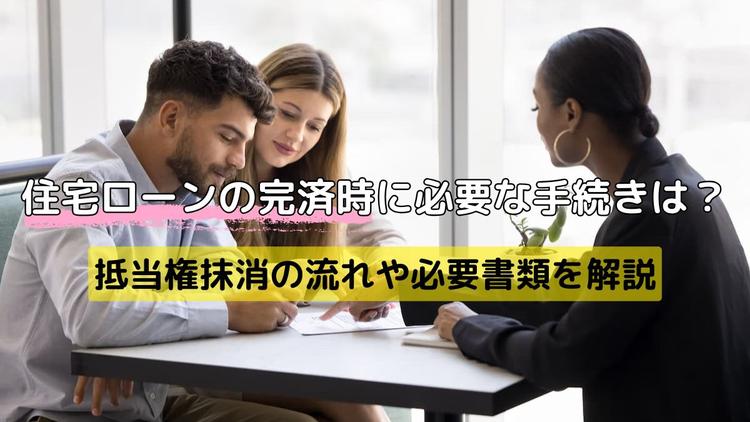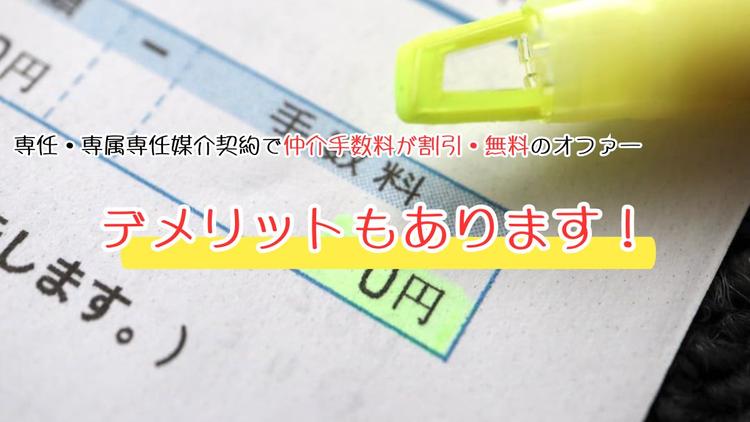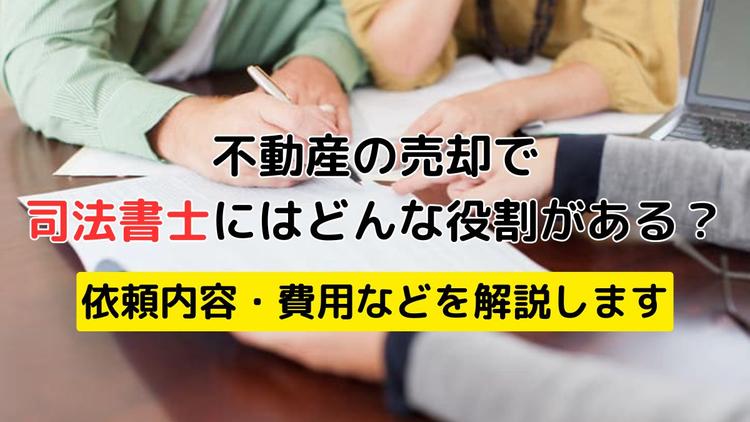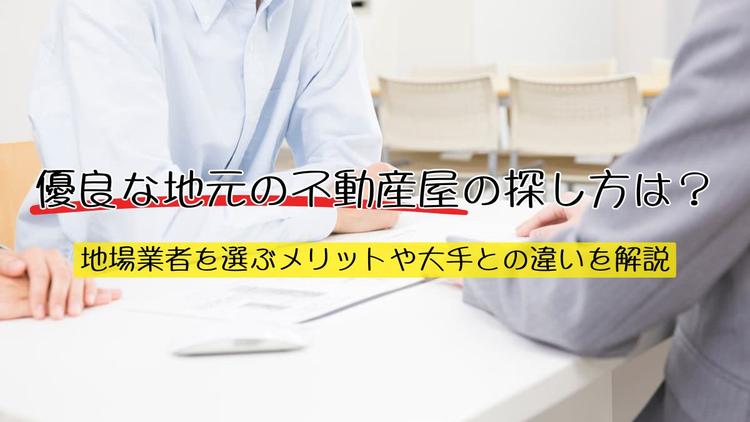「家が売れない時代になった」そのような話を耳にした方もいるでしょう。
人口減少や人件費の高騰などで、現在は対策しないと家が売りにくいケースが増えています。
また、今後は家が売れない状況がより深刻になるとも言われているので、その理由や対策を押さえておくことが重要です。
この記事では、家が売れない時代になったといわれる理由や今後の予測、売れない場合の対策などを分かりやすく解説します。
家が売れない時代になった理由
まずは、家が売れない時代になったといわれる理由を見ていきましょう。
人口減少
家が売れなくなる理由に人口減少があります。
家の需要は住む人の数に左右されるため、人口が少なくなれば需要も下がります。
総務省の人口推計によると直近の日本の人口は以下のとおりです1。
| 年次 | 総人口(10月1日時点) |
| 2005年 | 127,768,000 |
| 2010年 | 128,057,000 |
| 2015年 | 127,095,000 |
| 2020年 | 126,146,000 |
| 2021年 | 125,502,000 |
| 2022年 | 124,947,000 |
| 2023年 | 124,352,000 |
| 2024年 | 123,802,000 |
2024年の日本の人口が1億2,380万人で前年に比べ55万人の減少であり、2010年をピークに14年連続での減少となっています。
減少幅も13年連続で拡大しており、人口が年々減少傾向にあることが分かります。
人口が減少すると家を必要とする人の母数が減少するため、家が売りにくくなると考えられるのです。
人件費の高騰
家が売りにくくなる要因には、人口減少以外に住宅価格の高騰も考えられます。
国土交通省の不動産価格指数2では、2010年の価格を100%としたとき2024年12月の戸建てで117.4%、マンションで208.1%と上昇傾向です。
不動産価格が高騰する理由の一つに、人件費の高騰が挙げられます。
たとえば、東京都であれば平成14年の最低賃金が708円だったのに対し、令和6年には1,163円に増加しています3。
全国平均でみても、平成14年の663円に対して令和6年は1,055円と増加傾向です。
また、前述したように人口減少にともなる働き手の不足も人件費高騰につながる要因と言えるでしょう。
人件費が高騰すれば、住宅をつくる際のコストが増加し新築価格の高騰につながります。
新築価格が高騰すると、新築を避けて中古需要が高まることから、中古価格の高騰にもつながるのです。
新築・中古ともに家の価格が高くなることで、買い手が家を買いにくくなり売り手側の売りにくさにつながると考えられます。
資材高
家の価格が高くなる要因に、住宅資材の高騰もあります。
2021年頃から始まったウッドショックと呼ばれる木材の高騰や給湯器等の住宅設備の不足により、資材価格は上昇傾向にあります。
また、近年の物価高やガソリン代や電気料金の高騰も、住宅の建築費を上げる要因です。
金利が上がる可能性がある
金融緩和政策がとられて以降、超低金利と言われていた住宅ローンも近年上昇の兆しがあります。
2022年に日銀が長期金利の利上げを発表し、2022年~2023年には固定金利タイプの金利水準の上昇がみられました。
さらに、日銀では2024年にマイナス金利を解除、同年7月と2025年1月に利上げを行っています。
これにより、2025年4月に変動金利の基準金利を引き上げる金融機関も少なくなかったのです。
今後も追加利上げがされると見込まれており、将来金利が上がる可能性はゼロとはいえません。
住宅ローンの金利が上がると住宅ローンを組みにくくなるなどで、買い手の購入意欲が減退します。
また、借入できる額も少なくなることで、価格を下げなければ売れなくなり、家の価格下落にもつながりかねません。
金利も住宅価格や需要に大きく影響するため、今後の動向を注視しておきましょう。
今後はさらに家が売りづらくなる?
今後はさらに家が売りにくくなる可能性があります。
その要因として、今後の人口と金利をみてみましょう。
2050年には9,500万人まで人口が減る予測
減少傾向にある日本の人口ですが、今後はより深刻になると見込まれています。
厚生労働省によると、日本の推計人口は2020年の1億2,615人から2070年には8,700万人にまで減少するとされています4。
さらに、高齢化は進行し2020年の28.6%から2070年では38.7%に上昇する予測です。
出生率も2020年の1.33から2070年には1.13~1.36と大きく改善しない見込みであり、自然増による人口増加の見込みは低いといえるでしょう。
住宅ローン金利の上昇
住宅金融支援機構による直近の「フラット35借入金利の推移」は以下のとおりです5。
| 最低 | 最高 | |
| 2022.04 | 1.440 | 2.540 |
| 2023.04 | 1.760 | 3.070 |
| 2024.04 | 1.820 | 3.210 |
| 2025.04 | 1.840 | 3.930 |
長期固定金利が年々上昇傾向にあることが分かります。
また、変動金利についても前述したように、2025年1月に日銀が追加利上げしたことにより、4月に変動金利の基準金利を引きあげる金融機関が多くあります。
追加利上げについては3月・4月は見送られたものの、7月か9月に行われると見込まれており、今後の利上げは避けて通れないといえるでしょう。
住宅ローン金利が将来どうなるかの見通しは正確には行えません。
しかし、金利上昇の可能性がゼロではないことは覚えておきましょう。
家が売れないと起こりうるリスク
家が売れないと起こるリスクとしては以下の3つが挙げられます。
- 売れない期間が長期化すると資産価値が目減りする
- 住宅ローンを完済できないとそもそも売却できない
- 固定資産税はかかり続ける
それぞれ見ていきましょう。
売れない期間が長期化すると資産価値が目減りする
家は築年数の経過に応じて資産価値が減少します。
東日本不動産流通機構の「年報マーケットウォッチ2023年・年度」による、築年数別の戸建ての成約価格は以下のとおりです6。
| ��築年数 | ~築5年 | 築6~10年 | 築11~15年 | 築16~20年 | 築21~25年 | 築26年~30年 | 築31年~ |
| 価格 | 5,021万円 | 4,733万円 | 4,573万円 | 4,271万円 | 3,919万円 | 3,496万円 | 2,460万円 |
築5年以下に比べ、築31年超えは半額以下の価格になっていることが分かります。
木造住宅は耐用年数である22年を超えると、資産価値がゼロになるといわれています。
もちろん、築22年を超えても状態がよければ高値で売却でき、仮に建物の資産価値がほぼなくなっても戸建てであれば土地の価格で売却できます。
とはいえ、築年数が経過するほど価格が下がるため、少しでも高く売りたいなら築年数も考慮することが大切です。
売れない期間が長引くほど、その期間分築年数が経過し価格は下がります。
とくに、築10年や20年といった節目を超えると、買い手が物件を検索する際の対象からも外されやすくなるため、売却に不利になりかねないのです。
住宅ローンを完済できないとそもそも売却できない
家を売却するには、住宅ローンを完済することが前提です。
住宅ローンを組んだ際に抵当権(金融機関から担保として不動産に設定される権利)が設定されており、住宅ローンを完済し抵当権を抹消しなければ家の売却はできません。
売却金で完済できるなら問題ありませんが、売却金だけでは足りない場合は自己資金などでの補填が必要です。
売却金で住宅ローンの完済を検討している場合、売却が長期化することで価格が下がり、返済計画が崩れる恐れがあります。
また、売れない期間にも住宅ローンの返済が続くため、住宅ローンの返済が厳しくて売却を検討する場合も注意が必要です。
売却金で住宅ローンの返済ができない場合、売却を諦めるか住宅ローンが滞ってから任意売却を検討することになります。
任意売却とは、家を売った金額でローンを完済できない場合、売却後の残債務支払いについて金融機関と相談した上で売却を認めてもらうこと。一般的には、不動産会社に仲介業務と金融機関との交渉を依頼するケースが多い。
売れない期間が長くなり値下げを検討する場合は、再度住宅ローンの残債の正確な額をチェックし返済できるかも確認しましょう。
固定資産税はかかり続ける
固定資産税とは、不動産の所有者に毎年課せられる税金です。
売却中の家や空き家であっても、所有者が売主である以上は毎年固定資産税の納税義務が発生します。
さらに、家の所在地によっては都市計画税も対象です。
不動産によって税額は異なりますが、年間10~30万円ほど税金の負担があるため、長期化するほど金銭的な圧迫も大きくなるでしょう。
家が売れない場合の対策
家が売れないからと言ってそのまま放置していても、税金の負担や資産価値の低下などリスクが大きくなります。
家が売れない場合、以下の対策も検討するようにしましょう。
- 賃貸として活用する
- 価値が落ちる前に売却する
- 早い段階で買取を検討する
それぞれ見ていきましょう。
賃貸として活用する
人口は減少していますが、核家族化や転入などにより世帯数は増加傾向にあります。
また、家の価格の高さから持ち家ではなく賃貸にシフトチェンジする人もいるものです。
そのため、売却は難しくても賃貸としての需要があるケースがあります。
賃貸として活用できれば、毎月家賃収入を得られるので、維持管理費や固定資産税などをカバーできるだけでなく、賃料によっては手元にお金を残すことも可能です。
さらに、賃貸であれば入居者が建物を管理してくれるので、自分でメンテナンスしなくても家を維持しやすいのもメリットでしょう。
ただし、賃貸は立地に需要が大きく左右されるため、事前にエリアのニーズをしっかりリサーチし、需要のある立地や間取りかを調べることが大切です。
また、築年数が経過していると賃貸経営の初期段階でリフォーム費用などが高額になる可能性もあるため、資金計画もしっかり立てるようにしましょう。
価値が落ちる前に売却する
売れない期間が長引き資産価値が下がると、さらに買い手に悪いイメージを与え、売れにくくなる悪循環に陥りやすくなります。
そのため、売れないと感じたら資産価値が落ちる前の早い段階で対策することが大切です。
売れない理由としては、相場よりも価格が高いことや築年数が古いことが代表的ですが、それ以外にも以下のような要因で売れないケースもあります。
- 広告の写真映りが悪い
- 内覧対応で失敗している
- 不動産会社が熱心ではない
相場よりも価格が高いのであれば、価格を見直すことで売却できる可能性があります。
一方、それ以外の理由であれば、価格とは別の対策で売れる可能性があるでしょう。
まずは、売れない理由をしっかりと探し、理由に合わせた対策を行うことが大切です。
不動産会社の営業が適切ではない、熱心に営業��してくれないなど不動産会社が理由の場合は、信頼できる不動産会社と媒介契約を締結し直すことで売却できる可能性があります。
一度、他の不動産会社の査定を受けてみて、自分の不動産との相性をチェックするのも一つの方法です。
早い段階で買取を検討する
仲介では広告などで買主を探すため、築年数や立地など不動産の条件によっては買主がなかなか現れないケースも珍しくありません。
その場合は、仲介ではなく買取を視野に入れることでスムーズに売却できる可能性があります。
買取では不動産会社が直接買主となるので、不動産会社との交渉だけで売却が決まり、短期間での売却が可能です。
仲介よりも価格が下がる点がデメリットですが、仲介手数料やリフォーム費が不要なため、トータルではそれほど変わらないケースもあるでしょう。
また、いつまでも売れないまま保有するよりも、買取で短期間で売却した方がメリットが大きい可能性もあります。
買取に悩む場合は、一度買取査定を受けて価格をチェックしてから判断するのもおすすめです。
イエウリでは、仲介だけでなく買取の一括査定にも対応しています。
査定時には不動産会社に個人情報が伝わらないため、営業電話に悩まされる必要もありません。
まずは仲介・買取の査定を受けて売却方針を決めていくとよいでしょう。
家が売れない時代になったことに関するよくある質問
家が売れない時代になったことに関するよくある質問をみていきましょう。
マンションの買い手がつかない場合はどうすればいい?
マンションの売れない理由に合わせて対策が必要です。
売れない理由としては以下が考えられます。
- 価格が相場よりも高い
- 立地が悪い
- 築年数が古い
- 広告の写真が悪い
- 管理組合の管理が悪い
- 内覧対応が悪い
- 不動産会社が熱心ではない
価格が高いなら、一度相場を徹底的にリサーチし見直すことで売却できる可能性があります。
他の理由の場合も、理由に合わせた対策で売れる可能性があるので検討してみるとよいでしょう。
対策しても売れない、早く売りたいというのであれば、買取を視野に入れるのがおすすめです。
マンションはタダでも売れないって本当?
売れにくいケースはありますが、マンションは基本的に需要を調査し適した立地・間取りで建築しているため、対策することで売れる可能性があります。
どうしても売れない場合は、買取を視野に入れるとよいでしょう。
まとめ
近年は人口減少や家の価格の高騰・金利上昇などで、需要や買い手の意欲が下がり家が売りにくいといわれています。
また、今後は人口減少・金利上昇など売りにくさが進行する要因もあるため、売却を検討しているなら少しでも早く動くことが大切です。
家の売却の成功は不動産会社選びにも左右されます。
複数の不動産会社を比較し、販売力があり信頼できる不動産会社を選ぶことでスムーズな売却を目指せるでしょう。