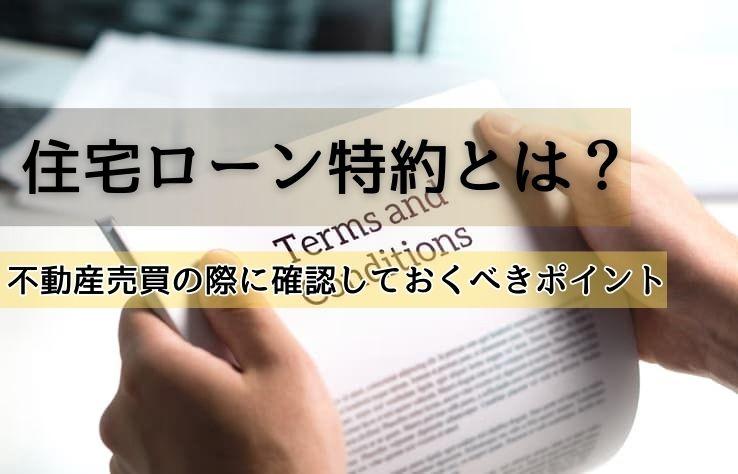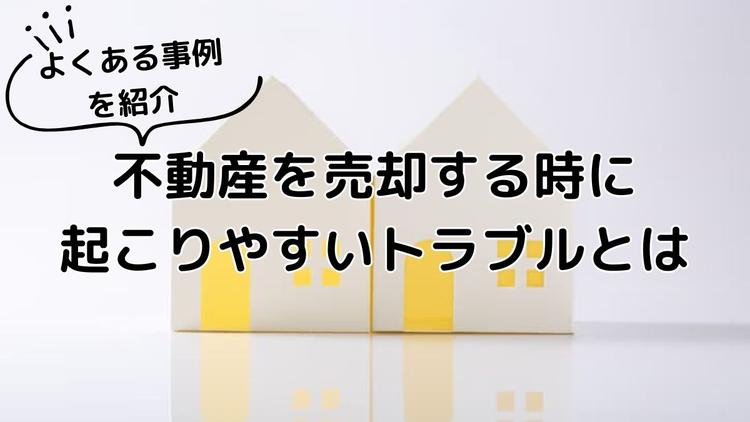住宅の売買を検討しているときに、よく耳にするのが「耐震基準適合証明書」です。
何となく重要な書類だとは思うものの、具体的にどのようなものなのか、なぜ取得する必要があるのか、よく分からないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、耐震基準適合証明書の基本から、売買時における重要性、取得の流れまでを分かりやすく解説します。
耐震基準適合証明書とは?
耐震基準適合証明書とは、その建物が現行の耐震基準を満たしていることを証明する書類です。
具体的には、建築士などの専門家が建物の構造や強度を評価し、地震に対する安全性が基準を満たしていると判断した場合に発行されます。
この証明書は、住宅ローン控除や不動産取得税・登録免許税の軽減措置、住宅ローンの利用など、様々な場面で必要となることがあります。
まずは、耐震基準適合証明書の基本的なポイントを押えていきましょう。
現行の耐震基準への適合性を証明する
耐震基準適合証明書は、建物が現行の建築基準法に基づく耐震基準に適合していることを、建築の専門家が証明する書類です。
具体的には、1981年6月1日以降に適用された新耐震基準、さらに2000年6月1日にはより厳しい基準(2000年基準)が適用されています。耐震基準適合証明書は、これらのいずれかの基準に適合していることを証明するものです。
証明されたことにより、その建物が中規模の地震(震度5強程度)に対しては構造体に損傷が生じにくく、大規模な地震(震度6強~7程度)に対しては倒壊・崩壊しにくい程度の耐震性能を有していると評価されたことを意味します。
耐震基準適合証明書を入手する方法
耐震基準適合証明書を入手するには、次の専門家や機関に依頼します。
- 建築士事務所……近くの建築士事務所に直接相談し、耐震診断と証明書の発行を依頼します。
- 指定確認検査機関……建築確認申請の審査や完了検査を行う機関ですが、耐震基準適合証明書の発行も行っています。
- 登録住宅性能評価機関……住宅の性能を評価する専門機関で、耐震性能についても評価・証明を行っています。
- ホームインスペクション会社……住宅の診断を行う専門の会社で、耐震診断を行い、提携している建築士事務所などを通して証明書の発行を依頼することができます。
依頼に際しては、建物の図面(配置図、平面図、構造図など)や建築確認済証、検査済証などが必要になる場合があります。
耐震基準適合証明書を取得する費用
耐震基準適合証明書の取得にかかる費用は、建物の種類、規模、構造、築年数、そして依頼する専門家や機関によって大きく変動します。
ここでは、費用の構成要素と、一般的な価格帯の目安についてお伝えします。
耐震診断費用は、木造住宅だと一般的に、数万円から20万円程度が目安となります。鉄骨造や鉄筋コンクリート造は、木造よりも構造計算が複雑になるため、20万円以上になることもあります。
証明書発行手数料�は、数千円から数万円程度が目安です。
建物の図面がない場合や不十分な場合、図面の作成費用が別途発生することがあります。この費用は、建物の複雑さによって大きく変動します。
売買時に耐震基準適合証明書を取得すべき理由とは
耐震基準適合証明書があることで、購入希望者はその住宅の耐震性について一定の安心感を得ることができます。中古住宅の購入を検討する際には、この証明書の有無を確認することが、安全な住まい選びの重要なポイントとなるのです。
中古住宅の売買において、耐震基準適合証明書を取得することによって、買主と売主双方に複数の重要なメリットがあります。
ここでは、耐震基準適合証明書を取得した方がよいとされる理由を解説していきましょう。
買主は住宅ローン控除が受けられる
住宅ローンを利用して中古住宅を購入する場合、一定の要件を満たすことで、住宅ローンの年末残高に応じた所得税控除を受けることができます。
住宅ローン控除を受けるには、購入者の所得や住宅の床面積などの条件に加えて、住宅が一定の耐震基準を満たしていることが必要です。具体的には、耐震基準適合証明書などでその適合を証明することが求められます。
買主は不動産取得税の軽減措置が受けられる
不動産取得税は、土地や家屋を取得した際に課される税金です。
しかし、一定の要件を満たす住宅については、住宅の固定資産税評価額から一定額が控除される軽減措置が適用されます。その要件の一つに「耐震基準適合住宅」であることが挙げられます。
1982年1月1日以前に建築された中古住宅であっても、耐震基準適合証明書によって現行の耐震基準に適合していることが証明されれば、不動産取得税の軽減措置を受けることが可能です。
買主は登録免許税の軽減措置が受けられる
登録免許税は、不動産の所有権移転登記や抵当権設定登記などを行う際に課される税金ですが、こちらも一定の要件を満たす住宅には軽減措置が適用されます。耐震基準適合住宅も、この軽減対象に含まれる場合があります。
前述の不動産取得税と同様に、1982年1月1日以前に建築された中古住宅であっても、耐震基準適合証明書によって現行の耐震基準に適合していることが証明されれば、登録免許税の軽減措置を受けることができます。
買主は住宅の安全性に対する安心感が得られる
地震はいつどこで発生するか予測が難しい自然災害です。中古住宅の場合、新築時にどのような耐震対策が施されたのか、その後の維持管理は適切に行われてきたのかなど、目に見えない部分に対する不安を感じる方も少なくありません。
耐震基準適合証明書は、建築の専門家がその建物が現行の耐震基準、またはそれに準ずる基準を満たしていることを証明するものです。
目に見えない建物の強度について、専門家による客観的な評価が得られるため、安心して購入の意思決定ができる大きな要素となります。
売主は有利な条件での売却ができる
耐震基準に適合していることは、物件の大きなアピー�ルポイントとなり、購入希望者に対して安心感を与え、早期売却につながる可能性があります。
近年、地震に対する人々の意識は非常に高まっており、住宅購入においても「安全性」が重要な判断基準となっています。特に中古住宅の場合、築年数によっては耐震性能に不安を感じる買い手も少なくありません。
このような状況下で、売却する物件に耐震基準適合証明書があれば、「この物件は現行の耐震基準を満たしている」ということを、専門家による客観的な証明書として提示できます。これにより、買い手は安心して購入を検討することができ、成約率の向上に繋がるのです。
売主は価格競争力が向上する
耐震性が確保されている物件は、そうでない物件と比べて、市場での評価が高まります。
複数の物件が売りに出されている場合、買い手はより安全性の高い物件を選ぶ傾向があり、耐震基準適合証明書があることで、価格競争において優位に立つことができます。
売却価格を少しでも上げたい売主にとって、耐震基準適合証明書の取得は有効な手段となるでしょう。
売却の競争力を高めるには、スピード感も重要な要素です。
不動産売却は、買い手探しから契約、引き渡しまで、ある程度の時間がかかるものです。しかし、耐震性に対する買い手の不安が解消されていれば、購入の意思決定がスムーズに進みやすくなります。
売却活動開始前に耐震基準適合証明書を取得しておくことで、買い手からの耐震性に関する質問や懸念に対応する手間を省くことができ、売却プロセス全体の効率化にも繋がります。
売主�は契約不適合責任のリスクが軽減する
中古住宅の場合、新築住宅と比べて物件の状態を正確に把握することが難しい場合があります。そのため、売買契約締結時には認識していなかった不具合が、引渡し後に発覚するケースも少なくありません。
特に、建物の耐震性能は目に見えにくく、専門家による調査なしには判断が難しいため、契約不適合責任を巡るトラブルに発展しやすい要因の一つとなります。
たとえば、「売買契約時には、現行の耐震基準を満たしていると説明していたが、実際には満たしていなかった」「過去の地震による損傷があることを告知していなかった」といった場合、売主は契約不適合責任を追及される可能性があります。
このようなリスクを軽減するために、売買対象となる中古住宅について、売主が事前に耐震基準適合証明書を取得しておくことが有効です。
耐震基準適合証明書の取得手続きの流れ
耐震基準適合証明書を取得するには、専門家による建物の調査と評価が必要です。
一般的な手続きは、次のように進めていきます。
①専門家へ依頼する
まずは、耐震診断および証明書の発行が可能な専門家を探し、依頼・相談を行いましょう。
専門家については前述のとおり、建築士事務所、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、ホームインスペクション会社などが該当します。
複数の専門家に見積もりを依頼し、費用や期間、実績などを比較検討してください。
②耐震診断の実施
依頼した専門家が、建物の図面や現地調査に基づいて耐震診断を行います。主な調査項目は次のとおりです。
- 建物の構造……基礎、柱、梁、壁などの構造部の種類や配置、劣化状況などを確認します。
- 接合部の状況……柱と梁、壁と柱などの接合部の強度や金物の有無などを確認します
- 地盤の状況(必要に応じて)……地盤の状況は、建物の構造や基礎に影響を与える可能性があるため、過去の地盤調査報告書などが参考になる場合があります。
耐震診断の結果、建物が現行の耐震基準を満たしているかどうかが評価されます。
③耐震改修工事(必要な場合)
耐震診断の結果、建物が現行の耐震基準を満たしていないと判断された場合、耐震基準適合証明書を取得するには、耐震改修工事を行う必要があります。改修計画の作成から工事の実施、完了までには相応の期間と費用がかかります。
耐震改修工事後に再度専門家による評価を受け、基準への適合が確認され�れば証明書の発行に進むことができます。
▼関連記事:戸建ての耐震補強リフォームは必要?判断基準・工事の内容・費用や補助金を解説
④耐震基準適合証明書の申請・発行
耐震診断または耐震改修工事後の評価に基づき、専門家が耐震基準適合証明書を作成・発行します。
申請に必要な書類は、依頼する専門家や機関によって異なる場合がありますが、一般的には以下のものが挙げられます。
- 建物の登記簿謄本または登記事項証明書
- 建築確認済証および検査済証
- 建物の図面(配置図、平面図、立面図、構造図など)
- 耐震診断報告書(耐震改修工事を行った場合は、その関連書類も含む)
- 申請者の本人確認書類
専門家はこれらの書類と診断結果などを確認し、建物が現行の耐震基準に適合していると判断した場合に、耐震基準適合証明書を発行します。
⑤証明書の受け取り
発行された耐震基準適合証明書を受け取ります。
この証明書は、住宅ローンの手続きや税制上の優遇措置の申請など、必要な場面で提出することになるので、大切に保管するようにしましょう。
注意点
診断から証明書の発行まで、建物の状況や専門家のスケジュールによって期間が異なります。売買のスケジュールに合わせて、余裕をもって手続きを進めることが重要です。
耐震基準適合証明書には特に定められた有効期限はありませんが、発行日があまりにも古い場合は金融機関や税務署から再取得を求め�られることがあります。
まとめ
耐震基準適合証明書は、中古住宅が現在の建築基準法に定める耐震基準を満たしていることを専門家が証明する重要な書類です。
この証明書を取得することで、住宅の買主は住宅ローン控除や不動産取得税・登録免許税の軽減措置といった経済的なメリットを享受できるだけでなく、何よりも建物の安全性に対する安心感を得られます。
一方、売主にとっては、物件の耐震性を客観的に示すことで、購入希望者に安心感を与え、有利な条件での売却や価格競争力の向上、さらには契約不適合責任のリスク軽減に繋がる可能性があります。
取得の手続きは、建築士事務所(設計・工事監理の専門家)、指定確認検査機関(建築確認・完了検査を行う第三者機関)、登録住宅性能評価機関(住宅性能を評価する専門機関)、ホームインスペクション会社(住宅診断の専門会社)といった専門家に依頼しましょう。耐震診断を受けた後、基準に適合していれば証明書が発行されるという流れが一般的です。建物の状況によっては耐震改修工事が必要となる場合もあります。
中古住宅の売買を検討する際には、買主・売主双方にとって、耐震基準適合証明書の取得が取引を円滑に進め、より良い条件での売買を実現するための重要な鍵となるでしょう。売買のスケジュールに合わせて、できるだけ早い段階で専門家への相談と手続きを進めてください。