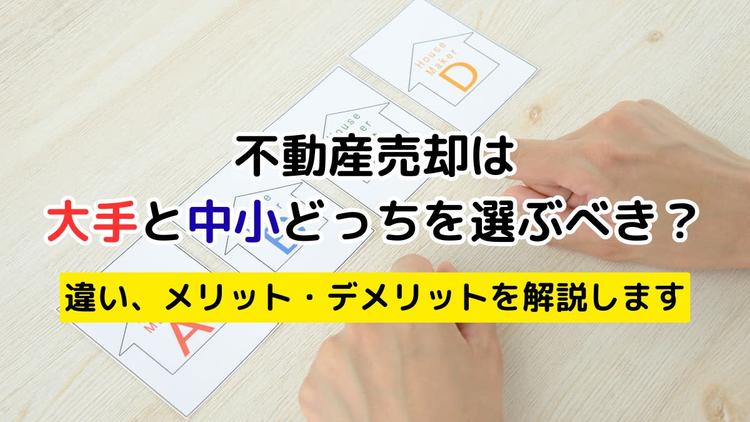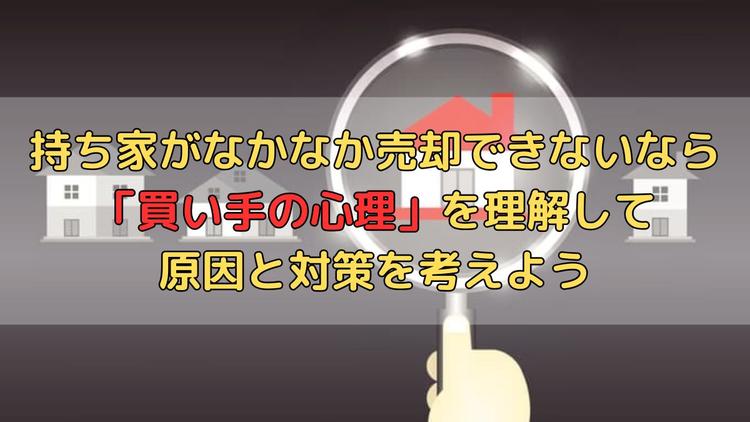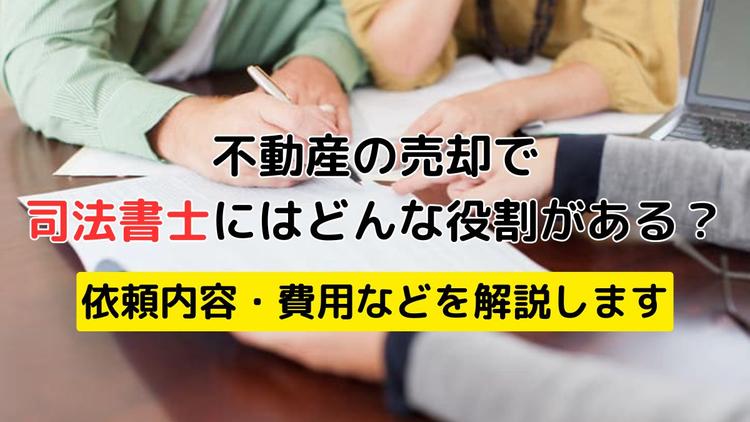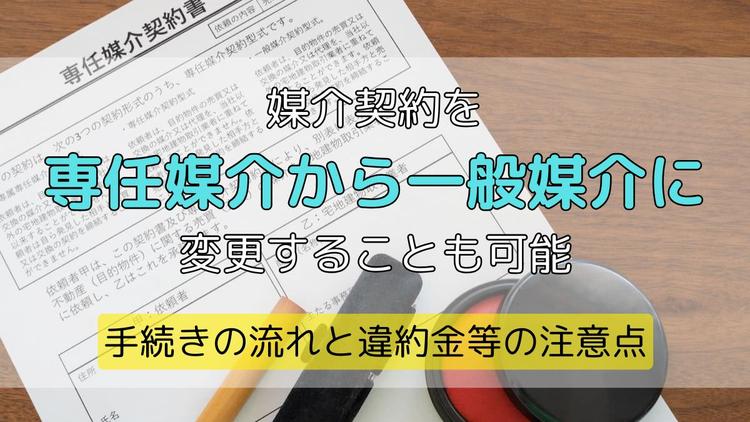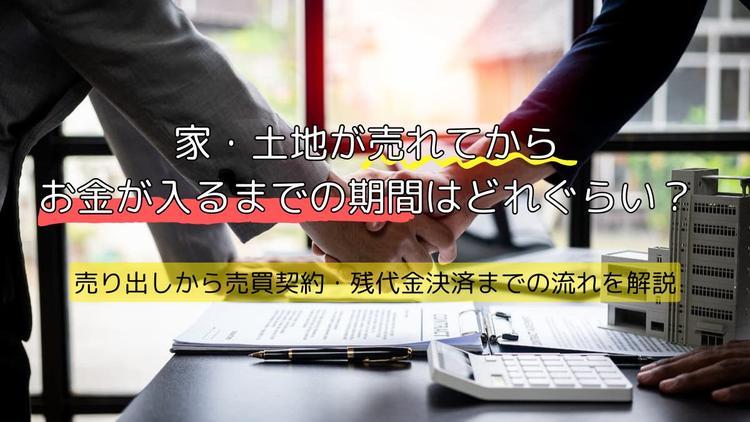中古物件を購入後、住み替えや転勤などの理由で購入した家を手放す人も多いものです。
中古で購入した家でも売却することは可能です。
しかし、中古で購入した家の売却にはいくつか押さえておきたい注意点があります。
この記事では、中古で購入した家を売る時の注意点を詳しく解説します。
中古で買った家を売ることはできる?
中古で購入した家でも、売却は可能です。
中古で購入したからといって売却できないわけではなく、通常の不動産同様に売却できます。
そもそも「中古物件」とは、新築物件以外を指し、それまでの売買回数は問われません。
新築で購入した物件も、中古で購入した物件もどちらも売却するにあたっては「中古物件(中古住宅)」に該当し、区別はないのです。
近年では、高額な新築物件を避けて中古物件を購入する人や、安い中古物件を購入して自分好みにリフォームしたいという人も多く、中古住宅のニーズも高くなっています。
そのため、中古で購入した家であっても、条件によってはスムーズな売却が期待できるでしょう。
しかし、中古で購入した家は新築で購入した家よりも売却が難しくなるケースも珍しくありません。
中古物件の売却ならではの注意点もあるので、しっかりと押さえておくことが重要です。
中古で買った家を売るときの注意点としては、以下の3つが挙げられます。
- 築年数が古いと買い手側の住宅ローン審査に不利になりやすい
- オーバーローン状態での売却に注意
- 契約不適合責任に注意
以下では、それぞれ詳しくみていきましょう。
注意点1:築年数が古いと買い手側の住宅ローン審査に不利になりやすい
中古で購入した家は、売却��時にはさらに年数が経過しているものです。
たとえば、所有期間が10年の場合、新築で購入して10年経過した場合なら築10年の物件ですが、築10年の中古物件を購入して10年後に売る際には築20年になっています。
築年数が古くなることは、価格が下がるだけでなく、買い手側の住宅ローンにも影響を与える可能性があります。
住宅ローン審査では物件の担保価値を見られる
住宅ローンの審査では、年収や勤務先といった個人の属性だけでなく、購入する家の担保価値もチェックされます。
金融機関は担保価値以上の融資は行いません。
たとえば、担保価値が2,000万円の物件に対して、3,000万円の住宅ローンは組めないのです。
担保価値以上の融資を行うと、返済が滞った際に強制的に売却しても、残債の回収が難しくなります。
また、建物は築年数が経過するごとに資産価値が減少するため、築年数が古い物件は担保価値が低くなりがちです。
そのため、買主が住宅ローンを組めない、または組めても希望額の融資を受けられない事態に陥る恐れがあります。
築年数の古い中古住宅は価格が抑えられるといっても、現金一括で購入するケースは稀です。
住宅ローンが組みにくいと、資金の都合により買い手から避けられやすくなってしまいます。
構造別の耐用年数
家の担保価値を考えるうえで指標の1つとなるのが耐用年数です。
耐用年数とは価値を保てる年数のことで、建物の場合構造によって以下のように定められています。
| 構造 | 耐�用年数 |
| 木造 | 22年 |
| 軽量鉄骨造 | 27年 |
| 鉄筋コンクリート造(RC造) | 47年 |
木造住宅の耐用年数は22年であり、22年を超えると税法上の資産価値は0円とみなされ、住宅ローン審査に不利になる恐れがあります。
ただし、耐用年数は会計上の価値であり、実際に耐用年数が超えたからといって住めなくなるほど建物が劣化するわけではありません。
そのため、耐用年数が超えていても条件によっては住宅ローンを組める可能性はあるでしょう。
とはいえ、耐用年数を超えると不利になりやすい点は覚えておく必要があります。
旧耐震基準だと住宅ローン控除の適用条件に注意が必要
住宅ローン控除の適用可否には「耐震基準」が大きく影響します。
1981年6月1日以前に建築確認を受けた「旧耐震基準」に相当する物件では、原則として住宅ローン控除は受けられず、そもそも金融機関も耐震性への不安から融資を行わないことがほとんどです。
旧耐震基準だから即倒壊するというわけではありませんが、新耐震基準よりも倒壊リスクは高くなるため、住宅ローン審査が不利になってしまいます。
住宅ローンで物件を購入する買い手の多くは、住宅ローン控除の適用を検討しているものです。
しかし、住宅ローン控除の適用要件1の1つに、昭和57年(1982年)以降の建築または新耐震基準に適合というものがあり、旧耐震基準のままでは適用できません。
旧耐震基準で建てられた家でも、耐震補強を行って新耐震基準に適合することを証明できれば適用可能ですが、耐震補強には大規模な工事が必要となり、費用も高額になりがちです。
住宅ローン控除を適用しにくいことも、買い手から避けられやすくなる要因と言えるでしょう。
新耐震基準の後、2000年からの「現行耐震基準(2000年基準とも呼ばれる)」では、さらに耐震性能が強化されている。
注意点2:オーバーローン状態での売却に注意
中古住宅購入時に住宅ローンを組んでいる場合、完済できるかどうかが売却を大きく左右します。
すでに完済しているなら問題なく売却できます。住宅ローン返済中であっても売却は可能ですが、売却時には住宅ローンの完済が必須です。
自己資金のみで完済できれば問題ありませんが、一般的には売却金で完済するケースが多いでしょう。
そのため、アンダーローンかオーバーローンかが重要になってくるのです。
アンダーローンとオーバーローン
アンダーローンとは、売却金が住宅ローン残高を上回る状態です。
この状態であれば売却すれば住宅ローンを完済できるので、売却を進められます。
一方、オーバーローンとは売却金よりも住宅ローン残債が多い状態です。
オーバーローンの家は売却しても、売却金だけでは住宅ローンが完済できないため、売却するには工夫が必要になってきます。
オーバーローンでの売却は差額分を現金で用意する必要がある
オーバーローンであっても、売却金だけで足りない分を補えれば売却は可能です。
たとえば、住宅ローン残債が2,000万円で売却金が1,800万円の場合、残り200万円を工面できれば完済できるので、売却に進めます。
差額分の工面方法としては、自己資金や親からの援助、住み替えローンなどの活用が考えられるでしょう。
しかし、��これらの方法でも完済できないとなれば、売却が難しくなります。
その場合は、売却時期を先延ばしして住宅ローンを減らすか、任意売却を検討することになるでしょう。
住宅ローン完済は売却可否に大きく関わってくるため、住宅ローンの正確な残債と査定額、自己資金をもとに、返済できるかどうかを見極めることが重要です。
購入時・売却時にそれぞれ諸経費がかかる
住宅ローンの完済計画を立てる際には、諸経費も考慮する必要があります。
購入・売却でかかる主な費用は以下のとおりです。
| 購入時 | 売却時 |
|
|
一般的に、購入時の諸経費・売却時の諸経費は、それぞれ購入額・売却額の5~10%ほどといわれています。
たとえば、3,000万円で売却するケースでは、150~300万円が目安です。
住み替えで4,000万円の新居を購入するなら、さらに200~400万円の費用がかかってきます。
売却金で住宅ローンを完済できても、諸経費を失念し捻出できないとなれば売却計画が崩れかねません。
あらかじめどの�ような費用がいくらかかるかもシミュレーションしたうえで、資金計画を立てることが大切です。
注意点3:契約不適合責任に注意
築年数が経過した家の売却では、契約不適合責任を問われるリスクが高くなります。
家の売却を検討する際には、契約不適合責任についても理解しておくことが重要です。
契約不適合責任とは
契約不適合責任とは、契約とは異なる目的物を引き渡した際に売主に問われる責任です。
不動産取引では、契約書に記載のない不具合が発覚した際に問われる恐れがあります。
代表的な契約不適合責任が問われるのは以下のような不具合です。
- シロアリ被害
- 雨漏りや漏水
- 傾きやひび割れ
- 土壌汚染や地中埋設物
- 土地の面積が契約書と異なっている
- 事故物件
上記のような告知義務のある不具合を告知せずに契約すると、契約不適合責任が問われ、買主から補修費や代金減額、損害賠償請求、契約解除を求められるリスクがあるのです。
なお、契約不適合責任は契約書に記載がない不具合が生じたケースで問われます。
不具合がある場合でも、告知し契約書に記載しておくことで、責任を追及されるリスクを避けられます。
よくある契約不適合責任への対応事例
取引後に告知されていないシロアリ被害が発覚したケースをみてみましょう。
この場合、まず買主は「履行の追完請求」として、物件が契約書に記載された状態と相違が出ないように補修を求めることが可能です。
具体的には、シロアリ駆除や腐食した柱の補修、または補修費の請求が行われるでしょう。
もし補修に応じない場合、買主は代金減額請求を行うことができます。
さらに、土地の面積が足りなかったり、自殺があった事故物件などの補修できないケースでは、最初から代金減額請求が可能です。
また、追完請求や代金減額請求に加えて、買主が被った損害に対する損害賠償請求をされるケ��ースもあります。
もし代金減額請求にも応じず、住むのが不可能だと判断される場合は、契約の解除により全額返還請求も可能です。
ただし、不具合の程度によっては契約解除が認められないこともあります。
このように、契約不適合責任を問われると、順を追って売主のリスクが高くなります。
早い段階で対応しておくことで、契約解除を避けられるでしょう。
物件の不具合など全て契約書に記載する
契約不適合責任を問われると負担が大きくなるため、これを避けるための対策が重要です。
前述のとおり、契約不適合責任は、不具合を契約書に記載することでリスクを回避することができます。
しかし、築年数が経過した中古物件では、不具合の箇所が多いことも予測できます。
そのような場合、買主の合意を得て契約不適合責任を免責とすることも可能なので、検討するとよいでしょう。
建物の解体を前提として「古家付きの家」として売却するのであれば、建物の不具合に関して契約不適合責任を問われることはありません。
ただしこの場合も、建物の解体後に埋設物が見つかり、新しく建築するために撤去が必要であれば、撤去費用の負担を求められる可能性があります。
また、売却前にインスペクション(既存住宅状況調査)を受けて、家の状態を正確に把握するのも1つの手です。
インスペクションを受ければ、不具合を正確に告知できるだけでなく、家の状態を証明する資料として活用でき、買主の安心材料となるメリットもあります。
中古で買った家の売却に関するよくある質問
最後に、中古で買った家を売ることに関するよくある質問をみていきましょう。
中古で買った家を売るときの税金はどうなる?
家の売却では、売買契約書にかかる印紙税、抵当権抹消登記が必要な場合の登録免許税、利益が出た場合の譲渡所得税の3つが課税されます。
譲渡所得税は、売却額から減価償却後の購入時の費用と、売却にかかった費用を差し引いた金額がプラスになった場合に課税されます。
また、税率は所有期間によって異なり、所有期間が5年以下の場合は税率が高くなるので注意しましょう。
なお、売却で損失が出た場合でも、確定申告により損失を損益通算できる特例を適用することができます。
売却を検討する際には、譲渡所得税についても理解しておくようにしましょう。
中古で買った家をすぐに売るよくある理由は?
代表的な売却理由には、転職や転勤、離婚、隣人トラブル、住宅ローンが返済できなくなったなどが挙げられます。
転職や転勤、離婚、住宅ローンの返済が理由であれば、売却にそれほど影響は出ないでしょう。
一方、隣人トラブルは、買主から避けられる可能性があるため注意が必要です。
さらに、隣人トラブルには告知義務があることも覚えておきましょう。
まとめ
中古で購入した家でも売却できますが、築年数が経過していることが見込まれるため、売却しにくくなる恐れがあります。
とくに、築年数の経過による買主の住宅ローンへの影響や、契約不適合責任には注意が必要です。
そもそも住宅ローンを完済できないと売却もできないので、まずは完済できるかをしっかり見極めるようにしましょう。
住宅ローン完済の見極めには正確な査定も重要になってきます。
できるだけ複数の不動産会社の査定を受けたうえで、売却を検討するようにしましょう。
イエウリなら、一度により多くの不動産会社の査定を受けられます。
買取査定にも対応しているので、より柔軟な売却プランを立てやすくなるでしょう。