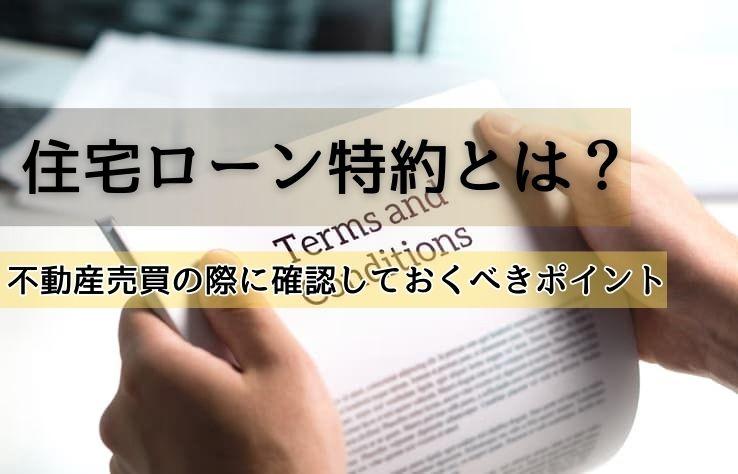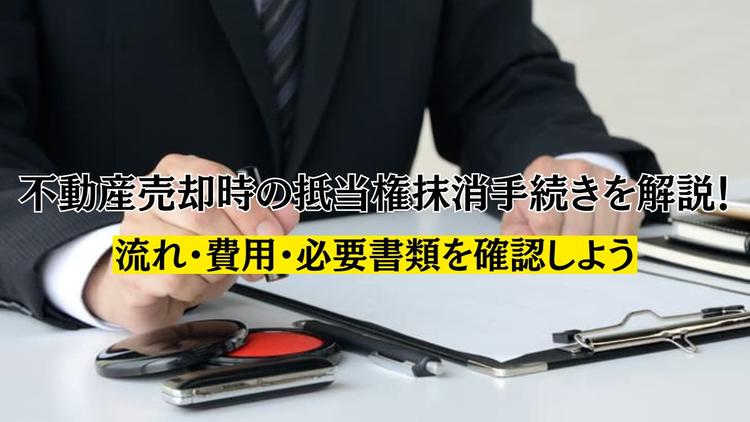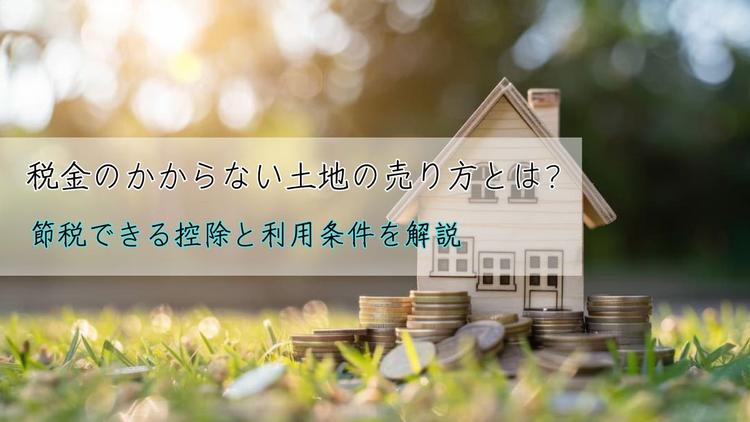家を建てる際には、建築確認申請という手続きが必要になります。
これは、建築物が建築基準法などの法律に適合しているかを確認するための大切なルールです。
この申請を怠ると、法律違反となるばかりでなく、住宅ローンを利用できなくなったり、売却時に不利になったりするといった、大きなリスクを背負うことになります。
この記事では、建築確認申請について、概要から申請の流れ、費用、増改築を行う際の注意点について解説します。
建築確認申請とは
建築確認申請とは、建築物を建築する際に、その計画が建築基準法等の規定に適合しているかどうかを確認するための手続きです。
具体的には、建物の規模、構造、防火設備、避難経路などが、法律で定められた基準を満たしていることを審査します。
では、建築確認申請はどのようなときに必要なのかについて解説していきましょう。
建築確認申請が必要なケース
建築確認申請は、次のような行為をする場合に必要になります。
- 新築……新たに建物を建てる。
- 増築……: 既存の建物がある敷地に建て増しをする。
- 改築……建築基準法でいう「改築」は、いわゆるリフォームではありません。従前の用途、規模、構造と著しく異ならない建築物を建て直すことをいいます。現実には、ほとんど改築での申請はありません。
- 大規模の修繕……建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕です。
- 大規模の模様替……建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替です。
- 用途変更……建物の用途を変更する。
- 移転……既存の建物を別の場所に移築する。
建築確認申請が不要なケース
建築確認申請が必要とされた行為でも、建物の規模等によって申請が不要になることがあります。
たとえば、次のようなケースは建築確認申請が不要です。
- 床面積10平方メートル以下の増築(防火地域、�準防火地域内を除く)
- 小規模な修繕…… 屋根の葺き替え、外壁の塗り替え、内装材のリフォームなど
- 大規模の修繕・模様替で木造2階建て、200平方メートル以下のもの
- 工事現場事務所
「建築確認申請が不要」での注意点
建築確認申請が不要なケースでは、その一部だけを理解し、他の要件を無視していたために、結果として違反建築物として行政から指導を受けるケースが少なくありません。
どのような事情で間違いが起こるのか解説をしていきましょう。
10平方メートル以下でも建築確認が必要なことがある
床面積が10平方メートル以下の増築は、建築確認申請が不要です。しかし、これは「法22条地域」と呼ばれる、防火地域にも準防火地域にも指定されていない地域に限られます(建築基準法第6条第2項)。
市街地では広い範囲が準防火地域に指定されていることがあるので、建築予定地の防火規制をしっかり調べることが重要です。
火災が起こると危険なエリア(商業地や駅前など)で、建物の構造に厳しい制限がある。原則として耐火建築物(鉄筋コンクリート造など)とする必要がある。
防火地域ほど厳しくはないが、火災の延焼を防ぐために一定の耐火性能を持つ建物が求められる区域。木造建築も可能だが、外壁や軒裏に不燃材料を使うなどの制限がある。
よくある間違いとして、「増築」を見落としているケースがあります。新築の場合は、たとえ1平方メートルでも建築確認申請が必要です。新築とは、まったく建物のない敷地に建築することをいいます。
たとえば、自宅前の道路を挟んだ向こう側の空き地に子ども部屋を建てる際、同一所有者の土地でも建築基準法上は別敷地になります。この場合、空き地に建物を建てる形になり、新築に該当するため、建築確認申請が必要です。
また、自宅と同じ敷地に10平方メートル以下の増築をする場合、建築確認申請は不要ですが、自由に増築できるわけではありません。建ぺい率などの建築基準法の規制が適用されるため、規制に適合しない建物を建てることはできません。
つまり、建築確認申請が不要であっても、建築基準法の規定は守らなければならないことは覚えておきましょう。
▼関連記事:物置やガレージの設置に建築確認申請は必要?
大規模の修繕・模様替で違反建築になることがある
大規模の修繕・模様替は、木造2階建て、500平方メートル以下の住宅であれば建築確認申請は不要です。
大規模の修繕・模様替は、古い家屋の壁を取り外して、柱や梁の過半を取り替えるような工事をいいます。
一般的な木造住宅で、大規模の修繕・模様替に建築確認申請が不要なことは、大工などの工事施工者にはよく知られており、建築士に相談することなく工事を進めることがあります。
このケースでよくある間違いは、建築確認申請が不要だからといって、建築基準法が適用されないと思い込む人がいることです。実際には、大規模の修繕・模様替を行えば建築基準法が適用されます(建築基準法第3条第3項第3号)。
それまで既存不適格建築物として、存続を許されていた建物でも、大規模な修理や改装を始めると、現在の法律の基準を守る必要が出てくるのです。
そのため、接道義務、建ぺい率、防火規定に適合しない建物は、たちまち違反建築物になることがあります。
既存不適格建築物の修繕をする場合は「大規模」にならない範囲で工事を進めることが重要です。
プレハブでも建築確認申請が必要
工事現場でよくみかけるプレハブの工事現場事務所は、建築確認申請が不要です(建築基準法第85条)。
ただし、工事現場事務所というものは「工事現場」があって初めて成立するものです。
たとえ見た目が工事現場事務所の仕様であっても、敷地内あるいは至近距離に工事現場がなければ、工事現場事務所ではなく一般的な建築物です。この場合、建築確認申請が必要となります。
また、「工事現場事務所は建築確認申請不要」がいつの間にか「プレハブ建物であれば建築確認申請は不要」と誤解され、庭の片隅や屋上に工場生産のボックス型建物を子ども部屋として設置することがあります。
この場合、プレハブ建物は例外なく建築物なので、設置すると新築もしくは増築となり、建築確認申請が必要になります。たとえ10平方メートル以下であったとしても、防火地域や準防火地域であれば、建築確認申請が必要です。
建築確認申請を怠るとどうなる
家を建てる際には、建築確認申請が必要となるケースがほとんどです。近年、違反建築物の発生件数が大幅に減っていることから、無確認等の違反建築物は目に付きやすく、発覚する可能性が高くなっています。
もし、建築確認申請を怠り、無確認で建築を進めてしまうと、どのような問題が生じるのか解説をしていきま��しょう。
工事停止命令・インフラの停止
無確認で工事が進められていることが露呈し、行政の指導に従うことなく工事を進めると、行政機関(特定行政庁)から工事停止命令が出されます。
工事停止命令を無視して工事を進めた場合、行政機関は、電気、ガス、水道事業者に供給停止の協力を求めます。国の通達により、これらの事業者は、行政からの要請に応じて供給を停止します。
さらに悪質と判断された場合には、行政代執行により建物が解体されることがあります。
また、これらの命令を無視した場合、罰金や刑事罰が科せられる可能性もあるので注意が必要です(建築基準法第100条)。
住宅ローンを受けられない
ほとんどの金融機関では、建築確認済証がない建物の工事に対して融資を実行することはありません。
最終的に工事完了後に検査済証がない建物には、住宅ローンの融資は実行されません。
売却が困難になる
建築確認済証がない建物は、売却が困難になります。
近年では、建築確認済証がない建物はレアケースです。
買主は、建築確認済証がない建物に対して安全性や適法性に不安を感じるため、取引を敬遠する傾向があります。
建築確認申請の流れ
建築確認申請がどのような流れで進められるのか解説していきましょう。
建築確認申請手続の依頼
行政に申請する手続きは行政書士の独占業務です。ただし、建築に関する手続の代理は、建築士が行うことができるとされています(建築士法第21条)。
現実に、建築確認申請手続の代理は、ほとんど建築士が行っています。
建物の設計は建築士に依頼する際、建築確認申請手続きも合わせて依頼するのが一般的です。
この場合、依頼された建築士が自ら手続きを行うこともありますが、建築確認申請手続きを得意とする建築士が行うこともあります。
建築士は、建築主の要望を踏まえ設計図書を作成します。申請手続きを行う建築士は、その図面を叩き台とした添付図書を作成して、行政機関等に申請します。
「事前相談」は原則なし
建築確認申請には、原則として「事前相談」という過程はありません。事前相談は、主に許可申請で行われるもので、許可の見込みのない申請を防止する目的で行われます。
そのため、事前相談を通過していない案件は、許可申請の受付けを拒否されることがあります。
しかし、建築確認申請には、建築物の確認や審査を行う公務員の裁量権がないため、建築基準法に適合する申請をすれば、法定期間内に確認済証が確実に交付されます。そのため事前相談をすることなく、ダイレクトに申請をするのが一般的な流れです。
一部の行政機関(特定行政庁)や指定確認検査機関の中には、事前の相談に応じているところがありますが、一般的な質疑応答の範疇であり、必須の工程ではありません。
申請
必要書類が揃ったら、建築主事のいる行政機関(特定行政庁)または民間の指定確認検査機関に建築確認申請書を提出します。
行政か民間かの選択は自由です。近年は、指定確認検査機関が近くにある地域の場合、圧倒的に指定確認検査機関のシェアが高くなっています。
その�理由として、一般的に指定確認検査機関の方が行政よりも審査期間が短く、手数料が安価な傾向があります。
審査
提出された確認申請書類は、建築基準法等の規定に適合しているかが審査されます。
審査期間は、木造の2階建て住宅であれば7日です。特殊建築物や構造計算を伴う申請をする場合は、21日が目途になります。構造が複雑な物件だと、さらに日数を要します。
審査期間は法律で定められているので、いたずらに長引くことはありません。ただし、指摘された訂正事項が修正されるまでは、審査は終了しません。
審査では、主に次の項目がチェックされます。
- 敷地の要件……敷地の面積、道路との関係、用途地域などが、建築基準法等の規定に適合しているか。
- 建物の要件……建物の構造、防火設備、避難経路などが、建築基準法等の規定に適合しているか。
確認済証の交付
計画が建築基準法に適合していることが確認されると、確認済証が交付されます。確認済証が交付されるまでは、例外なく工事に着手することはできません。
行政機関(特定行政庁)に申請した場合、知事名・市長名で発行されると思われる方もいますが、建築確認申請に限っては、必ず建築主事名で交付されます。どれほど大きな案件の建築確認申請であっても市長名で交付されることはありません。
この点が、他の許可書や命令書と異なる、建築確認申請書の特異性です。
工事の着手
確認済証が交付されると、工事に着手することができます。工事現場には建築確認済である旨を示す表示板を設置する義務があります��(建築基準法第89条)。
表示板には、次の内容を記載します。
- 建築基準法による確認済みの旨
- 建築主の氏名または名称
- 設計者の氏名または名称
- 工事施工者の氏名または名称
- 工事監理者の氏名または名称
- 確認済証の番号
- 確認年月日
工事は、確認済証の内容に基づいて行う必要があります。工事中は、工事監理者である建築士が現場を監理し、工事が設計図どおりに進められているかを確認します。
中間検査
基礎工事や躯体工事など、工事の途中で中間検査が行われます。中間検査は、工事が建築確認申請に記載された内容どおりに進められていることを確認するためのものです。
工事が一定の工程まで進捗したら、建築主は中間検査の申請書を提出する義務があります。
木造住宅の場合、柱や梁の金物、筋交い等をチェックするので、中間検査に合格するまでは、内壁を貼ることはできません。
中間検査に合格すると、中間検査合格証が交付されます。
完了検査
工事が完了したら、建築主は4日以内に工事完了検査申請書を提出します。建築主事または指定確認検査機関は、通知書を受け取った日から 7日以内に完了検査を実施します(建築基準法第7条)。
完了検査は、完成した建物が建築基準法等の規定に適合しているかを確認するためのものです。
完了検査では、建築確認申請書に添付した図面と一致した建物が、実際に建っていることについてチェックが行われます。
検査済証の交付
完了検査に合格すると、検査済証が交付されます。
検査済証は、建物��が建築基準法等の規定に適合していることを証明する重要な書類です。
建築確認申請の費用
建築確認申請には審査手数料がかかります。手数料の額は、建築物の規模や用途、地域によって異なります。
建築確認申請に関わる費用として、他に次のような手数料が発生することがあります。
- 計画変更手数料……確認申請後に設計変更を行う場合にかかる費用です。
- 中間検査手数料……建築工事の途中で検査を受ける場合にかかる費用です。
- 完了検査手数料……建築工事完了後に検査を受ける場合にかかる費用です。
ここでは、建築確認申請の手数料について紹介します。
建築確認申請手数料の事例
建築確認申請手数料は、建築物の規模や用途、地域によって大きく異なります。大まかに分類をすると次のようになります。
特殊な構造計算(構造計算適合性審査)を要する案件は、別途追加手数料か発生します。
- 小規模住宅(100平方メートル以下)…… 5千円~1万5千円程度
- 中規模住宅(100〜1,000平方メートル)……2万円〜3万円程度
- 大規模住宅(1,000平方メートル以上)……5万円〜数十万円程度
いくつかの事例を挙げていきましょう。
東京都に申請した場合
- 床面積:150平方メートル
- 用途:専用住宅
- 構造:木造2階建て
この場合、東京都の建築確認申請手数料は、14,000円です。
大阪府に申請した場合
- 床面積:500平方メートル
- 用途:事務所
- 構造:鉄骨造3階建て
- 防火地域:防火地域
この場合、大阪府の建築確認申請手数料は、60,000円です。
指定確認検査機関に申請した場合
【A社】
- 木造2階建て住宅(延床面積150平方メートル)……約50,000円
- 鉄骨造3階建て事務所(延床面積520平方メートル)……約160,000円
【B社】
- 木造平屋建て店舗(延床面積80平方メートル)……約35,000円
- 鉄骨造2階建て共同住宅(延床面積300平方メートル)……約70,000円
【C社】
- 木造2階建て住宅(延床面積120平方メートル)……約40,000円
- 鉄骨造4階建て病院(延床面積1000平方メートル)……約220,000円
まとめ
建築確認申請は、基本的に建物を建てる前に行う必要がある手続きです。
建築確認申請による審査を受けることで、申請した建物が安全性を維持した建物であることが分かります。
建築確認申請書の提出先は、行政機関の他に民間の確認審査機関があります。近年では、民間への申請件数の方が大幅に多くなっています。
もし、建築確認申請を怠ったまま工事を進めると、違反建築物として行政機関から厳しい指導を受けるばかりでなく、刑事罰の対象となることがあります。
また、建築確認申請をしていない建築物に対して、金融機関が住宅ローンを実行することはありません。
建築に際しては、設計を依頼した建築士などに依頼して確実に建築確認申請を提出してください。