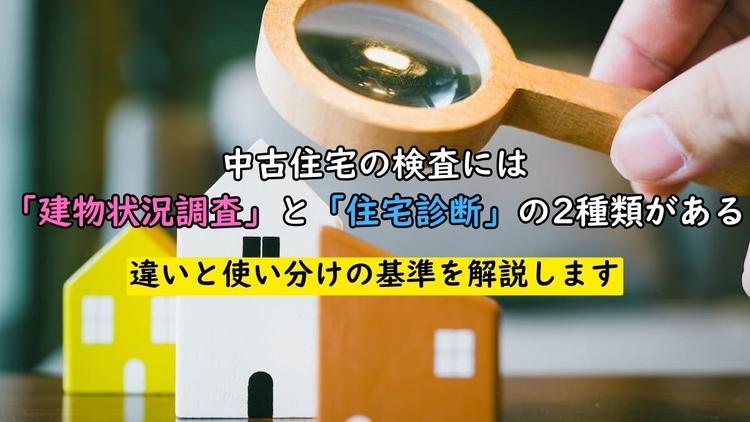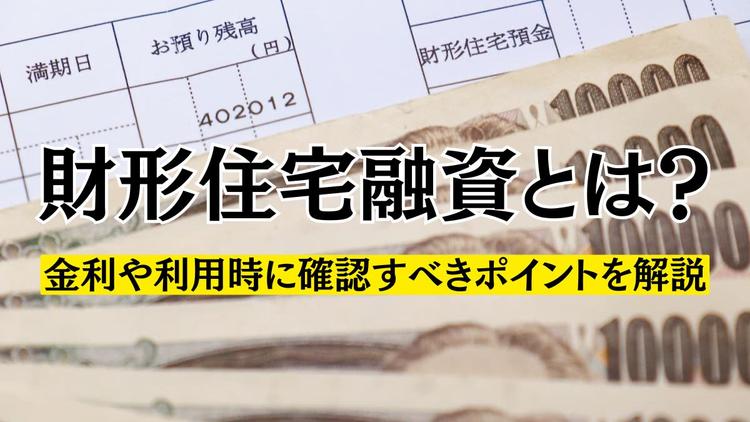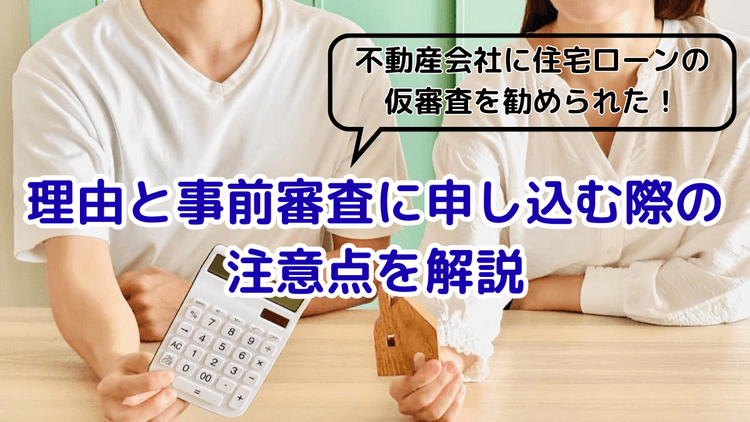耐震基準は、建物を地震から守るための規制です。大地震の被害を受けるごとに改正を重ねており、最新のものが「2000年の耐震基準」です。
この記事では、2000年の耐震基準にはどのような内容が盛り込まれているのかを明らかにするとともに、耐震基準の観点から住まい選びや売買時の注意点を解説します。
2000年の耐震基準改正までの経緯
耐震基準とは、地震に対して建物が安全を保てるよう建築基準法によって定められた規制です。
耐震基準は、大地震による被害を受けるごとに改正を繰り返してきました。最新の耐震基準である「2000年の耐震基準」まで、大きく次のような経緯で改正されています。
- 旧耐震基準(1950年以降)
- 新耐震基準(1981年以降)
- 2000年の耐震基準
時代ごとの耐震基準の内容を具体的に押えていきましょう。
旧耐震基準(1950年以降)
1923年(大正12年)に発生した関東大震災では、建築物に甚大な被害が生じました。その翌年に建築基準法の前身である市街地建築物法の基準が改正され、ここで初めて耐震計算の規定が取り入れられました。
そのうえで、耐震性強化のために、石造やれんが造の建築物の高さ制限、構造種別ごとの規定が設けられたのです。
1950年に施行された建築基準法においても、耐震基準については、「震度5強の地震が起きても建物が倒壊せず、修復が可能である」という市街地建築物法の理念が引き継がれました。
また、旧耐震基準の時代においても、何度か基準が見直されています。特に大きな改正としては、1968年に発生した十勝沖地震による被害を受けてのものです。
この地震では、鉄筋コンクリート造の建築物において、柱のせん断破壊による大きな被害が発生しました。
このため1971年に、鉄筋コンクリート造建築物の柱のせん断補強として帯筋の間隔を密にするという規定の強化が行われています。
新耐震基準(1981年以降)
耐震基準は、1978年の宮城県沖地震を契機に1981年に大きく改正されました。この改正が耐震基準の大きな節目となり、1980年以前は「旧耐震基準」、1981年以降は「新耐震基準」と呼ばれています。
この改正では、極めてまれに発生する大地震時において、建築物の倒壊を防止するための構造計算(二次設計)を柱とする「新耐震設計法」が導入され、さらに数多くの構造関係規定についても見直しが行われました。
この新耐震設計法により、震度6強~7程度の大地震でも建物が倒壊しないことが基準になり、中規模地震の規定も強化されるようになりました。
2000年の耐震基準(現行基準)
1995年に発生した阪神・淡路大震災では、建物も甚大な被害を受けました。その後の調査で明らかになったのは、新耐震設計法導入以降の建築物の被害は比較的軽微だったことです。一方で、多くの木造住宅が倒壊しています。
そのため、2000年には、木造建築物の接合部の規定などにより、新耐震基準をより強化する基準が設けられました。
合わせて、新耐震設計法導入前の既存建築物の耐震性の向上の重要性が認識され、耐震診断や耐震改修の促進のための法制度が新設されました。
2000年の耐震基準では何が改正されたのか
2000年の耐震基準は、1995年に発生した阪神・淡路大震災で多くの木造住宅が倒壊したことを受けて改正されました。木造住宅の耐震性を向上さ�せることを目的に、次のような内容が盛り込まれました。
- 地盤の耐力に応じた基礎の設計
- 柱を土台や梁に固定する接合部の金物の設定
- 耐力壁のバランスのよい配置
それぞれの項目においてどのような点が強化されたのか解説していきましょう。
地盤の耐力に応じた基礎の設計
2000年の耐震基準では、地盤の強度に応じて基礎を設計するよう求めています。
具体的には、建築基準法および「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」が2000年に改正されました。
これにより、建物を支える土台となる基礎を地盤に応じた形状にすることで、長期的に安定させることが求められるようになりました。
その結果、地盤が耐えられる重さを示す「地耐力」を調べる地盤調査の実施が事実上必須となっています。
不同沈下は、地盤の状況を把握せずに基礎工事が行われた結果により発生するため、建物を新築する際には、事前に地耐力を調べることが義務付けられました。
地盤調査の結果、地盤が軟弱であることが判明した場合には、地盤改良工事などが必要となります。そればかりでなく、施工者は引渡しから10年間に不同沈下が生じた場合、無償で修復する義務を負うことになりました。
柱を土台や梁に固定する接合部の金物の設定
1995年に発生した阪神・淡路大震災では、理論的には建物自体に十分な強度が確保されていながら、柱が梁や土台から抜けてしまったために崩壊した住宅が多数発生しました。
2000年耐震基準では、柱の抜けを防ぐために、木造住宅の柱を梁、土台、筋交いにしっかり固定できるよう専用の金物が指定されました。今では取り付けが義務付けられている「ホールダウン金物」が、住宅で一般的に使用されるようになったのは、この頃からです。
耐力壁のバランスのよい配置
耐力壁の量を増やし、接合部を強化するだけでは、建物全体の強度が偏り、地震時に建物がねじれて損傷しやすくなる点が課題とされました。
特に、リビングを南側に配置した場合、窓を多く設置したり広い空間を確保するため、南側の耐力壁が不足しがちです。その結果、耐力壁が北側に偏る構造になりやすく、建物全体がバランスを欠く状態になります。
こうした偏りが原因で、阪神・淡路大震災では、耐力壁の配置が偏った家が地震の揺れによってねじれて倒壊する事例が多く見られました。
このような問題を解決するために導入されたのが、「偏芯率」という指標です。
この値を0.3以下に抑えることで、耐力壁の配置が適切であるかを確認し、地震時のねじれ被害を軽減することが目的です。
偏芯率を考慮することで、単に耐力壁を増やすのではなく、建物全体の強度とバラ�ンスを保ちながら設計することが求められるようになりました。
住まい選びの注意点
安心して暮らせる家に住むには、新耐震基準の建物を選ぶことが重要です。特に木造の戸建て住宅であれば、2000年の耐震基準で建てられた物件が望ましいといえます。
ここでは、購入する物件について、耐震性能の観点から、どのような点に注意をすればいいのか解説をしていきましょう。
建築確認通知書と検査済証があるか
不動産会社で気になる物件を見つけた際は、まず建築確認通知書と検査済証があることを確認してください。
建築確認通知書とは、建築前に提出した建築確認申請書の内容が建築基準法に適合していることを建築主事が確認し、建築主へ通知する書面のことを言います。
工事が完成したら、建築確認通知書どおりに建物が施工されているかを建築主事(指定確認検査機関)から委任を受けた職員が検査をします。この検査に合格すると、検査済証が発行されます。
建築主(新築物件の買主)は、引渡しの際に建築確認通知書と検査済証を受取ります。この2つの書類が揃っていれば、建物が適法であることの証明となります。
建築基準法施行時から完了検査の受検義務は存在しましたが、過去には木造住宅を中心に完了検査の受検率が極端に低かった時代がありました。しかし、近年の住宅では融資条件などの理由から、検査済証を取得する率が飛躍的に上がっています。
検査済証が存在しない物件は、耐震性能に問題が含まれている可能性があるので、購入に際しては慎重な判断が求められます。
建築確認通知書の発行日で判別する
新耐震基準は、1981年6月1日に施行されました。建築確認通知書(1999年5月1日以降は確認済証)の発行日が1981年6月1日以降であれば、新耐震基準の建物です。
同様に、2000年6月1日以降に確認済証が交付された建物であれば、2000年の耐震基準による建物となります。
購入希望の物件がみつかった場合、まずその建物の建築確認通知書を手にして、交付日を確認することが重要です。
完成日は新耐震基準とは無関係
気をつけたいのは、2000年6月1日の直前に確認済証が交付された建物です。2000年の耐震基準により建てられた住宅は工事費が高く、また工事の手間もかかることから、この時期には従前の耐震基準で設計し、急いで申請した建物が多く存在しています。
ところが現在では、2000年の耐震基準で設計した建物の方が高く評価されます。そのため、物件の売り込みの際に営業担当者が「この建物は2000年6月1日以降に完成しているので、2000年の耐震基準です」と説�明をすることがあります。
しかし、2000年5月31日以前に確認済証が交付された住宅は、完成日に関係なく、それ以前の耐震基準で設計された物件なので、注意が必要です。
着工日も新耐震基準とは無関係
建築基準法は、工事を始めた時点の規定が適用されます。したがって、2000年6月1日以降に着工した建物は、2000年耐震基準で設計されていなければなりません。
その規定を逆手に取って、「建築確認通知書の発行日は2000年5月ですが、着工したのは6月になってからなので、この建物は新耐震基準の建物です」と売り込む営業担当者がいます。
もしその説明が事実に基づくものだとしたら、その建物は違反建築物ということになります。建築確認通知書が発行されていても、工事着手前に改正法が施行された場合、未着工の建築確認通知書は無効になるからです。この場合、改めて建築確認申請をする必要があります。
ただし、こうした大規模改正の施行日には、全国の行政機関は管轄内の未着工の工事現場をくまなくチェックするので、現実にはこうした事態はほぼ発生しません。
2000年の耐震基準は、確認済証の交付日が2000年6月1日以降であることが、何よりの証なのです。
売却時の注意点
自宅を売却する場合は、耐震基準に適合していることをアピールすることで、有利な条件での売却が実現します。具体的にどのように売り出せばいいのか解説をしていきましょう。
売却時は建築確認通知書と検査済証を提示する
家の売却では、旧耐震基準建物か新耐震基準建物かによって大きく評価が異なります。売却する家が、新耐�震基準建物であれば、有利な条件で売却することが可能です。仲介する不動産会社が金融機関に建築確認通知書と検査済証を提示することで、新耐震基準の建物として売り出すことができます。
これらの書類が見あたらない場合は、管轄の行政機関で交付済証明書を発行してもらえます。
旧耐震基準の家は耐震診断を受ける
家の耐震性能に不安がある場合は、耐震診断を依頼するという方法があります。
耐震診断は、「一般耐震技術認定者」の資格を取得した技術者が、旧耐震基準で設計された住宅の耐震性能を現在の耐震基準に照らし合わせて診断をします。これは、建築士事務所や地元の工務店で実施しています。
耐震診断にかかる費用は、依頼する会社、建物の構造、広さなどの要件により異なりますが、一般的に10万〜40万円程度かかります。助成や無料診断を受けられる制度を設けている自治体もあるので、確認してから依頼するのがおすすめです。
耐震基準適合証明書を取得する
新耐震基準に適合していなかった建物は、耐震診断の結果に基づき耐震リフォームを行うことで、新耐震基準に適合した建物になります。
耐震リフォーム工事後には建築士から「耐震基準適合証明書」を発行してもらえます。発行手数料は建築士にもよりますが、2万〜5万円程度です。この証明書によって、建物が現在の耐震基準に適合していることを第三者に証明することができます。
中古住宅の買主が住宅ローンを利用する場合、多くの金融機関は新耐震基準を満たしている物件であることを条件としています。また、住宅ローン控除や不動産取得税の減税措置��を受ける際にも、新耐震基準を満たしていることが必要条件とされています。
このような状況において、新耐震基準に適合していることを証明するのが「耐震基準適合証明書」です。
まとめ
耐震基準は、最新の耐震基準である2000年の耐震基準まで、大きく次のような経緯で改正されてきした。
- 旧耐震基準(1950年以降)
- 新耐震基準(1981年以降)
- 2000年の耐震基準
2000年の耐震基準は、1995年に発生した阪神・淡路大震災で多くの木造住宅が倒壊したことから、主に木造住宅の耐震性を向上させることを目的として、次のような内容が盛り込まれました。
- 地盤の耐力に応じた基礎の設計
- 柱を土台や梁に固定する接合部の金物の設定
- 耐力壁のバランスのよい配置
このため木造住宅の購入に際しては、2000年の耐震基準の規定に適合した住宅を選択することが重要なポイントになります。
安心で安全な住まいを手に入れるためにも、耐震基準の内容を正しく理解し、適切な選択を心がけましょう。