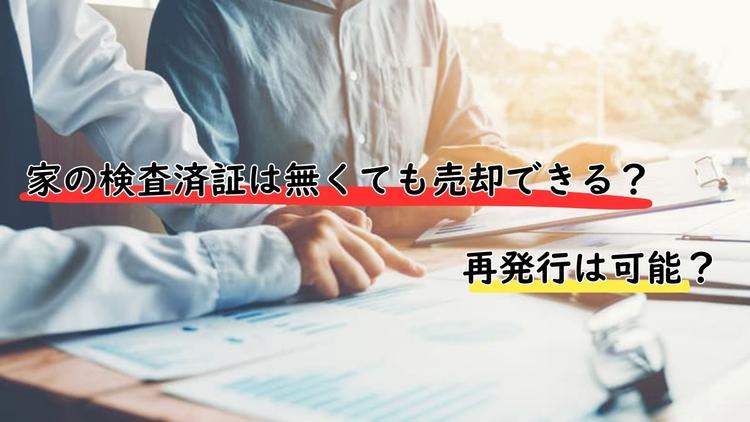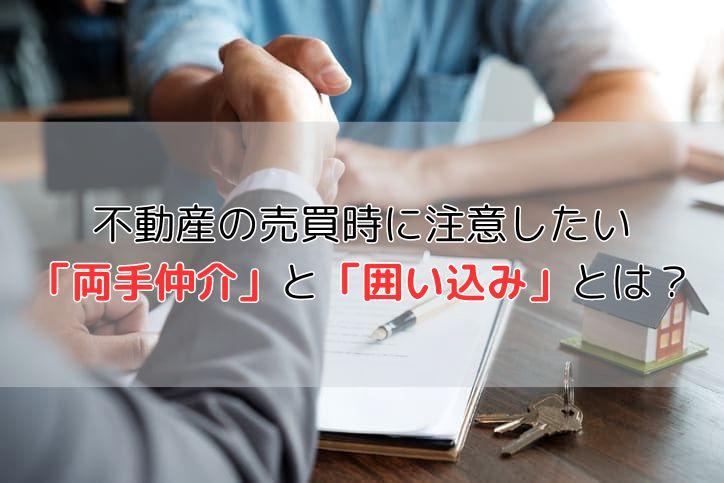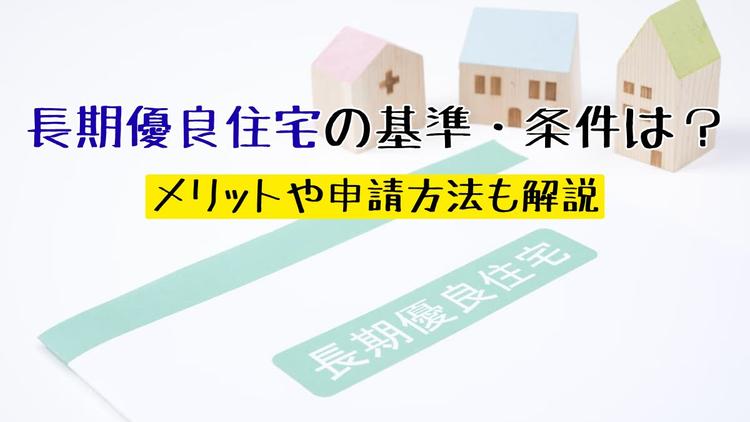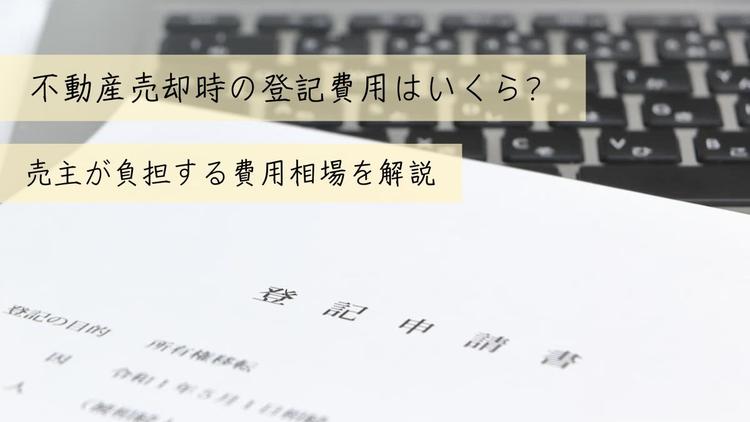家の売却に際して不動産会社に相談をすると、必ず検査済証の有無を問われます。検査済証の有る物件と無い物件では、購入希望者の反応が大きく異なるからです。それだけ売却活動に大きな影響を及ぼす検査済証ですが、もし無かったら、はたして家はスムーズに売却できるのでしょうか。
この記事では、検査済証の再発行の可否を明らかにしたうえで、検査済証の無い物件はどのように売却をすればいいのかについて解説します。
検査済証って何?
家の売却において、重要な役割を果たす「検査済証」ですが、まず、この検査済証とはどういうものなのかについて説明をしていきましょう。
建築確認申請書だけでは適法の証明にならない
建物を建てる際には、工事着手前に建築確認申請をします。しかし、この建築確認申請書だけでは、建築物が適法であることの証明にはなりません。建築確認申請は、これから建てようとする建物の内容を事前に提示したものであり、実際にその図面どおり建てられた保証はどこにもないからです。
建物が完成したら完了検査申請をする
建築物が完成したら、建築主は4日以内に完了検査申請書を提出しなければいけないと定められています1。この申請に基づき、地方自治体や指定確認検査機関が実施するのが完了検査です。
完了検査に合格すれば検査済が交付される
完了検査では、敷地形状や建物の仕様が建築確認申請書と合致しているか否かを検査します。この検査に合格して交付されるのが検査済証です。
これにより、検査済証が存在する建築物は、適法な建築物として取り扱われます。
なぜ家の売却で検査済証が重要なのか
建物が完成した際に交付される検査済証ですが、家を売却する際も仲介の不動産会社から検査済証の��有無を必ず問われます。なぜ家を売却するときも検査済証が必要なのか、その理由を解説していきましょう。
違反建築物は住宅ローンが使えない
家の購入希望者は、住宅ローンを利用するのが一般的です。しかし、現在ほとんどの銀行が違法な建物には住宅ローンを融資してくれません。融資をしてしまうと「違法建築物を延命させた」というコンプライアンス上の問題が発生するからです。
このため、住宅ローン融資の相談をすれば、適法な建築物であることの証しとして検査済証の提出を必ず求められます。
違反の責任は買主にも及ぶ
かつては部屋数が多いとの理由で建物を購入すると、実は建ぺい率や容積率をオーバーした違反建築物だったということがありました。
この場合、違反建築物を建てたのが前所有者であっても、違反の責任は新しい所有者にも及びます。事情を知らずに購入しただけなのに、厳しい行政指導や是正命令を受けて、一部解体工事をするという事態もあり得たのです。
このようなトラブルに巻き込まれないために、現在ではほとんどの買主が、建物の適合性を確認したうえで購入を決断します。したがって、検査済証のない建物は、どうしても敬遠される傾向があります。
増築や用途変更ができない
建物の購入後に増築や用途変更をしたいと考えていても、既存建物の適法性が証明できない場合は、建築確認申請を受け付けてもらえません。
検査済証のない家は、将来の計画が実現できないという理由で、購入を敬遠されてしまうことがあります。

検査済証が存在しない家はどう売却すればいいのか
検査済証のない家を売却しようとすれば、いろいろな障害があって、なかなか買主が現れないということは分かりました。それでは、検査済証がない家をスムーズに売却するにはどうすればいいでしょうか。ここでは、売却しようとする家に検査済証がないときの対処法について解説します。
中古住宅は検査済証がない物件が多い
現在、指定確認検査機関が扱う物件の完了検査受験率は90%を超えています。しかし、かつては検査済証に対する認識が浅かったために、住宅に限れば完了検査を受検する物件の方が少ないくらいでした。
国土交通省の資料によると、平成10年の建物全般の受験率は38%でした。それ以前に遡ると20%以下まで下がってしまいます2。このため、築20年を超える住宅では検査済証の無い物件が多いです。
検査済証の紛失は対策がある
建物を新築した際に検査済証を取得したはずだが、書類が紛失して資料として提示できないということがあります。あるいは、中古住宅を購入した際に、検査済証を取得していると聞いていたが、肝心の検査済証の引継ぎがなかったということもあります。
実際に検査済証を取得していながら、その書類を紛失した場合は、市役所等で「台帳記載事項証明書」を取得することで、検査済証が交付された建物である証明とすることができます。
既存不適格建物は検査済証がなくても適法
建築基準法は、昭和25年に施行された法律です。また現在に至るまで数多くの法改正を行っています。また、用途地域、建ぺい率、容積率は、1970年代以降に指定されたものです。
法律の施行や都市計画制限指定以前から存在していたものは、施行後の基準に適合しなくても、その部分の基準は適用しないとして建築基準法に定められています。
こうした建築物は、「既存不適格建築物」と呼ばれていますが、適法な建築物ですから、検査済証が存在していなくても、法律上は、違反建築物とは、まったく違った扱いになります。
「12条5項報告」によって適法性を証明する
適法な建物であるが完了検査を受検していない物件や既存不適格建築物は、「12条5項報告」を役所に提出することで、検査済証と同等の証明にすることができます。
次に建築基準法第12条第5項の条文(抜粋)を示します。
特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途、建築材料若しくは建築設備その他の建築物の部分、建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況又は建築物の敷地、構造若しくは建築設備に関する調査の状況に関する報告を求めることができる。
本来は、建物の適法性に疑義が生じたときに、建築主に対して報告を求める権限の根拠法令として機能していましたが、1999年の改正建築基準法の施行以後は、建築確認申請が民間の指定確認検査機関でも取り扱われるようになりました。
検査済証のない建物の増築などを処理するための方策として、この条文による報告書を活用するようになったのです。
12条5項報告の提出先は、建築主事がいる市役所です。建築主事は概ね人口10万人以上の市に配属されていますが、建築主事のいない市及び町村は、都道府県庁で受け付けます。
12条5項報告書の添付書類
12条5項報告には、次の書類を添付します。
- 12条5項報告書……建築主が申請者になります。専門的な知識を要するため、建築士が代理人になるのが一般的です。
- 既存不適格調書……法施行以前に工事に着手していたために、現行法規に適合していない部分を記載します。
- 現況の調査書……建物の現況を報告します。主要部分は写真を添付します。特に問題になるのは、構造部分です。状況によっては、壁や床を剥がしたうえで現況を調査して撮影する必要があります。
- 確認を受けた時の確認申請図書……申請書、配置図、平面図を提出します。当時の図面が紛失や破損している場合は、復元した図面を添付します。木造住宅の平面図においては、筋交い等の位置が重要なポイントになります。
- 委任状……申請者と代理者が異なる場合に添付します。
- 現地の付近見取り図
- その他、建築主事が求める書類
この報告書を正本と副本の2部提出し、書類審査の結果支障がなければ、市役所の受領印が押印された副本が返却されます。
検査済証と同等の効力を有する
12条5項報告は、増築や用途変更の建築確認申請をする際に、この副本を添付することで、検査済証がなくても受付可能とするのが本来の目的です。
このため12条5項報告をもって銀行が住宅ローンを融資してくれるのかという点については、銀行の判断次第です。
多くの場合、銀行の担当者が当該市役所に問い合わせをして、書類の内容を理解したうえで融資を決定するという流れになります。
民間のガイドライン調査機関の活用
国土交通省が示した「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」に基づく調査によって、適合性を証明する方法があります。
これは国土交通省に届出をした「ガイドライン調査機関」の調査によって建築物を調査して、既存不適格建築物であるが違反建築物でないことを明らかにするものです。
ただし民間会社によって運営される方式であり、増築や用途変更の建築確認申請を行うことを前提としています。したがって、法の適合性を示す役割を果たすものの、検査済証と同等の証明としての効果を果たすものではありません。
検査済証がない場合は買取専門の会社に相談を
検査済証のない家は、住宅ローンを融資してもらえないために売却が困難であることは明らかです。もし12条5項報告などによっても、適合性が証明できない場合は、買取専門の不動産会社に相談をしてみてはいかがでしょうか。
買取専門の不動産会社は、さまざまな物件を再生させるためのノウハウを有していますから、検査済証の無い物件にも資産価値を見出します。このため、思ったよりも高値で買い取ってもらえる可能性があるのです。
仲介による売却が困難だと感じたら、ぜひ買取専門の不動産会社に相談してみてください。
まとめ
検査済証のない物件は、単なる紛失が理由であれば、市役所等で証明書を取得することで同等の効力を発揮することができます。
しかし、完了検査を受検していない物件は、12条5項報告をすることによって適法性を証明する方法が最も現実的です。本来、増築や用途変更の建築確認申請ができない場合の救済措置として活用している制度ですが、受領印が押された報告書の副本が返却されることで、当該物件が建築基準法に適合していることが証明されます。
ただし、専門的な知識を要するため、建築士に依頼しないと作成は困難です。報告書提出の手数料は不要ですが、書類作成の報酬が発生します。
これらの手立てを講じることが困難な場合は、買取専門の不動産会社に買い取ってもらうという方法がありますから、選択肢のひとつに加えてみてはいかかでしょうか。