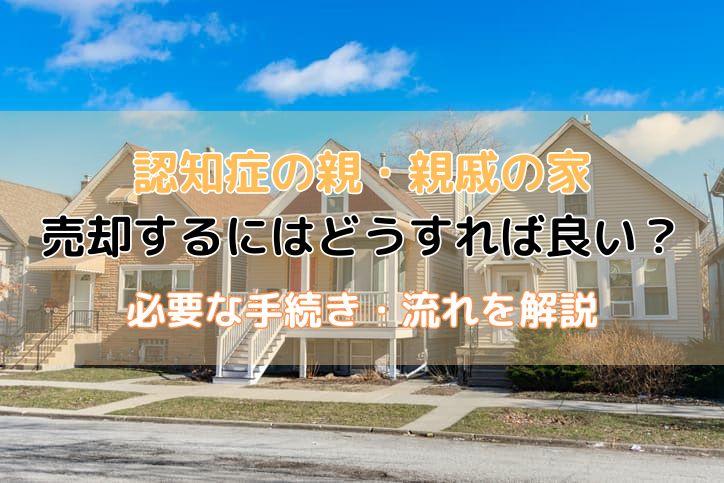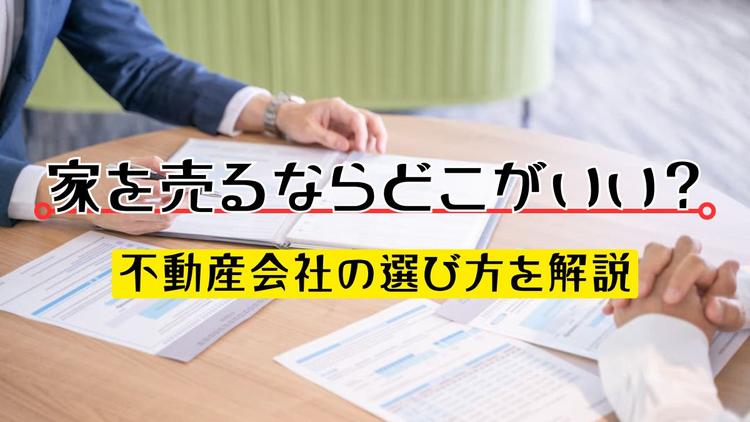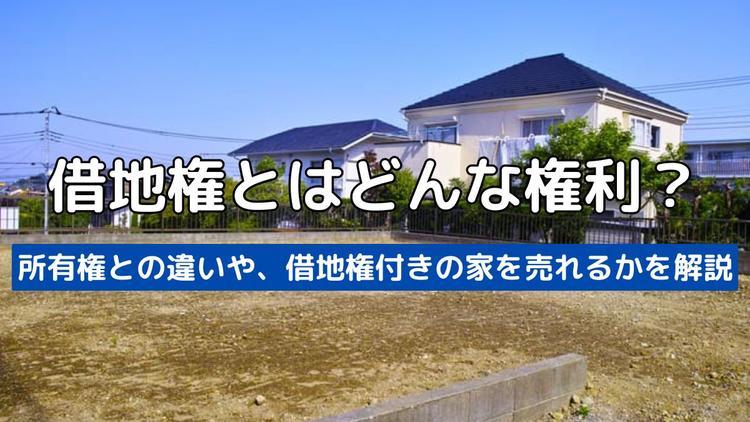不動産を売却する際、所有者本人が売却の意思を示すことが法律上求められます。しかし、もし売却を検討している実家や親族の家の所有者が認知症を患い、意思能力を失っていた場合、どうすればよいのでしょうか?
認知症の親や親族の家を売却するには、原則として 成年後見人を立てることが必須となります。成年後見人の選任には家庭裁判所の手続きを経る必要があり、すぐに売却できるわけではありません。
この記事では、成年後見制度を利用して不動産を売却する方法 を解説し、具体的な手続きの流れや注意点を詳しく説明します。
認知症の親の家を売却するために、まず何をすべきか確認していきましょう。
不動産を売却できるのは所有者本人のみ
不動産を売却できるのは、所有者本人のみです。不動産の売却においては、所有者本人の意思が非常に重要視されます。売却に際して、手続き自体は代理人に委任することができますが、最終的には司法書士が所有者本人に売却の意思を確認します。このとき意思が確認できない状態だと売買契約は成立しません。
たとえば、重い病で長期間入院していても、司法書士との面談で本人が不動産を売却したい意思をはっきりと示せば、契約は成立します。しかし反対に、自力で司法書士事務所に赴き、言語明瞭に会話ができたとしても、意思能力がないと判断されれば契約は成立しません。
子どもが立ち会っても売却できない
それでは、所有者の子どもが立ち会って契約を行ったとしたらどうなるでしょうか。この場合も、最終的に司法書士が直接所有者本人に売却の意思を確認するので、意思能力がないと判断されれば、たとえ子どもが売却したいと要望しても、売却は認められません。
認知症患者の財産は「成年後見人」に保護してもらう
認知症になれば、不動産ばかりでなく、その他の財産を管理することが困難になります。本人に不利益な契約をしないように、判断能力に欠ける人を保護する役割を果たすのが「成年後見人」です。
不動産の売却においても、重要な役割を担う成年後見人とはどのような制度なのかを見ていきましょう。
成年後見人の役割は3段階ある
成年後見人は、対象となる人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3段階に分類されます。
このうち「後見」は、「判断能力が欠けているのが通常の状態」の人が対象になります。後見の対象になった場合は、契約などの法律行為は成年後見人の同意が必要になり、所有者本人が契約をしても無効になります。
また民法第9条で、「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない」とされており、本人による法律行為を取り消すことができる場合があります。
たとえば、成年後見人から同意を得ていることを前提に、成年被後見人である本人が契約を進めたとしても、成年後見人からの契約取り消しの申し立てがあれば、契約は白紙に戻ることになります。
それだけ成年後見人制度は、成年被後見人を手厚く守る制度だということです。
家庭裁判所に成年後見人選任の申し出を行う
成年後見人を選任するためには、まず家庭裁判所に申し立てを行います。申し立てが行えるのは、「本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など」です。
申立書には、成年後見人の候補者が記載できますが、必ずその候補者の中から選ばれるわけではありません。状況によっては、弁護士、司法書士、行政書士などの専門職の人が選任されることがあります。
実際に現在は、成年後見人に選任されるのは、親族よりも専門職の方が多くなっています。
また親族が成年後見人に選ばれた場合であっても、家庭裁判所が必要と認めれば「後見監督人」を選任して、後見人に対する監督事務を行うことがあります。後見監督人に選ばれるのは、弁護士や司法書士などの専門職です。
後見監督人が選任されると、成年後見人は、遂行した職務内容を定期的に後見監督人に報告する義務が課せられます。
成年後見人が家を売却できる条件
親や親戚が認知症になったとしても、成年後継人を選任することで、不動産を売却することが可能になります。しかし、いくら親族の要望があったとしても、無条件で不動産が売却できるわけではありません。
どのような条件が整えば不動産を売却できるのか解説していきます。
本人の利益にならないと売却できない
親が住む家を売却する理由として、単に空き家を現金化したいという理由だけでは売却することはできません。本人の利益に繋がらないことには、成年後見人は同意できないからです。
たとえば、介護施設に入居するための費用を捻出するという理由であれば、本人の利益になるので、認められる可能性は高いでしょう。また空き家を放置しておくことで、膨大な管理費用が必要になるという事情も正当な理由となり得ます。
▼関連記事:親や親族が認知症になったけど施設に入居するお金がない!資金確保の手段や補助金について解説
家庭裁判所の許可が必要
所有者本人が住んでいた居住用不動産は、本人にとって重要な財産であるため、売却に際しては、家庭裁判所の許可が必要になります。もし家庭裁判所の許可なく売却した場合は、契約が無効になるので注意が必要です。
裁判所に許可を求める場合は、「居住用不動産処分許可申立書」を提出します。裁判所では、許可を申し立てる理由として、次のような事例を示しています。
- 親族に引取り扶養されることとなったので,居住用不動産が不要になった。
- 施設に入所することとなったので,居住�用不動産が不要になった。
- 施設入所資金の捻出のために,処分が必要になった。
- 医療費,生活費等の捻出のために,処分が必要になった。
- 建物が老朽化し,維持していると経費がかさむ。
この他の理由の場合、本人の利益にならないと判断されれば、許可を受けることができません。
成年後見制度を開始する際の注意点
親族が認知症になった場合、成年後見人を選任することで、法律行為が可能になります。しかし、その一方で、成年後見人を選任したことによるデメリットもあります。
この点をしっかり把握しておかないと、不動産の売却以外で頭を悩ませることになります。どのようなことに注意しておかないといけないのか解説をしていきましょう。
成年後見制度を開始したらやめられない
不動産の売却を目的にして成年後見人を選任した場合であっても、売却後に制度の利用を止めることはできません。制度上は、判断能力が回復したと認められればやめることができますが、現在の医学では、認知症が回復する事例はほぼないと考えられます。
生前贈与ができない
成年後見制度の目的は本人の利益を守ることです。生前贈与によって本人の財産を減らすことは、利益にならないと考えるのが一般的であるため、生前贈与は認められません。
資格を失う
成年後見開始の審判を受けた人は、医師、税理士等の資格を失います。また株式会社の役員や公務員であっても地位を失うことになります。
成年後見人は利益相反行為ができない
利益相反行為とは一方の利益になることが同時に別の一方の不利益に繋がる行為です。
成年後見人には、利益相反行為は認められません。
たとえば、一人娘である長女が母親の成年後見人になっている場合で考えてみましょう。
父親が死亡すれば、相続人は長女と母親です。相続が円満に解決するかどうかは別にして、立場上は利益が対立する立場になります。一方で長女は母親の利益を守る成年後見人でもあります。
こうした立場が利益相反行為になる場合は、どちらか一方を放棄する必要があります。
このため、状況によっては相続を放棄せざるを得ないことになります。あるいは成年後見人を一時的に放棄したいのであれば、家庭裁判所に特別代理人の専任を申し立てて、特別代理人を選任してもらうという方法も選択可能です。
また後見監督人がいる場合であれば、遺産分割に関しては後見監督人に成年後見人の役割を代理してもらうことができます。
報酬が発生する
成年後見人が選任されると報酬が発生します。親族が成年後見人の場合、無償で行うケースもありますが、基本的に本人の財産から報酬を支払うことになります。
報酬額は、申し立てがあれば裁判所で決定されます。裁判所が示す目安としては、管理財産額が5,000万円以下の場合は、月額3~4万円、管理財産が5,000万円を超える場合は、月額5万円~6万円としています。この他特別困難な事情があれば、50%の範囲内で報酬が加算されることがあります。
認知症の親が不動産を売却するまでの手続きと流れ
親や親戚が認知症になった場合に、不動産を売却はどのように進めればいいのか、手続きの方法とその流れを追っていきましょう。
成年後見開始の審判の申し立てる
成年後見人を選任する必要性が生じた場合、本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長などが、本人の所在地を管轄する家庭裁判所に「成年後見開始」の審判を申し立てます。
審理開始
申し立てを受理した後に家庭裁判所によって審理が開始されます。調査官が本人、申立人、後見人候補者に対して事情を聴取します。
また医師による鑑定が必要と判断した場合、依頼を受けた医師が本人の意思能力を鑑定します。
成年後見の開始
審理を経て成年後見人が選定され、成年後見が開始されます。鑑定手続きや成年後見人の候補者の適格性の調査、関係者の陳述聴取などで時間を要するために、申し立てから成年後見の開始までの期間は約4カ月を要します。
不動産会社と媒介契約を結ぶ
売却を依頼するために、成年後見人が不動産会社と媒介契約を結びます。早期に売却をするために相場よりも安い金額での売り出しを望んでも、極端に低い額での売却は本人の利益に反するために認められません。
売却活動をする
売却活動は、一般の売却と同じなので、購入希望者による内覧も行われます。認知症が進行していた場合、室内の整理整頓がおざなりになっていることがあります。売却をスムーズに行うためにも、室内の破損部分の補修や整理整頓を実施することが重要です。
家庭裁判所の許可を受ける
不動産の売却に際しては、家庭裁判所の許可が必要になるため、買主が決まった段階で「居住用不動産処分許可申立書」を提出します。この際、次の書類を添付します。
- 不動産の全部事項証明書
- 不動産売買契約書の案
- 処分する不動産の評価証明書
- 不動産業者作成の査定書
「不動産売買契約書の案」は、実印を捺印すれば契約が成立する状態のものを提出します。このため、売却金額や買主の住所・氏名も正確に記載する必要があります。
買主と売買契約を結ぶ
家庭裁判所の許可が下りれば、買主と成年後見人が不動産会社などに集まり、正式に売買契約を結びます。
なお諸事情によって、家庭裁判所の許可前に正式契約を結びたいのであれば、契約書に「家庭裁判所の許可が受けられなかった場合には、買主は不動産を購入する契約を解除して、契約を白紙に戻すことができる」という特約を盛り込んだうえで契約をします。
売買代金の清算~所有権移転登記
売買代金の清算は、金融機関などに買主、成年後見人、司法書士が集まって行われるのが一般的です。
買主から成年後見人が売買代金の残金を受取り、物件の引き渡しをします。同日に司法書士が法務局で所有権移転登記の手続きを行います。
任意後見制度という選択肢もある
ここまで紹介をしてきた成年後見制度は、いわゆる法定後見制度と呼ばれるものです。本人が既に認知症を発症している場合に後見人を選任しようとすれば、この法定後見制度しか選択肢はありません。
しかし、本人にまだ十分な判断能力があるのであれば、任意後見制度という選択肢もあります。
これは予め自分が選んだ人物に、財産管理に関する事務の代理権を与えられるものです。
代理権を与える契約を公証人が作成した公正証書で結んでおくことで、将来自分自身の判断能力が低下した際に、任意後見人として契約の代理行為が行えることになります。
法定後見制度の場合、誰が成年後見人になるかは裁判所の判断に委ねることになりますが、任意後見制度は、自分の意思で成年後見人を選択可能です。
そのため、所有する不動産の売却を信頼のできる人に任せられるという安心感があります。
まとめ
親や親戚が認知症になった場合、それまで住んでいた家を売却しようとすれば、成年後見制度が非常に有効な制度であることを説明してきました。
しかし、成年後見人は本人の利益になる場合のみ同意します。さらに自宅の売却となると家庭裁判所の許可も必要になります。
このために、単に家を売却して現金化したいというだけでは、家の売却は認められません。認知症の親や親戚の家を売却するにあたっては、なぜ売却が本人の利益になるのかを明確にすることが非常に重要なのです。