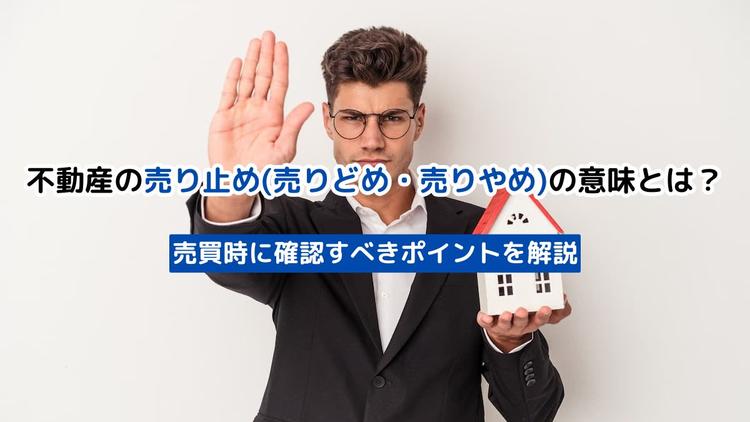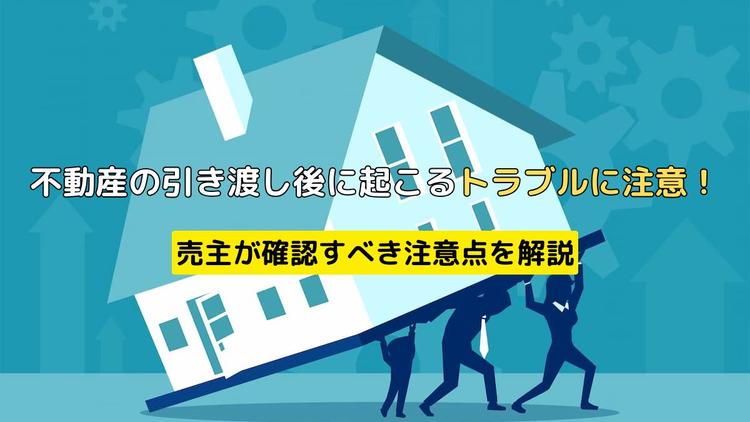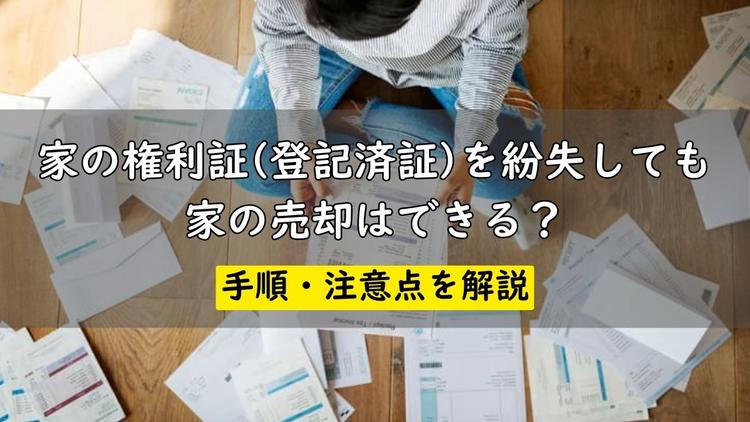不動産を贈与すると、その価値に応じて、贈与を受けた側が税金を納める必要があります。贈与税は税率が高く設定されているため、注意が必要です。
ところで、不動産を売却したときにも贈与税がかかるケースがあることをご存知でしょうか。
本記事では、贈与税について基本的な内容をお伝えするとともに、不動産の売却時、どのようなケースで贈与税がかかってしまう可能性があるか、さらには相続に備えて生前贈与を行うメリット・デメリットをお伝えしていきます。
贈与税とは?
そもそも贈与税とはどのような税金なのでしょうか?
贈与とは、「何らかの財産を無償で第三者に提供する行為」のことで、贈与した財産の価値に応じて、贈与を受けた側が納める必要があるのが贈与税です。
以下、贈与税の基本的な仕組みについて見ていきましょう。
暦年課税と相続時精算課税
贈与税の課税の仕組みには暦年課税と相続時精算課税の2つがあります。
暦年課税とは、「毎年110万円の基礎控除枠」があり、1年間で贈与した額の総額が110万円を超えると、その資産価値に応じて贈与税が課されることになります。
一方、相続時精算課税とは、直系尊属であるなど一定の要件を満たした人との間で選べる制度で、一度選択すると、それ以降2,500万円まで非課税となり、2,500万円を超えた分について一律20%の税率が課されます。
なお、相続時精算課税で非課税となった分は相続税の計算時に、相続財産に合算されることになります。
相続税の基礎控除枠は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と定められています。
相続時精算課税は、資産額の合計がその額以下の場合に、生前にまとまった額の資産を贈与したい場合に有効です。
他には、「贈与時の時価」を元に課税されることになるため、将来的に価値が上がる可能性が高い資産の相続の場合にお得に利用できます。
| 暦年課税 | 相続時精算課税 | |
| 基礎控除 | 毎年110万円 | 選択した年以降2,500万円まで |
| 税率 | 累進課税 | 一律20% |
| その他 | – | 相続時に合算して計算 |
暦年課税の税率
暦年課税の税率は贈与した財産の価格が高ければ高い程税率の高くなる累進課税となっています。
また、直系尊属から18歳以上の子や孫に贈与する場合は特例税率、それ以外の税率は一般税率となり、その税率は以下のようになっています。
一般税率
| 基礎控除後の課税価格 | 税 率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | ‐ |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
例えば、兄弟から500万円の贈与を受けたようなケースでは、500万円-110万円×20%-25万円=53万円が贈与税として課されます。
特例税率
| 基礎控除後の課税価格 | 税 率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | ‐ |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 25万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 125万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 175万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 250万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 400万円 |
例えば、25歳の子が父親から500万円の贈与を受けたケースで納める必要のある贈与税は、500万円-110万円×10%=39万円となります。
不動産の売却時に贈与税がかかることがある?
贈与税は第三者に無償で財産を提供したときに課される税金ですが、以下のようなケースでは、不動産を売却したときに贈与税がかかることもあります。
- 親族間取引
- 法人間取引
不動産を売却しただだけなのに贈与税がかかるとは、どういうことなのでしょうか?
詳しく見てみましょう。
親族間取引
親族間取引とは親子や兄弟など親族の間で不動産を売買する行為のことです。
例えば、親から子に土地を譲るような場合、贈与してしまうと贈与税がかかるため、本来は1,000万円する土地を100万円で売却することがあります。
上記のようなケースでは、売買契約したのにも関わらず、実際の相場と売買価格その差額(上記でいえば900万円)に対して贈与税が課されます。
もちろん、親族間であっても適性な価格で取引されていれば、贈与税は発生しません。親族間の取引は税務署から特にマークされているため、親族間取引こそ適正な価格で売買契約を結ぶべきなのです。
関係会社間取引や代表者と法人の取引
2つ目は関係会社間取引や代表者と法人の取引です。
関係会社間取引や代表者と法人の取引も、親族間取引と同じように、適性価格で売買していれば問題ありませんが、実際の相場と売買価格との間に差額がある場合には、その差額に対して贈与税が課されることになります。
なお、法人の場合は贈与税ではなく法人税が課されます。親族間取引と同じように、関係会社間取引や代表者と法人の取引も税務署からマークされているので、特に気をつけて取引する必要があるといえるでしょう。
低額譲渡に注意
上記でお伝えした「親族間取引」や「関係会社間取引」、「代表者と法人間取引」のいずれにおいても相場よりも安い価格で売買する「低額譲渡」であることが問題となります。税�務署は、不動産を売買したことやその額を登記簿謄本や確定申告で把握しています。
仮に、不動産を低額譲渡したものの、そのことを確定申告しなかった場合には、「登記簿謄本で所有者が移転しているのに確定申告されていない」となり、税務調査が入ることになります。
再三お伝えしている通り、特に親族間取引等は低額譲渡が起こりやすいため、より慎重に取り組むようにしましょう。
必要に応じて税理士など専門家のアドバイスを受けることも大切です。
▼関連記事:土地などの不動産を評価額より安く売ることはできる?
贈与税をできるだけ安く抑えるには?
財産を贈与すると贈与税が課されることになりますが、これを安く抑える方法はあるのでしょうか?
以下、贈与税をできるだけ安く抑える代表的な方法を見ていきましょう。
毎年110万円ずつ贈与する
まずは、暦年課税の場合に設けられる毎年110万円の基礎控除枠を利用して贈与税を安く抑える方法です。
例えば、1,000万円の財産を贈与するのであれば、110万円ずつ10年かけて贈与していけば基礎控除枠内で済ませることができます。
不動産を贈与するのであれば、共有持分を少しずつ贈与していくか、110万円ずつ現金を贈与し、最終的に売買契約を結ぶ(例えば、1,000万円の土地を贈与するのであれば、10年間かけて1,000万円の現金を贈与し、10年後に1,000万円の売買契約を結ぶ)という方法が考えられるでしょう。
ただし、毎年同額の贈与をしていると税務署に「定期贈与」とみなされる可能性があります。
定期贈与とみなされると後から贈与税が課される可能性があるため、注意が必要です。
このため、以下のように工夫する必要があります。
- 毎回贈与契約書を作成する
- 毎回の贈与額を変える
- 毎回の贈与時期を変える
税務署の動向など状況により異なるため、税理士など専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
相続税精算課税制度
また、冒頭でご紹介した相続税精算課税制度を活用することで贈与税を安く抑えることができることがあります。相続時精算課税制度は、一度選択すると、その贈与者との間で2,500万円まで非課税となる制度です。
相続時精算課税制度で非課税となった財産は、相続時に相続財産と合算して計算されることになりますが、相続財産が相続税の基礎控除額である「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を大きく超えないようであればお得に活用しやすい制度です。
なお、相続時精算課税制度は「贈与をした年の1月1日において60歳以上の直系尊属から、18歳以上の直系卑属である推定相続人への贈与」において適用を受けることができます。
例えば、2,000万円ほどの価値を持つ実家と現金1,000万円、1,000万円の土地を持つ方が、1,000万円の土地を子どもに贈与した場合で見てみましょう。
暦年課税だと基礎控除額を差し引いた890万円に対して贈与税が課されてしまいますが、相続時精算課税制度の適用を受けることで非課税とすることができます。
また、相続時精算課税制度で贈与した財産は、相続時に相続財産として計算する必要があります。
しかし、上記のケースで法定相続人が妻と子1人の場合は、相続税の基礎控除額が3,000万円+600万円×2人=4,200万円となり、相続税も非課税となるため問題がありません。
贈与税の配偶者特例
婚姻期間が20年以上の妻に、マイホームやマイホームの購入資金を贈与する場合、2,000万円まで非課税にできる「贈与税の配偶者特例」という制度があります。
この制度を利用すると、暦年課税の場合で2,110万円まで、相続時精算課税制度で4,500万円まで贈与税を非課税とできます。
住宅取得等資金の贈与の特例
18歳(贈与を受けた年の1月1日時点で)以上の方が直系尊属(父母や祖父母など)からマイホームの取得のための金銭について贈与を受ける場合、一定額について非課税とできる制度が住宅取得等資金の贈与の特例です。
贈与を受けた人ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
なお、この制度は定期的に適用される住宅の条件や、非課税枠の見直しが行われているため、自身が資金提供を受けたタイミングでの条件を確認しておくようにしましょう。
令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下「非課税の特例」といいます。)。
なお、住宅取得等資金の特例についても暦年課税や相続時精算課税制度の基礎控除額と合わせて利用することができます。
相続より生前贈与を選ぶメリット・デメリット
生前贈与とは、生存している間に贈与していることを指します。生前贈与されなかった財産は、亡くなった後に相続税の課税対象となることもあり、贈与と相続との間には深い関係があります。
親が所有している財産について、相続より生前贈与を選ぶようなケースでは、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
メリット1:早い段階から準備することで税額を安くできる
相続の場合、自分がいつ亡くなってしまうかは分からず、亡くなったときに一括して課税されることになります。
一方、贈与の場合、生前から計画を立てて準備することができ、相続時精算課税制度や特例等を利用することにより、税額を安く抑えることができます。
メリット2:意思を反映しやすい
相続は突然に起こる可能性があります。
遺書を遺していない限り、相続が始まると法定相続人が集まって遺産分割協議が執り行われ、相続人達の意思によって財産が分割されることになります。
一方、贈与の場合生前から贈与者の意思に基づいて計画的に進めることができるというメリットがあります。
メリット3:トラブルが起きにくい
上記通り、相続で遺書が遺されていない場合、相続開始後に法定相続人が集まって遺産分割協議が行われます。
特に財産の中に不動産が含まれているようなケースでは、法定相続人で財産を均等に分けるといったことが難しいことが多くなります。
例えば、相続財産が3,000万円の価値を持つ実家と現金1,000万円で、法定相続人が3人いたようなケースでは、法定相続人の1人が3,000万円の実家を、残り2人が500万ずつの現金を相続するといった形にやりやすく、相続人間で不公平が生じてしまいます。
元々は中のよかった家族が、相続を原因としてトラブルに発展し、険悪になってしまうようなこともあります。
一方、計画的に生前贈与を進めておけば、こうしたトラブルに発展する心配もありません。
デメリット1:課税されてしまうこともある
生前贈与のデメリットとしては、暦年課税の110万円の基礎控除を利用して計画的に贈与するようなケース��では、定額贈与と見なされてしまい、贈与されてしまうケースもあることです。
税理士など専門家の相談を受けながら計画的に進めるようにしましょう。
デメリット2:贈与者の老後資金が不足することがある
また、生存中に財産を贈与してしまうことで、贈与者の老後資金が不足してしまう可能性があることにも注意が必要です。
納税額をできるだけ安く抑える計画を立てることも大切ですが、贈与者の老後の生活についてもよく考慮した上で贈与を進めることが大切だといえるでしょう。
まとめ
不動産売却時、親族間取引や関係会社間取引など特殊な関係性を持つ相手の場合、税務署から目をつけられてしまう可能性が高いため、適性な価格での売買となるよう、より慎重に進める必要があります。
また、生前贈与については計画的に進めることで納税額を安くできたり、贈与者の意思を反映しやすくなったりといったメリットがある一方、定額贈与とみなされて課税されたり、贈与者の老後の生活を圧迫してしまったりする可能性がある点に注意が必要です。
いずれについても、税理士など専門家の相談を受けながら進めるようにするとよいでしょう。