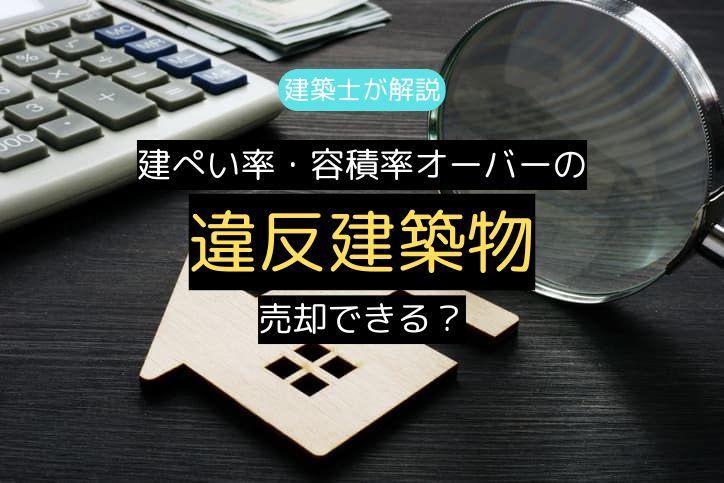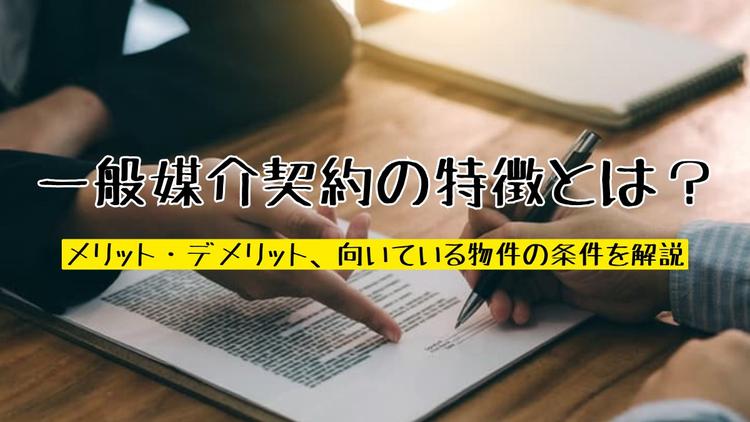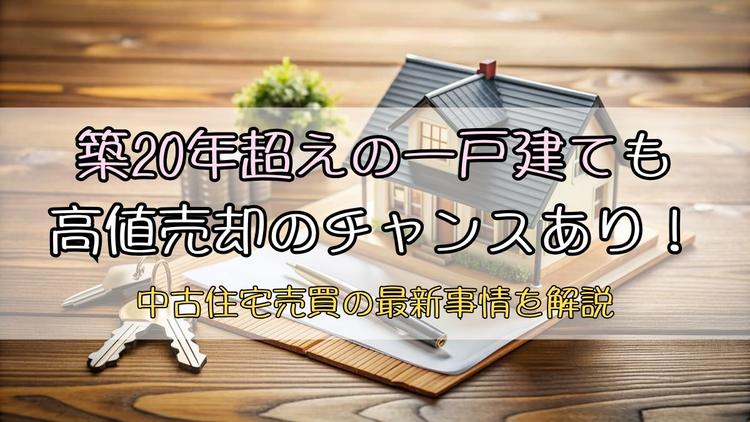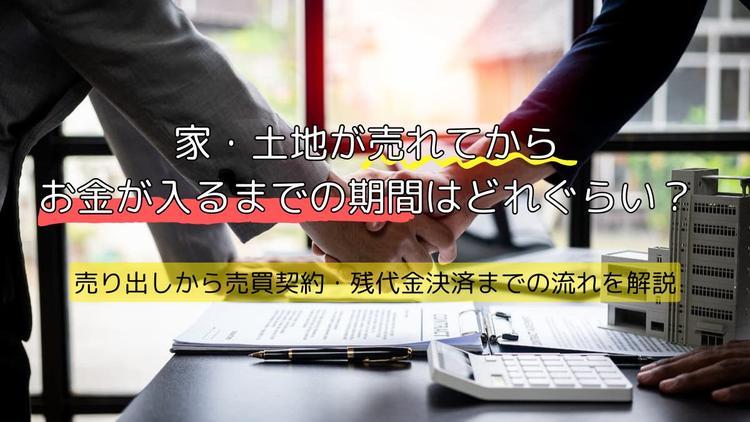「不動産には“建ぺい率”や“容積率”という重要な規制がある」と聞いたことはありませんか?
どちらも建物の大きさを決める重要な指標ですが、内容まで詳しく知っている方は意外と少ないものです。
簡単に言うと、
を示すルールです。
では、この制限をオーバーしてしまった「違反建築物(違法建築)」は、売却時にどう扱われるのでしょうか?
ここでは、建ぺい率・容積率の概要と、オーバーしている場合、売買にどのような影響が及ぶのかを解説します。
建ぺい率・容積率オーバーの建物は売却できるのか
建ぺい率・容積率、それぞれの用語の解説は一旦後回しにして、まずは売却について確認していきます。
古い家屋の中には、建ぺい率や容積率の制限をオーバーしているものがあります。
制限を超えている物件は、大きく分けて次の2種類に分類されます。
- 既存不適格建築物:当時の法律では適法だったが、後から法改正により制限を超えてしまった建物
- 違反建築物:建築時点で制限を守っていなかった建物
この違いが、売却のしやすさを大きく左右します。
既存不適格建築物であれば可能性はある
1971年以降、各地で建ぺい率や容積率の都市計画決定が始まりました。
この指定以前に建築された建物で制限をオーバーしているものが、既存不適格建築物です。
- 増築や大規模改修をしない限り、適法な建物として利用可能
- 金融機関によっては住宅ローンの融資が可能な場合もある
- 建築確認申請書や建築計画概要書などで“既存不適格”であることを証明できれば売却しやすい
▼関連記事:既存不適格建築物をリフォームする際の注意点は?制限や建築確認が必要なケースを解説
違反でオーバーしている建物は売却が厳しい
制限をオーバーしている理由として、残念ながら違反によるものがあります。
- 違反に時効はなく、役所の記録もほぼ永年保存される
- 是正義務は新しい所有者にも引き継がれる
- 金融機関のローンはほぼ不可
- 基本的に土地価格のみでの取引になりやすい
違反の事実を知りながら、わざわざ現金で建物を購入する人は、通常想定できませんから、違反で制限をオーバーしている建物は、まず売却できない(建物部分の価値はないものと見なされる)と考えた方がいいでしょう。
「違反建築物が付いた土地」として売買される場合も、解体や違反の是正に必要な費用を差し引いた価格でなければ売れない可能性が高いです。
買取専門の不動産会社に売却する方法がある
仲介での売却が難しい物件も、買取専門の不動産会社に買い取ってもらえる可能性があります。
買取専門の会社は、建築物を解体してから新しい建物を建てるといったノウハウを保有しています。
「仲介」による物件の売却が難しいと感じたら、ぜひ「買取」による売却も検討してみてください。
「イエウリ」で物件の無料査定に申し込む
- 既存不適格であれば仲介による売却も可能
- 違反建築物には住宅ローンの審�査が下りないため、土地部分しか評価されず、仲介で個人の買主を見つけるのは難しい
- 買取再販を行なっている業者への売却はスムーズに進みやすいが、この際も建物部分の価値ゼロと判断されることがほとんど(査定額は相場よりも大幅に下がる)
▼関連記事:【建築士が解説】違反建築・既存不適格とは?
建ぺい率とは何か
建ぺい率とは、建物の建築面積の敷地面積に対する割合のことです。
少し分かりにくいので、これを数式にしてみると、次のように表せます。
建築面積とは「外壁や柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」と定義付けされています。
これではやや難解なので、1階の面積が上階よりも大きい一般的な形式の住宅であれば、1階の床面積に玄関ポーチの柱で囲まれた部分を加えたものが建築面積になると考えてください。
その建ぺい率の意義や特徴について解説していきましょう。
建ぺい率は敷地の空間を確保するのが目的
第一種低層住居専用地域などの住宅地では、30%~60%の建ぺい率制限があります。
この中で最も緩い制限である60%の地域であっても、敷地面積が150平方メートル以上あれば、2台の駐車スペースとちょっとした庭を確保することができます。
建ぺい率の目的は、敷地周囲の空間を確保して日照や風通しを確保するとともに、万が一の火災の際の延焼を最小限にとどめる効果を期待したものです。
一方、商業地では、敷地の空間よりも販売スペースや執務スペースを確保することを重視して、ほぼ敷地いっぱいに建てられる80%を建ぺい率制限としている地域もあります。
建ぺい率は角地緩和がある
地方の建築条例で角地による建ぺい率緩和を設けている場合があります。
これは、一般的な長方形の敷地のうち二辺が道路に接している場合は、建ぺい率を1割緩和するというものです。
たとえば60%の建ぺい率制限がある地域でも、角地緩和が適用できる敷地であれば、70%まで建築することができます。
ただし、角地適用が可能になる道路幅員や敷地面積などの条件が地方ごとに異なるため、詳細は建築しようとする地域の地方条例によります。
建ぺい率100%の地域もある?
商業地域のように建ぺい率制限が80%であり、かつ防火地域に指定されている地域であれば、耐火建築物を建てることで建ぺい率制限が適用されなくなります。
防火地域は、すべての建物を耐火建築物にして、そのエリアで延焼を遮断することを目的としています。
建物を隙間なく建て込ませた方が目的を達成できるので、あえて建ぺい率制限を適用しないようにしているのです。
ただし、建物の建築面積は壁の中心で計算するので、敷地いっぱいに建てたとしても建ぺい率は100%にはなりません。
用途地域ごとの建築に関するルールや規制は、下記の記事で解説しています。
▼関連記事:13種類の用途地域の違いは?不動産取引や家を選ぶ際の注意点も解説
信頼できる不動産会社をご紹介
イエウリ の不動産査定はこちら
容積率とは何か
容積率とは、建物の延べ面積の敷地面積に対する割合のことです。
これを数式にすると次のように表せます。
例えば、各階100平方メートルの5階建てビルが、200平方メートルの敷地に建っているとすると、建物の延べ面積は、「100平方メートル×5=500平方メートル」から、次の計算になります。
500平方メートル÷200平方メートル=250%
これにより、この建物の容積率は250%です。
この容積率の意義や特徴について解説していきましょう。
容積率は面積を規制することで高さやボリュームを抑える
容積率によって建物の延べ面積を制限することで、建物の高さを抑える効果があります。
また高さを優先して建築したい場合には、各階の床面積を抑えられるので、建物の上部で空間を確保できることになります。
一方で、飛行機の格納庫や屋根付きスタジアムのように、巨大な空間を保有する建物は、建物の規模が大きくても、基本的に低層階しか床面積が発生しないので、容積率制限の意義を生かすことができません。
前面道路が狭いと容積率制限が厳しくなる
容積率は、建ぺい率と同様に都市計画決定により、制限が定められます。
しかし、敷地の前面道路幅員が狭い場合は、さらに厳しい制限がかかることになります。
道路幅員による容積率制限は、用途地域によって次のように定められています。
- 住居系用途地域:道路幅員(m)×4/10=容積率制限(%)
- その他の用途地域:道路幅員(m)×6/10=容積率制限(%)
たとえば商業地域で容積率制限が800%だとしても、前面道路幅員が4mであれば、240%しか建築できないことになります。
容積率に算入されない用途がある
容積率は建物の延べ面積に対する敷地面積の割合です。
ところが、使用用途によって、容積率の計算の際に、延べ面積から除外されるものがあります。
その代表的なものが駐車場や駐輪場で、全体の面積の5分の1までは、容積率の計算から除外できます。
たとえば各階100平方メートルの5階建てビルの内、1階をすべて駐車場とした場合で考えてみましょう。
敷地面積は200平方メートルとします。
この場合、建物の延べ面積は500平方メートルです。
もし、この地域の容積率制限が200%だとしたら、容積率が250%になるので建築できません。
しかし、1階の駐車場は延べ面積の計算から除外できるので、次の計算式になります。
これにより、1階部分をすべて駐車場にすれば、容積率制限が200%の地域であっても5階建てのビルが建築できることになります。
1階部分が駐車場のマンション(札幌市中央区)
この他、容積率の計算から延べ面積を除外できるのは、次のようなものです。
- マンションの共用廊下と階段
- 住宅の地階(全体の1/3以下)
- エレベータの1階部分以外の階
- 防災用備蓄倉庫(全体の1/50以下)
- 蓄電池置き場(全体の1/50以下)
- 自家発電設備設置部分(全体の1/100以下)
- 貯水槽設置部分(全体の1/100以下)
信頼できる不動産会社をご紹介
イエウリ の不動産査定はこちら
まとめ
一戸建ての住宅の場合は、建築確認済証や検査済証を確認することで、建ぺい率や容積率の制限をクリアしていることが確認可能です。
物件の売却の際にも、こうした書類を用意することで買主も安心して購入することができます。
マンションの場合は、建物の築年数が古い物件だと、容積率の既存不適格建築物になっていることがあります。
建物の経過を証明する書類を保有していない場合は、都道府県か市役所の窓口で建築計画概要書と検査済証明書を入手することで、既存不適格であることを証明することができます。
また、マンションの共用廊下や階段が容積率の計算から除外される規制は、容積率の指定後に改正された基準ですから、再計算をすることで、既存不適格ではなく実は適格な建築物になっていたということも十分あり得ます。
建ぺい率や容積率の制限をオーバーしている物件は、既存不適格建築物であることを証明することが重要です。
物件の履歴を証する書類をしっかりと確保して、できる限り有利な条件で物件の売却に臨みましょう。