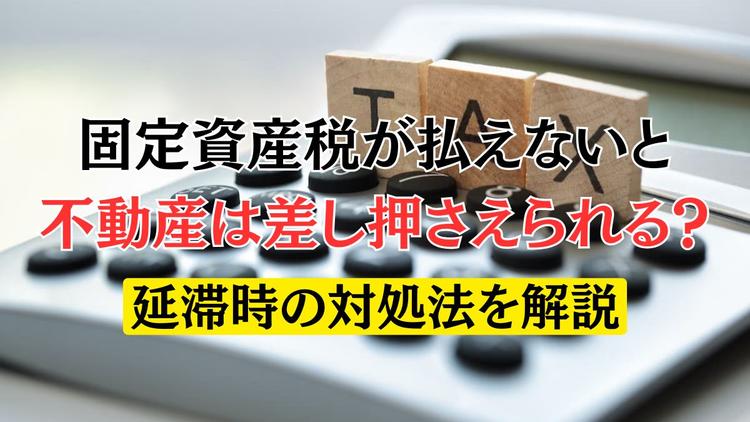不動産の所有者には、固定資産税の納税義務があります。でも、何かの事情で納税をしなかったら、どんな事態が待ち受けているのでしょうか。
実は、固定資産税などの税金は、たとえ自己破産しても免除されることはありません。
督促を無視して滞納を続けたら、最終的には不動産ばかりか給与まで差し押さえられてしまうのです。
この記事では、固定資産税が払えなかった場合の不動産の差し押さえについて明らかにするとともに、延滞時の対処法について解説をします。
固定資産税が払えないとどうなる?
一般的に「固定資産税」と呼ばれている税金は、土地と家屋にかかる固定資産税と都市計画税をそれぞれ合算したもの。都道府県に支払う地方税の分類。
不動産の所有者には、固定資産税の納税義務があります。何らかの事情で納税を怠れば、いったいどのような事態になるのか解説していきましょう。
自己破産しても納税義務は免除されない
最初に押さえておきたいのは、固定資産税を含むすべての税金は、たとえ自己破産をしても、けっして免除されないということです。
また、税金の時効は3〜7年とされていますが、時効は督促状や催告状が送られるごとにリセットされます。当然役所も承知していることなので、時効が成立しないタイミングで督促が繰り返されます。
つまり、滞納した税金は全額を納めない限り、生涯免れられないのです。したがって、多額の負債を抱えて自己破産が避けられない事態になったとしても、その前に税金を納める手立てを講じなければなりません。
延滞金の発生
固定資産税を滞納すると、次のような延滞金が発生します。
- 納期限の翌日から1カ月経過するまでの税率……年7.3%
- 納期限の翌日から1カ月を経過する日からの税率……14.6%
ただし、令和2年12月31日までは特例基準割合が適用されているので、次のような利率で計算されます。
- 納期限の翌日から1カ月経過するまでの税率……年2.6%
- 納期限の翌日から1カ月を経過する日からの税率……8.9%
たとえば、納期限が6月30日、納税額100,000 円の固定資産税��を1年間滞納した場合は、次の計算により延滞金は、16,000円になります。
200,000円×8.9%×(334日/365日)=16,288円
441円+16,288円=16,000円(千円未満切捨)
役所は差し押さえの準備を進める
納期限を過ぎても税が納められないと、役所の方では、粛々と差し押さえの準備を進めていきます。
まず滞納者の自宅に督促状が届きます。督促状は、法律に基づき納期限から20日以内に発送しなければならないことになっているため、たとえ電話等で納税の意思を伝えたとしても、納期限を過ぎれば必ず送付されてきます。
さらに、地方税法第373条により、督促状を発行した日から起算して10日を経過した日までに税金を納められないときは、滞納者の財産を差し押えなければならないとされています。そのため、遅くない時期に確実に差し押さえが行われます。
差し押えの予兆
ただし、多くの役所では、実際に差し押さえをする前に、電話や文書催告または訪問により自主的に納付してもらうよう納付の催告を行っています。しかし、督促状が届いている以上、こうした催告が行われないまま、いきなり差し押さえられることも十分にあり得ます。
督促や納付の催告を行っても納付されない場合、いよいよ役所は、官公署、金融機関、勤務先、取引先といった滞納者の財産を占有する第三者に対して財産調査を行います。給与、預貯金、不動産、動産、自動車、売掛金などすべての財産が調査対象です。
財産調査は滞納者の了承なしで実施される
財産調査は、国税徴収法に基づき実施されるので、滞納者に事前に了承を得ずに行うことができます。財産の発見、差押えなどで必要であれば、滞納者やその関係者の住居等を相手方の意思にかかわりなく強制的に捜索する強い権限があります。
財産が差押えられる
役所は、財産調査により差し押さえる財産を決定すると、いよいよ滞納者の財産を差し押さえます。差押えを行った場合、財産の種類によっては滞納者本人だけでなく、その財産の利害関係人に対しても「差押通知書」が送付されます。
不動産の差押え
不動産が差し押さえられると、動産の登記簿上に「差押」と記載されます。さらに、抵当権者等、登記簿上の権利者に「差押通知書」を送付し、不動産を差し押さえたことを通知します。
差し押さえられた不動産は、売却や贈与ができなくなります。たとえ差押え後に所有権の移転があったとしても、差押登記が優先されるため、役所は所有権移転前の滞納者の財産として換価することができます。
給与、預貯金、財産の差押え
滞納者の勤務先に差押通知書送付し、給与を差し押さえます。一旦差し押さえられた給与は、滞納した税が完納に至るまで、毎月の給与等から一定額が差し引かれます。
ただし全額が差し押さえられるのではなく、次のものを除いた金額が差押えの対象になります。
- 所得税、住民税、社会保険料など
- 10万円
- 扶養家族1人につき4万5000円
- 給料から1~3を差し引いた金額の20%
最低限の生活ができる金額については差し押さえが行われません。このため、たとえば給与が10万円である人の場合は、給与が差し押さえられることはありません。
預貯金を差し押さえる場合は口座のある金融機関へ「差押通知書」を送付します。差し押さえた預貯金は、滞納した税金に充てられます。
差し押えの対象
この他、生命保険契約や自動車、有価証券、家賃収入、売掛金、動産(電化製品、宝石などの貴金属、骨董品、絵画等)など、金銭的価値があり換価処分により税に充てることが可能なものはすべて差押えの対象となります。
ただし、差し押さえの対象は財産のすべてではなく、生活に欠かせない、衣服、寝具、家具、台所用具、生活に必要な3カ月の食料と燃料、実印などは対象にはなりません。
公売
差し押さえられた財産は公売によって売却され、売却代金の中から納税資金が支払われます。もし自宅が公売にかかり、買主が決まると、いよいよ家を出なくてはなりません。
ただし、不動産の公売は、山林、田、空き家で実施されるケースが多く、現に居住している家が対象になることは、全国的にもあまりありません。
しかし、差し押さえや公売が保留になっている間にも延滞金はどんどん増えていき、しかも生涯消滅することはないのですから、いずれにしても早い段階での完納を目指した方が負担が軽減できます。
固定資産税が払えない時の対処法
固定資産税が払えない場合、そのまま放置しておくと、やがて財産が差し押さえられることになります。そうした事態を防ぐためには、次のような方法が有効です。
- 分割払いを相談する
- 徴収の猶予・換価の猶予を受ける
- 任意売却をして納税する
それぞれどのように進めればいいのか解説をしていきましょう。
分割払いを相談する
財産を差し押さえられないようにするには、とにかく納付する意思があることを示して、それを実践することです。
そのためには、可能な納付額を分割で納付する方法を所轄の市区町村役場へ相談をしてみましょう。
本来、固定資産税は4回分割納付ができますが、交渉次第で、さらに分割回数を増やして月々の負担を減らしながら返済を認めてもらえることがあります。
収入が大幅に減ったといった窮状を訴えて、現実的に可能な返済方法を提示することで、役所の方が返済可能と判断すれば、分割払いを認めてもらえます。ただし、この取り決めすら守らずに滞納をした場合には、差し押さえが執行される可能性が高まります。
徴収の猶予・換価の猶予を受ける
徴収の猶予を受けられるのは、次のような特殊な事情がある場合に限定されます。この条件に該当するのであれば、申請することで納税を猶予することができます。
- 災害や盗難になったとき
- 本人、またはその生計を一にする親族などが病気や負傷したとき
- 事業を廃止、または休止したとき
- 事業について著しい損失を受けたとき
- 法廷納期限から1年以上後に納付税額が確定��したとき
また、新型コロナウイルス感染症の影響等により固定資産税の納付が困難なときには「徴収猶予の特例制度」が適用されました。
既に差し押さえを受けている財産や差押予定の財産の売却を最大で6年間猶予してもらえるのが、「換価の猶予」です。
コロナ禍のような経済不安が今後起こった際には、財産が売却された場合生活が困難になる等の一定の理由がある場合に認められることがあるので、報道や政府の発表をチェックしておきましょう。

任意売却をして納税する
住宅ローンを滞納したときに用いられる最終手段として、任意売却があります。
任意売却とは、住宅ローンの返済ができなくなったときに、銀行や保証会社と相談をしたうえで、自宅を売却する方法です。銀行としても、競売をするよりも高値で売却できる可能性があるので、交渉次第で任意売却に合意してくれます。
既に差し押さえを受けている場合でも、役所と話し合いを行うことで、差し押さえの解除をしたうえで、任意売却できる可能性があります。ただし、不動産を売った際の譲渡所得で税金が確実に納められる状況でなければ、役所の同意を得ることは難しいでしょう。
任意売却をした場合、投資家、不動産会社、親族に購入してもらうことで、リースバックという方法で、引き続き今の家に住み続けられることがあります。売却した自宅と賃貸契約を結ぶことで、借家として住み続けることができるのです。
売却資金によって滞納分を支払うことができれば、すでにその物件の所有者ではないので、他に不動産を所有していない限り、その後固定資産税の納付書が届くことはありません。
まとめ
滞納した固定資産税ぱ、生涯免除されることはありません。民間の金融機関等への負債と比較して、税金の滞納は取り立てが緩いというイメージを持つ人もいますが、実のところ、自己破産をしても、納付の督促は続けられるのです。
固定資産税の滞納を続けると、やがて督促状が届きます。これを無視して滞納を続けると、やがて不動産や預貯金、給与が差し押さえられることになります。差し押さえる際には、勤務先や金融機関にも通知書が届きますから、社会的信用は大きく失墜します。
どうしても固定資産税が納められないときは、役所に相談するのが先決です。本来の4分割をさらに分割して納めることを認めてもらえることがあります。つまり、納税が厳しい状況になれば、無断で滞納するのではなく、ともかく役所に相談をするのが最善の選択だということです。