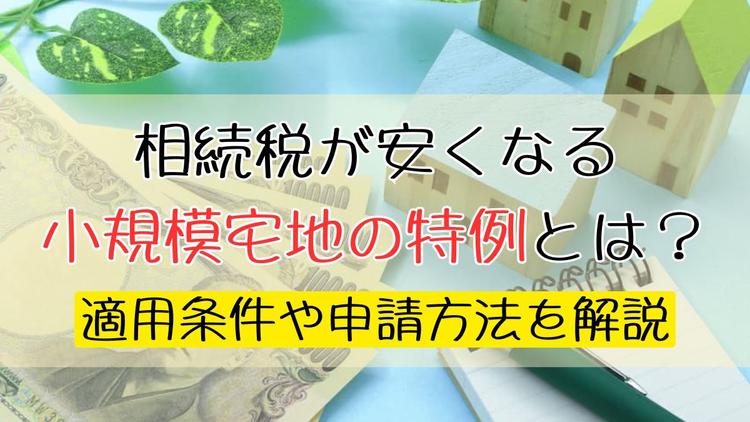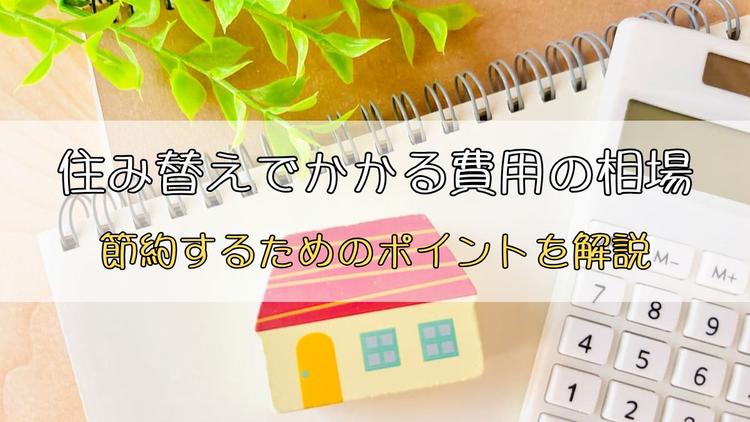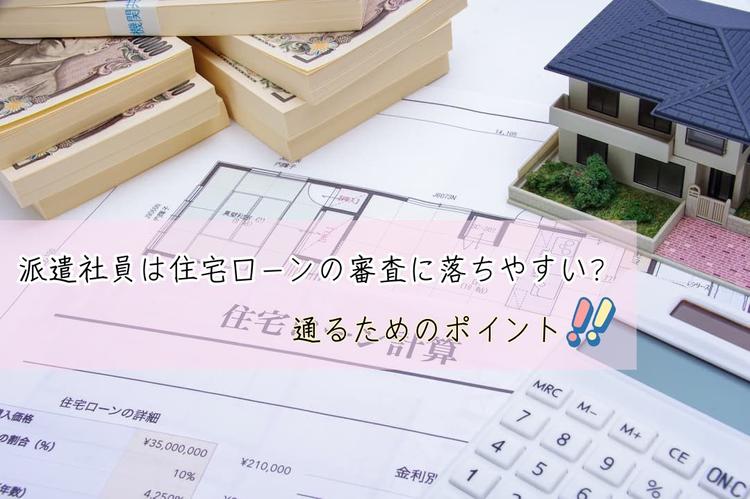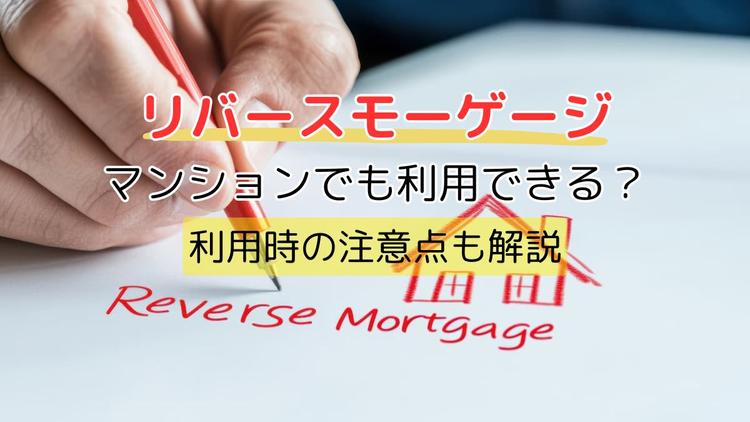小規模宅地の特例は、宅地の相続税評価額が最大で80%減額される制度です。相続税対策としてたいへん有効な一方で、適用されるための条件がいくつかあります。この記事では、相続税が安くなる小規模宅地の特例とはどのような制度なのか、そして適用されるには、どのような条件を満たせばいいのかについて解説をします。また申請方法についても併せてごらんください。
小規模宅地の特例とは
小規模宅地の特例とは、個人が相続によって取得した宅地のうち、一定の面積までの部分について、相続税の評価額を減額できる制度です。
対象となる宅地は、居住用・事業用・貸付用の3種類です。特例が適用されると、居住用と事業用の評価額は80%、貸付用は50%減額されます。
この特例が適用されると、相続税評価額が大幅に下がるので、相続税の節税ができます。それぞれに細かな適用条件が設定されていますので、各種類別に解説をしていきましょう。
居住用(特定居住用宅地等)の宅地
居住用の宅地とは、被相続人が亡くなる直前まで居住の用に供されていた宅地をいいます。対象となるのは330平方メートルまでで、減額率は80%です。
たとえば500平方の自宅を相続した場合、そのうちの330平方メートルまでが、相続税評価額の80%を減額され、残りの170平方メートルについては、通常の相続税評価額が適用されます。
適用条件は、居住用の宅地を相続した人が、次のうちのいずれかに該当する場合です。
- 被相続人の配偶者
- 被相続人と同居していた親族で、相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地を相続税の申告期限まで有している
- 被相続人に配偶者も同居人もいない場合で、3年間借家住まいの相続人がその宅地を相続税の申告期限まで有している
つまり、被相続人が住んでいた宅地について、小規模宅地の特例が適用されるのは、➀配偶者、②同居親族、③家なき子、となります。
③のケースが「家なき子」と呼ばれるのは、「相続開始前3年以内に日本国内��にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族または取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋に居住したことがないこと」と「相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと」が要件となっているためです。
被相続人が老人ホームに入居していたら
小規模宅地の特例は、亡くなった人が住んでいた宅地に適用されます。亡くなった時点で老人ホームに入居している場合には、次の要件を満たせば、入居する前に住んでいた宅地は、被相続人が住んでいた宅地として扱われます。
- 被相続人が亡くなる直前に要介護認定、要支援認定または障害支援区分の認定を受けていた。
- 被相続人が(特別)養護老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、サービス付き高齢者向け住宅等または障害者支援施設等に入所していた。
- 被相続人が②の施設に入所後、その宅地等が事業用または新たに被相続人等以外の人の居住用になっていない。
近年は、多くの被相続人が老人ホームに入居中に亡くなっています。老人ホームへの入居自体は、小規模宅地の特例適用を阻害するものではありませんが、老人ホーム入居後に自宅を他人の入居用に供していた場合等には適用されなくなるので注意が必要です。
被相続人が建物を所有していない
被相続人が、自ら所有する宅地の上に建つ建物を所有していない場合でも、建物の所有者が親族であり、亡くなる直前まで被相続人が住んでいたのであれば、特例は適用されます。
生計を一にする親族が使っていた宅地を相続した場合�にも適用
小規模宅地等の特例は、亡くなった人が住んでいなかった宅地であっても、被相続人と生計を一(いつ)にする親族が使っていた宅地を相続した場合にも適用されます。
適用の対象となるのは、被相続人の配偶者か居住していた親族です。
被相続人の配偶者が相続する場合の要件はありません。居住していた親族が相続する場合は、「被相続人の死亡前から相続税の申告期限まで引き続きそこに居住すること」と「その宅地を相続税の申告期限まで保有していること」が要件となります。
なお、「生計を一にする」とは、被相続人と同居して生活費を共有している状態が一般的です。被相続人が住んでいない宅地に住む親族と生計を一にしているケースとしては、被相続人が所有する宅地に、長女が住み、被相続人の仕送りで生活をしている場合などが想定できます。
事業用(特定事業用宅地等)の宅地
小規模宅地の特例が適用される事業用の宅地とは、被相続人や生計を一にしていた親族が事業をしていた宅地をいいます。ただし、事業のうち不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業等の事業については除きます。
小規模宅地等の特例が適用される限度面積は400平方メートルで、減額率は80%です。たとえば500平方の宅地を相続した場合、そのうちの400平方メートルまでが相続税評価額の80%を減額され、残りの100平方メートルについては、通常の相続税評価額が適用されます。
被相続人の事業の用に供されていた宅地が小規模宅地の特例を受ける場合には、次の要件を満たさなければなりません。
- 事業承継要件……その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること。
- 保有継続要件……その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。
被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用に供されていた宅地が小規模宅地の特例を受ける場合には、次の要件を満たさなければなりません。
- 事業承継要件……相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等の上で事業を営んでいること。
- 保有継続要件……その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。
貸付用(貸付事業用宅地等)の宅地
貸付用の宅地とは、被相続人が亡くなる直前まで、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業等の用に供されていた宅地です。
たとえば、他人に貸したり、賃貸アパートを建てたりしている宅地のことです。こうした宅地を被相続人や生計を一にしている親族が所有していた場合に、小規模宅地の特例が適用されます。
被相続人が亡くなる前からその宅地で不動産貸付業をおこなっていることが要件となります。ただし、亡くなる前3年以内に貸し付けた宅地は該当しないので注意が必要です。
貸付用の宅地の場合、特例の適用面積は200平方メートルで減額率は50%です。たとえば500平方の自宅を相続した場合、そのうちの200平方メートルまでが相続税評価額の50%を減額され、残りの300平方メートルについては、通常の相続税評価額が適用されます。
被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地が小規模宅地の特例を受ける場合には、次の要��件を満たさなければなりません。
- 事業承継要件……その宅地等に係る被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその貸付事業を行っていること。
- 保有継続要件……その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。
被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業の用に供されていた宅地が小規模宅地の特例を受ける場合には、次の要件を満たさなければなりません。
- 事業承継要件……相続開始前から相続税の申告期限まで、その宅地等に係る貸付事業を行っていること。
- 保有継続要件……その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。
小規模宅地の特例の申請方法
小規模宅地等の特例は相続税の制度ですから、相続税の申告することで特例が適用されます。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。 申告が遅れた場合、延滞税等のペナルティがあるばかりでなく、特例を受けられなくなる可能性があります。
課税価格が基礎控除の範囲内であり、相続税がかからない場合には申告は不要ですが、小規模宅地の特例を適用した結果として、基礎控除の範囲内となり相続税がゼロ円になった場合には、相続税の申告が必要です。この申告がないと、特例の適用がされないので、最終的に相続税を納めることになります。
共通の添付��書類
小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、次の書類を添付する必要があります。
- 被相続人のすべての相続人を明らかにする戸籍の謄本……相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの。
- 遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書……遺産分割協議書に実印を押印したもの。
- 住民票の写し……相続開始日以降に作成されたもの。
居住用で必要な添付書類
居住用で特例を受ける場合、被相続人の配偶者や被相続人と同居していた親族が申告するのであれば、上述の共通の添付書類のみを提出することになります。
しかし、被相続人と同居していなかった親族が申告する場合には、相続開始前3年以内に居住していた家屋が自己または自己の配偶者の所有する家屋以外の家屋である旨を証明するために次の書類が必要となります。
- 住民票の写し……相続開始日以降に作成されたもの。
- 戸籍の付票の写し……相続開始日以降に作成されたもの。
- 相続する家屋の登記簿謄本、借家の賃貸借契約書など
被相続人が養護老人ホームに入所していた場合は、当該宅地が特例の対象になることを証明するために次の書類が必要になります。
- 被相続人の戸籍の附票の写し……相続開始の日以後に作成されたもの。
- 介護保険の被保険者証、障害福祉サービス受給者証、要介護認定証、要支援認定証などの写し
- 施設に入所したときの契約書の写し
事業用で必要な添付書類
事業用の場合は、上述の共通の添付書類の他に必要となる書類はありません。
貸付用で必要な添付書類
平成30年4月1日以後の相続または遺贈により取得した宅地等については、相続開始前3年以内に新たに貸付用に供されたものである場合は、被相続人が相続開始の日まで3年を超えて特定貸付事業を行っていたことを明らかにする書類が必要になります。
まとめ
小規模宅地の特例とは、個人が相続によって取得した宅地のうち、一定の面積までの部分について、相続税評価額を減額できる制度です。
対象となる宅地は、居住用・事業用・貸付用の3種類です。特例が適用されると、居住用と事務用の評価額は80%、貸付用は50%減額されます。
居住用の場合、被相続人が住んでいた宅地について、小規模宅地の特例が適用されるのは、配偶者、同居親族と、いわゆる「家なき子」です。
また生計を一にする親族が使っていた宅地を相続した場合には、配偶者か生計を一にする親族に適用されます。この場合、配偶者には適用要件はありませんが、親族には、「被相続人の死亡前から相続税の申告期限まで引き続きそこに居住すること」と「その宅地を相続税の申告期限まで保有していること」が要件となります。
貸付用の宅地は、亡くなる前3年以内に貸し付けた宅地には特例が適用されないので注意が必要です。
課税価格が基礎控除の範囲内で、相続税がかからないケースでは、相続税の申告は必要ありません。しかし、小規模宅地の特例を適用した結果として、基礎控除の範囲内となり相続税がゼロ円になるケースでは、きちんと相続税の申告をしておかないと、最終的に相続税を納めることになります。